■ 週末に(いや、週末に限らないが)観た映画について何か書こうとカテゴリーを設けてある。このところサボっていたので、まとめて3作品を備忘録として載せておきたい。
寅さんシリーズ第7作「男はつらいよ 奮闘篇」
マドンナは旅先の沼津で出会った花子(榊原るみ)。花子には軽度の知的障害がある。そんな彼女に寅さんは優しく接する。旅先の寅さんは本当に人に優しい。なんらかのトラブルを抱えた人と出会うことが多いけれど、寅さんはそんな人たちをいつも励ます。柴又のとらやではおいちゃんやタコ社長とよくケンカするけど。
何かあったらとらやを訪ねるようにと言って、用立てた青森までの汽車賃を花子に渡す。青森に帰るはずの花子はとらやに来ていた。花子のために何かと世話をする寅さん。
何日か経って、青森から福士先生(田中邦衛)がとらやに花子を迎えにくる。花子は先生と一緒に青森へ帰っていく・・・。
マドンナ花子の「寅さん好き度」 花子は寅さんの優しさに惹かれていた。
★★★☆☆ 福士先生と一緒に青森へ
天空の城 ラピュタ
宮崎作品を「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」「となりのトトロ」「風の谷のナウシカ」「風立ちぬ」と観てきた。で、しばらく前に「天空の城 ラピュタ」を観た。宮崎 駿という人は空が好きなんだろうな、飛ぶことが好きなんだろな・・・。これで主な宮崎作品を観たことになるのかな。
ブルージャスミン
偶々、TSUTAYAのレンタルDVDのコメディの棚で目にした。予備知識は全く無かったがコメディ作品なら笑ってしまうような場面が頻出するだろうと思って借りた。
ニューヨークでセレブな生活をしていた女性の転落物語で、笑う場面など無かった。なんだか期待外れだなと途中で思ったけれど、最後までなんとか観た。
3作品ともおもしろいと思わなかったのはこちらの心模様故か。たぶんそうだろう。

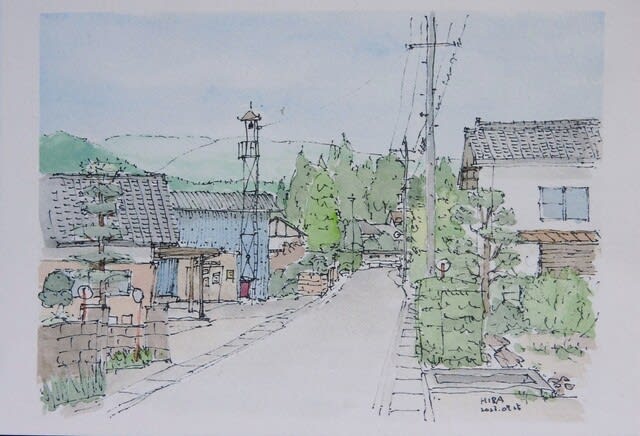


 530
530













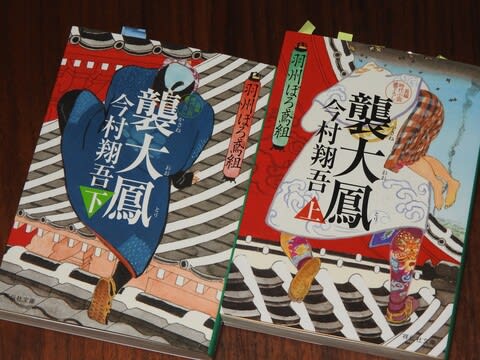








 ①
① ②
② ③
③ ④
④



 360
360
 480
480 480
480 420
420
