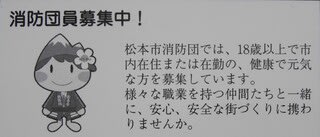■ 時の経つのは早い。7月が終る。
7月の読了本は5冊。小説は読まなかった。
『カラー版 名画を見る眼 Ⅱ』高階秀爾(岩波新書1971年、2023年カラー版)
西洋の近代絵画の大きな流れ、その概観を解く教科書的な新書。
**累計82万部、50年以上読み継がれてきた美術史入門の大定番**(帯のことば)
『言語の本質 言葉はどう生まれ、進化したか』今井むつみ・秋田喜美(中公新書2023年)
言語はどのようにして生まれ、どのように進化してきたのか・・・。ふたりの著者が実証的に解き明かす。そのロジカルな展開は推理小説よりおもしろい。
『堤 未果のショック・ドクトリン 政府のやりたい放題から身を守る方法』堤 未果(幻冬舎新書2023年)
本書に取り上げられているのはマイナンバー、コロナ、脱炭素。今一番気になるのはマイナンバーカードのトラブル。続出する個人情報のひも付けミス。任意だったはずのカードの取得がいつのまにか強制にすり替えられ・・・。マイナンバー、政府の本当の狙いは何か。本書に書かれていることが真実だとは思いたくない。
『データサイエンスが解く邪馬台国 北部九州説はゆるがない』安本美典(朝日新書2021年)
邪馬台国はどこにあったのか、古代史最大の謎にデータサイエンスで迫る。示されたデータに畿内説を唱える研究者は反論できるのだろうか。実に説得力のある論説。
ひとつだけ、残念に思うことは「魏志倭人伝」に書かれていて、何通りにも解釈できるる邪馬台国の所在地への方向、旅程に関する考察が示されていないこと。別にこのことに触れなくても、充分実証できるということだろうが、やはり読者のごく基本的な関心事だと思うのに。
『槍・穂高・上高地 地学ノート 地形を知れば山の見え方が変わる』竹下光士・原山 智(山と渓谷社2023年)
なぜ槍の穂先が傾いているか? なぜ常念岳は三角形に尖っているのか・・・。本書は北アルプスの槍ヶ岳、穂高連峰、そして上高地の地形がどのようにできたのか、解き明かしている。
撮影日2017.05.29 松本市内から見た常念岳
常念岳をつくっている花崗岩は約6,400万年前にできた、と書かれている。イメージすらできない遠い遠い過去。なぜ、あの三角形ができたのかなどと考えたこともなかった。本書ではこのことについても解き明かしている。
槍の穂先が傾いているということを本書で知った。槍・穂高連峰は少し東に倒れるように隆起したという。「傾動」というこの隆起のメカニズムが分かりやすく図解されている。なるほど! こういうことか。
7月20日、21日と上高地に出かけたが、その前に本書を読んでいたら、上高地の風景が違って見えたと思う。
8月、夏休み、読書感想文。8月は小説を読もう。












 ①
① ②
② ③
③ ④
④ ⑤
⑤ ⑥
⑥ ⑦
⑦ 420
420 、
、 なんてこともあったらしい。らしい、などと当事者でないような書き方をする)と一緒に上高地に出かけたのは今月(7月)の20日,21日のことだった(
なんてこともあったらしい。らしい、などと当事者でないような書き方をする)と一緒に上高地に出かけたのは今月(7月)の20日,21日のことだった(
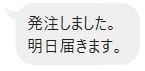

 とぼくが書くと
とぼくが書くと ①
① ②
②













 420
420 ①
① ②
② ③
③ ④
④ ⑤
⑤
 ⑥
⑥ ⑦
⑦ ⑧
⑧ ⑨
⑨ ⑩
⑩ ⑪
⑪ ⑫
⑫ ⑬
⑬
 ラインで早くもこんなリクエストが。
ラインで早くもこんなリクエストが。