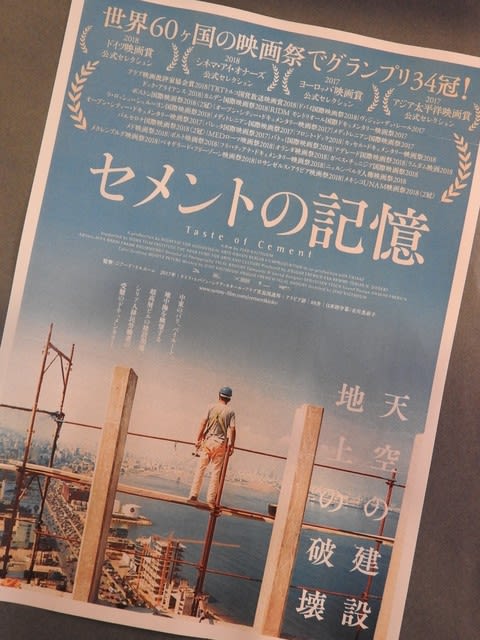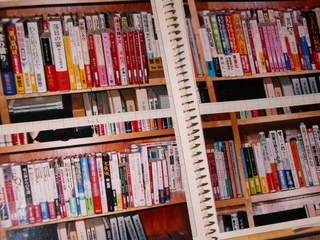
■ 読み終えた本を書棚に順番に並べていく。それを写真に撮ってダイアリーに貼っておく。以前はこのような簡単な方法で読んだ本の記録に代えていた。ブログを始めてからも同様の方法を続けてきている。
令和元年の5月は5冊の本を読んだ。
『新聞記者』望月衣塑子/文春新書
新書より文庫の方がふさわしいのではないかと思う。本書を原案にした映画が6月に公開される。公開されたら観たいと思う。
『桜』勝木敏雄/岩波新書
桜の分布種と分布域について書かれた本。分類に関する考え方は大いに参考になると思う。
『虫や鳥が見ている世界 ―紫外線写真が明かす生存戦略』浅間 茂/岩波新書
『僕って何』三田誠広/河出書房新社
著者の講演を聴いて、およそ40年ぶりに再読した青春小説。
『三四郎』夏目漱石/新潮文庫
三田さんの講演で取り上げられた小説。50年ぶりの再読か。**三四郎は何とも答えなかった。ただ口の中で迷羊、迷羊と繰返した。** (337頁)
5月、ストレイシープ・・・。
6月は『3001年終局への旅』アーサー・C・クラーク/ハヤカワ文庫、「宇宙の旅」シリーズ完結篇 の再読から。