 360
360
■『夢の逃亡』安部公房(新潮文庫1977年)を読んだ。奥付を見ると、この本の発行日は昭和52年(1977年)10月30日。この本を読み始めたのが同年11月2日と記録されている。発行された直後に早速読み始めたことが分かる。この初読の後に再読した記録も記憶もないので、今回46年ぶりに再読したことになる。
この『夢の逃亡』には初期の短編が7編収められている。初読の時に引いた傍線が数か所ある。
**そういった存在の窪みである頁の間からようしゃない実体としてこぼれ出たこの本だけを、真に〈名前〉に耐え得るものであったと書かねばなるまい。**(76頁) この引用箇所に傍線を引いてある。前後の文脈を考慮しても意味がよく分からない。
7編ともよく理解できず、字面を追っただけだった。従って読み終えたとは言えないが、読んだということにしておく。46年前はどうだったのか、理解できたのかどうか。傍線を引いたり、▽印を付けたりしてあることから、それなりに読み解いていたのだろう・・・。
今回再読して付箋を貼った箇所から引く。
**一体、性格なんていうものがあるのでしょうか。仮にあるとしても、それが人間の本質とどう関係してくるのでしょう。**(「牧草」20頁)
**第一、人間を掴むといったって、実際問題として、一体どうやったら良いでしょう。一体人間とは何者でしょう。**(「牧草」21頁)
人間とはなにか、人間が存在するとはどういうことなのか、安部公房がずっと問い続けることになるテーマがこの文庫に収録されている最も初期の作品にも出ている。
私の脳は加齢とともに確実に劣化していて、読解力も記憶力も低下していることを実感する。先日、図書館の職員とも話したけれど、本は若い時にたくさん読んでおくべきだ。
手元にある安部公房の作品リスト(新潮文庫22冊 文庫発行順 戯曲作品は手元にない 2024年3月以降に再読した作品を赤色表示する。*印は絶版と思われる作品)
『他人の顔』1968年12月
『壁』1969年5月
『けものたちは故郷をめざす』1970年5月
『飢餓同盟』1970年9月
『第四間氷期』1970年11月
『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月
『無関係な死・時の壁』1974年5月
『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月
『石の眼』1975年1月*
『終りし道の標べに』1975年8月*
『人間そっくり』1976年4月
『夢の逃亡』1977年10月*
『燃えつきた地図』1980年1月
『砂の女』1981年2月
『箱男』1982年10月
『密会』1983年5月
『笑う月』1984年7月
『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*
『方舟さくら丸』1990年10月
『死に急ぐ鯨たち』1991年1月*
『カンガルー・ノート』1995年2月
『飛ぶ男』2024年3月













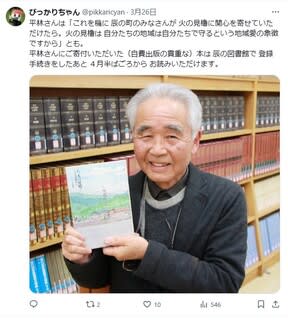


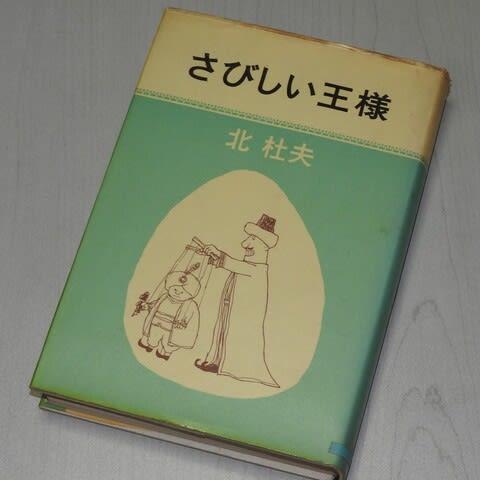
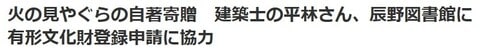



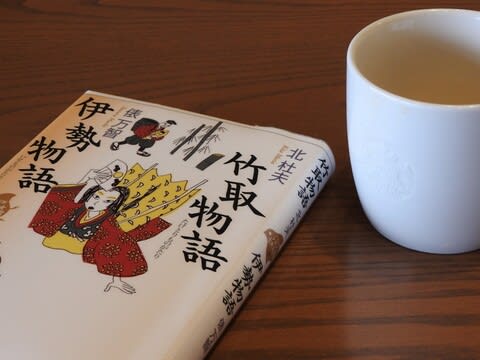






 360
360



 ①
① ②
② ③
③

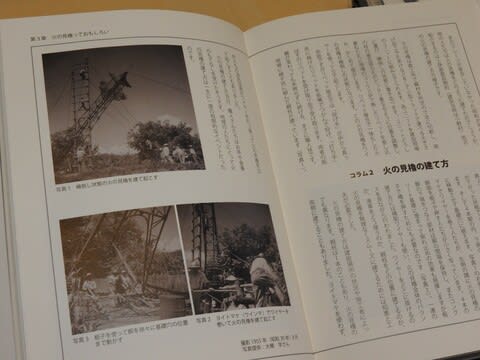 ⑥
⑥ ⑦
⑦ ⑧
⑧ ⑨
⑨ ⑩
⑩ ⑪
⑪
 360
360