■ いままでどんなことを書いてきたのか、過去ログを読んでいた。で、この記事(20070817 初稿)を再読した。そうか、こんなことを書いていたのか・・・。少し手を加えて載せる。
「秩序のヨーロッパ 混沌のアジア」
『村上春樹のなかの中国』に出てくる「森高羊低」はアジアでは「ノルウェイの森」の人気が高くて「羊をめぐる冒険」が低く、「羊高森低」は欧米ではその逆で、「羊」の人気が高く「森」の人気が低いという傾向を指摘することばだが、それは何故だろうと考えていた。
そこで先のことばを思い出したというわけだ。このことばは都市の様相を簡潔にして的確に捉えている。都市の様相にはそこに暮らす人々の嗜好が反映されている。好みにあった建築が造られてそれらが集積して好みにあった都市が出来ていく・・・、これは必然だ。
欧米人は秩序を好みアジア人は混沌を好むということが都市の様相に表れているというわけだ。
自然の中に数理的に表現できるようなシンプルな秩序をヨーロッパ人が希求して「自然科学」を生み、自然の混沌をそにまま受け入れてそれをモデルとして「漢字」を生んだ中国人、こんなところにも両者の違いが表れていると指摘できるかもしれない。
秩序は抽象とか知性・理性に通ずるし、混沌は具象、感性に通ずる。その具体例としてこの例の他にはヨーロッパとアジア(とりわけ日本)それぞれの庭園を挙げることもできるだろう。
さて『ノルウェイの森』と『羊をめぐる冒険』。
『ノルウェイの森』は村上自身が河合隼雄との対談で明らかにしている(注)ように「セックスと死」について書かれた小説だ。これを通俗的なポルノ小説とした評論も頷けないこともない。ギトギトのポルノ、複雑さや難解さがなく具体的な表現で、アジア人が好むということも分かる。いやなにもアジア人がヨーロッパ人より好色だと言いたいわけではない。先の文脈に沿ってそう指摘しているのだ。
一方『羊をめぐる冒険』はミステリアスで抽象的、知的。 となればやはりヨーロッパの、特に知性派好みの小説ということになるだろう。
香港は「森羊双高」だという。香港が東西の人、文化の混成であることを考えればこの傾向もなんとなく分かる。
『村上春樹のなかの中国』は以前書いたように大学教授が研究の成果を基にしたもの。だから実証的に論考している。こちらはブログ、気楽なものだ。だからこんな根拠のないことも書ける。
ついでに・・・、「森」は暑い季節に汗をかきながら読むのがいいかもしれない。「羊」、こちらは静かな秋の夜に読むのがいい。
注 **あの小説ではセックスと死のことしか書いていないのです** 『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』/新潮文庫













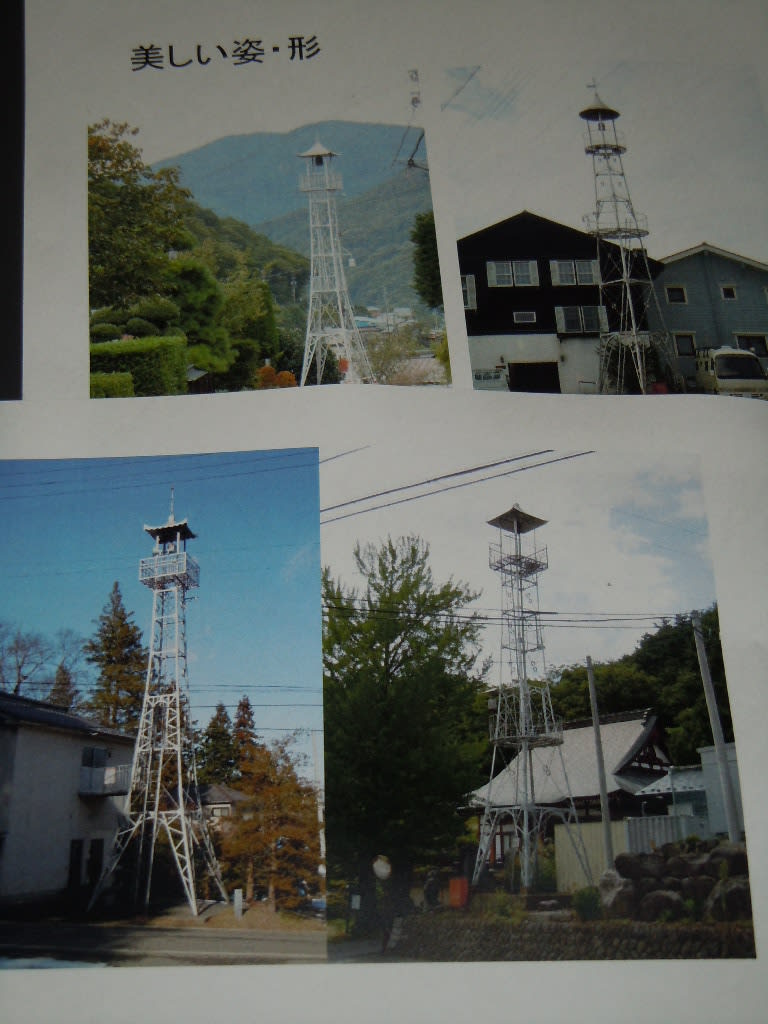


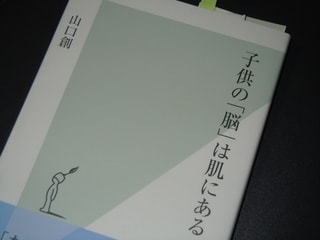















 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9







