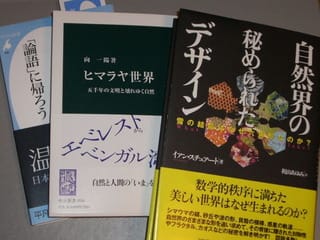
■ 今月の読了本は『新・建築入門』隈研吾/ちくま新書のみだった。レビューは省略。来月(早いな、もう師走か)に読む予定の本のプレビュー。
『ヒマラヤ世界』向 一陽/中公新書:エベレストの麓では一体どんな暮らしが営まれているんだろう・・・。
『「論語」に帰ろう』守屋淳/平凡社新書:君子は義に喩り、小人は利に喩る
『自然界の秘められたデザイン 雪の結晶はなぜ六角形なのか』イアン・スチュアート/河出書房新社:数学的秩序に満ちた美しい世界はなぜ生まれるのか?
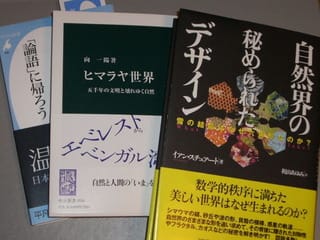
■ 今月の読了本は『新・建築入門』隈研吾/ちくま新書のみだった。レビューは省略。来月(早いな、もう師走か)に読む予定の本のプレビュー。
『ヒマラヤ世界』向 一陽/中公新書:エベレストの麓では一体どんな暮らしが営まれているんだろう・・・。
『「論語」に帰ろう』守屋淳/平凡社新書:君子は義に喩り、小人は利に喩る
『自然界の秘められたデザイン 雪の結晶はなぜ六角形なのか』イアン・スチュアート/河出書房新社:数学的秩序に満ちた美しい世界はなぜ生まれるのか?
■ 鉄道マニアの人たちはそれぞれ自分の「鉄」の世界を見つけ、自らいくつかの条件を課すことで、デープな世界を築いている。
「鉄分補給スペシャル 2009」というNHKの番組を観て鉄っちゃんたちのこだわりに感動した。前々稿でも書いたが、番組に登場した「103系撮影熱中人」は103系車両のすべてを写真に撮るという信じられない試みを34年間も続けてきたという。
34年間!! そして全3637両(番組で紹介された数字)のうち、3605両撮影したそうだ。しかもヘッドライトが新しくなったとか、色が変わったとか、車両が改修された場合には改めて撮り直しているのだそうだ。
103系は首都圏の通勤・通学電車として中央線(オレンジ色)、山手線(ウグイス色)、総武線(黄色)などで運行されていたから、むかし私もよく利用した。この103系、首都圏では既に全廃状態だが、関西以西ではまだ現役で頑張っている。
以前、全国のすべての駅(JR、私鉄とも)のホームで駅名を入れて写真を撮っている鉄っちゃんが紹介された(自分も写真に納まるという条件付き)。新しい駅も出来るから、すべて撮り終えるということにはなかなかならないが、ほとんど撮り終えたというからすごい。
私も鉄の世界にほんの少し入り込んでいる。それは古くて味のある駅舎の全景写真を撮ることだ。
中央線 国立駅 200606撮影(高架化に伴い取り壊された)
高山本線 高山駅 200610撮影
上高地線 新村駅 200908撮影
篠ノ井線 姨捨駅 200909撮影

■ CAFE VALO
このカフェのデザインについて書く前に藤森照信さんが説いた建築家の「赤派」と「白派」について再度取り上げておきます。
「赤派」というのは建築に具象性、ものとしての実在性、要するに素材感をストレートに表現する建築家のこと、対して「白派」は材料の素材感を消して建築に抽象性を求める建築家のことです。ですから白派の建築では使ってある、例えば内装材料がスチールなのかボードなのか木なのかはっきり分からないことがよくあります。
抽象性の「白」に対し、具象性を「赤」としたところは、藤森さん流石です。
このところ白派から赤派へ転向する建築家が少なくありません。隈研吾さん然り(隈さんはギャラリー間の展覧会の挨拶文を**抽象的なものから抜け出して、有機的なものへと向かいたいと考えている。**と書き出しています)、伊東豊雄さん然り(伊東さんの白から赤への転向宣言は以前書きました)。
藤森さん自身は赤派の代表といってもいい。元々「建築は素材だ」と唱えていましたから。頑なに白派なのは谷口吉生さん、槇文彦さん。ふたりとも知的で上品な建築をデザインします。
さてこのカフェのデザイン、少しだけ赤味を帯びた白、ごく薄いピンクといっていいでしょう、ってなんのことか分かりませんネ。
ガルバリウム鋼板で包んだキューブ(四角い箱)。このキューブというシンプルな形は「白」の最たる特徴。上の写真にはキューブの全体が写っていませんが、正面の壁には小さな四角い窓がふたつあるのみ。そして薄いことも「白」の特徴ですが、テラスの屋根、木造なのに薄いですね。
テラスの柱やエントランスの枠に木が使われています。このことが少しだけ赤味を帯びているとする理由です。柱や枠がペンキされていて木の質感が消されていたら、もう、真っ白な建築といっていいでしょう。
このカフェをデザインしたMさん、彼の設計した住宅をいくつか見学させてもらいましたが、床にはムク材のフローリングを使い、壁は左官材で仕上げ、天井は木の梁や化粧野地板を室内に表すことが多いと思います。そう「赤」の空間。でもざっくりとした空間ではありません。細かな部分を端整に納めていますから、少し「白」の入った「赤」、と私は見ています。
このカフェもそのようにデザインしてもよかったかもしれません。自然素材に包まれた安らぎの「赤」。でもそうはしなかった・・・。
写真は撮りませんでしたが、内部は抽象的でストイック、端整な「白」の空間です。床に唐松のムク材を使っていますから、少しだけ赤味を帯びた「白」。そのバランスがいい。
オーナーもMさんも非日常な抽象性、「白」を求めたのだろうと解釈しました。そう、このカフェは日常から離れて、ひと時を静かに過ごす非日常な「白」の空間なのです。
白い壁に青のポスターが見事に決まっていました。素敵な空間。「白」もいい・・・。
やはり設計者の知性と感性ってデザインに出るんだなぁ~、そう思いながら美味しいコーヒーとケーキをいただきました。
CAFE VALO 松本市梓川倭

■ 民家 昔の記録 青梅の民家 198003
東京の郊外青梅市内で見かけた民家。まず大きさがいいです。漂う日々の暮らしの雰囲気がいいです。
「清貧」という言葉が何年か前に流行りました。そんな暮らしぶりが伺えます。もう30年近く前の撮影ですから、プライバシーを覗くようなこの写真の掲載も容赦していただけるでしょう。
季節の移ろいを感じながら静かに暮らす・・・、あこがれます。

■ 民家 昔の記録 佃島 観察日820429
狭い路地だが、共有空間として機能している。一見雑然としているが、生活感がにじみ出ていてなんとも好ましい。以上、当時の記録を転載。
僕にとって街並みの魅力ってこういうことなのかもしれない。生活感の乏しい映画のセットのような街並みではなくて、そこに暮らす人びとの日常の表情がちらほら見えること。
東京湾での漁業や佃煮を生業としていた漁民が長年かけてつくってきた街の表情。人情に厚い人びとの暮らし。佃島の路地って今でもこんなに緑豊かな空間なんだろうか・・・。

最近取り付けられた看板
久しぶりに休日の午後のひと時をカフェ・シュトラッセで過ごした。深煎りのケニヤをゆっくり味わいながらあれこれ雑想・・・。
□ 昨晩NHK・BS2で聴いたあきなおみの歌。2時間番組で何曲も聴いたがベスト3を挙げるなら「港が見える丘」「さだめ川」「星影の小径」かな・・・。
□ 今朝見た「日曜美術館」ではバロックが取り上げられ、一つ前の時代のルネサンスと比較して何点もの芸術作品が紹介された。秩序的なルネッサンス、聖堂ではドームの頂部が真円、理想的な秩序を崩したバロックでは楕円か・・・、なるほど。ラファエロとカラヴァッジョの宗教画、ルネッサンスとバロックの表現の違い。カラヴァッジョの絵の方が好きだな。
黒川紀章は若尾文子を「君はバロックだ」と口説いた、どういう意味だったんだろう・・・。
番組にゲスト出演していた分子生物学者の福岡伸一さんが、フェルメールの「デルフト眺望」について、部分は細密には描かれてはいないものの、全体はリアルだという主旨の指摘をしていた。上野で観たフェルメールは確かに指摘の通りだった。
この時代、数学の微分法が確立して、連続的な変化の瞬間を捉えるようになるが、絵画の世界にもこの概念が適用できて「デルフト眺望」も時の流れの一瞬を捉えたものだという。絵から時の流れの連続性がイメージできるという指摘は「なるほど!」だったなぁ。
□ 部分と全体。まちを構成する個々の要素の魅力とまち総体の魅力の関係・・・。そうか、福笑い! 顔を構成する目や眉や鼻、口などはグッドデザインなのにそれらのレイアウトの結果としての顔全体のデザインはどうも・・・、ということと似ているのかも。そこに何があるのだろう・・・。部分と全体を関係付けるシステム?
まちの魅力に欠かせない要素は、まちの規模が小さいこと、まち全体を俯瞰できる場所、まちなかを流れる川、情緒ある街並み・・・。角館を訪れたことは未だないが、あのまちにはこれらの要素がすべて揃っている・・・。調べてみて分かった。古城山という俯瞰場、桧木内川、しだれ桜がきれいな武家屋敷の街並み・・・。では、長崎は?
□ 司馬遼太郎はマップラバー、歴史や人の一生を俯瞰的に、総体的に捉えようとした。藤沢周平はストリートラバー、市井の人々の日々の暮らしのディテールを表現した、と言っていいかも。
*****
あれこれ雑想していて、持参した『脳で旅する日本のクオリア』はいくらも読み進むことができなかった。

茅野市民館:古谷誠章
JR茅野駅に直結する複合施設。この計画のポイントは駅という「日常」と美術館やホールという「非日常」を結ぶこの空間。緩やかなスロープに添って図書スペースが配置されている。プロポーザルではこの空間が評価されたという。

根津美術館:隈研吾
都会の喧騒的な「日常」から美術館という「非日常」へ導くアプローチ空間。機能的には茅野市民館のスロープと全く同じ。前面道路に接する敷地のエッジに沿って竹のスクリーンを配し、うまくその空間を確保している。
まつもと市民芸術館:伊東豊雄
松本の中心市街地の狭小な敷地に計画された。ホールへのアプローチ空間が屋外に確保できないため、大ホールの入り口を後方に配して、ホールの側面にその空間を確保するという解決法を伊東さんは採った。市役所に展示された応募案を見たがこのようなプランを提示したのは伊東さんだけだった。
演奏会が終って直ぐに街の喧騒に巻き込まれたら、すばらしい演奏でもその余韻を楽しむことができない。「非日常」から「日常」へゆったりとした空間で結ぶ・・・。
今回取り上げた3つの計画に共通するのは「日常」と「非日常」とを結ぶ空間の確保が難しい条件にもかかわらずきちんと計画されていること。茶室に至る露地にも通じるが、いずれもシークエンスが意識され、行き先が見通せないような演出がなされている。
■ マップラバーとマップヘイター、分子生物学者の福岡伸一さんが「建築雑誌」の今年の9月号に寄稿したコラムによると世の中の人間はこのふたつに分類できるということだ。
マップラバー、すなわち地図好きとは俯瞰的な全体像を把握したからでないと行動を始めないタイプ。これに対してマップへイター、すなわち地図嫌いは自分の行きたいところに行くのに地図を頼りにしない、「通り」の様子を頼りに目的地に到達できるタイプ。
数稿前にまち(町という漢字表記よりひらがなの方がいい)の魅力は一体何によって決まるのだろう、と書いた。郡上八幡と松本はまちの基本的な構成要素が似ていて、個々の要素は松本の方が魅力的ではないかと思うのだが、まちの総体としての魅力はどうも郡上八幡の方が勝っている、というのが私の印象。
どうもマップラバーとマップへイターがまちの魅力を考えるキーワードになりそうな気がする。私はマップへイターをストリートラバーと言いかえたい。福岡さんはこのふたつのタイプに人間は分かれると書いているが、私は人間は実はどちらも好むのではないか、と思う。
で、まちの魅力とはこのふたつの、欲求といったらいいのか、を満足できるかどうかに大いに関係していると思う。すなわち、俯瞰的にまちの全体像が把握できる場所があること、街並み(この場合はひらがなではなくて街がいい)が魅力的なこと。
郡上八幡は小高い丘の上の天守閣からまちを一望できるし、松本は城山と呼ばれるやはり小高い丘から市街地を一望できる。白川郷も函館も神戸も・・・。
樋口忠彦は名著『日本の景観』でまちの全体像が把握できる小高い場所があることを魅力的なまちに欠かせない条件として挙げていたように思う。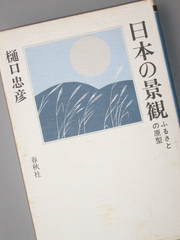
まちの全体像が把握しやすいかどうかはまちの大きさに関係している。ケビン・リンチは『都市のイメージ』で都市の構造が分かりやすいことを魅力的な都市の条件に挙げてはいなかったか。 この点、松本より郡上八幡の方がかなり小規模で全体像が把握しやすい。
街並みはというと、郡上八幡にも松本にも古い街並みが残っているが、どうも郡上八幡の方が、風情というか情緒があるような気がする。情緒などという曖昧なことばを持ち出したくないが、他に適当なことばが見つからない。
まちなかに川が流れているとまち全体の骨格が分かりやすいが、松本にも郡上八幡にも川が流れている。
先日郡上八幡を初めて訪れた際の「松本より魅力的なまちだな~」という印象。それがなぜなのか、少し分かってきたような気がする。
まちの全体像が把握しやすい「俯瞰場」があること。そしてまちが小規模なこと。まち全体の構造が理解しやすい川があること(やはり道路などより川)。街並みに情緒があって魅力的なこと。これらがポイントではないか・・・。
実例に当て嵌めてこの考えの妥当性を帰納するには、実際に訪ねたまちがあまりにも少ない。弘前、角館、萩、岩国、長崎、・・・・、出かけてみたいまちはいくつもある。これからか・・・。

■ 安曇野市内のA保育園に出かける機会がありました。
保育園はごく一般的な平面計画の場合、各年齢の保育室を南面させて、直線的に配置しますから、保育室前面のテラスは「繰り返しの美学」が成立する基本的な要件(直線的に伸びる空間)を満たします。あとは設計者がそれを意識してデザインするかどうか、です。
この保育園のテラスは床が再生木材のデッキ、壁が板張り、屋根は膜構造です。等間隔に並んだ鋼管柱、その頂部の両腕を広げたような斜材が「繰り返しの美学」していますね。
すっきりした構造で、園庭からみると美しいウェーブを描いています。膜屋根の上の外壁は鋼板の立てハゼ張り。モスグリーンが上品で膜の白との対比がきれい(この写真にも写っています)。デザインから設計者の人柄が窺えます。衒いのない素直なデザインでした。


■ このところ多忙で読書をする隙間時間がなかなか無い。今月はまだ読了本が1冊も無い・・・。
過日東京した際、買い求めた『新・建築入門』ちくま新書。 西洋建築史に関するベーシックな知識は欠かせない。隈研吾氏設計の根津美術館や展覧会を観たあと、同氏の著書を買い求めた。
**(前略)二十世紀を代表する建築家ミース・ファン・デル・ローエによる、ガラス箱のような建築もまた、ガラスという透明な皮膜を通じて、外部の自然に建築を従属化させようとした試みに他ならない。** などというくだりを「そうなのかなぁ~」と思いつつ読み進む。
『脳で旅する日本のクオリア』茂木健一郎/小学館
先日、友人から借りた。パラパラと見たがなかなか面白そう。この本は書店で見たことがなかった・・・。週末、一気読みしようと思うが、そんな時間取れるかな・・・。昴さん、返却が遅くなります。m(_ _)m



■ 穂高町(現安曇野市)で撮影しました。撮影年月は不明。用途は外観からリゾートホテル、保養所の類ではないかと思います。
先日この写真を見て気がつきました。そうか、「繰り返しの美学」な構成に惹かれていたんだ! と。当時はそんなことは意識していなかった、というか何に惹かれるのか分析ができていなかったと思います。
回廊のコンクリートの円柱、部屋ごとに造られたバルコニーと緩やかにカーブさせた庇、屋根の煙突(?)、それらのリズミカルな繰り返し。
コンクリートとタイルを組み合わせた外壁のデザインはよくあります。「別にどうってことない、普通のデザインじゃん」という指摘も聞こえてきそうです。
どこかに行く途中でわざわざ車を停めてカメラを向けたという記憶がありますが、繰り返しの美学 に惹かれたんだな、と得心しました。
に惹かれたんだな、と得心しました。
■ 町なかを川が流れていること、町を一望できる小高い場所があること、このふたつは魅力的な町に欠かせない条件だと思う。
松本は町なかを女鳥羽川が流れ、城山からは市内を一望できる。そして、昨日(14日)訪ねた郡上八幡も町なかを吉田川と小駄良川が流れ、町の西側を北から南に貫流する長良川に注いでいる。町の北東になるだろうか、小高い山の頂上にある郡上八幡城からは町を一望できる。
松本と郡上八幡は町の基本的な構造がよく似ている。郡上市(郡上八幡)は郡上郡下7町村の合併で2004年に誕生した。人口およそ45000人の小さな市。
松本から郡上八幡までは高山を経由、東海北陸自動車道を利用しておよそ3時間(160km)、意外に近い。
1 郡上八幡駅
最初に訪ねたのは長良川鉄道の郡上八幡駅。木造の古い駅舎。繰り返しの美学なホームの木柱の連なり。


2 旧八幡町役場
木造の駅舎の後、昭和11年に建てられた庁舎へ。木造2階建て。平成10年に国の登録有形文化財に指定されている。

3 郡上八幡楽藝館
旧医院を公開している。下の写真は内科の診察室だった部屋。

4 蔵の窓
5 米穀店
これぞ繰り返しの美学!! 飛騨古川や高山でも見られる軒先のデザイン。
6 街並み @鍛冶屋町
紅殻格子と袖壁に注目
7 大乗寺の山門(鐘楼門)
この空間構成、秀逸!
境内の紅葉に高揚。

8 錦秋
郡上八幡城に向かう・・・ 急な坂道の途中で
9 郡上八幡城
昭和8年に再建された木造の城
10 郡上八幡には龍が棲んでいた!
11 神農薬師
岩に祠を掘って祀られた薬師如来
12 昼めし
魅力的な町の条件、先に挙げたふたつの条件に加えて美味い郷土料理があること。
朴葉すしと鶏汁ざるそば 美味!!


同行のふたりは飲み友達。感謝、感謝!

路上観察日 091107
御茶ノ水、ここはなんだかエッシャーのだまし絵のような空間だ。
山田守設計の聖橋が妙に高い位置にあるような気がする・・・。
この橋の両側にはちゃんと道路が繋がっているんだろうか・・・。
中央線の電車は聖橋の下を潜ると空中に飛び出してしまうんじゃ・・・。
地下鉄の電車は神田川に次第に沈んで行きそう・・・。
森の緑が波のように押し寄せているかのよう・・・。