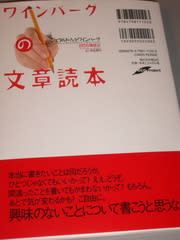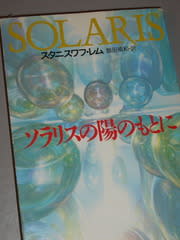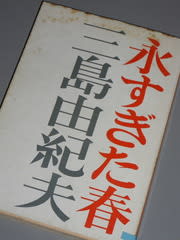
■ 先日、春を感じた日のことを書きました。そのとき春がタイトルについている小説とエッセイとして、思いつくままに島崎藤村の「春」と日高敏隆の「春の数えかた」を挙げました。
その後タイトルに春がつく小説ならもっとあるだろう・・・、と思い浮かんだのが『永すぎた春』でした。40年も前に読んだ小説です。三島由紀夫にしてはライトな恋愛小説だったかな・・・、ストーリーが思い出せません。
この小説を思い出したのも何かの縁かもしれません。『ソラリスの陽のもとに』スタニスワフ・レム/ハヤカワ文庫を読み終えたら再読してみようと思います。
本はいいですね、何十年経っても再会できるのですから・・・。