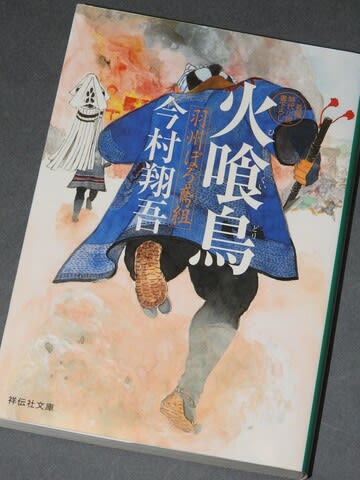■ 拙ブログの前の記事「ブックレビュー 2022.02」に、将来歴史の教科書に太文字で表記されるであろう出来事が続いていると書いた。そこに挙げた福島第一原発の大事故はなんとなく過去の出来事のような捉え方になってしまっている。だが、事故処理は続く、この先まだ何年も何年も・・・。
25日(金)の午後、久しぶりに松本駅近くにある丸善に立ち寄った。買い求めたのは『「廃炉」という幻想 福島第一原発、本当の物語』。 **私事になるが、筆者は福島第一原発事故、通称1F(いちえふ)事故の発生初日から現在まで、民放テレビ局の記者として、一貫して1F事故収束を取材している。**「はじめに」にこのような著者・吉野 実さんの自己紹介がある。これも光文社新書。
読み始めるといきなり次のような記述があった。**高い放射性物質であるデブリ取り出しについては、これまで、わずかなサンプルの取り出しもできず、技術的には全く見通しが立っていない。現場は成算も立たないまま、様々な試みをしているが、大量のデブリ取り出しができる保証はない。
百歩譲って、デブリ取り出しに成功したとしても、現状では、デブリや、原発解体に伴って発生する膨大な廃棄物を、安定的に保管する場所は存在しないし、見つかる目途も全くない。(後略)**(26頁)
デブリってなんだっけ? デブリとは燃料と構造物等が溶けて固まったもの(原子炉建屋の概念図などは東京電力のホームページに掲載されているので検索・確認願います)。
このデブリの取り出しについて著者の吉野さんは無理なんじゃやないか、という見解をお持ちなのだ。本書の帯に**不可能に近い「デブリ取り出し」**とある。
デブリの量は1、2、3号機で合計880トン(もっと多い可能性もある)(45頁) こんなに多いのか、びっくり。
バイアスがかかっていようがいまいがそれは自分のフィルターを通して判断するだけ。本書を読んで、福島第一原発の現状と今後に関する知識を得ることができれば・・・。
余談だが、本書に掲載されている写真や図の大半がカラーだ。美術作品を取り上げるような新書、例えば先日読んだ『日本美術の核心』矢島 新(ちくま新書)などは掲載する絵画がカラーの方が有難い、割高になっても。










 320
320





 480
480 360
360






 280
280
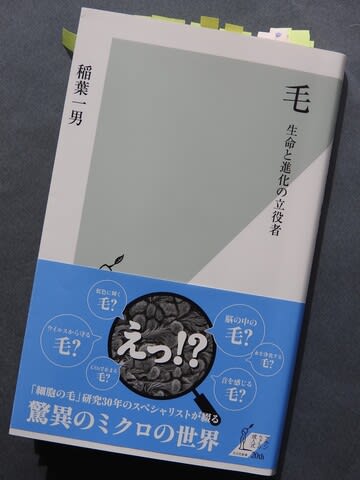 360
360
 520
520 360
360