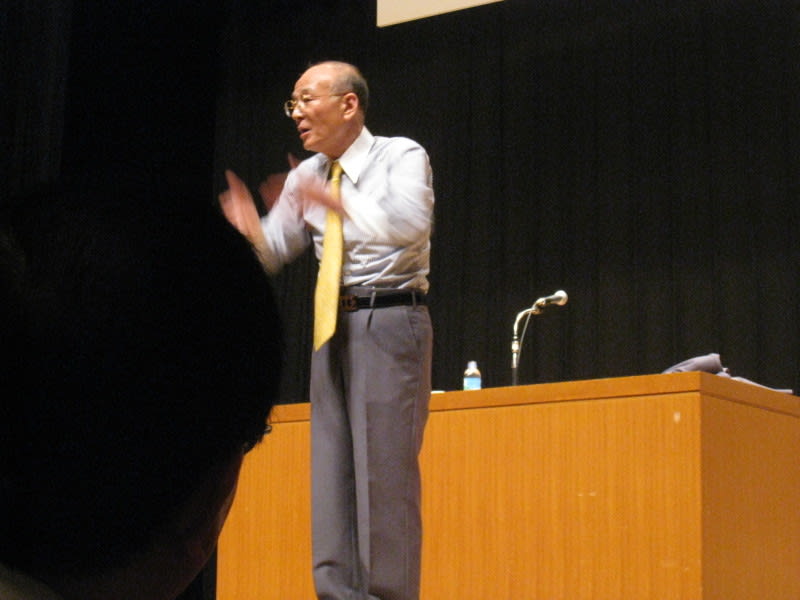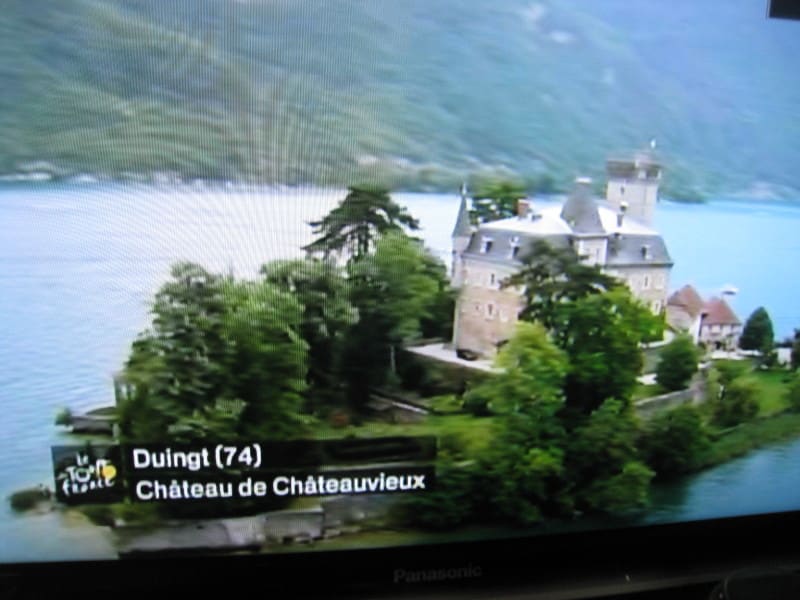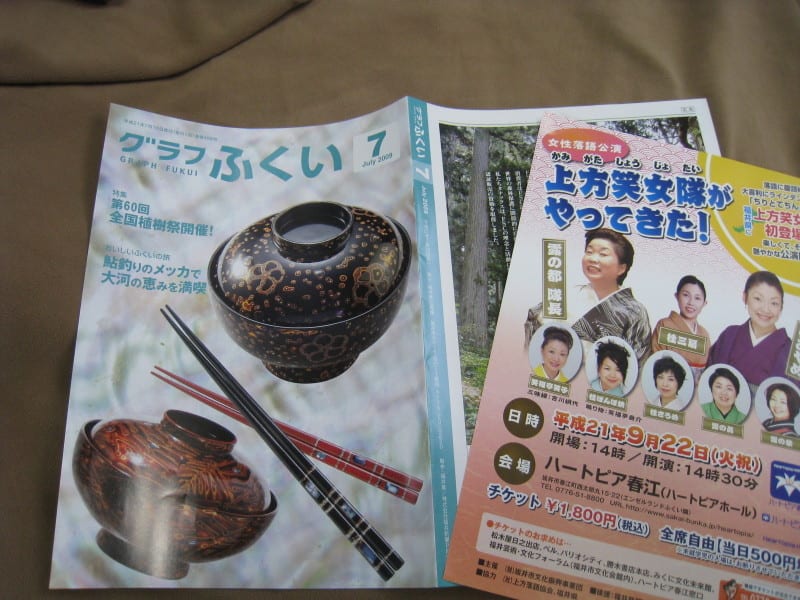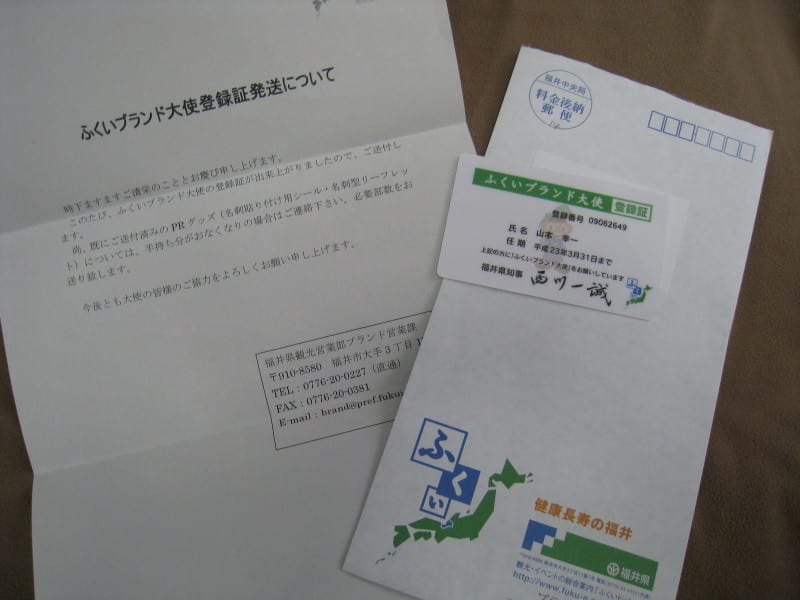夏休みに入り、小・中学校のプールの一般開放が始まった。
学校プールを効果的に活用し、広く市民の健康増進と親子のふれあいや地域コミュニテイ作りの促進のために開放される。
毎年、経験しているが地域の小学校のプールが開放されて、多くの地域住民に利用され大変好評のようである。
しかし、万が一にも事故があってはならないので、利用者の安全確保とプールの管理に万全を期して、
地域の体育指導員の方々で管理指導の役を託されている。
管理指導員の役割は、シーズン初めにプールの機械操作や水質管理、利用状況の監視、救命救急など多岐にわたる。
先日の開放日は、梅雨明けの快晴となり、光化学スモック注意報が出るのでは?と案じたほどの暑い一日であったので、
朝から多くの家族連れや子供たちが、開場を待ちわびたように、来場して楽しんでいたようだ。
我々の時代は、市民プールもまだ普及していないころで、近くの川で泳いでいたのが懐かしいが、
現在は小学校単位で利用できる環境が整っており、格段に進歩していると思う。
全国有数の海水浴場にも恵まれており、いつでもどこでも泳げる物理的環境は整っていると思う。
ところが、プール利用状況の近年の傾向を見ると、減少傾向が見られ、過ってのようにプールが満員状況にはほど遠い。
10年位前は、競泳や宝探しなどを企画してプールは、泳ぎをやりたい子ども達は、ぶつかって泳げないほどであった。
しかし、現在は、泳ぎたい子ども達は、スポーツジムのプールに毎日通ってしっかり泳ぎ、学校プールは、もっぱら遊びの場。
また、子ども達だけで遊びに出かけることも、安全などを考慮して少なくなっているようだ。
家庭でも親子で触れ合いながら休日を過ごそうという、家庭環境もあまり多くないのだろうか?
以前には、父兄会が主体で子供たちをプールで遊ばせるという機会もあったが、いつの間にかなくなっている。
少子高齢化が進んでいる社会環境も、プール利用状況にも現れているように感じている。
この日も、利用者には絶好のコンデイションだったようで、泳ぎの基本を教えたり、一緒に遊んだりの触れ合いもあり、
水に親しんで楽しい一日だったようで、喜んで帰る笑顔を見て管理者としては安堵した。
一日の管理の代償は、手足にしっかりと日焼けのあとが残っていた。




















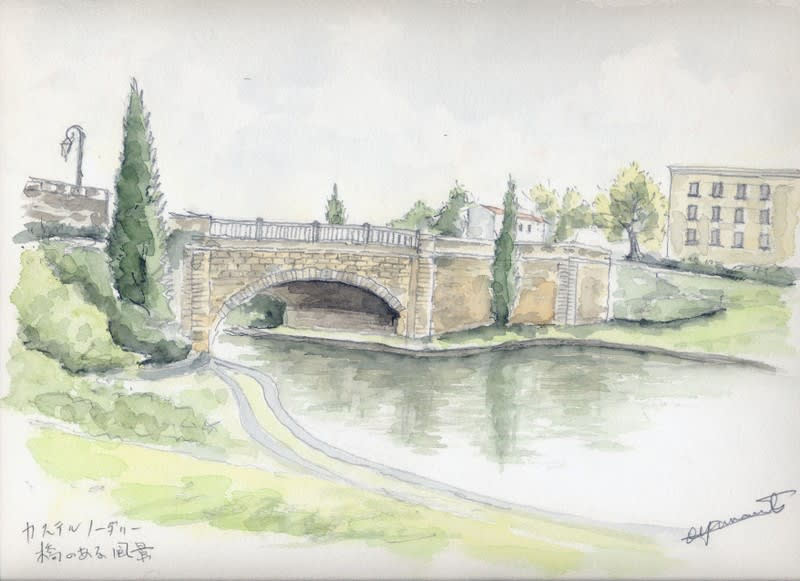














 SUPER」でお馴染みの橋本五郎氏の特別講演会の招待を受けて、参加してきた。
SUPER」でお馴染みの橋本五郎氏の特別講演会の招待を受けて、参加してきた。