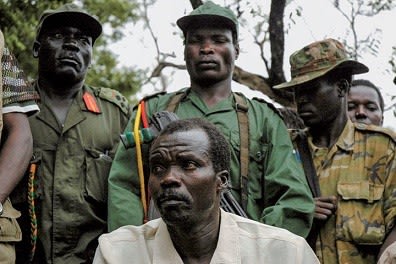(サウジアラビアで自動車を運転する様子をインターネット上で公開したルジャイン・ハズルールさん=2014年11月撮影、AP【12月30日 毎日】)
【サウジアラビア 女性活動家に禁錮刑 バイデン新政権の人権問題への対応をうかがう姿勢】
サウジアラビアでは、実力者ムハンマド皇太子が「改革」路線をとっているものの、あくまでも「上からの改革」であり、政府・王室の権威に逆らうような草の根的な人権活動は認められていません。
そのことを象徴しているのが、女性の自動車運転を解禁するという世界的に注目された「改革」の直前に、同様の要求を行っていた活動家十数人を一斉逮捕したことです。
****サウジ、著名女性活動家に禁錮刑 米新政権との問題化も****
サウジアラビアの裁判所は28日、著名な女性人権活動家のロウジャン・ハズルール氏(31)に禁錮5年8月の実刑判決を言い渡した。同氏の家族が明らかにした。
ハズルール氏は女性の権利擁護を求める少なくとも十数人の人権活動家とともに逮捕され、2018年から拘束されている。
地元紙によると、国の政治体制の変更を試み、国家安全保障を脅かした罪で起訴されていた。条件付きで刑が停止され、来年3月に釈放される可能性があるという。
国連の人権専門家はこれまで、ハズルール氏の起訴を「誤り」と非難。国連人権高等弁務官事務所も今回の有罪判決について「極めて問題だ」とツイッターに投稿し、直ちに釈放するよう求めた。
バイデン次期米大統領はこれまでサウジの人権対応を批判しており、今回の判決はムハンマド皇太子にとって両国関係を巡る問題になる可能性がある。【12月29日 ロイター】
***********************
“条件付きで刑が停止され、来年3月に釈放される可能性がある”ということについては、“サウジの裁判所はハズルールさんへの判決で、判決前の拘束期間を含めて刑期の半分(2年10カ月)が経過後は保釈が可能になるとの条件をつけており、早ければ21年3月に保釈される。サウジ側は21年1月に発足するバイデン政権の出方を見極めた上で、対応を検討するとみられる。”【12月30日 毎日】とのこと。
トランプ政権より人権重視の立場をとると思われるアメリカ・バイデン新政権の出方を見ながら、ハズルールさんの刑期に対処しようということで、「カード」の1枚として利用する構えのようです。
そういう流れで、バイデン新政権の対応が注目されています。
****サウジ女性活動家に実刑 バイデン氏側近は非難、人権重視の姿勢反映****
サウジアラビアの裁判所が女性の権利拡充を訴えていた活動家に実刑判決を言い渡したことに対して、バイデン次期米大統領の側近が「不当な判決だ」と批判した。バイデン氏は対サウジ政策で人権問題を重視する姿勢を示しており、女性の地位向上も焦点の一つになりそうだ。
ロイター通信によると、実刑判決を受けたのは、ルジャイン・ハズルールさん(31)。女性の自動車運転禁止(2018年6月解禁)や、結婚や旅行をする際は男性親族らの許可が必要な「後見人制度」(19年8月一部緩和)の撤廃を訴える運動で中心的役割を果たしていた。
しかし、運転解禁直前の18年5月に当局に拘束され、今年12月28日に「公共秩序を乱した罪」などで禁錮5年8月の実刑判決を受けた。ハズルールさんは上訴する意向だという。
バイデン次期米政権で大統領補佐官(国家安全保障担当)に起用されるサリバン氏はツイッターで「単に世界共通の権利を行使しただけで実刑判決を受けることは、不当であり問題だ。バイデン政権はどこで起きたかに関係なく人権侵害に立ち向かう」と判決を批判した。
米国務省のブラウン首席副報道官もツイッターで「実刑判決の報道を懸念している」と発信したが、サリバン氏の方が非難のトーンが強かった。
バイデン氏は大統領選前の10月に出した声明で、18年にトルコでサウジ人記者カショギ氏がサウジ当局者に殺害された事件を非難して「サウジとの関係を見直す」と表明。「相手国が安全保障上の緊密なパートナーであっても、米国は民主的価値観や人権の問題に優先的に取り組んでいく」との方針を示していた。【同上 毎日】
***********************
ムハンマド皇太子に関しては、カショギ氏暗殺を指示したとの疑惑(多分、事実)がありますが、「安全保障上の緊密なパートナー」の実力者の人権無視の行動にどのように対応するのか、ハズルールさんの処遇に対する反応と合わせて、バイデン新政権の人権問題に対する試金石となりそうです。
【中国 「絶対的な報道の自由は誤り」「中国は国情に合った人権発展の道を歩んでいる」】
人権上の問題を抱える国は上記サウジアラビア以外にも多々ありますが(日本を含めてすべての国は大なり小なりの問題はありますが、特に“目立つ”という意味で)、中国もその代表的な存在。
「報道の自由」という観点では、世界最悪との評価も。
****取材で投獄のジャーナリスト、過去最多274人…中国は47人で2年連続ワースト****
米国の非営利団体「ジャーナリスト保護委員会」(CPJ、本部・ニューヨーク)は15日、取材活動を理由に投獄されているジャーナリストが今月1日時点で、少なくとも274人に上ると発表した。1990年代前半の調査開始以降、最多を記録した。
国別では、中国が47人に上り、2年連続で最も多かった。これにトルコの37人、エジプトの27人、サウジアラビアの24人が続いた。新型コロナウイルスや政情不安に関する報道への締め付けが強化されているという。
CPJは、中国では、新疆ウイグル自治区で罪状が明らかにされないまま投獄されたり、新型コロナに関して政府の立場とは異なる報道を行って逮捕されたりしているとした。
世界で投獄されているジャーナリストの3分の2は、テロリズムなど反国家的な犯罪に関わったとして罪に問われている。エジプトと中米ホンジュラスで少なくとも2人が新型コロナに感染して死亡したという。【12月16日 読売】
*************************
その中国の事態が懸念される案件はいろいろありますが、特に目下の新型コロナに関しては、武漢の実情を報じた市民ジャーナリストの張展氏が懲役4年の判決が出ています。
****武漢で取材の市民記者、年内に初公判 懲役5年の可能性も****
新型コロナウイルスの感染が最初に拡大した中国・武漢で取材、発信していたことから拘束されていた市民ジャーナリストの張展氏の公判が、年内に始まることが分かった。張氏の弁護人が18日、明らかにした。張氏はハンガーストライキを行っており、健康状態が心配されている。
同ウイルスは昨年末、武漢で初めて確認された。中国政府は、初期の流行の隠蔽(いんぺい)や告発者らの口封じを図ったとして批判にさらされている。
元弁護士の張氏は今年2月に武漢入りし、ソーシャルメディア上で自身の実体験を発信。さらに、政府の対応を批判する文章も書いている。
AFPが入手した裁判所の発表によると、張氏は5月に拘束され、「社会秩序びん乱」の罪に問われている。この罪状は、反体制派の抑え込みに頻繁に使われており、有罪と認められれば、最高で懲役5年を言い渡される可能性もある。
張氏の弁護人は今週、上海の裁判所で今月28日に初公判を行うという通知を受け取った。
同弁護人によると、張氏は6月にハンガーストライキを開始。以後、鼻に管を挿入され、強制的に栄養を取らされているという。
ソーシャルメディアで広く拡散している文章の中で同弁護人は、張氏の体調は著しく悪化しており、頭痛やめまい、胃痛に悩まされていると明かしている。「24時間拘束され、トイレに行くにも介助を必要とする」状態だという。(中略)
張氏は武漢における当局の初期対応に批判的で、2月には、政府は「人々に十分な情報提供を行わず、ただ街を封鎖した」「これは甚大な人権侵害だ」とする文章を公開していた。
武漢で取材し当局に拘束された市民ジャーナリストは、張氏をはじめ4人。裁判に臨むのは張氏が初めてとなる。 【12月21日 AFP】
********************
結局、上海の裁判所は28日、懲役4年の判決を言い渡しました。
欧米はこの問題を批判しています。
****米とEU、武漢の市民記者の釈放求める****
米国と欧州連合は29日、中国・武漢から新型コロナウイルスの流行に関する情報を発信し、有罪判決を受けた市民記者、張展氏の釈放を中国に求めた。マイク・ポンペオ米国務長官は、ウイルスの流行の隠蔽(いんぺい)を図っているとして中国政府を批判をした。
元弁護士の張展氏はウイルスの流行初期、謎に包まれた病だった新型コロナウイルス感染症について、現地の情報をネットで発信。5月以降は拘束下に置かれ、28日に禁錮4年の有罪判決を受けた。
ポンペオ氏は中国に対し、張展氏の「即時かつ無条件の釈放を求める」と表明。「中国共産党は、重要な公衆衛生上の情報に関することであっても、同党の公式見解に疑問を投げかける人々の口を封じるためならば何でもすることを改めて示した」と批判した。
張展氏の釈放を求めたEUの外務省に当たる、欧州対外活動庁のピーター・スターノ報道官は、「信頼できる情報筋によると、張展氏は拘束中に拷問や虐待を受け、健康状態がひどく悪化している」と表明。張氏が「適切な医療支援を受けることが極めて重要」だと訴えた。EUは張展氏の他、香港の活動家12人の釈放も要求した。 【12月30日 AFP】
********************
中国・習近平政権は、こうした報道の自由に関する欧米の批判への反発を強めています。
****絶対的な報道の自由は誤り・欧米メディアは中国を滑稽に描く…習氏発言録****
中国の習近平シージンピン国家主席が、欧米などのメディアによる中国報道を批判し、絶対的な報道の自由は誤りであるとの考えを示した発言が、11月に出版された習氏の発言録に掲載された。外国での中国批判報道へ警戒感を示したものとみられる。
2016年2月に開かれたメディア関係者との会合での発言。習氏は欧米メディアを「色眼鏡で中国を見ており、中国を滑稽に描いている」と批判し、欧米などとイデオロギーが異なる場所で街頭での抗議行動やテロが起きれば「民主や自由を勝ち取ろうとする行動だと伝えるだろう」との見方を示した。「いわゆる『報道の自由』の本質を見極めねばならない」とも強調した。
習政権は、香港情勢や新型コロナウイルスへの対応を巡る欧米メディアなどの批判報道が国内に波及する事態を警戒しているとみられる。過去も含めた習氏の報道活動に対する発言を紹介することで、国内での宣伝体制のさらなる引き締めを図る狙いがあるようだ。【12月27日 読売】
***********************
「報道の自由」のあり方に関する議論はさておいても、いまや押しも押されぬ大国となった中国が、なぜにそこまで国内の批判的言動を警戒・恐れるのか・・・「政権は批判されて当たり前」という日本にいる者としては、理解しがたいところがあります。
多少の批判を許したとしても、多くの中国国民は、経済的反映を実現し、国際社会で重きをなすようになった、また、新型コロナに関しても「世界で一番安全な国」になった、共産党の指導をおおむね肯定的に評価しているだろうに・・・。
中国政府は、新型コロナ・武漢に関しては、当時の状況を徹底して隠蔽したいようです。
****武漢を書いたら「売国奴」 作家が直面した冷たい暴力****
新型コロナウイルスで封鎖された武漢にとどまり、日々の暮らしや社会への思いをつづった「武漢日記」をネットで発信した女性作家、方方(ファンファン)さん(65)の作品が中国で出版できない状況になっている。本人が朝日新聞の書面取材に応じ、思いを吐露した。
「私は今、国家の冷たい暴力に直面している。こんな状況が長く続くとは思いたくないが、今はただ、この冷たい暴力がやむのを耐えて待つしかない」
方方さんによると、今年出版予定だった長編小説と、すでに出版の契約書を交わしていた作品の全てについて、複数の出版社から出版見送りの連絡を受けたという。
理由について明確な説明はなかったが、方方さんはこう受け止めている。
「全国各地の出版社が、みな突然私の作品の出版を取りやめた。上から何らかのプレッシャーがあったと考えるのが普通だ」
方方さんは都市封鎖直後の1月25日から3月24日まで、日々の思いを連日ブログに投稿。緊迫する街の空気や、友人の死に接した思いを描いた。政府の対応への疑問や批判も率直につづった60編の日記は「武漢の真実を伝えている」と評判を呼び、読者は中国国内外で1億人以上に達したといわれる。
「当局に目をつけられるのを嫌がり…」
だが4月、日記が「武漢日記」として米国や欧州など外国で出版されることが決まると、一気に風向きが変わった。「金もうけのために中国の恥を外国に宣伝している」「売国奴」など、ネット上には方方さんを攻撃する言葉があふれた。日記を支持した大学教授が処分を受ける事態も起きた。
方方さんの「武漢日記」は米英独仏などのほか、日本でも9月に出版された。
中国の出版関係者によると、中国国内でも日記の書籍化の話が出たことがあったが、4月以降、「武漢日記を出版する米国の出版社の全ての本が中国国内で販売差し止めになる」といううわさが業界に広がった。
実際米国出版社の販売差し止めはなかったが、日記の国内出版は立ち消えとなり、「当局に目を付けられるのをみんな嫌がり、方方作品から各社手を引いている状況だ」と明かす。
「ネットでの誹謗(ひぼう)中傷は今も相変わらずだが、それは気にしなければいいだけのこと。でも、一冊の本も世に出せないというのは、作家として心から悔しく、悲しくてたまらないことだ」
方方さんは取材に対し、こう続けた。
「閉じ込められた暮らしの中で、一個人が感じたことを全て書くのは許されないことなのだろうか?病人や死者に同情するのはいけないことなのだろうか?政府の対応が適切でなかったという親身な批判の声すら許されないのだろうか?」
そして、今の中国社会を覆う空気に対し、疑問を投げかける。
「私たちの言論空間はなぜこんなに狭くなってしまったのだろうか?中国は今や新型コロナの感染を完全にコントロールできている。それなのに、一体何を怖がっているのだろうか?」【11月28日 朝日】
****************************
中国・習近平政権の人権抑圧的対応は新型コロナ報道にとどまりません。
****「国家安全」盾に接見拒否 中国、人権派弁護士ら拘束1年****
中国で昨年12月、国家政権転覆扇動容疑などで一斉に摘発された人権派弁護士らが、弁護人との接見や家族との手紙のやりとりができない状態が続いている。支援者によると、「国家の安全保障」を理由に容疑者や被告の人権が大幅に制限される事例が増えている。
「当局は法律を思うがままに解釈している」。拘束が続く丁家喜弁護士(53)の妻、羅勝春さん(52)は電話取材にこう訴えた。
米国在住の羅さんは昨年12月26日、北京の友人からのショートメールで丁氏が警察に連行されたことを知った。ハワイで合流し新年を一緒に過ごす計画について、2時間前に電話で話したばかりだった。以来、連絡がとれないままだ。
弁護士に何度も接見を掛け合ってもらったが、「捜査に支障がある」と許可されなかったという。夫に宛てた20通近い手紙も、警察は「上司の許可が必要」などとして渡すのを拒んでいるという。警察から届いたのは今年6月、丁氏の姉が受け取った「国家政権転覆扇動容疑で正式逮捕した」との通知だけだ。
「健康なのか、ひどい仕打ちを受けていないのか、何一つ情報はない。毎日焦りと不安の中で暮らしている」と羅さんは語る。
昨年12月26日に始まった一斉摘発では、丁氏のほか人権派弁護士や改革派の学者ら十数人が国家政権転覆扇動容疑で拘束された。多くは同月に福建省アモイであった会合に参加。一時拘束された弁護士によると、警察はこの会合に「海外勢力」から資金の提供があったと疑っていたという。
多くは釈放されたが、丁氏と法学者の許志永氏(47)は逮捕され、今も拘束が続く。許氏と親しい弁護士によると、許氏も2月に拘束されて以来、弁護人との接見が許されず、親族らの手紙にも返信がない。
一度は釈放された常イ平弁護士も10月になって再び拘束され、弁護人の面会は許可されていない。
■国連報告者「人権を無視」
人権を守る活動に関わる人々の状況を調べる国連のメアリー・ローラー特別報告者は16日に声明を出し、中国の弁護士らが国家の安全保障を口実に拘束されたり拷問を受けたりしていると指摘。常氏の事例に触れつつ、「当局は人権擁護者を再び拘束し、国家安全保障の脅威に仕立てた。人権無視を衝撃的な形で示した」と批判し、弁護士らの即時釈放を求めた。
中国の刑事訴訟法は容疑者や被告人が弁護人と接見する権利を認める一方、「国家の安全に危害を与える事件」では接見に捜査機関の許可が必要と規定。近年、これを理由に接見を拒む例が増えていると複数の弁護士が口をそろえる。
習近平(シーチンピン)指導部は、米欧諸国が人権派弁護士やNGOへの支援を通して中国の政治体制を揺さぶろうとしていると警戒し、「国家安全保障」の名の下、市民運動などへの弾圧を強めた。米欧への根深い不信は香港への対応にも表れており、香港国家安全維持法施行後、外国と結託したなどとして著名民主活動家らを相次ぎ逮捕、起訴している。
中国も未批准ながら署名した国際人権B規約は、すべての人に自分が選んだ弁護人に連絡する権利があると定めている。しかし、人権より国家や体制の安定を優先する習指導部の構えは鮮明だ。
世界人権デーだった今月10日、外務省の華春瑩報道局長は定例会見で、各国が中国の人権状況に懸念を寄せていることに「中国は国情に合った人権発展の道を歩んでいる」と反論した。【12月19日 朝日】
********************
「中国は国情に合った人権発展の道を歩んでいる」・・・「なんじゃ、それ?」ってところですが・・・。
もっとも“高須院長が村上春樹氏の発言を批判「先生は日本人ですか?」”【12月27日 東スポWEB】という日本の風潮も、“武漢を書いたら「売国奴」”と同じ発想です。