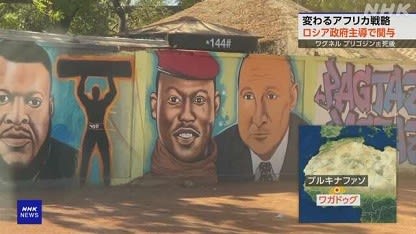(チャドのスーダン難民は人道支援がなければ生きていけない【6月19日 国連WFP】)
【スーダンで続く「忘れられた紛争」】
2023年4月15日に始まったスーダンでの紛争・・・国軍(SAF)と準軍事組織「即応支援部隊」(RSF)の統合問題を背景に、軍が主導する統治評議会議長のトップ、ブルハン国軍最高司令官と、同副議長でRSF司令官のダガロ氏の権力闘争としての武力衝突が発生・・・は、パレスチナやウクライナでの戦争とは違って、それらの戦争に匹敵する犠牲者を出しながらもあまりメディアに取り上げられることなく続く「忘れられた紛争」となっています。
「忘れられた」かどうかに関係なく、紛争の戦火から逃げまどい、飢えや医療崩壊に苦しむ住民にとっては等しく悲劇・地獄であり、「忘れられた紛争」の場合は人道支援も行き届かないというということでより悲惨な状況にもなります。
死者は推計で1万5千人にのぼるとされていますが、実際にはその10~15倍に上る可能性があるとの見方(バイデン米政権のスーダン特使トム・ペリエロ氏)もあります。
メディア報道があまりないので詳細はわかりませんが、戦闘の方は相変わらず続いているようです。
****スーダン中部の村で虐殺か 準軍事組織が襲撃、「百人」死亡****
国軍と準軍事組織「即応支援部隊(RSF)」の戦闘が続くアフリカ北東部スーダンの活動家団体は5日、中部ジャジーラ州の村をRSFが襲撃し、民間人を虐殺した疑いがあると発表した。2回の襲撃で約100人が殺害されたとしている。
RSFは声明で村周辺への攻撃を認めたものの、民間人殺害には触れなかった。
国軍とRSFの戦闘は昨年4月に始まり、1万5千人以上が死亡。停戦交渉は停滞し、収束の兆しは見えていない。ロイター通信によると、RSFは昨年12月に同州の州都ワドマダニを掌握後、州内で小さな村への襲撃を繰り返している。
団体はワドマダニを中心に活動する「ワドマダニ抵抗委員会」。【6月6日 共同】
*******************
RSFは2000年代にスーダン西部ダルフールで、村々を焼き払い、人々を虐殺・強姦して「最悪の人道危機」と呼ばれる状況をもたらした民兵組織「ジャンジャウィード」が母体となっています。
RSFの集団殺害や略奪に対し、国軍は救援要請に応じなかったとも。【6月6日 時事より】
国連人道問題調整事務所(OCHA)によると、6月7日までに民間人への攻撃は1400件にのぼり、1万5550人が犠牲になったとのことです。
軍トップを狙った攻撃も報じられています。
****スーダン軍首脳暗殺未遂か 基地に攻撃、5人死亡 「即応支援部隊」と交戦中****
アフリカ・スーダンで準軍事組織「即応支援部隊(RSF)」との内戦を続ける国軍は31日、北東部の基地に無人機攻撃があり、5人が死亡したと発表した。
ロイター通信によると、基地では同日、軍トップのブルハン統治評議会議長が出席した式典が行われており、暗殺を狙った可能性がある。ブルハン氏は無事とみられる。
犯行声明は出ていない。RSF関係者はロイターに攻撃を否定した。停戦の仲介を目指す米政府は8月14日からスイスで開く協議に軍とRSFを招待しているが、激しい戦闘が続いており、双方が出席するかどうかは不透明だ。
AP通信によると、攻撃が行われたのは式典終了後だったという。
内戦は昨年4月に始まり、国内外の避難民は1000万人を超えた。国内では食料不足など深刻な人道危機も起きている。【7月31日 産経】
*******************
上記記事によれば、一応今月14日からアメリカ主導の協議は予定されているようです。あまり期待はできないようですが。
【人口の20%に当たる1000万人以上が自宅を追われ国内外に避難】
こうした紛争が長期化するなかで、1万5千人、あるいはその10~15倍の犠牲者だけでなく、国内外に逃れた避難民は1千万人を超えています。
****内戦のスーダン、国民の20%が国内外に避難 食料危機も深刻化*****
国際移住機関(IOM)は16日、スーダンで昨年4月に内戦が始まって以来、人口の20%に当たる1000万人以上が自宅を追われたと明らかにした。世界最大の避難危機が悪化し続けている。
また、人口の半数が内戦で食料危機に直面し、人道支援が必要な状況で、その規模は世界最多だと指摘した。
内戦開始以来、220万人以上が国外に逃れ、約780万人が国内で避難している。このほか、過去の内戦で既に280万人が避難しているという。
国連の専門家らは、支援物資輸送が困難なダルフールを離れる最大の理由が暴力から食料危機に変わっていると指摘。
避難民の半数を占めるダルフールからの難民をチャドで訪問した世界保健機関(WHO)の担当者は「私が会った難民は全員、避難の理由に飢えを挙げた。アドレに到着したばかりの女性は、ダルフールで生産していた食料は全て戦闘員に奪われたと報告した」と述べた。【7月17日 ロイター】
また、人口の半数が内戦で食料危機に直面し、人道支援が必要な状況で、その規模は世界最多だと指摘した。
内戦開始以来、220万人以上が国外に逃れ、約780万人が国内で避難している。このほか、過去の内戦で既に280万人が避難しているという。
国連の専門家らは、支援物資輸送が困難なダルフールを離れる最大の理由が暴力から食料危機に変わっていると指摘。
避難民の半数を占めるダルフールからの難民をチャドで訪問した世界保健機関(WHO)の担当者は「私が会った難民は全員、避難の理由に飢えを挙げた。アドレに到着したばかりの女性は、ダルフールで生産していた食料は全て戦闘員に奪われたと報告した」と述べた。【7月17日 ロイター】
*********************
IOMによれば、避難民の半数は18歳未満の子どもとのことです。
【横行する性暴力】
こうした紛争につきものの性暴力も横行しています。
****スーダン内戦で性暴力横行 9歳から60歳の262人が被害 ヒューマン・ライツ・ウォッチが報告****
国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」は、内戦が続くアフリカ・スーダンで女性に対する性暴力が横行しているとする報告書をまとめました。被害者は9歳から60歳に及びます。
スーダンでは去年4月に、軍と準軍事組織「RSF」との戦闘が始まって以来、これまでに1万5000人以上が死亡し、人口の2割にあたる1000万人以上が避難を強いられています。
「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」は29日、スーダンの医療従事者ら42人の証言をまとめた報告書を公表し、首都ハルツームなどでRSFによる性暴力が横行していると明かしました。
報告書によりますと、性暴力や集団暴行の被害者は9歳から60歳までの少女や女性たちで、戦闘が始まってから今年2月までの間で少なくとも262人にのぼります。
多くの女性が性暴力により深刻なけがを負っていて、少なくとも4人がけがが原因で亡くなったということです。
さらに、家族の前で繰り返し暴行された母子の被害や、性暴力により妊娠しても適切な医療処置が受けられず、人工妊娠中絶が叶わなかったケースなどが多数、報告されています。
ヒューマン・ライツ・ウォッチはRSFに申し立てを行ったものの適切な対応は取られなかったとしていて、「国際社会は、スーダンおよびスーダンからの難民を受け入れている近隣諸国への性暴力対策資金を増額すべきだ」と訴えています。【7月31日 TBS NEWS DIG】
スーダンでは去年4月に、軍と準軍事組織「RSF」との戦闘が始まって以来、これまでに1万5000人以上が死亡し、人口の2割にあたる1000万人以上が避難を強いられています。
「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」は29日、スーダンの医療従事者ら42人の証言をまとめた報告書を公表し、首都ハルツームなどでRSFによる性暴力が横行していると明かしました。
報告書によりますと、性暴力や集団暴行の被害者は9歳から60歳までの少女や女性たちで、戦闘が始まってから今年2月までの間で少なくとも262人にのぼります。
多くの女性が性暴力により深刻なけがを負っていて、少なくとも4人がけがが原因で亡くなったということです。
さらに、家族の前で繰り返し暴行された母子の被害や、性暴力により妊娠しても適切な医療処置が受けられず、人工妊娠中絶が叶わなかったケースなどが多数、報告されています。
ヒューマン・ライツ・ウォッチはRSFに申し立てを行ったものの適切な対応は取られなかったとしていて、「国際社会は、スーダンおよびスーダンからの難民を受け入れている近隣諸国への性暴力対策資金を増額すべきだ」と訴えています。【7月31日 TBS NEWS DIG】
*********************
ノーベル平和賞を受賞したコンゴ民主共和国のデニ・ムクウェゲ医師も指摘しているように、紛争においては「武器」としての性暴力が横行します。
****“戦場の武器”としての性暴力****
取材から浮かび上がってきたのは、個々の女性を痛めつけることに加えて、家庭を破壊し、地域社会を崩壊させる性暴力の卑劣さです。
武装グループは、性的な欲望を満たすこと以上に住民たちに恐怖を与え、屈服させるために女性たちを襲っています。銃や弾薬も使わずに、力を誇示する手段として、性暴力がまさに“戦場の武器”になっているのです。【NHK「“戦場の武器”性暴力の根絶を ノーベル平和賞で世界に訴え」】
********************
【チャドや南スーダンなど周辺国にも影響】
難民が周辺国に押し寄せることで、周辺国にもその影響が及びます。
****急速に深刻化する飢餓と物価高 スーダン周辺国の難民危機に対する取り組み****
チャド国境の町アドレの難民キャンプでは、祖国スーダンのポピュラーな民族音楽がスピーカーから繰り返し流れる中、アフマットさんが足踏みミシンに青い布を送り込んでいます。小さな木が、灼熱の太陽をかろうじて遮っています。
「このキャンプで私にできるのは仕立ての仕事だけです」曲に合わせて頭を揺らしながらこう話すのは35歳の縫製職人、アフマットさん(安全上の理由から名字は非公開)です。「持ち込まれた布をスーダンの民族衣装や、シャツ、ズボンに仕立てます」
アフマットさんが祖国を揺るがす紛争から逃れてチャドに避難したのは、この20年で2度目です。スーダンに平和が戻ることを願いつつも、当分は難しいのではないかとアフマットさんは考えています。
「私の子どもたちが学校に通えるよう、安定した国に住む必要があります」とアフマットさんは話します。
スーダン危機が長引く中、その影響は近隣諸国にも及んでいます。戦争により国外で暮らすことを余儀なくされた200万人を超えるスーダン避難民の半数以上が、チャドと南スーダンに住んでいますが、これらの国でも既に飢餓が深刻化しています。
この地域は8月まで雨季が続きます。道路がぬかるみ、人道支援物資の輸送が困難になるなど、食料不安のリスクが高まっています。
国連WFPは、拡大する食料不安に対応する中、非常に大きな課題に直面しています。例えばチャドでは、難民を含む200万人以上の人びとに、雨季の緊急支援を提供することを目指しています。しかし、資金が逼迫しており、特に南スーダンでは、最も深刻な飢餓の状態にある人への対応で精一杯の状況です。
国連WFPのチャド事務所代表のエンリコ・ポーシリは「リソースが限られている中、チャドで危機的状況にあるコミュニティー内で緊張が高まらないよう安定を維持するためには、適切な支援を遅滞なく広く届けることが非常に重要です。気候変動の打撃、安全保障、経済危機の影響が複合的に絡み合う中で、増大する人道ニーズを将来的に縮小していくためには、レジリエンスへの大規模な投資も必要です」と言います。
より大きな危機への食料支援
南スーダンではすでに約700万人が急性食料不安かそれ以上の深刻な飢餓の段階に直面しており、このうち70万人近くがスーダンから逃れてきた戦争避難民です。スーダンの東ダルフール州から避難してきたザハラさん一家のように、今も毎週何千人もの人が、飢えとトラウマを抱え、国境を越えて流入しています。
「3度目の空爆の後、避難しようと決めました」4児の母ザハラさんは、1歳2カ月の娘、ムーナちゃんを腕の中であやしながら言います。「国境にたどり着くまで2日かかりました。容器に入れた水と、子どもたちのためのビスケットを持って出ましたが、ようやく到着した時、子どもたちは本当にお腹をすかせていました」
それは幼いムーナちゃんにとって過酷な道のりでした。南スーダンの北西部にあるウェドウェイル難民居住地に着くと、ザハラさんはムーナちゃんを保健所に連れて行きました。そこでムーナちゃんは栄養不良と診断されました。
その後、国連WFPの栄養強化食品により体重が増え、再び遊べるようになりました。しかし、人があふれかえる難民キャンプでは、今後大雨となり、水系感染症が拡大する恐れがあります。
問題はそれだけではありません。スーダンでの戦闘で、南スーダンにとって非常に重要な石油の輸出が中断し、経済を大きく悪化させています。南スーダンポンドが60%急落し、食料や燃料の価格は高騰しています。
国連WFPの予測によると、同国の経済危機により、主食の入手が困難になり、さらに50万人の人びとが中程度から重度の飢餓に追い込まれる可能性があります。
「経済危機が起きる前は、子どもたちは1日2回食事ができていましたが、今は無理な状況です」首都ジュバでは、この町出身のメアリー・イケさんが、何か口にできるものを市場で買いながら、こう言います。「子どもたちは朝起きてから夜まで何も食べるものがありません。状況は悪くなるばかりです。子どもが6人いるので、食べさせるのも大変です」
2023年4月にスーダンの紛争が勃発して以来、国連WFPの南スーダン事務所はこれまでに国境を越えた戦争避難民55万7000人近くに支援を行い、現在も流入する人々の支援を続けています。しかし、多くの状況が重なっており、食料不安が最悪の状態に陥る危険性があります。
「南スーダンではすでに人道危機が長期化しており、状況は急速に悪化しています」国連WFPの南スーダン事務所代表のメアリー=エレン・マクグローティーは言います。「私たちが恐れているのは、スーダンの戦争による壊滅的な影響が続き、すでに急性食料不安の状態にある地域にさらに洪水の危機が迫り、飢餓と栄養不良がかつてない水準となることです」
さらに続けて、「深刻な飢餓と栄養不良の波を食い止めるためには、スーダンの停戦と南スーダンの社会的セーフティーネットの強化が必要です」と話しました。
難民が急増
チャドでも食料不安の危機が高まり、雨季が迫る中、事態はさらに悪化すると見られます。この時期、推定340万人のチャド人や難民が深刻な食料不安に直面すると予想され、気候変動の打撃、食料や燃料費の高騰、そして難民危機によって飢餓が深刻化しています。
この14カ月間に、およそ60万人のスーダン難民がこの乾燥したサヘル地域の国に流入し、既にアフリカで最も多くの難民を受け入れている国の一つであるチャドでは、亡命希望者の数が倍増しています。
そのほとんどは、難民によって形成されたチャド東部の39カ所の難民キャンプに住んでいます。縫製職人のアフマットさんのように、多くの人が飢えとトラウマの重荷を背負っています。
「スーダンでは非常に長い間、戦闘状態が続いています。2023年に勃発した戦闘は特に激しいものでした」と話すアフマットさんは、スーダンの西ダルフールの州都エル・ジェニーナ出身です。20年前、最初のダルフール紛争が勃発した時も、アフマットさんは10代でチャドに避難しました。
その後祖国に戻り、エル・ジェニーナで名を知られる仕立屋となりました。電動ミシンを数台、自家用車、そしてバイクを2台所有していました。ですが、攻撃ですべてを奪われ、工房も家も焼き払われました。
「ほとんどの人が家で襲われ、家財を盗まれました」とアフマットさんはエル・ジェニーナでともに暮らした人びとについて語ります。「チャドに向かう途中で多くの人が殺されました。道は多くの死体で覆い尽くされていました」
アフマットさんをはじめ、チャドに住む難民にとって人道支援は頼みの綱です。国連WFPなどの調査によると、多くの難民、そして受け入れ地域の住民が、食料消費レベルが低い、またはボーダーラインの水準にあります。子どもたちの半数近くが貧血に苦しんでいます。
「ここでの生活は楽ではありません」とアフマットさんは言います。
自分の子どもたち、そしてアフマットさんが仕事場にしている屋外の作業場の周りで遊んでいる子どもたちの将来を心配しています。
「私たちはアッラーの救いを待ち望んでいます」とアフマットさん。「いつか私たちの生活が改善する日が来ることを願います」【6月19日 国連WFP】
******************