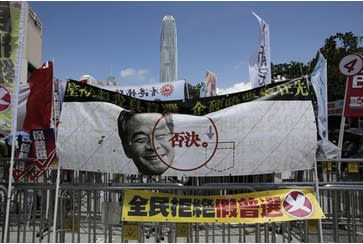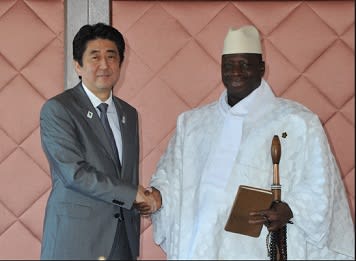(1月18日、エルドアン大統領と石井国土交通大臣の会談が首都アンカラの大統領府総合施設で行われました。
トルコが建国100周年となる2023年の完成を目指している巨大プロジェクト「チャナッカレ1915年橋」の建設を行う企業を選ぶにあたり、石井大臣は日本企業参加をアピールしたようです。
国際入札の締め切りは1月26日で、トルコでのつり橋建設の経験がある日本の企業と韓国や中国の企業の競争となっています。【1月20日 TRTより】)
【強力な権限を有する大統領制へ突き進むエルドアン大統領】
「新しい時代の始まりになるだろう」・・・・話題のアメリカ・トランプ新大統領ではなく、トルコ・エルドアン大統領の昨年12月の発言です。
昨年7月のトルコ・クーデター未遂後、首謀したとされるギュレン派だけでなく、エルドアン政権に批判的なメディア・野党勢力、クルド系勢力などを対象に続けられる大規模な“粛清”、イスラム国(IS)やクルド系がん政府勢力による頻発するテロ、分断される国民世論、強権姿勢を強める政権への欧米諸国の批判等については、1月7日ブログ「トルコ 政府批判を許さないエルドアン政権 “テロ地獄”更に悪化の懸念も”」http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20170107でも取り上げたところです。
エルドアン大統領は、すでに現在においても十分すぎるほどの権力を行使しているように見えますが、本来は現行のトルコ政治システムにおける大統領権限は限定的であることから、名実ともに強力な権限を有する大統領制への変更のための憲法改正を進めています。
****トルコ国会が改憲案承認、大統領権限を大幅に拡大 国民投票へ****
トルコ国会(定数550)は21日未明、レジェプ・タイップ・エルドアン(Recep Tayyip Erdogan)大統領の権限を大幅に拡大する憲法改正案を承認した。今年4月に改憲の是非を問う国民投票が行われる見通しとなった。
深夜に開かれた議会で、改憲案は賛成339、反対142で承認された。賛成票は憲法改正を最終承認する国民投票を行うために必要とされている全議員の5分の3に当たる330票を上回った。
トルコは大統領が国家元首だが議院内閣制を採用しており首相の権限が強い。改憲案は現代トルコで初めて大統領に行政権を持たせる内容で、広範囲に影響を及ぼすとして論争を呼んでいた。
改憲案では大統領が閣僚任免権を持ち、トルコ史上初めて首相が廃止される代わりに1人以上の副大統領が置かれる。憲法が改正されれば議会選と大統領選が同時に行われることとなり、改憲案は最初の選挙の投票日を2019年11月3日と定めている。
大統領が非常事態を宣言できる条件も緩和されるほか、当初宣言できる非常事態の期間も現行の12週間から6か月に延長される。
国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチのトルコ代表、エマ・シンクレアウェブ氏はトルコの改憲案は米国やフランスなどの憲法と異なり、大統領の権力をチェックする機能がないと指摘。
トルコ弁護士連合会のメチン・フェイジオール会長はトルコをオスマン帝国時代に引き戻すものだとして改憲案を厳しく批判している。【1月21日 AFP】
*******************
憲法改正案を審議する国会は“乱闘騒ぎ”の大荒れともなりました。
****トルコ議会で乱闘、議員2人負傷 改憲案の審議中に****
トルコ議会で19日、大統領の権限を強化する憲法改正案の審議中に支持派と反対派の議員同士による乱闘騒ぎが起き、少なくとも議員2人が負傷した。現地メディアが報じた。
報道によると、負傷したのはクルド系主要政党の野党・国民民主主義党(HDP)の議員と与党・公正発展党(AKP)の議員各1人ら。(中略)
事の発端は、無所属のアイリン・ナズルアカ議員が改憲案への抗議として、議場の壇上で自分の手首を手錠によってマイクに結び付け、その場に1時間以上にわたって居座ったことだった。
地元メディアは、与党議員らがナズルアカ議員を追い立てようとしたところ、HDPと野党・共和人民党(CHP)の議員らがナズルアカ氏を擁護しようと駆け寄り、殴る蹴るの乱闘に発展したと伝えている。
日刊紙ヒュリエト(Hurriyet)によると、腕と脚に義肢を使用している車いすのCHP議員、サファク・パベイ(Safak Pavey)氏が床に投げ出され、同僚議員らに助け起こされる一幕もあった。【1月20日 AFP】
*****************
クルド系反政府組織PKKに関与しているとして、エルドアン政権による粛清の“標的”ともなっているクルド系主要政党の野党・国民民主主義党(HDP)ですが、党首は現在逮捕・拘束されています。
****クルド系党首に最大142年求刑=「テロ組織運営」―トルコ検察****
トルコの検察当局は17日、反政府武装組織クルド労働者党(PKK)との関係を疑われ逮捕されたクルド系政党・国民民主主義党(HDP)のデミルタシュ共同党首に対し、禁錮43〜142年を求刑した。地元メディアが伝えた。
エルドアン大統領に批判的なことで知られるデミルタシュ氏は、「テロ組織を運営した罪」や「暴力や憎悪を扇動した罪」などに問われているという。同氏はPKKとの関係を否定し、政治的動機に基づく逮捕だと非難していた。 【1月18日 時事】
********************
“敵”をつくろことで、強い指導力(別名“強権”)をアピールする政権への国民の求心力を高めるというのは、多くの権力の常套手段でもありますが、エルドアン大統領もその路線を進んでいます。
********************
2015年6月、AKPは総選挙で敗北し13年ぶりに過半数を割り込んだ。背景には強権化を進めるエルドアンへの拒絶感があったとされる。
この事態を受けてエルドアンは危機的状況を自ら作り出す賭けに出る。それまでのクルド人組織への融和策、ISILへの傍観策を改め、両勢力に軍事的な攻撃を加えた。
その結果、国内でテロが頻発するなど治安が悪化するが、人々が安定を求めた結果AKPへの支持は広がり、2015年11月の再選挙ではAKPが過半数を獲得した。”【ウィキペディア】
********************
“危機的状況を自ら作り出す賭けに出る”というほど明確な意図があったかどうかは知りませんが、危機を訴えることで強権行使を正当化する流れにあります。
その結果として国内緊張の高まりから、前回ブログでも取り上げたような現在の“テロ地獄”があり、また、昨年の“クーデター未遂”もあった訳ですが、そことが更にエルドアン大統領を“権限強化”の方向に駆り立てているように見えます。
****改憲で大統領の基盤強化目指す=クーデター未遂から半年―トルコ****
トルコで昨年7月に起きたクーデター未遂事件から15日で半年。エルドアン政権は、事件の黒幕とみている在米イスラム指導者ギュレン師の関係者をはじめ、反政府派の大規模な取り締まりを続けている。
一方、エルドアン大統領の権力基盤をより強固なものとするため、大統領の権限強化を柱とする憲法改正に向けた手続きが進められている。
エルドアン政権はこれまで、昨年7月15日の事件を受けて発令した非常事態宣言を2回延長し、軍人や警官、司法当局者ら4万人以上を逮捕。10万人以上を解雇や停職処分とした。
エルドアン大統領は昨年末の演説で「法的手段を使って、国家機関やNGO、企業に潜入した(ギュレン師を支持する)メンバーを一掃する」と強調。しかし、大規模摘発により治安維持能力が低下し、過激派組織「イスラム国」(IS)やクルド人勢力によるテロ事件への対応が後手に回っている印象はぬぐえない。
こうした中、国会では大統領権限を強化するための改憲案の審議が行われている。国会で承認されれば、4月にも改憲の是非を問う国民投票が実施される。
「新しい時代の始まりになるだろう」。エルドアン大統領は昨年12月、自身が実権を握るイスラム系与党・公正発展党(AKP)が国会に改憲案を提出すると、こう語った。
首相を11年間務め、2014年夏に大統領に就任したエルドアン氏はかねて、米国やフランスのように、行政権を大統領に集中させる制度実現を悲願としてきた。
18項目の改正を目指す法案では、現在は象徴的な存在の大統領を行政の唯一の長と位置付け、首相職を廃止するほか、出身政党の党籍維持や党首との兼任を認める。大統領任期は2期10年となり、19年の施行を受けて29年まで大統領職にとどまることができる算段だ。
しかし、その道のりは容易ではない。今月11日、国会での審議中、大統領の独裁化を危惧する中道左派野党の共和人民党(CHP)とAKPの議員の間で乱闘が発生。
国民投票に掛けられた場合、過半数の支持を得る必要があるが、AKP支持者の中でも反対の声が少なくなく、「トルコ型大統領制」を実現できるかは不透明だ。【1月14日 時事】
*******************
【ロシアと強調 さらにトランプ新政権にも期待】
外交面では、ロシアとの関係強化が目立っています。ロシアと強調してのシリアでの停戦・和平交渉も進めていますが、ISへの合同空爆も行っています。
****ロシアとトルコ IS拠点に初めて合同で空爆****
ロシアは、シリアにある過激派組織IS=イスラミックステートの拠点に対する空爆を、初めてトルコと合同で行ったと発表し、アメリカのトランプ次期大統領にIS対策で連携を呼びかける狙いがあると見られます。
ロシア軍参謀本部のルツコイ作戦総局長は18日、モスクワで記者会見を開き、シリアにある過激派組織ISの拠点に対する空爆を、初めてトルコ軍と合同で行ったと発表しました。
空爆に参加したのは、ロシア軍の戦闘爆撃機など9機とトルコ軍の戦闘機8機で、ISが主要な拠点としている北部の都市、バーブを攻撃しました。
ルツコイ作戦総局長は、ISの施設36か所を破壊したと述べたうえで、「ロシア軍とトルコ軍の合同作戦が非常に有効だということを示した」と、成果を強調しました。
シリアの内戦でアメリカは反政府勢力を支援しアサド政権を支援するロシアと対立してきましたが、トランプ次期大統領はロシアとの関係改善に強い意欲を示しています。トルコも反政府勢力を支援してきましたが、先月、ロシアとともに停戦を仲介しました。
ロシアとしては、これに続いてトルコと合同で対IS作戦を実施し成果を強調することで、今週20日に就任するトランプ次期大統領にIS対策で連携を呼びかける狙いがあると見られます。【1月19日 NHK】
*********************
アサド政権の処遇については、ロシアが求める存続を認める方向にトルコも舵を切りつつあるのでは・・・ということは、かねてより指摘されているところです。
トルコ側の見返りは、シリア北部のクルド人勢力への強硬姿勢をロシアに容認させる・・・といったあたりでしょうか。
強権姿勢を強めるエルドアン政権はオバマ政権末期にはアメリカとの関係が悪化しましたが、上記のようなロシア協調のシリア・IS対策にはアメリカ・トランプ新政権も乗ってくるのでは・・・との期待があります。
****トルコ大統領、対米修復狙う 米次期政権発足の「追い風」期待、対クルド支援は見直し促す****
トルコのエルドアン大統領は、トランプ次期米大統領に熱い期待をかける。
「トランプ氏とは(中東)地域の問題で合意できるだろう」。9日には首都アンカラで外交関係者らを前にこう語り、対米関係の改善に意欲を示した。
トルコは米主導の北大西洋条約機構(NATO)で中東唯一の加盟国。両国は半世紀以上、同盟関係で結ばれている。だが、エルドアン氏とオバマ米大統領の関係は良好ではなかった。
それが鮮明になったのは昨年7月、トルコで軍の一部がクーデター未遂を起こした時だ。エルドアン氏は軍に信奉者が多い在米のイスラム教指導者フェトフッラー・ギュレン師を黒幕と断定。オバマ政権に対し、身柄引き渡しを要求した。
オバマ政権は応じなかった。報道機関への圧迫など強権体質を強めるエルドアン政権を警戒する。エルドアン氏はいら立ちを募らせ、オバマ政権による“陰謀論”を展開した。「西側の国がクーデターを支援した」、「米主導の有志連合が(イスラム教スンニ派過激組織)イスラム国(IS)を支援している証拠がある」−オバマ氏への嫌悪感を隠さなかった。
■ ■
さらなる確執の種は、オバマ政権による少数民族クルド人の民主連合党(PYD)支援だ。シリア北部のIS攻撃で地上戦を担うPYDは、トルコでテロ闘争を続ける非合法武装組織、クルド労働者党(PKK)の実質傘下にある。トルコは昨年夏、シリア北部に派兵し、IS攻撃に乗じて勢力圏を拡大するPYDの押さえ込みに出た。
対米関係が冷却化する中、トルコはロシアに急接近した。
昨年末、トルコはロシアとともにシリア停戦合意を発表。ロシアが支えるシリアのアサド政権存続を事実上、容認した。米国と並んでアサド政権退陣を要求してきたが、方針を変えた。ロシアに協力する見返りに、クルド人勢力封じ込めでロシアの黙認を取りつける狙いが透けて見える。
■ ■
トルコのユルドゥルム首相は今月3日、「米国がPYDのテロリストを支援してきたのはオバマ政権の問題だ。新政権の責任を問うつもりはない」と述べ、トランプ次期政権にPYD支援を打ち切るよう促した。
トランプ氏に対する期待には理由がある。
トランプ氏は昨年11月の大統領選直後、米紙ウォールストリート・ジャーナルとのインタビューで「我々はシリア反体制派を支援しているが、彼らが何者だか分かっていない」と述べ、PYDに対する米国の支援見直しを示唆した。大統領補佐官(国家安全保障問題担当)に就任するマイケル・フリン氏も同月、「トルコは国益に不可欠」とした上で、米国からのギュレン師追放を主張する寄稿文を発表した。
トランプ氏がロシアとの関係改善に意欲的なことも、対露接近を進めるエルドアン氏には好材料だ。
トルコ国会では今月、大統領の権限強化に向けた憲法改正案の審議が始まった。米新政権の後ろ盾を得て権力集中を進めたいエルドアン氏の思惑がにじむ。トランプ政権発足という追い風に賭けている。【1月16日 産経】
********************
エルサレムへの大使館移転・ユダヤ人入植活動容認など、トランプ新政権のイスラエル偏重路線も含め、ロシア=トルコ=トランプ新政権=イスラエルの協調体制で今後のシリア・中東政策は進められそうです。
民主主義とか共存といった理念ではなく、既存の大国間の利害を調整する“取引”で物事をきめていこうという路線とも言えます。第1次大戦後の列強による“取引”“線引き”が現在の中東混乱の根底にありますが、その焼き直しの感も。
シリアについてはアサド政権を一定に容認する方向が現実的だと個人的にも考えますが、全体的な中東政策のなかで切り捨てられるクルド人勢力やパレスチナによる抵抗・混乱も想定されます。
“新秩序”となるのか、“新たな混乱”の始まりとなるのか。
1月9日ブログで取り上げたキプロス再統合問題に関しては、北部にトルコ軍を進駐させているトルコ・エルドアン大統領の説得で難航しているようです。
****キプロス再統合交渉、合意ならず=多国間会合継続へ****
40年以上分断が続く地中海のキプロス島の再統合交渉で、仲介役の国連は12日、声明を出し、当事者と関係国3カ国が参加する多国間会合を今後も継続することを決めたと発表した。12日にスイスのジュネーブで開かれた同会合では、島の北側に駐留するトルコ軍部隊の扱いなど安全保障問題について協議されたが、合意に至らなかった。
AFP通信によると、南部のキプロス共和国(ギリシャ系)のアナスタシアディス大統領は13日、「トルコ軍の撤退について合意しなければいけない」と述べたが、トルコのエルドアン大統領は、トルコ軍部隊の撤退は「問題外」だとはねつけた。【1月13日 時事】
*********************
【蛇足ながら・・・】
最後に付け加えれば、エルドアン大統領はISやクルド人勢力という“敵”による危機を煽ることで、権力の求心力を高めてきましたが、それによって国内の分断・緊張も高まっています。
同様の話は、移民やイスラム教徒、あるいは外国経済による危機をアピールすることで政権を手にしたトランプ新政権にも言えるところです。
危機を煽れば、緊張のなかで互いの憎悪も増し、実際に衝突も発生します。そのことで更に危機感が高まり・・・というスパイラルに陥ることも懸念されます。