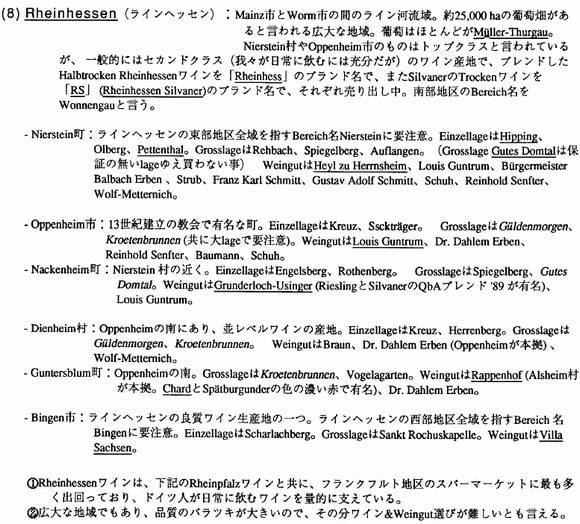(3-16) その他の表示事項と表記
Schloss、Burg、Klosterなど従来からNaturweinの供給者であった感の残る用語は、その城や寺院を除き使用が禁止されている。
(3-17) EC諸国生産物を原料とした並級酒と弱発泡ワイン
EC域内産のブドウを原料としてドイツで生産するターフェルワインやパールワインに関する規定。 原産国の割合に応じその国名を表示する。
(4) 表示法の一部改訂
Schloss Johannisbergで遅摘み法が発見されるまで、ドイツワインは辛口が中心であった。 ドイツワインは地理的な条件によりブドウの成熟がゆっくり進むため、果実酸が分解されずに残り豊かな情緒をもたらす。 これと遅摘みによる残糖が素晴らしい調和をもたらすのが最大の特徴であると考えられる。
一方、2000年以降,辛口仕上げのワイン表示法が改訂された。 クラシック、セレクションの2表示である。 従来、Auslese trocken、Spaetlese trockenなどと表示されていたものがセレクションと呼ばれている。
----------- -----------
「ドイツワイン法概説」は これで終了です。
「ドイツの白ワイン」シリーズも 一旦これで終了とします。
左欄下側「ブックマーク」中の「ドイツの白ワインの解説目次」を活用ください。
→個々の解説ページにジャンプするようにリンクを貼ってあります。