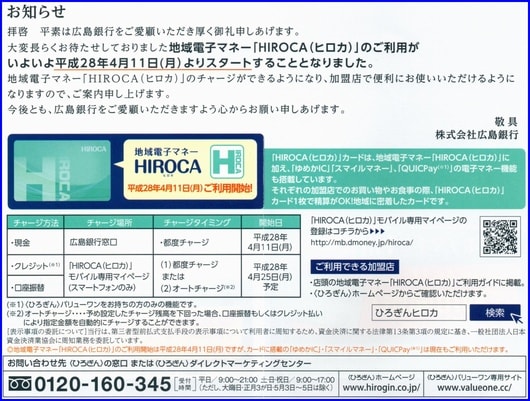「鳴門のコウノトリ」の第2回目です。(→ 前回の第1回目は こちら)
放鳥された、あるいは野外で生れたコウノトリの背中にはGPS発信機 が付けられているため、約1年間は人工衛星で行動範囲を監視できるようになっています。
(↓)や(↑)の写真で、背中にGPS発信機のアンテナが1本出ているのが判ると思います。

(↓)が巣内で立ち上がっているコウノトリのほぼ正面の姿です。

(↓)が後ろ姿です。

私めが去る3月末に撮影した徳島県鳴門市某所のコウノトリは、1971年に国内の野生コウノトリが絶滅後、兵庫県豊岡市近郊以外の野外での産卵は国内初 のことで、雛が孵ることが大いに期待されていました。 例えば、親鳥や雛が、万が一にも電線で感電してはいけないからと、四国電力は別に何本もの電柱を建てて送電経路を変更して、巣がある電柱の電線には送電しないようにしたそうです。
巣のある電柱から半径400メートル以内への立入りが禁止されましたので、双眼鏡で見ても小さくしか見れないので、コウノトリを見守るボランティアの人達が、見物に来た人達に少しでもコウノトリのことを知ってもらおうと、(↓)のような「田んぼギャラリー」を設置したりもしました。



しかし残念ながら、私めが撮影した数日後に、コウノトリの番(つがい)が共に巣を離れたわずかな隙に、何とハシボソガラスに卵を食べられてしまいました!!
ハシボソガラスが捨てた卵の殻を「コウノトリの郷公園」に送って鑑定した結果、少なくとも2週間近く抱卵した有精卵ならば卵内で胚の発生と共に血管が発達し始めるが、問題の卵の殻には血管の組織が全く認められなかったので、無精卵 だった可能性が極めて高いという結論が出ました。
鳴門のコウノトリは、昨年も無精卵を産んだ可能性があったらしいのですが、今年はそれが確認できた訳です。 生後3年のメスでは未だ若すぎるらしいです。
ということで、1泊2日で徳島県鳴門市まで撮影旅行に行った「鳴門のコウノトリ」のお話は、これで一旦終わりとします。 支払ったホテル代、高速代、ガソリン代以上に価値のある撮影旅行でした。 とは言え、現実には 私めの小遣いが…。(泣)
(画像をクリックすれば大きな画像になりますので、お試し下さい)