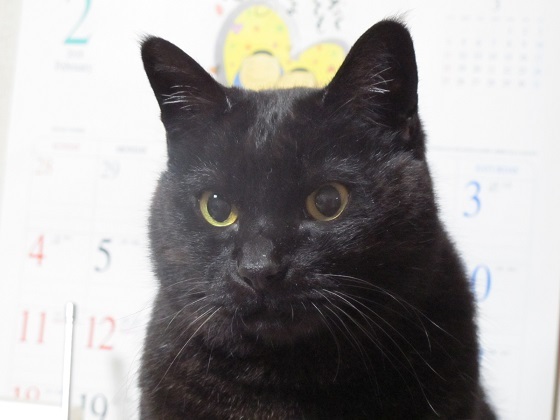ジャパンローヤルゼリーの小冊子12月号
『もっと知的に美しく・アールR』が、どこからか・・・昨日、
主人が新聞を整理していたので、
その間からかな・・・でてきました。
「クヨクヨをスッキリへ」の記事が目に留まりました。
内容は「40代女性に多い、
対象喪失による、落ちこみの解消法。」
40代だけでなく、すべての年代にいいと思う。
対象とは、自分が一生懸命愛情をかけてきた存在。
家族だけでなく、自分も対象として存在。
喪失というのは、家族や自分自身の変容。
両親は年老いて、あるいは亡くなり、
夫は働き盛りで、仕事一筋で忙しく、家のことは妻に任せっきり、
子どもたちは、進学や就職だ、と家庭から巣立っていく。
自分は若いころと比べて、
容姿(確かに、納得!)も身体機能も衰えてくる。
持っていたものがだんだんと失われてくる。
孤立感、孤独感にさいなまれて気持ちが晴れない。
このような心の状態はどの年代にもあるよね。
そんなときに、気持ちを切り替える
以下の方法が紹介されていました。 短所を長所に言い換えてみよう
短所を長所に言い換えてみよう
例えば「頑固で融通がきかない」→「自分の信念をもっている」
「人付き合いが苦手」→「少数精鋭の人間関係を築く」
「小さなことにこだわっていつまでもくよくよする」
→「神経が細やかで思慮深い」 6D2Sに心を支配されない
6D2Sに心を支配されない
6D「でも」「どうせ」「だって」「ダメだ」
「できない」「どうしよう」
2S「しなければいけない」「しょせん」  あだ名をつけるのも得策
あだ名をつけるのも得策
例えば「慢性責任転嫁病」「自己愛性障害者」などと
相手に病名をつける。
相手が病気だと思えば腹も立ちません。 効果的な呪文を唱えてみよう
効果的な呪文を唱えてみよう
例1.「いいかげん」なくらいがいい加減と心得よう
2.100%でなくてもいい、80%でよしとしよう
3.「がんばらない」は「サボる」とは違う
4.「~ねばならない」の発想パターンをやめよう
5.休むことは決して悪いことではない
6.理不尽なことでも、「ま、いいか」で割り切ろう!
7.「他人」と「過去」は変えられない。自分が変わろう
8.反省はするけど、後悔はしない
9.嫌なことにははっきり「NO」断り方を覚えよう!
10. 「私がいなくても会社はつぶれないワ」でOK!
11.言いたいやつには言わせておけ
12.明日でいいことは明日やろう
13.がんばればがんがるほど、肩の荷は重くなる
14.ストレスは逃げれば逃げるほど追いかけてくる
15.「心配のタネ」は小さい芽のうちに摘んでおこう
16.「いい子でない自分」「できない自分」を認めよう
17.自分は自分、この世で私はオンリーワン
18.いちばん大切なのは自分を好きでいられること
19.人生に無駄なんてない。プラス発想を身につけよう
20.ピンチのときには必ずチャンスが潜んでいる
21.眉間にシワを寄せてちゃダメ。にっこり笑って!
22.自分は今、どこに追い込まれ、何と闘っているのか
23.グチの「こぼし先」をしっかり確保しておこう
24.ものごとには必ず終わりがある
少なからず、しらずしらずにどれかを自然にしてませんか?
これは人間の体に備わっている防衛反応なのかな。
中年女性がはまりまくった『冬のソナタ』。
私は見たことがなくて、ヨン様ファンでもありませんが
女性が脚本を書いたんだそうです。
ぺ・ヨンジュン扮する主人公のセリフに、
女性が男性から言われたいと思う
言葉がたくさん盛り込んである。
日本の男性はまず使わない言葉・・・・どんなん?
一度DVD見てみようかな
だから女性たちが、ヨン様をみて、胸をときめかせた。
擬似恋愛をしたということらしい。
この擬似恋愛、「ドーパミンが出て、行動的になれ、
女性ホルモンの分泌もさかんになり、
女性ホルモンのエストロゲンは記憶力に関係するので、
記憶力もよくなる。」といった効果をもたらすそうです。
しかし、一応、主婦ですから、
やたらに するわけにはいきません。
するわけにはいきません。
そこで、 印の方法を
印の方法を
アドバイスされた先生紹介
姫野友美 ひめのともみクリニック院長
心療内科医
テレビなどのコメンテーターとしても活躍
著書『女は突然なぜ怒り出すのか?』
角川書店
平成19年2月3日(土)
早朝6時に家を出て、
JR中央線勝川→名古屋7:05発→米原→山科9:21発
→湖西線比叡山坂本9:30着。快速を3回、乗り継いで。
片道一人2940円。
この日の最大の目的は、日本最古の茶園を見ることでした。
比叡山坂本駅から10分ぐらいの所、
日吉大社までの道すじにあります。
茶園のことはお茶関係を見てね。
茶園から、日吉大社までは約10分。
写真は日吉大社の参道に続く道です。
ここの日吉大社は全国の日吉大社の総本宮だそうです。 
節分祭まで時間があると思って,欲張ったので、後で慌てました。
電車を降りてすぐに、湖国十一面観音霊場の第3番霊場である
聖衆来迎寺(しょうじゅうらいこうじ)に行きました。
拝観には事前に予約が必要で、
観音様は観ることができませんでした。
ここには、森蘭丸(1565~1582)の父
可成のお墓がありました。
ちなみに、森蘭丸の生誕地は
我が家からさほど遠くない、岐阜県可児市兼山。
金山と表記してあるものもありますが地名が兼山で
金山はお城の名前のようです。
地図を見ると金山城址跡とあるので。
チョット横道にそれちゃいました。
参道までの道沿いには、最澄生誕地の生源寺があります。
穴太(あのお)衆積みという石垣が見えてくると、
日吉大社の参道は近い。
この石垣は、かって穴太に住んでいた石工集団穴太衆によって
様々な積み方がされている石垣です。
お城の石垣みたいだなと思っていたら、
名古屋城の石垣造りにも活躍したとのこと。
日吉大社の二十一もある山王社の
どこで節分祭が行われるのかわからず
大回りしましたが、間に合ってホッ。
日吉大社は広すぎて今回はまわりきれませんでした。
次回、ゆっくりこよ・・・
紅葉の季節が最高に美しいということだから、秋にでもネ。
節分祭のことは体験記に書いておきました。
ちなみに、東本宮に祭られている神は
大山咋神で、比叡山の地主神。
「咋(クイ)」は、山の樹木やその麓の田畑の五穀を
グイグイと伸ばし育てる意味。
また、この神の兄弟は竃や庭・玄関・土の神で、
両親は稲と水の神ということから、
東本宮は五穀豊穣、家庭日常生活の守り神として
信仰されているそうです。
どこにも神がいるんだね。
昔の人って想像力豊かだね。
そうやって物を大切にしたんだろうね。 反省!
日吉神社の参道を出てすぐの道を左に
15分ぐらい行くと、西教寺があります。
聖徳太子(574~622)が恩師の僧のために
建てたと伝えられています。
明智光秀が寄贈したお寺の門。
坂本城主となった明智光秀が西教寺の檀徒となり、
寺の復興に力を尽くしたことから、
境内には明智光秀と妻熙子(ひろこ)、
明智一族のお墓があります。
門や鋲などには羽を広げた三羽のすずめ。「三つ集め雀」。
西教寺の家紋らしい。
『身代わりの手白猿』
室町時代、坂本で一揆が起こった時、
首謀者がこの寺の真盛上人と誤解した
山門の僧兵が西教寺に攻め入った。
しかし、境内には人影がなく、
ただ鉦の音だけが本堂から聞こえてきた。
それを聞いた僧兵が本堂に駆け込むと、
そこには一匹の手白の猿が上人の身代わりとなって
鉦をたたいていた。
猿までが上人の不断念仏の教化を受けて
念仏を唱えていることに感じ入った僧兵は
その場を立ち去ったという話があり、
寺の屋根のいたるところに、
いろいろな姿をした猿がのっていました。 

西教寺からの琵琶湖の眺望はすばらしい!
遠く近江富士(三上山)も見えました。
この日は少し霞がかかっていて、写りが悪く、残念 
霞のせいにするのか・・・・・
この日は節分だったので、重文の阿弥陀如来像や
鶴の間・猿猴の間・賢人の間など
六つの客殿の襖絵が公開され、観ることができました。
客殿の庭園は裏山の急傾斜を利用したもので小堀遠州の作。
一昨日に降った雪がまだ残っていて、
凛とした趣のある風情でした。
来た道を帰る途中、里に下りて来た猿の大群に遭遇しました。
社務所の入り口にも
「猿が入るので必ず閉めてください」と張り紙がしてあり、
「襖絵を見たら扉、閉めてくださいね」に、納得。
すれ違った地元の人が、
「ねぎの白い部分が甘くて、そこを食べに来る。」
「畑が全滅だ」
と嘆いていました。
日吉大社の神使は「神猿マサルー魔去る・勝る」、
西教寺も「身代わりの手白猿」・・・・
いずれにも猿が関係しているわけが、わかったような気がします。
猿の大群を見るのは、子どもの頃、大分の高崎山の猿以来です。
地元の方は困り果てているでしょうに、
私は子どものように興奮しました。
この辺り一帯、猿は「神使」なので捕まえられないようです。
見かねて、何処からか、空砲が何発も鳴っています。
しかし、猿も慣れたもので、
さほど慌てふためいて逃げているといった様子ではありません。
空砲が虚しく聞こえます。
歩き疲れて、お腹も空いて、遅いお昼は、
280年前に創業という、
建物も築100年の重厚な風格のある店構え、
店内は意外に普通の
「本家鶴き(きは漢字で七が三つ)そば」で
そば定食を食べました。
麺はもう少し固めの方が好みですが、
おつゆはとても美味しかった。


食事をする前に寄った、「水琴窟の音色を、
ご自由に庭に入ってお聴きください」と張り紙がしてある民家?
で売られていた唐辛子の「家内安全」のおまもり。
日吉大社の二十一の山王社にちなんで、
唐辛子が21個つながっています。
数えてみてください。
掛け紐(稲の穂がついた藁)に烏帽子をかぶった
「神猿」の絵に「家内安全」と書かれた和紙がついています。
1つ1000円。買ってしまいました。

ご主人のお知り合いの方が、「皆さんにあげてください」と、
リハビリに作られたという千代人形のしおりをいただきました。
「ありがとうございました。」「お身体、お大事に」
水琴窟の音色、耳をそばだてて聞かないと
聞き逃すぐらいの小さな音ですが、
ひかえめな、物静かだけど、重みのある音色に思わず、感動!
水琴窟は小堀遠州が考えたつくばい周りの排水装置
「洞水門」から発祥したのだと
「珈琲人こひびと」という名前の、老夫婦と
その娘さん?お嫁さん?らしき人がやっている喫茶店で
食後の珈琲を飲みました。
クラシックが流れていてとても温かい雰囲気のお店でした。
下の写真は、料亭風のお店の玄関先にありました。
和風な玄関にピッタリ、マッチしていました。

湖国十一面観音霊場の第2番霊場盛安寺がこの坂本にあり、
また、第1番霊場の三井寺も京阪石山坂本線沿いにあり
途中下車して行く予定にしていましたが、観音像の拝観は
事前に予約か、特別な日にしか拝観できないのかもしれません。
事前に問い合わせてきた方がよいと・・・・
今回は、あっさり、あきらめました。
比叡山坂本駅を15:04発の電車で、帰路へ
久しぶりの遠出で、
欲張っていろいろ観る場所を計画していたのですが・・・・
それでも、満足!満足!
二兎追うものは一兎も追えず.
若い時と違って、この歳になると
旅はじっくり、ゆっくり、のんびり
ところで、西教寺の芭蕉の句碑が、
明智光秀の妻熙子(ひろこ)の墓の傍にあったと思うけど
「月さびよ明智が妻の咄(はなし)せむ」
を芭蕉はどのような気持ちで詠んだのかな?