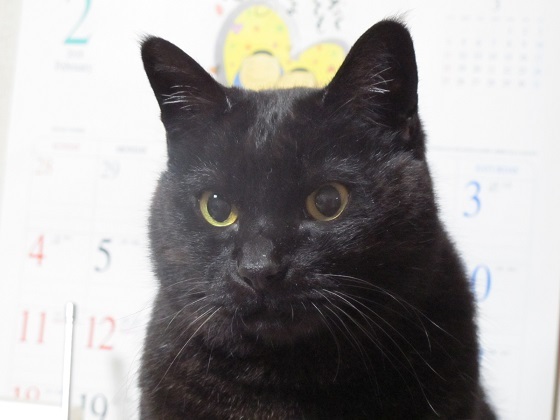「月さびよ明智が妻のはなしせむ」
伊勢神宮の下級神職で芭蕉の門弟
島崎味右衛門(俳号を又玄)宅に宿泊した時、
貧しさにもかかわらず、夫と心を合わせ、
けなげに暖かくもてなしてくれた
又玄の妻に感激しておくった句。
「明智が妻のはなし」をそのままとするのではなく、
「が妻」のところで、
又玄の妻に転ずるものと解するほうがよい。
と「日本古典文学28巻芭蕉」の
「芭蕉と古典」の項に書かれている。
句の意味は
「月よいっそうさび極まれ、
明智の妻に比すべき又玄の妻の話をしよう」
「明智の妻に比すべき」とは、明智光秀がまだ貧しくて
連歌会を営む費用に窮していた時、
妻の熙子(ひろこ)がひそかに髪を切って金に換え、
連歌の席を設け、客をもてなし、夫の面目を立てたという古事。
西教寺の熙子のお墓の傍にその句碑はあるけど、
主役は熙子ではなく又玄の妻だったんだ。
まぎらわしいなあ。
でも、熙子も又玄の妻も、妻の鏡。
爪の垢でも煎じて飲みたいわ・・・・・
三浦綾子著「細川ガラシャ夫人」主婦の友社を読みました。
ガラシャは明智光秀と熙子の娘で、
名前は玉子。ガラシャは洗礼名。
これは歴史小説ですが、「本能寺の変」の状況や秀吉、
石田三成、徳川家康の政権争いがよくわかります。
女性が男性の所有物であった時代、
毅然と生きたガラシャの生き方に、
信仰ゆえかもしれませんが深く心を打たれました。
1600年7月17日、石田三成の人質を拒み、
家来に胸を刺させ、屋敷に火を放たせ、
38歳で非業の死をとげました。
「散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ」
ガラシャの辞世の句ですが、非があるときはきっぱり謝るとか、
相手を認め潔く引くことも必要とか・・・・・・
この句を私の好きな言葉にいれました。