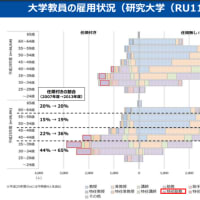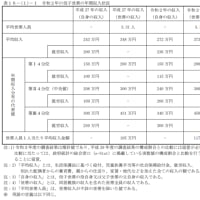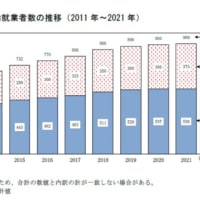日頃欠かさず行っているWebニュースのチェックをしていたら、筆記具メーカーのパイロットが「木布(「もくふ」と読む)を使ったペンケースを発売する」という記事があった。
PILOT:ペンケース Ki:ro(キーロ)発売
ペンケースの価格としては、決して安いものではないと思う。
それでも、間伐材からセルロースを取り出し、セルロースを一旦紙にすき、細く切って糸として寄り、布として織り上げる、といういくつもの工程を経て作られる為に、思いのほか高い価格になってしまうようだ。
同様に、数年前から「竹布(「たけふ」と読む)」という素材も話題になったりした。
おそらく「竹布」そのものは、随分前から夏の服地素材として注目されてきたと思うのだが、ここにきて注目されるようになってきた理由は「竹布」が持つ抗菌作用のようだ。
「抗菌作用」という言葉だけで、どのような需要が高まっているのか?ということは、「コロナ禍」での生活が長引く現在、多くの人が分かるキーワードだと思う。
とはいうものの、「竹布」そのものも、機能という点で注目をされてはいるのだが、アパレル素材として注目されているという状況とは程遠いような印象を持っている。
それに対し「木布」にはそのような、機能があるのか?ということが不明なため、SDGsという観点からの需要見込みという点だけになっている、という気がしている。
例えば、抗菌作用や防虫性だけではなくアロマ的な効果もあるといわれる、ヒノキの間伐材から作られた「木布」に、ヒノキが持っている効果があるとすれば、それは大きな付加価値となるだろうし、用途そのものの幅が広がる。
他にも自然染料との相性が良ければ、藍染めや草木染等でアパレル用の布としての用途が生まれるはずだ。
「木布」も「竹布」のどちらも、都市部で生産できるものではない、という点においては、地方での産業化ということが可能ではないか?と、考えられる。
それは「地域創生」とか「地域経済の活性化」にも、繋がる可能性を秘めている、ということでもあるのでは?と、考えられる。
何より重要なことは、このような「国内で作られる新しい自然素材を活用していく」という、気運のような気がしている。
今のようなファストファッション全盛期において、このような手間ひまをかけて作られるアパレル素材は、現在のアパレル市場に出すということ自体難しいのでは?と、感じている。
とすれば、このような「ものづくり」に共感するデザイナー等を通して、認知度を上げつつ量産化を目指し、少しでも生活者の手に届きやすい環境を作っていく、ということが重要になってくるだろう。
国が旗振り役で、「COOL Japan」などと宣伝をするのではなく、このような素材を作っている企業が海外へアピールしやすい環境を作っていく、ということの方が重要かもしれない。
そうすれば、日本国内よりも海外のデザイナーのほうが、面白がって使ってくれる可能性もあるだろう。
せっかく新しい技術によって、日本らしい素材ができたということを考えたとき、市場をつくりだしていくということの難しさと、その意味を考える必要があると感じている。