塩釜の綾瀬さんからエキスパック500が到着。はて? 何か届く予定はないけれど……と開封してさらに困惑。仙台の漬け物と本が1冊。
本の方は、ローカル出版物で『杜の都のボールパーク』。四半世紀前、仙台に数年だけ拠点を置いていたプロ野球チーム、ロッテオリオンズをモデルにした架空のプロ野球チーム「仙台ツインズ」をめぐる……というより、仙台を舞台にした野球短編集。
野球小説というと、『フィールド・オブ・ドリームス』や『消えた巨人軍』を勘定に入れなければ、『プレーボール!2002年』くらいしか読んでなかったのだけれど(ああ、もう2002年を過ぎている!)、けっこう面白かったです。『あぶさん』も好きだしね。考えてないようで考えていて、でも結局考えないで行動する監督の金田某とかまさかりみたいに剛球を放つ投手の村田某とか、かろうじて覚えているからかな。『アストロ球団』はこの作品の前になるのか後になるのか……。
そして、やっぱりここでも「名古屋ドラゴンズ」はパ球団に勝てませんでしたとさ。
読み終わっても謎は解けず、悩みつつ連絡してみたら「いやあ、この前、お茶をもらった御礼に、ローカルなもので見繕ってみましたぁ」とのこと。いや、ありがとうございます。
【杜の都のボールパーク】【大泉浩一】【野球小説】【プライド】
本の方は、ローカル出版物で『杜の都のボールパーク』。四半世紀前、仙台に数年だけ拠点を置いていたプロ野球チーム、ロッテオリオンズをモデルにした架空のプロ野球チーム「仙台ツインズ」をめぐる……というより、仙台を舞台にした野球短編集。
野球小説というと、『フィールド・オブ・ドリームス』や『消えた巨人軍』を勘定に入れなければ、『プレーボール!2002年』くらいしか読んでなかったのだけれど(ああ、もう2002年を過ぎている!)、けっこう面白かったです。『あぶさん』も好きだしね。考えてないようで考えていて、でも結局考えないで行動する監督の金田某とかまさかりみたいに剛球を放つ投手の村田某とか、かろうじて覚えているからかな。『アストロ球団』はこの作品の前になるのか後になるのか……。
そして、やっぱりここでも「名古屋ドラゴンズ」はパ球団に勝てませんでしたとさ。
読み終わっても謎は解けず、悩みつつ連絡してみたら「いやあ、この前、お茶をもらった御礼に、ローカルなもので見繕ってみましたぁ」とのこと。いや、ありがとうございます。
【杜の都のボールパーク】【大泉浩一】【野球小説】【プライド】











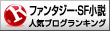
 表紙に惹かれて日日日の『アンダカの怪造学~ネームレス・フェニックス』を手に取り、ぱらぱらと内容を確認し、面白そうかなと購入。久々の角川スニーカー文庫ですね。
表紙に惹かれて日日日の『アンダカの怪造学~ネームレス・フェニックス』を手に取り、ぱらぱらと内容を確認し、面白そうかなと購入。久々の角川スニーカー文庫ですね。
 元ネタは短編『物体O』。突然、東京を巨大なリングが取り囲み、交通が遮断されたことによるドタバタを描いた物語。それを膨らませ、東京という存在がいきなり消えてしまったとき、政策決定のシステムは、外交関係はどうなるのか、各地に配備されている自衛隊と在日米軍の関係は、物流・出版は……と、政治・経済・軍事面をしっかり描き込んだのが『首都消失』ということになります。(結末を見れば判るように)SFというより、ポリティカル・シミュレーション小説。
元ネタは短編『物体O』。突然、東京を巨大なリングが取り囲み、交通が遮断されたことによるドタバタを描いた物語。それを膨らませ、東京という存在がいきなり消えてしまったとき、政策決定のシステムは、外交関係はどうなるのか、各地に配備されている自衛隊と在日米軍の関係は、物流・出版は……と、政治・経済・軍事面をしっかり描き込んだのが『首都消失』ということになります。(結末を見れば判るように)SFというより、ポリティカル・シミュレーション小説。





