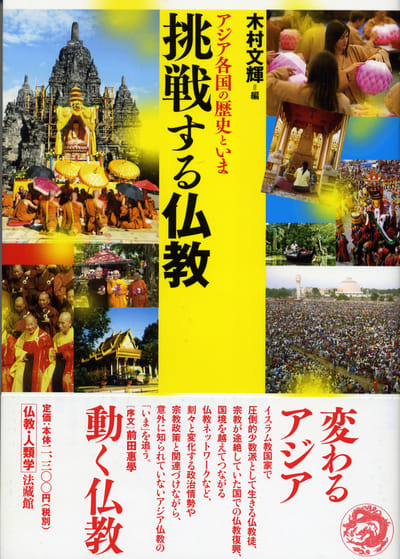今晩は、和食。お造りに、かわいい蛙が乗っていた。
NICE!

法然院から、北にあがって、西に向かい、最後に訪れたのが、下鴨神社。
西に向かうと、当然鴨川を渡ることとなるが、橋を使わずに鴨川を渡れることを知った。

鴨川の中央には、黄色い花が咲き誇っていた。

二本の川が合流し、鴨川になる地点にある下鴨神社に到着。凄い人が、帰ってくる。その日、ちょうど流鏑馬の日で、終わったところだった。
京都に住んでいれば、そういうタイミングはのがさなかっただろうに。

平安京が作られる前から京都を治めていた賀茂氏の氏神。年季が違う。世界遺産にも指定されている。

朱塗りの鳥居と楼門が見事。

豪華な楼門だ。

特別公開があったが、間に合わなかった。
本殿は、檜皮葺きの古風なもので、国宝に指定されている。
参道も含めると、巨大な神社で、流石という感じ。