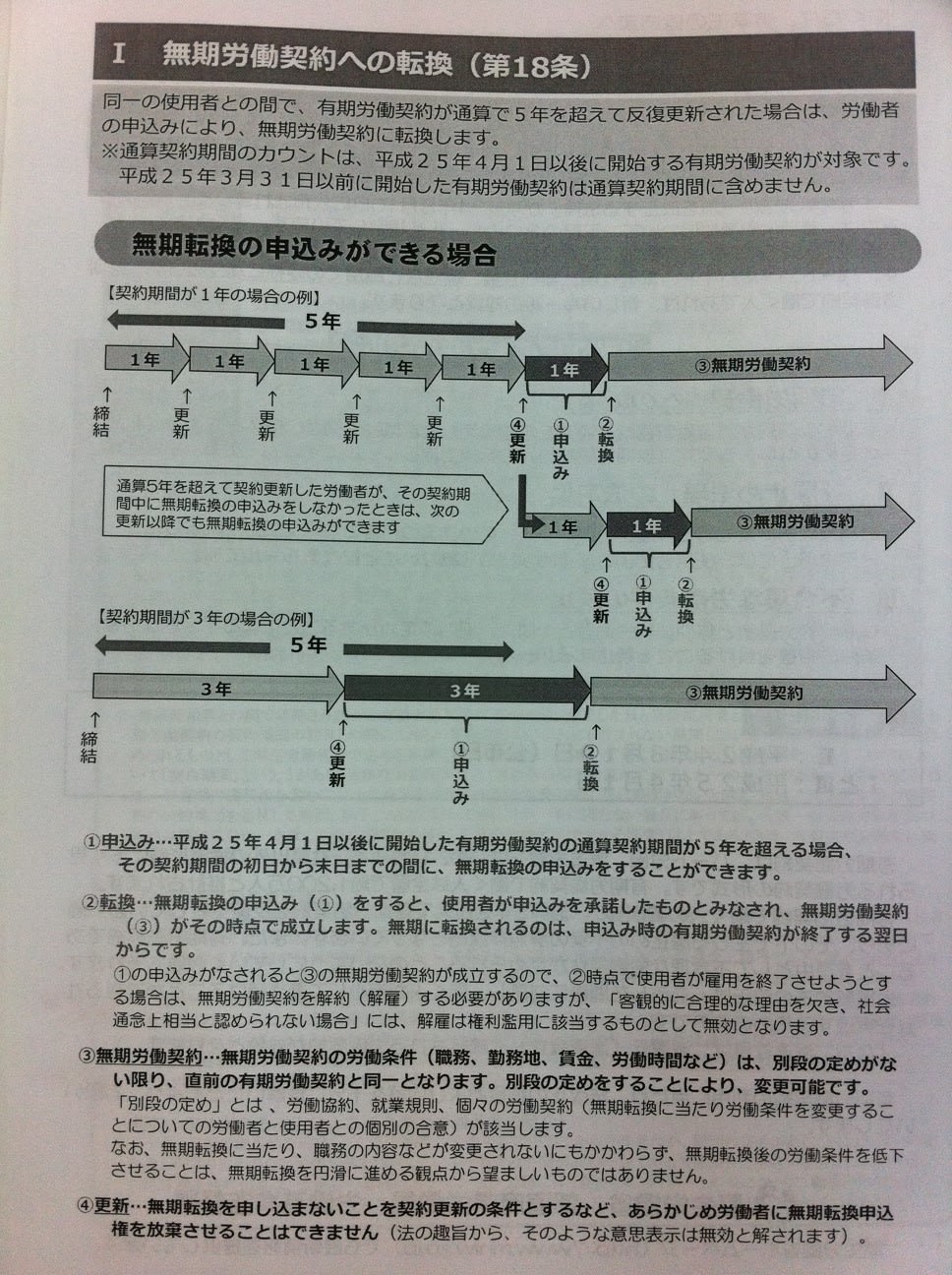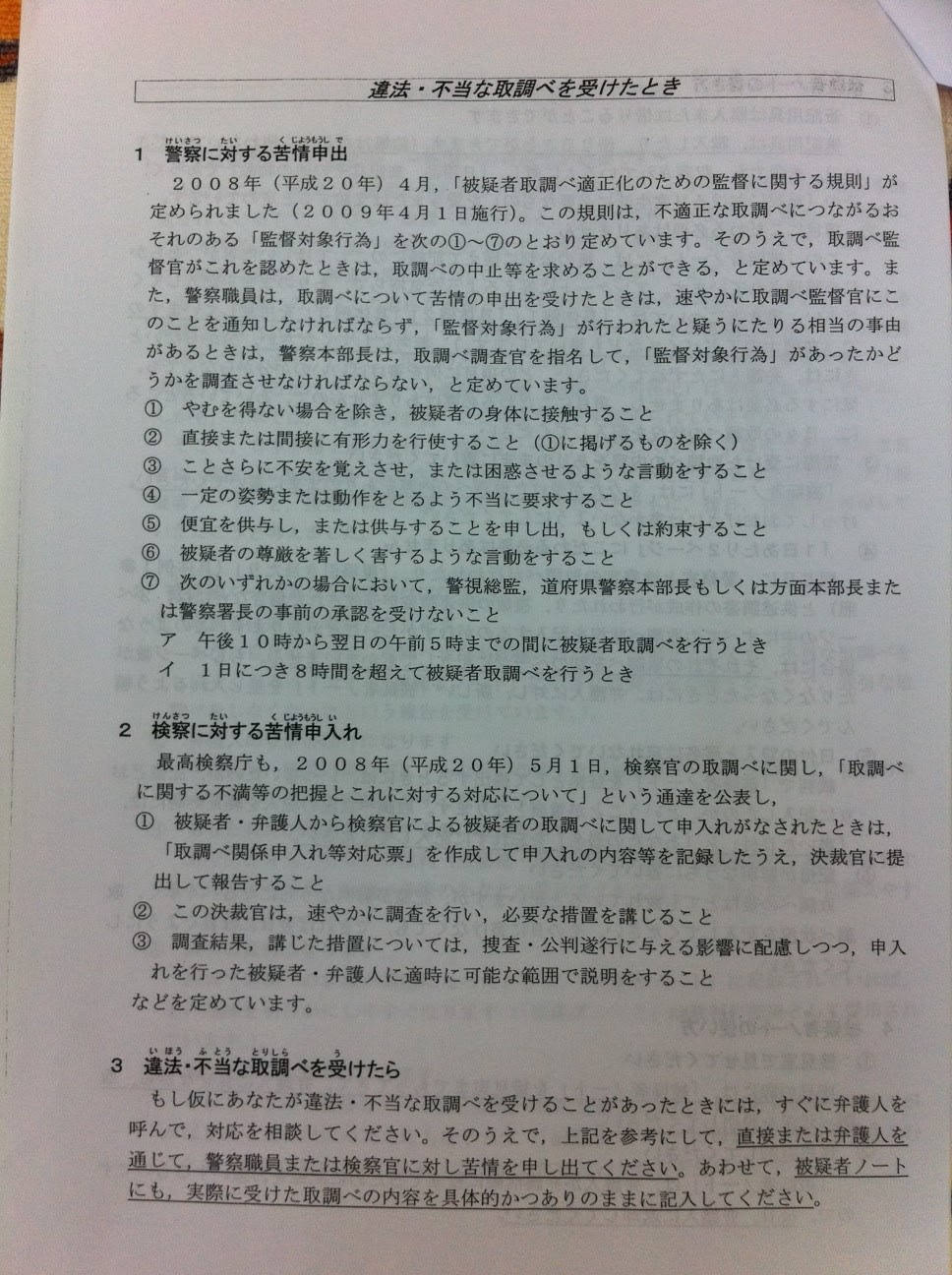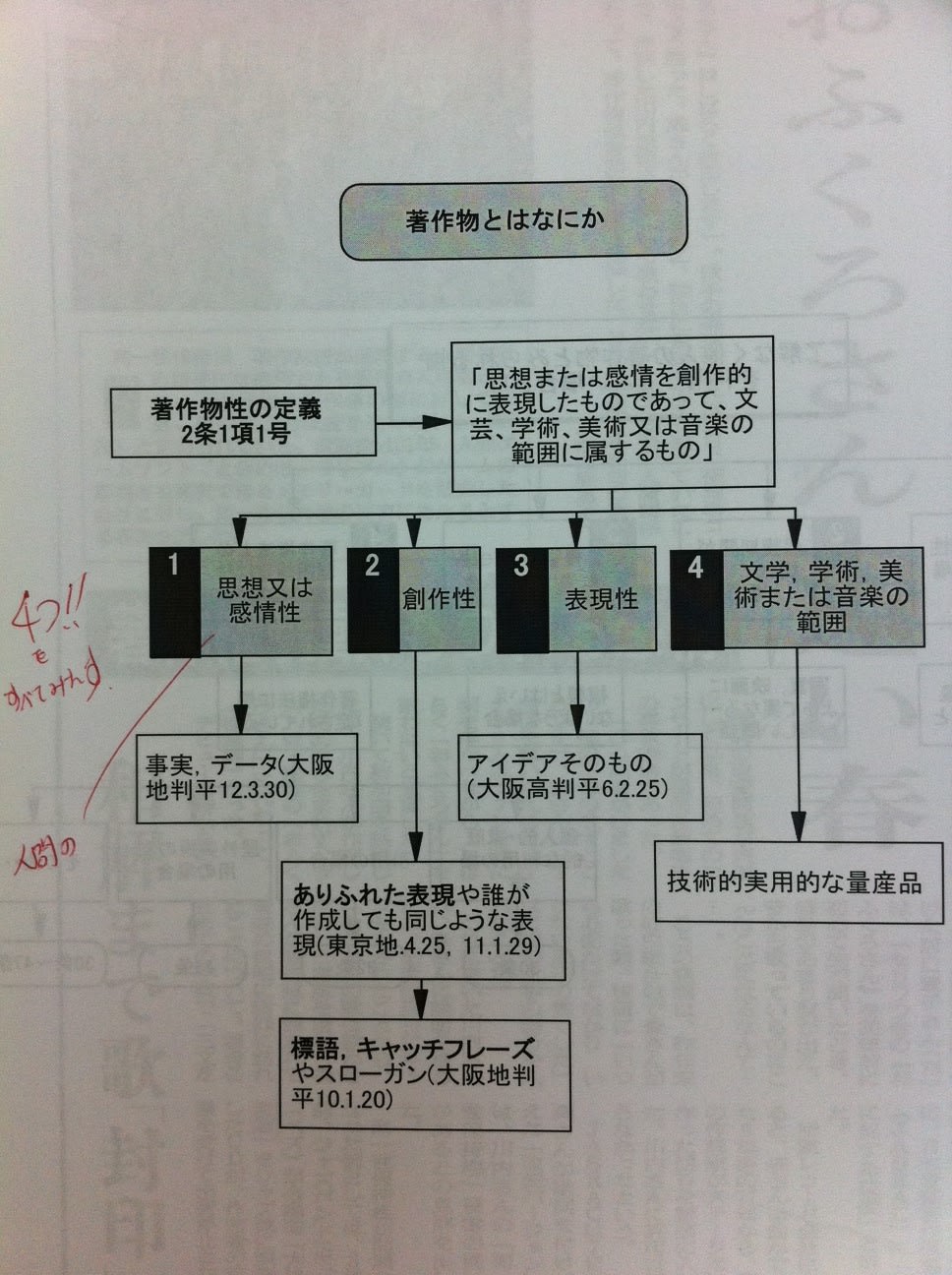働く人全員にとって、最も大事なことの一つは、就業規則に関する理解だと思います。
労働法で就業規則について学び、その重要性について、目からうろこが落ちる思いをしました。
大切なものですから、皆さん、ぜひとも、ご自身の就業規則をご確認ください。
以下、就業規則について、労働法の講義を参考に書きます。
就業規則 菅野 126 頁~、下井 81 頁~
(1)意義
多数の労働者が協働する事業においては、労働条件を公平・統一的に設定し、かつ職場規律を規則として設定することが、効率的な事業経営のために必要となる。事業経営の必要上、職場規律や労働条件に関する規則類を制定したものが「就業規則」
(2)労働基準法上の規制等
*****労働基準法 関連する9章89条~93条及び106条 全文 抜粋*****
第九章 就業規則
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、
労働契約法 (平成十九年法律第百二十八号)
第十二条 の定めるところによる。
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、
就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
(3)就業規則の効力 菅野 134 頁
ア 労働基準法 92 条
法令・労働協約の優越性
****労働基準法92条*****
第九十二条 就業規則は、
法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
****************
イ 労働基準法 93 条
最低基準効→労働契約法12条へ
****労働基準法93条*****
(労働契約との関係)
第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、
労働契約法 (平成十九年法律第百二十八号)
第十二条 の定めるところによる。
****************
****労働契約法 12条*****
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
*****************
⇒個別の同意(労働契約)は無効であり、従来からの就業規則の定めによることが定められています。
ウ 労働契約法 7条
****労働契約法 7条*****
第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が
合理的な労働条件が定められている
就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
****************
1労働契約規律効
就業規則が合理的な労働条件を定めるものである限り、労働条件はその就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法規範性が認められてきたが(判例法理:秋北バス事件最大判43.12.25)、この判例法理の内容を、「事実たる慣習」といった媒介法理を用いずして立法化したもの。
2要件
・就業規則を周知させていたこと
⇒実質的にみて、事業場の労働者集団に対して当該就業規則の内容を知りうる状態においていたことであって、労働者が実際に知っていたかどうかは問わない。
・合理的な労働条件を定めていること
⇒就業規則が定める労働条件それ自体の合理性。
エ 就業規則の変更における労働契約規律効(労働契約法 8条 9 条、10 条)
*****労働契約法 9条 10条*****
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
第九条 使用者は、
労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である
労働条件を変更することはできない。ただし、
次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、
労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況その他の
就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
********************
1合意による変更の原則
労働契約法8条⇒合意による労働契約の変更ができる。
労働契約法9条⇒
原則:労働契約の変更については、合意による
2合理的変更
労働契約法10条⇒合意による労働契約の変更の原則の
例外:合意によらなくても就業規則の変更が合理的なものである限り、就業規則の適用がある。
3合理性の判断要素
労働契約法10条
1)労働者の受ける不利益の程度(第四銀行事件:ア就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度)
2)労働条件の変更の必要性(第四銀行事件:イ使用者側の変更の必要性の内容・程度)
3)変更後の就業規則の内容の相当性(第四銀行事件:ウ変更後の就業規則の内容自体の相当性、エ代償措置、その他関連する労働条件の改善状況)
4)労働組合等との交渉の状況(第四銀行事件:オ労働組合等との交渉の経緯、カ他の労働組合又は他の従業員の対応)
5)その他の就業規則の変更に係る事情(第四銀行事件:キ同種事項に関する我が国社会における一般状況等)
『労働法』 菅野和夫著 144ページ

【判例】
秋北バス事件 最大判昭和 43.12.25 民集 22 巻 13 号 3459 頁 百選 21
大曲市農協事件 最3小判昭和63.2.16民集42巻2号60頁
第四銀行事件 最2小判平成9.2.28民集51巻2号705頁 百選23
みちのく銀行事件 最1小判平成12.9.7民集54巻7号2075頁 百選7版28
以上