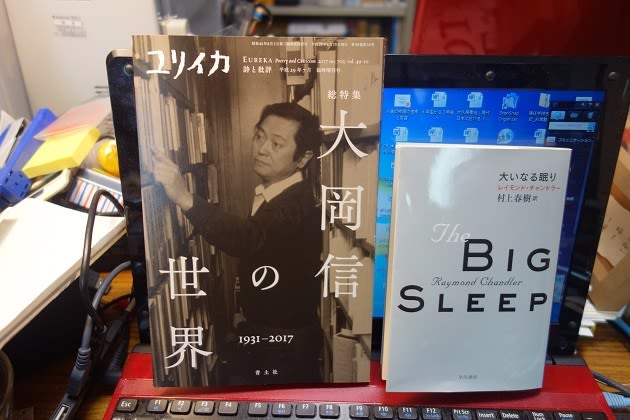8時、起床。
トースト、カレー、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。
牛乳はガラスのコップに入っている。ブログ仲間の「多田さん」のブログ(笑う門には福来る)に私が「コップ」という言葉を使っていることについて書いてあった。多田さんは長年飲食業界で働いてきた方だが、そこでは「コップ」という言葉はまず使われないそうだ。では、なんというのかというと、「グラス」というのだそうだ。そうなのか。そういわれるとそうだなと思う。

お昼に家を出て、大学へ。
7月19日と7月20日ととではずいぶんと違う。「18」と「19」の間は連続的だが、「19」と「20」の間は一段階進んで感じがする。「夏休み」という言葉を口に出してもいいように思う。実際、都内の小学校は今日、一学期の終業式が行われ、明日から夏休みだ。かつて大学は小学校より一足早く7月中旬には夏休みに入っていたが、いまは7月末まで授業期間だ。誰に聞いても(学内では)、かつての方がよかったという。ならぼ戻せばよさそうなものだが、そうならないのが時流というものである。たしかに教室には冷房が利いている。通学の電車の中も冷房が利いている。でも、自宅から駅までの路上、駅から学校までの路上は、猛暑である。この点を忘れてはいけない。
大学に到着した時点でかなりエネルギーを消耗している。

3限は大学院の演習。
それをすませて昼食は研究室でおにぎり。

3時からKさんのゼミ論指導。シュークリームの差し入れをいただく。おにぎりは2つにしておくべきだった。

5限は講義「日常生活の社会学」。パワポのスライドのファイルを入れたUSBを自宅に忘れてきてしまった。猛暑のせいだ。幸いプリントアウトしたものは鞄に入っていたので、それを書画カメラでスクリーンに映して授業をする。授業で使う資料の一部を研究室に忘れて来てしまった。これも猛暑のせいだ。映像資料を流している間に取りに戻る。授業の最後に来週の教場試験の話をする。みんな、授業よりも真剣に聞いていたかもしれない。答案というのは「私は授業の内容をちゃんと理解しています」というアピールである。それをお忘れなく。
帰りに「あゆみブックス」に寄って『将棋世界』8月号を購入。「電王戦」の第2局(佐藤名人が将棋ソフト「ポナンザ」に敗れた将棋)の棋譜が載っていたからである。電車の中でじっくり読む。先手(佐藤名人)の●2六歩に後手(ボナンザ)が○4二金と定跡にない(常識外れの)手を指して話題になったが、私に理解できなかったのは、そこから●2五歩、○3二金と進んで、そこでなぜ名人が●2四歩と指さなかったのかということだ。そう指せば、○同歩、●同飛、○2三歩、2六飛という進行になり、先手だけ飛車先を切って、一歩を手持ちにできるわけで、不満はないように思うのだが、なぜそういう風に「自然に」指さなかったのだろう。コンピューターの注文(○4二玉としたときにコンピューターが想定していた進行)を外すという意味があったのだろうか。あるいは2六飛という浮飛車の形が将来的に弱点になると考えたのだろうか。昨年の電王戦では山崎八段が「ボナンザ」にいいところなく連敗したが、そのときの将棋も山崎八段の指し手は「自然さ」を欠いていた。相手がコンピューターということを過剰に意識して、その想定されるコースを外すような手を志向して、自分から指しにくい局面にもっていってしまったような将棋だった。棋譜だけを観るととてもプロの高段者の将棋ではない。今回の佐藤名人も、途中から穴熊に組み替えて、玉の守りの堅さで終盤勝負にもっていこうという戦術をとったが、的確に攻められて、一方的な終盤になってしまった。同じ負けるにしても、序盤、「先手だけ飛車先を切り、一歩を手持ちしてよし」という棋理に照らして「自然な」手を指した上で、負けた方がよかった。そうすれば、従来の「棋理」を一から見直そうという一種の宗教改革、あるいは科学におけるパラダイム転換が起こって、将棋の進歩が新しい次元に入っていくことを名人が先導する結果になっただろう。実は、結果は同じで、名人の敗戦を観て、プロ棋士の多くはそういう宗教改革やパラダイム転換の必要を感じることになった訳だが、名人が「棋理」に殉じて敗れるのと、「棋理」に反して敗れるのとでは、大きな違いがある。「名人」というのはたんなるタイトルの一つでなく、(人間の)棋界の第一人者という意味づけを将棋ファンの多くはもっているからだ。名人には棋理の体現者として盤に向かってほしかった。

夕食はラムチョップ、サラダ、味噌汁、ご飯。

「ラムチョップは3本食べたい」という私の願いは今日も聞き入れてもらえなかった。夫も2本、妻も2本というのは一見、男女平等の理念に叶っているようだが、食欲の大きさの違いというのが考慮されないのは、道理に反しているのではなかろうか。妻もその点はわかっているはずだが、生協がラムチョップ4本入りで商品化している点が問題なのである。つまり私が3本だと妻は1本になってしまう。5本入りにしてくれるか、一本単位で注文できるようになるのがベストである。

蒲田の「有隣堂」でNHKの俳句のテキスト(8月号)を購入した。

先日、NHK全国俳句大会の案内状が届いた。投句の締め切りは9月末日。今回の題詠は「山」である。去年同様、自由題で二区、題詠で一句を作ろうか。それとも今回は新作15句一組の「飯田龍太賞」に(も)頑張って応募してみようかしら。投句料は前者の3句一組が3000円、後者の15句一組が5000円で、そんなに違わないのだ。

今夜は外が蒸し暑いらしく、冷房の効いた書斎でなつが寛いでいる。

4時、就寝。













 た
た








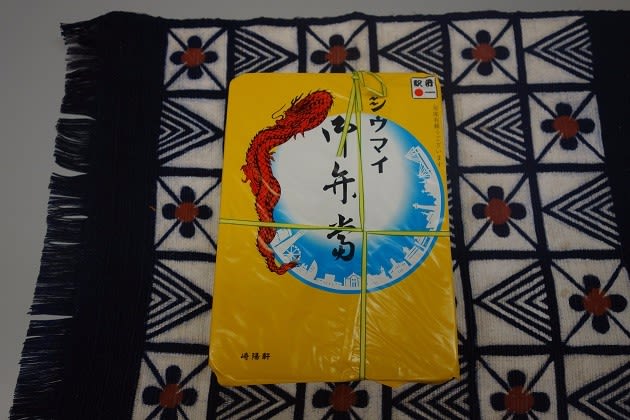











 桃は無農薬や減農薬というわけにはいきませんが、桃がある時だけ提供したいと思います
桃は無農薬や減農薬というわけにはいきませんが、桃がある時だけ提供したいと思います 基本的には
基本的には 金曜日、土曜日
金曜日、土曜日 桃パン2個で500円、ドリンクとセットで800円となります。」
桃パン2個で500円、ドリンクとセットで800円となります。」