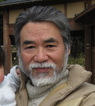子育て相談にきた質問を、紹介させていただきます。
多くのことを感じていただけると思います。
****************
1歳半になる娘の癖が気になり始めました。
たぶんチックではないかと思い、いろいろ調べました。その可能性は高いと思います。
1歳前から無意識頻繁に、鼻にしわをよせることがありました。そのときは何も感じませんでした。
最近はあまりありませんが、そのかわり、ふとした瞬間に両肩をもちあげる動作がでてきました。
最初は髪の毛がのびて首元が気になるのかと思っていましたが、なんだかそうではないと思い始めました。というのは、チックになるであろう原因に心当たりがあるからです。
娘は7ヶ月頃からひどい便秘になり、おまるできばる練習をはじめました。
それは成功し、硬いウンチはおまるで出せるようになって便秘も解消しました。しかし、それと同時に、私の中で、おまるでウンチができるということが誇りになりました。
それまで周りの赤ちゃんより寝返りなどすべてにおいて遅かったので、おまるでウンチできるんだから、他が遅くてもこの子はすごいんだ、と思い込もうとするようになりました。
1歳前になって、急におまるに座ることを嫌がり、オムツにウンチをするようになりました。私はそれが悔しくてたまりませんでした。
どうしておまるにウンチしないの?!できるくせに!?と、イライラし、はじめて娘のお尻をたたいたのはそのときでした。
しばらく無理やりおまるに座らせたり、オムツにウンチをするとお尻をたたいてしまったりしました。いけないことだとわかっているのに、唯一の誇りだったことがなくなってしまったかのようで、悔しくてイライラして、主人にもたたいてしまうことを相談し、なんとか自分の苛立ちをおさえることができました。
最近は、ムラ食いをするようになって、イスに座るのを嫌がったりスプーンを投げたり、べえっと吐き出したり、そういう行動がどうしてもカチンときて怒ってしまうことが多くなりました。
お尻をたたくことは以前よりは減った、というか、たたきたくなる衝動を抑えるために、ソファのうしろから出られないように閉じ込めるというおしおきをしてしまうようになりました。
娘はもちろん怒られて閉じ込められて、泣きながら私の顔を見ます。でもどうしてもしばらくの間は、抱っこしてあげることができないのです。元来の性格だと思います。イライラがなかなかおさまりません。ソファのうしろから出してあげると、娘は泣きながらおっぱいをほしがりますが、まだイライラしている私は「おっぱいはなし!」と言います。娘はまた泣きます。
少しすると娘はあきらめて、泣き止んでおもちゃで遊び始めます。私はしばらく育児放棄のような、娘が私の機嫌をとりに来ても無視してしまいます。
もちろん、すべて自分が間違っていることはわかっています。
抱っこしてあげられたらどんなに自分もこの子も、こんな嫌な気分にならずにすむだろう、救われるだろうと思います。こうしてメールをうっている横で、すやすやとかわいい顔をして眠るこの子を愛しいと思います。
だけど、自分の感情をコントロールできないのです。
涙がでます。この先、このままチックが出続けるようなことがないように、できるだけ怒らずにいよう、そう思うには思うのです。
決意するのです。でも、いざその場面になると、やっぱり言葉や行動には我慢していても、心の中の怒りには、きっと娘も気づいているんだと思います。
おおらかに子育てできる人が本当にうらやましいと思ってしまいます。
それぞれに悩みや不安はあるだろうに、感情をうまくコントロールできて楽しく子育てができる人が、本当にうらやましい。そうなりたい。
私の主人はこのタイプなんです。娘はまだ救われているかもしれません。
仕事から帰ってくると娘とたくさん遊んでくれます。
私の性格の問題なんです。チックも、遺伝性・家族性のものかもしれません。姉が中学時代に髪の毛を抜くという症状がありました。
*****************
連絡いただきました状況は比較的良くあります。
母親の養育体験が悪く、父親の養育体験がよい、そのために父親は母親の気持ちが理解できず、さらに母親は実母との関係性も悪いため、実母の助けが得られず、実母との関係性障害により、基本的信頼関係を築く能力がないので、他人を信頼できず、親友がなく孤立する。
このような状況を乗り越えるためには、母乳を吸わせることができる時期であれば、母乳を吸わせてオキシトシンの分泌により子どもとの関係性を強めることができます。
しかし、母乳が終わる時期になるとイライラしてきます。本人の力ではどうにもならないので、そのような状態を改善する最も早い方法は薬物です。
バルプロ酸と呼ばれる抗てんかん薬を200mgねる前に内服するとイライラがかなり消えます。
次に心を抱きしめてもらうことです。
実母や夫が心を理解できるようであれば、育児をじっと見つめてもらうだけでも楽になります。
非難せず全てを受け入れる姿勢をもち、じっと見つめます。それは無理なことが多いので、同性の誰か理解していただける人に支えてもらう必要があります。
最も危険なことは母親と子どもが二人だけになることです。
子どもの頃抱っこされず、ほめてもらえず、子どもが本来もっている行動を受け入れてもらえず、行動様式を変えるようにしつけや教育を受けたりして、つらい養育期間をすごすと、将来、自分の子どもを抱きしめたり誉めたりできなくなります。
決してその母親が悪いのではなく、子どもの時に受けた養育によって、自分の子どもを攻撃するように脳が形を変えてしまっています。気持ちを変えたりするような簡単な方法ではうまく行かないので治療がいります。
前頭葉をきたえる方法も幾分有効で、音読がよいです。文字の大きい本、絵本でも良いと思いますが、1日10分以上声に出して読むこと、脈拍が120~140/分程度まで増加する有酸素運動を1日1時間ほどすること。夫婦の性行為でも良いと思います。性器の刺激や、オルガスムスで、男女ともオキシトシンが分泌され、夫婦の絆も強まります。
それ以外にも、木の香りを嗅ぐこと、木の多いところに行くこと、テルペンと呼ばれる木の香りに精神安定作用があります。などです。1つずつ実行されては如何でしょうか。
(白川嘉継先生 福岡新水巻病院小児科)
********
養育体験は、子育てに大きく影響します。
私たちは、親への支援がどこまでできるのか模索しながら働かせていただいています。
不幸な養育体験を持った親への支援は、世代間連鎖を絶つためにもとても重要です。
ただ私に出来るのは、聴いてあげることだけです。
それを今後も続けていきます。いい聞き手になれるように。
多くのことを感じていただけると思います。
****************
1歳半になる娘の癖が気になり始めました。
たぶんチックではないかと思い、いろいろ調べました。その可能性は高いと思います。
1歳前から無意識頻繁に、鼻にしわをよせることがありました。そのときは何も感じませんでした。
最近はあまりありませんが、そのかわり、ふとした瞬間に両肩をもちあげる動作がでてきました。
最初は髪の毛がのびて首元が気になるのかと思っていましたが、なんだかそうではないと思い始めました。というのは、チックになるであろう原因に心当たりがあるからです。
娘は7ヶ月頃からひどい便秘になり、おまるできばる練習をはじめました。
それは成功し、硬いウンチはおまるで出せるようになって便秘も解消しました。しかし、それと同時に、私の中で、おまるでウンチができるということが誇りになりました。
それまで周りの赤ちゃんより寝返りなどすべてにおいて遅かったので、おまるでウンチできるんだから、他が遅くてもこの子はすごいんだ、と思い込もうとするようになりました。
1歳前になって、急におまるに座ることを嫌がり、オムツにウンチをするようになりました。私はそれが悔しくてたまりませんでした。
どうしておまるにウンチしないの?!できるくせに!?と、イライラし、はじめて娘のお尻をたたいたのはそのときでした。
しばらく無理やりおまるに座らせたり、オムツにウンチをするとお尻をたたいてしまったりしました。いけないことだとわかっているのに、唯一の誇りだったことがなくなってしまったかのようで、悔しくてイライラして、主人にもたたいてしまうことを相談し、なんとか自分の苛立ちをおさえることができました。
最近は、ムラ食いをするようになって、イスに座るのを嫌がったりスプーンを投げたり、べえっと吐き出したり、そういう行動がどうしてもカチンときて怒ってしまうことが多くなりました。
お尻をたたくことは以前よりは減った、というか、たたきたくなる衝動を抑えるために、ソファのうしろから出られないように閉じ込めるというおしおきをしてしまうようになりました。
娘はもちろん怒られて閉じ込められて、泣きながら私の顔を見ます。でもどうしてもしばらくの間は、抱っこしてあげることができないのです。元来の性格だと思います。イライラがなかなかおさまりません。ソファのうしろから出してあげると、娘は泣きながらおっぱいをほしがりますが、まだイライラしている私は「おっぱいはなし!」と言います。娘はまた泣きます。
少しすると娘はあきらめて、泣き止んでおもちゃで遊び始めます。私はしばらく育児放棄のような、娘が私の機嫌をとりに来ても無視してしまいます。
もちろん、すべて自分が間違っていることはわかっています。
抱っこしてあげられたらどんなに自分もこの子も、こんな嫌な気分にならずにすむだろう、救われるだろうと思います。こうしてメールをうっている横で、すやすやとかわいい顔をして眠るこの子を愛しいと思います。
だけど、自分の感情をコントロールできないのです。
涙がでます。この先、このままチックが出続けるようなことがないように、できるだけ怒らずにいよう、そう思うには思うのです。
決意するのです。でも、いざその場面になると、やっぱり言葉や行動には我慢していても、心の中の怒りには、きっと娘も気づいているんだと思います。
おおらかに子育てできる人が本当にうらやましいと思ってしまいます。
それぞれに悩みや不安はあるだろうに、感情をうまくコントロールできて楽しく子育てができる人が、本当にうらやましい。そうなりたい。
私の主人はこのタイプなんです。娘はまだ救われているかもしれません。
仕事から帰ってくると娘とたくさん遊んでくれます。
私の性格の問題なんです。チックも、遺伝性・家族性のものかもしれません。姉が中学時代に髪の毛を抜くという症状がありました。
*****************
連絡いただきました状況は比較的良くあります。
母親の養育体験が悪く、父親の養育体験がよい、そのために父親は母親の気持ちが理解できず、さらに母親は実母との関係性も悪いため、実母の助けが得られず、実母との関係性障害により、基本的信頼関係を築く能力がないので、他人を信頼できず、親友がなく孤立する。
このような状況を乗り越えるためには、母乳を吸わせることができる時期であれば、母乳を吸わせてオキシトシンの分泌により子どもとの関係性を強めることができます。
しかし、母乳が終わる時期になるとイライラしてきます。本人の力ではどうにもならないので、そのような状態を改善する最も早い方法は薬物です。
バルプロ酸と呼ばれる抗てんかん薬を200mgねる前に内服するとイライラがかなり消えます。
次に心を抱きしめてもらうことです。
実母や夫が心を理解できるようであれば、育児をじっと見つめてもらうだけでも楽になります。
非難せず全てを受け入れる姿勢をもち、じっと見つめます。それは無理なことが多いので、同性の誰か理解していただける人に支えてもらう必要があります。
最も危険なことは母親と子どもが二人だけになることです。
子どもの頃抱っこされず、ほめてもらえず、子どもが本来もっている行動を受け入れてもらえず、行動様式を変えるようにしつけや教育を受けたりして、つらい養育期間をすごすと、将来、自分の子どもを抱きしめたり誉めたりできなくなります。
決してその母親が悪いのではなく、子どもの時に受けた養育によって、自分の子どもを攻撃するように脳が形を変えてしまっています。気持ちを変えたりするような簡単な方法ではうまく行かないので治療がいります。
前頭葉をきたえる方法も幾分有効で、音読がよいです。文字の大きい本、絵本でも良いと思いますが、1日10分以上声に出して読むこと、脈拍が120~140/分程度まで増加する有酸素運動を1日1時間ほどすること。夫婦の性行為でも良いと思います。性器の刺激や、オルガスムスで、男女ともオキシトシンが分泌され、夫婦の絆も強まります。
それ以外にも、木の香りを嗅ぐこと、木の多いところに行くこと、テルペンと呼ばれる木の香りに精神安定作用があります。などです。1つずつ実行されては如何でしょうか。
(白川嘉継先生 福岡新水巻病院小児科)
********
養育体験は、子育てに大きく影響します。
私たちは、親への支援がどこまでできるのか模索しながら働かせていただいています。
不幸な養育体験を持った親への支援は、世代間連鎖を絶つためにもとても重要です。
ただ私に出来るのは、聴いてあげることだけです。
それを今後も続けていきます。いい聞き手になれるように。