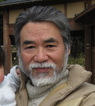オキシトシンの研究をされている東北大学農学部西森克彦教授は「学問的なレベルで、オキシトシンやオキシトシン受容体が動物のみ成らず、ヒトとヒト間の母性行動や敵対行動、或いは自閉症のような精神疾患と深く関連しているという概念の確立に、科学的に至る迄にはまだまだ長い年月と多くの研究者のこの分野への参加・貢献が必要と思われます。」
そこで今回はこれまでに寄せられた質問の中からオキシトシンに関連する質問から選んでみました。新井一令
**********************************
母乳育児と赤ちゃんの精神面、親子関係について質問させて下さい。6ヶ月になったばかりの娘ですが今まで完母にするためがんばってきたがどうしても母乳量が増えずミルク中心になっています。以前、別の方の相談で6ヶ月までが親子関係の構築に重要とありました。頻繁におっぱいを吸わせるようにしていますが母乳量が少ないとオキシトシン(親子関係にとても重要なホルモンと聞きました)が充分に伝わらないのではないでしょうか?また将来、ストレスに弱い子にならないでしょうか?結果的に乳首をおしゃぶりがわりにしてしまっているような状態です。娘の心の発達にとって問題はないでしょうか?私自身、子どもの頃から実母との関係がうまくいっておらず(私は完ミで育ちました)それだけに母乳にこだわってやってきました。しかし、最近はうまく吸ってくれないことにイライラしてしまいます。もうこの子とよい親子関係が築けないのではとても不安です。
回答 たまごママネット医師団
心地よさを与えられられた乳獣は、脳内でオキシトシンが産生され、ストレスから脳が護られたり、将来子育て行動を取りやすくなったりすることが知られています。人間でも同様であることが考えられますが、人は前頭葉の機能が高く、乳幼児期以降にも、人格の発達は行われます。実母との関係が悪い場合は、母子関係性障害が存在し、基本的信頼関係が欠如している可能性があります。
基本的信頼関係が欠如すると、自分に自信がない、他人を信頼できない人生になってしまします。自分に自身が無く他人を信頼できないと依存症に陥りやすく、学業依存、スポ-ツ依存、職業依存、アルコール依存、薬物依存として現れることがあります。基本的信頼関係が欠如していても、赤ちゃんが産まれ、心静かに赤ちゃんの瞳を見つめ、赤ちゃんの瞳に写る自分の姿を見つけることができた時には、生まれて初めて他人から信頼されること、他人を信頼することを知ることができるでしょう。育児環境は世代間伝達するので、つらい乳幼児期を過ごしてしまうと、自分自身の子育てに影響することは良くあります。
多く見積もって7割の両親が、子育てに喜びを感じていないかもしれません。
また、子どもと関係性を結ぶ能力が高い母親でも、母子だけが二人きりで取り残されると、不安定になってしまうこともあります。子どもが心地よい感覚を与えられるのは、母乳栄養が全てではなく、最も大切なことは、母親が楽しんで育児できているかどうかにあります。つらいときには可能な限り、子どもと二人の世界に入らず、じっと静かに見つめてくれる人を探し、頼ることが大切です。夫が最も良いとおもいます。それ以外にも、育児支援を行っているグループに助けを求めるのも良いでしょう。人間は人として産まれて、人と人の間で支えられて人間に発達します。決して一人で頑張るべきではありません。
自分自身が精神的に安定し幸せになることが大切です。それには母乳を与えることが、最も簡単な手段になりますが、それが全てではありません。心を静かにして赤ちゃんの瞳を見つめて微笑むと、きっと微笑み返してくれるでしょう。
それが赤ちゃんに与えることのできる心地よさです。
福岡新水巻病院小児科 白川嘉継先生
****************
赤ちゃんとの間で基本的信頼関係を構築してください。
心を落ち着かせて赤ちゃんの瞳の中にあなたの優しい顔を映してあげてください。赤ちゃんがきっと微笑みかえしてくれます。
そこで今回はこれまでに寄せられた質問の中からオキシトシンに関連する質問から選んでみました。新井一令
**********************************
母乳育児と赤ちゃんの精神面、親子関係について質問させて下さい。6ヶ月になったばかりの娘ですが今まで完母にするためがんばってきたがどうしても母乳量が増えずミルク中心になっています。以前、別の方の相談で6ヶ月までが親子関係の構築に重要とありました。頻繁におっぱいを吸わせるようにしていますが母乳量が少ないとオキシトシン(親子関係にとても重要なホルモンと聞きました)が充分に伝わらないのではないでしょうか?また将来、ストレスに弱い子にならないでしょうか?結果的に乳首をおしゃぶりがわりにしてしまっているような状態です。娘の心の発達にとって問題はないでしょうか?私自身、子どもの頃から実母との関係がうまくいっておらず(私は完ミで育ちました)それだけに母乳にこだわってやってきました。しかし、最近はうまく吸ってくれないことにイライラしてしまいます。もうこの子とよい親子関係が築けないのではとても不安です。
回答 たまごママネット医師団
心地よさを与えられられた乳獣は、脳内でオキシトシンが産生され、ストレスから脳が護られたり、将来子育て行動を取りやすくなったりすることが知られています。人間でも同様であることが考えられますが、人は前頭葉の機能が高く、乳幼児期以降にも、人格の発達は行われます。実母との関係が悪い場合は、母子関係性障害が存在し、基本的信頼関係が欠如している可能性があります。
基本的信頼関係が欠如すると、自分に自信がない、他人を信頼できない人生になってしまします。自分に自身が無く他人を信頼できないと依存症に陥りやすく、学業依存、スポ-ツ依存、職業依存、アルコール依存、薬物依存として現れることがあります。基本的信頼関係が欠如していても、赤ちゃんが産まれ、心静かに赤ちゃんの瞳を見つめ、赤ちゃんの瞳に写る自分の姿を見つけることができた時には、生まれて初めて他人から信頼されること、他人を信頼することを知ることができるでしょう。育児環境は世代間伝達するので、つらい乳幼児期を過ごしてしまうと、自分自身の子育てに影響することは良くあります。
多く見積もって7割の両親が、子育てに喜びを感じていないかもしれません。
また、子どもと関係性を結ぶ能力が高い母親でも、母子だけが二人きりで取り残されると、不安定になってしまうこともあります。子どもが心地よい感覚を与えられるのは、母乳栄養が全てではなく、最も大切なことは、母親が楽しんで育児できているかどうかにあります。つらいときには可能な限り、子どもと二人の世界に入らず、じっと静かに見つめてくれる人を探し、頼ることが大切です。夫が最も良いとおもいます。それ以外にも、育児支援を行っているグループに助けを求めるのも良いでしょう。人間は人として産まれて、人と人の間で支えられて人間に発達します。決して一人で頑張るべきではありません。
自分自身が精神的に安定し幸せになることが大切です。それには母乳を与えることが、最も簡単な手段になりますが、それが全てではありません。心を静かにして赤ちゃんの瞳を見つめて微笑むと、きっと微笑み返してくれるでしょう。
それが赤ちゃんに与えることのできる心地よさです。
福岡新水巻病院小児科 白川嘉継先生
****************
赤ちゃんとの間で基本的信頼関係を構築してください。
心を落ち着かせて赤ちゃんの瞳の中にあなたの優しい顔を映してあげてください。赤ちゃんがきっと微笑みかえしてくれます。