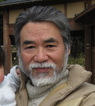今回は、祖母の間違ったアドバイスについてお知らせします。
昔の育児知識でいいものもあるのですが、間違った知識も多いのです。
特に団塊の世代が受けた子育てをそのまま引きずっている人たちが困りものです。
かくいう私も61歳ですから困った世代です。
******
生後1ヶ月と少しがたちましたが母乳だけでいいのでしょうか?
先日1ヶ月健診で、おむつかぶれが少し心配ですが、特に問題もなく、体重も母乳のみで1.5キロ増えてました。
1ヶ月が過ぎたので、徐々に母乳以外の味も・・と思い、麦茶やお白湯を飲ませようとするのですが、哺乳瓶の乳首の感触が嫌いみたいで飲んでくれません。
水分補給という意味で、母乳だけでいいのでしょうか?
このところ、気温も高くなってきてのどが渇いたりしないのですかね・・。
私の母は、母乳だけだと、濃いのでお白湯やお茶を、飲ませないと・・・と言うのですが、お風呂あがりも、飲んでくれないので母乳をあげています。
甘い味なら飲んでくれるようですが、砂糖を入れたりしても良いのですか?
特にぐずったりしないので問題ないのかなぁと思いながら、やはり日々大きくなってきたので、水分は足りているのか心配ですというお尋ねがありました。
****************
母乳で1.5キロも増えているということはすごいですね。
母乳が良く出ていて、赤ちゃんの飲み方も上手なのでしょう。
赤ちゃんはお母さんの母乳が大好きで、哺乳びんの乳首との違いをはっきり知っているためにいやがります。
母乳だけで他に何も与える必要はありません。
哺乳びんを使うのは止めましょう。
母乳には赤ちゃんが6ヶ月まで育つのに充分の栄養が含まれます。
お母さんが食べたものの成分がその味と匂いとともに母乳の中に入ります。
赤ちゃんはお母さんと同じものを食べていることになります。
お母さんが普通に食事をとって入れば赤ちゃんの栄養が足りなくなるということはありません。
様々な味を経験していますから離乳準備食というものも必要ありません。
6ヶ月までの赤ちゃんの腸の粘膜は、大きい分子の蛋白や本来体の中に入ってはいけない物質まで通過させてしまうということがわかってきました。
これは早い時期に様々なものを赤ちゃんに与えるとアレルギー性疾患の発症の危険性を高くすることを意味します。
6ヶ月を過ぎる頃になると粘膜の成長によってこの様なことが少なくなることがわかっています。ですから6ヶ月までは母乳以外のものを与えることは赤ちゃんにとって良くないことなのです。
湯冷ましも赤ちゃんにとって必要のないものです。母乳の成分の88%は水分です。十分に母乳を飲んでいる赤ちゃんはそれだけ多くの水分もとっているのです。オシッコで重たくなったオムツを見てください。
腎臓はオッパイの水分を処理するのに一生懸命です。そこに湯冷ましを与えることは腎臓に負担を掛けるだけで、良いことは何もありません。
お風呂上がりにも母乳をあげれば十分です。
果汁や湯冷ましを与える慣習は、戦後間もないころ、品質の悪いミルクを飲ませていたために必要だったことが、その後改められることもなく続いているのです。また腸管組織の発達から見ても6ヶ月までは母乳やミルクの他には与えない方がよいと考えられています。
アメリカの小児科学会では2001年に「6ヶ月前には果汁は決して与えてはいけない」との声明を出していますが、日本ではまだ慣習として与えられる場合が多いのが現状です。
我が国でも昨年3月に、厚生労働省から「授乳・離乳のガイド」が出され。
6ヶ月までは、果汁などの水分を与える必要はないとされました。
まわりの間違った無責任なアドバイスに惑わされないでくださいね。
昔の育児知識でいいものもあるのですが、間違った知識も多いのです。
特に団塊の世代が受けた子育てをそのまま引きずっている人たちが困りものです。
かくいう私も61歳ですから困った世代です。
******
生後1ヶ月と少しがたちましたが母乳だけでいいのでしょうか?
先日1ヶ月健診で、おむつかぶれが少し心配ですが、特に問題もなく、体重も母乳のみで1.5キロ増えてました。
1ヶ月が過ぎたので、徐々に母乳以外の味も・・と思い、麦茶やお白湯を飲ませようとするのですが、哺乳瓶の乳首の感触が嫌いみたいで飲んでくれません。
水分補給という意味で、母乳だけでいいのでしょうか?
このところ、気温も高くなってきてのどが渇いたりしないのですかね・・。
私の母は、母乳だけだと、濃いのでお白湯やお茶を、飲ませないと・・・と言うのですが、お風呂あがりも、飲んでくれないので母乳をあげています。
甘い味なら飲んでくれるようですが、砂糖を入れたりしても良いのですか?
特にぐずったりしないので問題ないのかなぁと思いながら、やはり日々大きくなってきたので、水分は足りているのか心配ですというお尋ねがありました。
****************
母乳で1.5キロも増えているということはすごいですね。
母乳が良く出ていて、赤ちゃんの飲み方も上手なのでしょう。
赤ちゃんはお母さんの母乳が大好きで、哺乳びんの乳首との違いをはっきり知っているためにいやがります。
母乳だけで他に何も与える必要はありません。
哺乳びんを使うのは止めましょう。
母乳には赤ちゃんが6ヶ月まで育つのに充分の栄養が含まれます。
お母さんが食べたものの成分がその味と匂いとともに母乳の中に入ります。
赤ちゃんはお母さんと同じものを食べていることになります。
お母さんが普通に食事をとって入れば赤ちゃんの栄養が足りなくなるということはありません。
様々な味を経験していますから離乳準備食というものも必要ありません。
6ヶ月までの赤ちゃんの腸の粘膜は、大きい分子の蛋白や本来体の中に入ってはいけない物質まで通過させてしまうということがわかってきました。
これは早い時期に様々なものを赤ちゃんに与えるとアレルギー性疾患の発症の危険性を高くすることを意味します。
6ヶ月を過ぎる頃になると粘膜の成長によってこの様なことが少なくなることがわかっています。ですから6ヶ月までは母乳以外のものを与えることは赤ちゃんにとって良くないことなのです。
湯冷ましも赤ちゃんにとって必要のないものです。母乳の成分の88%は水分です。十分に母乳を飲んでいる赤ちゃんはそれだけ多くの水分もとっているのです。オシッコで重たくなったオムツを見てください。
腎臓はオッパイの水分を処理するのに一生懸命です。そこに湯冷ましを与えることは腎臓に負担を掛けるだけで、良いことは何もありません。
お風呂上がりにも母乳をあげれば十分です。
果汁や湯冷ましを与える慣習は、戦後間もないころ、品質の悪いミルクを飲ませていたために必要だったことが、その後改められることもなく続いているのです。また腸管組織の発達から見ても6ヶ月までは母乳やミルクの他には与えない方がよいと考えられています。
アメリカの小児科学会では2001年に「6ヶ月前には果汁は決して与えてはいけない」との声明を出していますが、日本ではまだ慣習として与えられる場合が多いのが現状です。
我が国でも昨年3月に、厚生労働省から「授乳・離乳のガイド」が出され。
6ヶ月までは、果汁などの水分を与える必要はないとされました。
まわりの間違った無責任なアドバイスに惑わされないでくださいね。