
《自作の織部風のニシン鉢に漬ける》
庭のサンショウが勢いよく新芽を伸ばしている。終わった花をルーペで見ると、らっきょ形のタマがペアになって見える。これが青い実に成長して次第に赤く色づいていき、秋には黒い実となって弾ける。サンショウは毎年、芽吹きから実りまで、そして葉を落とし実の殻だけが残る晩秋まで、興味深く観察を楽しませてくれる。
(ところで、俳句の季語で、「山椒の芽」は春。「山椒の花」は夏。「山椒の実」は秋だそうだ。)
この時期、わが家ではこの山椒を使ってニシンを漬ける。
この山椒漬けは、簡単だし、酒の肴を楽しむ私なので毎年私の仕事だ。
会津は海から遠い山国、ニシンの山椒漬けは棒タラ*と共に古くから海の幸を干物に利用してきた会津の伝統料理である。
このニシンの山椒漬けはもちろん自作した「ニシン鉢」に漬けなければダメ。タッパーではどうしても気分的に美味しくない。また、今は真空パックでスーパーやお土産で売っていていつでも食べることができるが、やはりこの時期に食べる”旬の味”が何とも言えない。
私が煮物が好きなので、妻はいろいろ作ってくれる。会津では干物の身欠きニシンに対して生のニシンをカドイワシと呼んでいるが、このニシンを使った煮物は、大根干しやタケノコ、椎茸、ジャガイモなどと、またワラビやイラなど山菜によく合いとても美味しい。
先ほど漬けて冷蔵庫に入れた、3,4日後の出来上がりが楽しみだ。
--------------------------------
<ニシンの山椒漬けの作り方>
材料:・身欠ニシン(10本)・山椒の葉(20~30枚)・しょうゆ(150cc)
・酢(100cc)・酒(100cc)・赤唐からし1本
①ニシンは水でよく洗い、米のとぎ汁でアクを抜く。
②山椒の葉も水でよく洗って水気を切っておく。
③ニシンを漬ける器に①のニシンと②の山椒の葉を交互に重ねる。
④漬け汁にしょう油・酢・酒に、種子を取り除いた赤唐辛子をみじん切りにして加え、火にかけて汁を作る。
⑤上から汁をかけて、押しぶたと軽い重石をのせて漬ける。
--------------------------------
*拙ブログ(2006.1.10)「お正月に 会津の食文化を楽しむ」
庭のサンショウが勢いよく新芽を伸ばしている。終わった花をルーペで見ると、らっきょ形のタマがペアになって見える。これが青い実に成長して次第に赤く色づいていき、秋には黒い実となって弾ける。サンショウは毎年、芽吹きから実りまで、そして葉を落とし実の殻だけが残る晩秋まで、興味深く観察を楽しませてくれる。
(ところで、俳句の季語で、「山椒の芽」は春。「山椒の花」は夏。「山椒の実」は秋だそうだ。)
この時期、わが家ではこの山椒を使ってニシンを漬ける。
この山椒漬けは、簡単だし、酒の肴を楽しむ私なので毎年私の仕事だ。
会津は海から遠い山国、ニシンの山椒漬けは棒タラ*と共に古くから海の幸を干物に利用してきた会津の伝統料理である。
このニシンの山椒漬けはもちろん自作した「ニシン鉢」に漬けなければダメ。タッパーではどうしても気分的に美味しくない。また、今は真空パックでスーパーやお土産で売っていていつでも食べることができるが、やはりこの時期に食べる”旬の味”が何とも言えない。
私が煮物が好きなので、妻はいろいろ作ってくれる。会津では干物の身欠きニシンに対して生のニシンをカドイワシと呼んでいるが、このニシンを使った煮物は、大根干しやタケノコ、椎茸、ジャガイモなどと、またワラビやイラなど山菜によく合いとても美味しい。
先ほど漬けて冷蔵庫に入れた、3,4日後の出来上がりが楽しみだ。
--------------------------------
<ニシンの山椒漬けの作り方>
材料:・身欠ニシン(10本)・山椒の葉(20~30枚)・しょうゆ(150cc)
・酢(100cc)・酒(100cc)・赤唐からし1本
①ニシンは水でよく洗い、米のとぎ汁でアクを抜く。
②山椒の葉も水でよく洗って水気を切っておく。
③ニシンを漬ける器に①のニシンと②の山椒の葉を交互に重ねる。
④漬け汁にしょう油・酢・酒に、種子を取り除いた赤唐辛子をみじん切りにして加え、火にかけて汁を作る。
⑤上から汁をかけて、押しぶたと軽い重石をのせて漬ける。
--------------------------------
*拙ブログ(2006.1.10)「お正月に 会津の食文化を楽しむ」











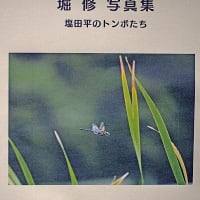








姿や形が違うので別種の魚と思っていました。
会津のカドイワシの意味はわかりませんが、信州と似ていますね。
ニシンの山椒漬けなる珍味が存在することはじめて知りました。
山椒漬けは、会津の料理屋、居酒屋では必ず出る郷土食です。
ネットで検索してみたら【東北、北海道ではカド、関東ではカドイワシともいい、アイヌ語でニシンのことをカド数の子は「カドの子」がなまったもの。とありました。】
こんなにうまい魚なのに、家ではニシンは臭いが嫌と、私以外は敬遠しています。