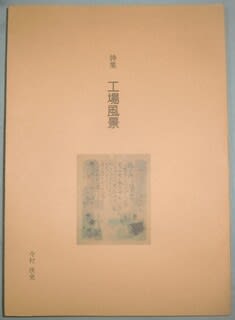「KOBECCO」5月号に書いたエッセイ「飛騨高山」です。

こちらから読めます。→「飛騨高山の山鳥」。
この原稿を書くために、「飛騨高山まちの博物館」さんにお世話になりました。
なので、この5月号をお礼代わりにお送りしました。
するとそれへの礼状が届きました。
ご丁寧なことです。
こんなことが書かれています。
《課内で回覧いたしました。職員一同、紹介いただきましたことを大変喜んでおりました。(略)高山にお越しの際は、当館へ是非お立ち寄りください。》
うれしいことでした。
機会があれば行ってみたいですねえ。
『コーヒーカップの耳』おもしろうて、やがて哀しき喫茶店。

こちらから読めます。→「飛騨高山の山鳥」。
この原稿を書くために、「飛騨高山まちの博物館」さんにお世話になりました。
なので、この5月号をお礼代わりにお送りしました。
するとそれへの礼状が届きました。
ご丁寧なことです。
こんなことが書かれています。
《課内で回覧いたしました。職員一同、紹介いただきましたことを大変喜んでおりました。(略)高山にお越しの際は、当館へ是非お立ち寄りください。》
うれしいことでした。
機会があれば行ってみたいですねえ。
『コーヒーカップの耳』おもしろうて、やがて哀しき喫茶店。