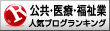6月6日の「第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会」の席上、介護労働者を定着させるかをテーマに先進的実践例が報告されたという。そのなかでの発言「事務業務が苦手なため、管理者になってマネジメントの割合が高くなると退職してしまう例が出て」くる、「現行の介護職の養成カリキュラムには、マネジメントを養成する要素がない」という。
ここで明らかになったのは現場で求められる能力と管理者の能力とは異なることで、次に行うことは現場からスキルアップさせることが課題であることが分かった。議論の先にはこれを国として行うかどうかということなのだろう。
どこまでが国がおこなうことか法人はどこまで行うのか、その議論をせずになにがなんでもすべて厚労省に任せる、おんぶに抱っこでいいのだろうか。
国に任せるということは介護は一律でいいということを意味しているがその方法は以前大蔵省がとっていた銀行への指導、護衛船団方式があったがこの方法が機能していた戦後間もなくの経済状況では有効であったが経済のグローバル化によって護衛船団方式では力ある銀行は存在しえないという認識のもとこの護衛船団方式は否定されたのではなかったか。
いま介護は福祉政策から転換し保険として行っていることから銀行への集団的護衛船団方式が否定されたとの同じ意味を持っている。
介護職のスキル養成を国に委ねる方法から各職能で求められるスキル、グレードを分析しその達成方法を提示するということで事足りると考える。職能で求められるスキルがあればその後はスキルをいかに身につけるかであり、その実行者は法人が行うべき業務であろう。
人事のマネジメント能力の養成は法人が行うことではないのか、なにがなんでもすべて厚労省に任せる、おんぶに抱っこで一律の介護で、その法人であるための特色というものは必要ないのだろうか。かりに一律の内容でいいというならば法人に事業をゆだねる理由はどこに求めるのだろうか。
ここで明らかになったのは現場で求められる能力と管理者の能力とは異なることで、次に行うことは現場からスキルアップさせることが課題であることが分かった。議論の先にはこれを国として行うかどうかということなのだろう。
どこまでが国がおこなうことか法人はどこまで行うのか、その議論をせずになにがなんでもすべて厚労省に任せる、おんぶに抱っこでいいのだろうか。
国に任せるということは介護は一律でいいということを意味しているがその方法は以前大蔵省がとっていた銀行への指導、護衛船団方式があったがこの方法が機能していた戦後間もなくの経済状況では有効であったが経済のグローバル化によって護衛船団方式では力ある銀行は存在しえないという認識のもとこの護衛船団方式は否定されたのではなかったか。
いま介護は福祉政策から転換し保険として行っていることから銀行への集団的護衛船団方式が否定されたとの同じ意味を持っている。
介護職のスキル養成を国に委ねる方法から各職能で求められるスキル、グレードを分析しその達成方法を提示するということで事足りると考える。職能で求められるスキルがあればその後はスキルをいかに身につけるかであり、その実行者は法人が行うべき業務であろう。
人事のマネジメント能力の養成は法人が行うことではないのか、なにがなんでもすべて厚労省に任せる、おんぶに抱っこで一律の介護で、その法人であるための特色というものは必要ないのだろうか。かりに一律の内容でいいというならば法人に事業をゆだねる理由はどこに求めるのだろうか。