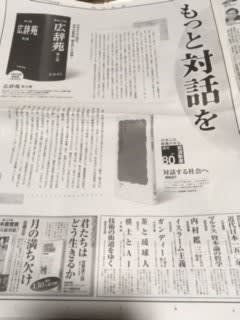日経新聞のWEBサイトを見ていたら、とても懐かしいコピーを見た。
日経新聞:「やわらか頭」再び? オリンパスなど企業CMに女優
「やわらか頭」と言われても、バブル経済を知らない世代にとっては「一体何を言っているの?」というコピーだろう。
バブル経済真っ盛りの頃、一般生活者にはあまりなじみの無い「重化学工業」の企業を中心に、積極的にテレビCMが制作された。
その時「重化学工業」というイメージとは似ても似つかない(と言っては失礼だが)女優さんやタレントさんたちが、積極的に起用され、リクルートに一役買ったといわれている。
その代表的なキャッチコピーが住友金属の「やわらか頭」だったのだ。
youtube:住友金属CM 1990年 山瀬まみ
他にも、新日鉄は映画・「エイリアン」の大ヒットで一躍有名になった?シガニー・ウィーバーを起用していた。
youtube:新日鉄CMシガニー・ウィーバー
紹介をした新日鉄のCMは、皮肉にも昨年暮れに閉園した「スペース・ワールド」のCMだが、住友金属にしても新日鉄にしても、それまでの基幹産業の一つとしての「重厚感さ」ではなく、軽やかなイメージをCMを通して伝えたい、という姿勢が見える内容になっていた。
特に山瀬まみさんを起用した住友金属の「やわらか頭」というキャッチコピーは、そのままリクルートでも使われ、住友金属が求める(新入)社員像となった、と言われた。
それから30年近く経ち、再び「やわらか頭」を企業が求めている、ということなのだろうか?
おそらく半分は当たっていると思うが、もう半分は違うのでは?という気がしている。
というのも、この30年の間で理工系学部に進学する女子学生は、随分と増えている。
「リケジョ」という言葉も、もはや一般的になりつつある。
オリンパスが宮崎あおいさんを起用したからと言って、一眼レフカメラで写真を撮る「カメラ女子」が普通になった今では、1990年の頃のような違和感や驚きはない。
採用される新卒者についても、かつてのような男女差は無くなりつつあるのではないだろうか?
もちろん、「総合職・一般職」という振り分けでの男女比は明らかにあるとは思うが、それでも随分差はなくなってきているのでは?と想像する。
何よりも今回の記事に書かれている企業は、いわゆる「基幹産業」と呼ばれる企業の中でも、比較的女性が活躍しやすい分野なのではないだろうか。
そう考えると、今の若手女優を積極的に企業がCMに起用する理由は、むしろ企業側の「やわらかさ」を生活者に訴えたいからでは?
言い換えれば、「親しみ度を上げたい」ということになるのではないだろうか?