 軽井沢に住む若者たちの青春群像として大人気だったコミックで、ある意味、日本の若者向け創作におけるターニングポイント。1981年スタートの1985年完結。
軽井沢に住む若者たちの青春群像として大人気だったコミックで、ある意味、日本の若者向け創作におけるターニングポイント。1981年スタートの1985年完結。「あいつの辞書には常識と羞恥の文字はねえな……絶対!!」
久遠寺紀子の耕平評。
その特徴の1つは、シリアスなシーンの八頭身キャラと三頭身のギャグキャラが頻繁に入れ替わって登場すること。それまでにも赤塚不二夫の作品みたいにギャグキャラが突然シリアスになることはあったし、山上たつひこのように作品ごとにギャグとシリアスを描き分ける作家はいたけれど、コマごとにギャグ-シリアスが入れ替わるのが常態という作品はなかった。それで、ダンバインやガンダムのコスプレをしてたりするのだけれど、これについては少女マンガの方が先行してたよね?
2つめは、もともとの読みとは違うルビを会話にふって二重三重の意味をもたせたこと。「幽波紋」と書いて「スタンド」と読ませた『ジョジョの奇妙な冒険』も、後続の作品やライトノベルに大きな影響を与えたのだろうけれど1987年スタートなので、こちらの方が先。ウィキペディアあたりだと「要出典」とか注意されるけれど、リアルで見ていたから出典もなにもないよなあ。
第1話冒頭で「碓氷峠」と書いて「とうげ」と読ませていたけれど、有名なのは第2話の「悪いコト」と書いて「いいこと」とルビをふったやつかな。
3つめは、主人公の回りに複数のヒロインがレギュラーで登場し、最終的にハーレムを構成したこと。それまでは、主人公は1人のヒロインと結ばれるものであり、複数の女性キャラと関係を持ってずるずると続けるというのはほとんどなかった。本宮ひろ志の『俺の空』も主人公の女性遍歴がひとつの物語の要素にはなっていたけれど、基本はゆきずりの関係というかたった1人のための修行の旅でした。あえていうなら同じく1981年スタートの『弐十手物語』もそういう展開になっていたはずだけれど、全編読み通していないし、ウィキペディアにも項目がないので確認できてません。
ツィッターでそういうことをつぶやいたら、『イヤハヤ南友』とかギリシア神話や『源氏物語』もそうじゃないかと指摘され、考えました。
永井豪の『イヤハヤ南友』は好きな作品だけれど、ハーレムが成立したのは最終回の最後の1ページで、それまでそんなに全キャラとは親しくなってなかったよね?(個人的には弁天ゆりと家早さよこだけのような気がします)
それにハーレムもののポイントは、1人の男性と彼に好意を寄せる複数の女性が一所に存在し、女性間に緊張感はあっても憎悪や殺意があっちゃいけない。ギリシア神話や源氏物語は、嫉妬に狂った女性がライバルを怪物にしたり祟り殺しているので論外。本当のハーレムや宮中がどうなのかはともかく、女性が不幸になってはいけないと思います。呪い禁止。そういうのは「大奥もの」と呼ぼう。で、単にあちこちふらふらして女性遍歴を繰り広げるのは、ただの「ドンファンもの」。
あ、定義したらなんかすっきりしたぞ。
【軽井沢シンドローム】【たがみよしひさ】【ビッグコミックスピリッツ】【フリーカメラマン】【ドム】【ビグ・ザム】










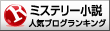
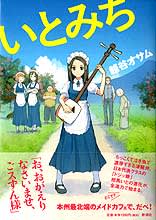 パッと見て、もしドラとサマーウォーズを足して割ったような表紙だなあと手に取り、そのまま購入。読了は早朝1時半。
パッと見て、もしドラとサマーウォーズを足して割ったような表紙だなあと手に取り、そのまま購入。読了は早朝1時半。




