
今日は、昨日とうってかわって、素晴らしい秋晴れ。富士山の見えるゴルフ場で、プレーしたが、一度も雲がかかることはなく、風もなく、気温も低すぎず、言い訳のできない完璧なコンディション。でもいまいちだった。紅葉の美しさに、気をとられたということにしよう。![]() 新幹線が青森まだ開通した。東北育ちの私にとっては、感慨深いものがある。最初は、大宮までしか来てなかったし。そこからがまた長かった。
新幹線が青森まだ開通した。東北育ちの私にとっては、感慨深いものがある。最初は、大宮までしか来てなかったし。そこからがまた長かった。
28年前と、環境は様変わりになっている。どんどん人口が減って行く地域に、高価な新幹線網を作って行く余力が残されているのか?高速道路網は、どうするのか?空港はどうするのか?今が、考え時だと思うのだが。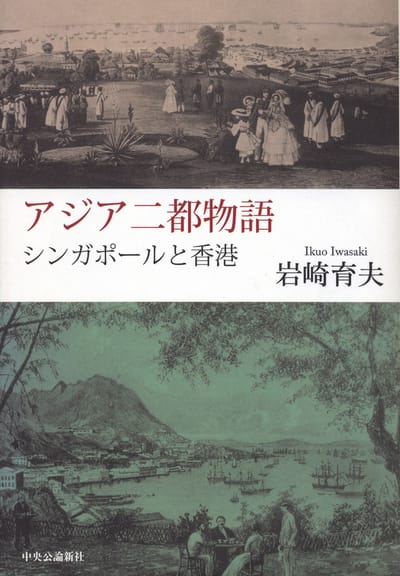
アジア二都物語を読んだ。シンガポールには、住んでいたし、香港にもしょっちゅう行っていたので、興味深く読めた。
この二都は、東南アジア(マレーシア)や、中国とちょっと離れた島国であり、イギリスの植民地であり、主な住民が中国系という共通点を持つ。本書は、その歴史を紐解き、二都の共通点や特徴を明らかにしていく。ちょっと真面目すぎる本かなと思って心配していたのだが、ひじょうに面白く読めた。
この二都を語るには、まず植民地時代のことに触れなくてはいけない。アジアに最初に参入したのは、ポルトガルとスペインだったが、それは貿易港確保が目的で、領域支配が目的ではなかった。その後、オランダが進出し、領域支配を始め、イギリス、フランスが、インドや、インドシナ半島を起点に植民地政策を進めた。著者は、日本の戦国時代の国盗り合戦に例えている。
二都は、イギリスの中継貿易の拠点として、大拠点に変ぼうしていく。そして、そこに、製造業が発展していく。香港は、軽工業品や、日常雑貨品から工業化が進められた。それに比較し、シンガポールは、政府と外資系企業が主導し、重化学工業品や、ハイテク製品が主な輸出品となった。この辺、二都は全く違う発展をした。
しかし、その後、アジアや中国の発展を背景に企業家が成長したところは、二都とも同じ。著者は、シンガポールを「おとなしい妹」、香港「快活な妹」と呼んでいる。これは、なかなか的を得た表現だと思う。二都に住んだことがある人、または二都の人とつきあったことがある人は、思わず肯いてしまうのではないか。
二都の一つである香港は、中国に返還された。そのため、外国籍に移した香港人は、60万人もいるそうだ。ジャーディンや、香港上海銀行もその際、海外に籍を移したのだそうだ。
それに比し、シンガポール人は、国に対する態度が曖昧。これは、独立前は、イギリスに、独立後は、人民行動党に政治を任せてきたことが原因ではないかという。
二都の共通の特徴としては、①多民族社会②民族的階層社会、そして二都の特異な点としては、①単一機能都市②華人の街③脱民族的な国際都市をあげている。まさにそうで、他にこんな例を見つけることはできない。特異である。この特異点は、西欧(イギリス)の考え方と、土地土地の華人のパワーとの融合といえるのではないか。
最後に著者は、二都の意義を二点挙げている。①近代都市というのは、このように創るのだという、「グローバ化のモデルハウス」がアジアの地に創られたこと。それが「本物のハウス」へと自力で成長したこと。②アジア社会歴史的過程を先取りした存在であること。
香港とシンガポールは、アジアの経済の中心となるべく、今も競い合っている。アジアのビジネスに携わる人であれば、読んでみて、損はない本だと思う。















