二大政党政治を夢見た国民はバカでしたよといわんばかりの今日のていたらく。
日本で、政党政治を定着させる術はあるのか?
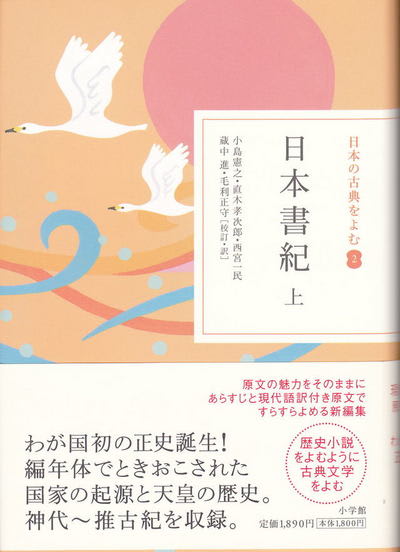
小学館の日本の古典を読むシリーズは、結構前に出て、何冊かGETしたが、まだ読んでなかった。
”歴史小説を読むように、古典文学を読む”が、キャッチフレーズになっていたが、日本書紀など、まさにそうだろう。
現代語訳と、読み下し文が、交互に書かれているが、どうしても、現代語訳中心に読むことになってします。読み下し文のところは、興味のある固有名詞が出ているところを読むぐらい。
改めて、古事記と、日本書紀との書きぶりの違いを感じる。
硬い。
神話の部分はもちろん共通する部分が多いのだが、本流中心の記載で、古事記のような人間味あふれる壮大な物語にはなっていない。出雲の話もない。
最初の頃の天皇の、あまりにもさっぱりした記載にも驚く。単なる作り話なのか、血統だけは残っていたが、ほとんど史実は、忘れ去られていたのか。
上巻は、推古天皇までの部分だが、継体天皇の前で天皇家が途絶えかけたことと、聖徳太子の功績が、他の天皇の功績と比較しても、強調されていることが、目につく。
時代が新しくなればなるほど、史実は明らかだが、今に通じる分、都合よく創作されていたのだろうが。
地名が、今につながる部分が、意外と多いのにもびっくり。
”歴史小説を読むように、古典文学を読む”
なかなかいいフレーズだ。
日本で、政党政治を定着させる術はあるのか?
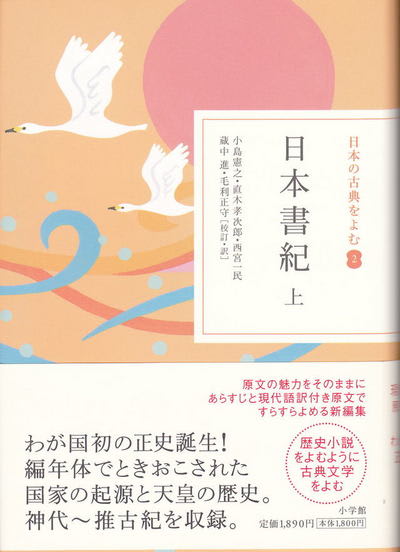
小学館の日本の古典を読むシリーズは、結構前に出て、何冊かGETしたが、まだ読んでなかった。
”歴史小説を読むように、古典文学を読む”が、キャッチフレーズになっていたが、日本書紀など、まさにそうだろう。
現代語訳と、読み下し文が、交互に書かれているが、どうしても、現代語訳中心に読むことになってします。読み下し文のところは、興味のある固有名詞が出ているところを読むぐらい。
改めて、古事記と、日本書紀との書きぶりの違いを感じる。
硬い。
神話の部分はもちろん共通する部分が多いのだが、本流中心の記載で、古事記のような人間味あふれる壮大な物語にはなっていない。出雲の話もない。
最初の頃の天皇の、あまりにもさっぱりした記載にも驚く。単なる作り話なのか、血統だけは残っていたが、ほとんど史実は、忘れ去られていたのか。
上巻は、推古天皇までの部分だが、継体天皇の前で天皇家が途絶えかけたことと、聖徳太子の功績が、他の天皇の功績と比較しても、強調されていることが、目につく。
時代が新しくなればなるほど、史実は明らかだが、今に通じる分、都合よく創作されていたのだろうが。
地名が、今につながる部分が、意外と多いのにもびっくり。
”歴史小説を読むように、古典文学を読む”
なかなかいいフレーズだ。















