週間予報では、気温が回復するはずだったのだが、今日も冷たい雨。
野菜が心配。
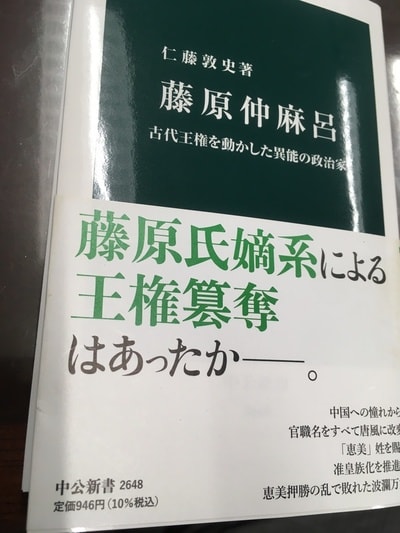
本書は、今年6月に出た。
奈良時代に活躍した藤原仲麻呂についての本。
先日の聖徳太子展で、法隆寺への献物帳の筆頭に彼の署名があったが、奈良時代中期に絶大なる権力を握るも、乱を起こしたとして、滅ぼされた。
かなり前だが、吉備真備に滅ぼされた藤原仲麻呂のNHKドラマがあったが、悪者に描かれていた。
その本当の姿を、史実の分析を通して明らかにしようとしたのが本書になる。
天皇家の支配を試み滅ぼされたということになっているが、それは、続日本紀に遺されている物語で、藤原仲麻呂の功績は、過小評価されていると本書は、いう。
藤原仲麻呂は、極めて有能な人物で、彼の施策は、その後、平安時代へ引き継がれたものも多い。
墾田永年私財法や、養老律令など、好例だ。
唐風家政策や、仏教政策、学問重視なども、別に非難されるべきものではない。
では、なぜこうなってしまったのかというと、彼の権力の源であった亡き聖武天皇の夫人であった光明皇太后が亡くなった後、その権力を維持しようと過激な政策を取り(それまでも身内ばかりを優遇する人事、反対者を失脚、左遷する人事などひどかったのではあるが)、それが限界点を超え、上皇に祀り上げられた孝謙上皇が、反旗を魔オたのが実態という。
つまり、仲麻呂側が乱を起こしたのではなく、仲麻呂の度を越した身勝手な政治に対し、上皇が乱を起こしたという方が、実態に近いのだという。
そこに、吉備真備という、仲麻呂により、左遷されていた有能なブレインが、孝謙上皇側についたことにより、あっけなく、仲麻呂は滅び、藤原家の中でも、南家が没落し、北家が、平安時代にかけ、栄華を誇ることになる。
孝謙上皇も、称徳天皇として重祚するが、道鏡の台頭を招いた。
ただ、道鏡の台頭というのも、続日本紀が伝えているもので、本気で天皇に代わろうとしたのかは、定かではない。
少なくとも、それをきっかけに、道鏡が失脚し、藤原家が息を吹き返したのは、確かである。
古代、特に飛鳥時代から奈良時代は、今の日本のベースが形作られた時代で、その過程のどろどろが、何とも興味深い。
悪人とした片づけられがちな藤原仲麻呂の、正の部分にも光を当てた本書は、面白かった。
野菜が心配。
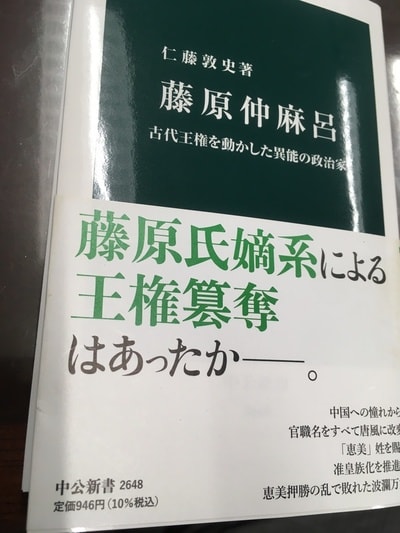
本書は、今年6月に出た。
奈良時代に活躍した藤原仲麻呂についての本。
先日の聖徳太子展で、法隆寺への献物帳の筆頭に彼の署名があったが、奈良時代中期に絶大なる権力を握るも、乱を起こしたとして、滅ぼされた。
かなり前だが、吉備真備に滅ぼされた藤原仲麻呂のNHKドラマがあったが、悪者に描かれていた。
その本当の姿を、史実の分析を通して明らかにしようとしたのが本書になる。
天皇家の支配を試み滅ぼされたということになっているが、それは、続日本紀に遺されている物語で、藤原仲麻呂の功績は、過小評価されていると本書は、いう。
藤原仲麻呂は、極めて有能な人物で、彼の施策は、その後、平安時代へ引き継がれたものも多い。
墾田永年私財法や、養老律令など、好例だ。
唐風家政策や、仏教政策、学問重視なども、別に非難されるべきものではない。
では、なぜこうなってしまったのかというと、彼の権力の源であった亡き聖武天皇の夫人であった光明皇太后が亡くなった後、その権力を維持しようと過激な政策を取り(それまでも身内ばかりを優遇する人事、反対者を失脚、左遷する人事などひどかったのではあるが)、それが限界点を超え、上皇に祀り上げられた孝謙上皇が、反旗を魔オたのが実態という。
つまり、仲麻呂側が乱を起こしたのではなく、仲麻呂の度を越した身勝手な政治に対し、上皇が乱を起こしたという方が、実態に近いのだという。
そこに、吉備真備という、仲麻呂により、左遷されていた有能なブレインが、孝謙上皇側についたことにより、あっけなく、仲麻呂は滅び、藤原家の中でも、南家が没落し、北家が、平安時代にかけ、栄華を誇ることになる。
孝謙上皇も、称徳天皇として重祚するが、道鏡の台頭を招いた。
ただ、道鏡の台頭というのも、続日本紀が伝えているもので、本気で天皇に代わろうとしたのかは、定かではない。
少なくとも、それをきっかけに、道鏡が失脚し、藤原家が息を吹き返したのは、確かである。
古代、特に飛鳥時代から奈良時代は、今の日本のベースが形作られた時代で、その過程のどろどろが、何とも興味深い。
悪人とした片づけられがちな藤原仲麻呂の、正の部分にも光を当てた本書は、面白かった。















