ご挨拶記事です。
今年もコロナは収束せず、目下第8波の真っ最中。来年もコロナ禍は続くのか。波は第何波まで続くのでしょうか。気になるのが無くなられた方の数。弱毒化しているはずなのに数が多い。世の中わからない事だらけ。この冬はインフルエンザの感染者も多いとか。読者の皆さん、お気を付けください。さて、当ブログなりに今年を振り返ってみたいと思います。
今年はやはりW杯ですかね。当ブログとしての森保ジャパンの評価は別の記事でしっかり書いているのでご覧ください。4年後のW杯は一気に48チームが参加する事になり、アジア予選も緩い事になりそうです。FIFAの思惑で中国に参加して欲しいとか聞きましたが、さすがに2年に1度案は消えましたね。さて、森保監督は北中米W杯で指揮を執れるのでしょうか。スポーツ界全体ではそんなところでしょうか。


1年最後の記事は、いつも紅白を観ながら今年を振り返りながら書いています。行動制限も消えて、今年はすっかり元に戻りましたね。里庄町出身の藤井風さん、今年も出場しました。インパクトある曲でしたが、去年より目立っていなかったかな。
岡山のスポーツ界としてまずは2大スポーツの状況から。まずはファジアーノ。Cスタも100%入場に回復し、コロナ前までは行きませんが、結構入場者数は回復しました。Cスタでの観戦で前後左右にびっしり座られてもだいぶ慣れました。今年は大型補強でちょうど1年前はすごいなすごいなというニュースが続き、J1昇格できるかもしれないと思いました。開幕前の順位予想は4~7位。結果は上振れで3位でした。でもプレーオフで惨敗。そして、補強ばなしが続く中での今日、残念なニュースが入りました。デューク選手が町田さんへ移籍するとか。やはり、原強化部長の存在は大きかったのかな。


トライフープ岡山は2021-22シーズンではB2昇格決定戦に出場するも、A千葉さん相手に完敗し、夢は砕けました。今日現在2022-23シーズンの真っ只中ですが、けが人が多いためか負けが込んでおり、5位に低迷。やはり補強が上手くいかなかったのかな。今季は上位8チームによるプレーオフがあり、上位2チームがB2に昇格できますが、今のままでは難しいかな。正直昨季のメガクラブ2つがいなくなったので、今季は行けるかもと思っていましたが甘くなかった。どうすれば強くなるのか、どこに原因があるのかもう一度検証すべきなのかもしれません。


岡山シーガルズは今季も低迷しています。今のところ12チーム中9位です。昨季よりは若干ましですが、慢性的に強くなません。佐伯選手、タナッチャ選手など少しレギュラーが入れ替わりました。宇賀神選手も出場が増えましたね。一度完勝で2タテという試合がありましたが、すぐに元に戻ってしまう。なぜ強さを継続できないのか。まさか入替戦には回らないでしょうが、シーガルズもどこに原因があるのか検証すべきですね。


岡山リベッツは岡山武道館が現在改装中という事で、今季も岡山市外で試合をやっています。ハオ選手は前期MVPを獲得しましたね。今季は1強だった東京さんが低迷し、チャンスあると思っていましたが、現在4位。定位置じゃねえかと思ってしまう。東京さんにも快勝したし、強い選手も補強できたし、全然善戦しているのになぜこの順位に陥ってしまったのか。なぜ強さを継続できないのか。リベッツもどこに原因があるのか検証すべきですね。4チーム共通なのですが、検証して一言申す存在がいない。サポカン(ファンミーティング)やらないし、そこが一番の原因なのかもしれません。
あと、女子サッカーですが、なでしこリーグ2部(実質3部)では湯郷ベルと吉備国大シャルム岡山高梁の立場がすっかり逆転してしまい、ベルがまたしても入替戦に回って今回は本当にやばかったです。レジェンド横山選手の加入という吉報もありましたが、タッチの差で生き残りました。毎年の振り返りですが、今年はこんな感じでしょうか。


①ボランティア活動
◇FSS(FAGiANO Okayama Support Staff)(2009年4月発足):http://www.fagiano-okayama.com/supporters/volunteer.html
FSSのサポートスタッフとして参加しましたが、コロナ禍もあり、今年も2回参加だったのかな。もう少し参加したかったのですが、行こうと思ったら波にぶつかっていました。仕事もあり、感染力も増しており、やはり気にしなければならない所なもので。コロナ禍がまだ収束しないでしょうが、来季はもう少し参加したいですね。FSSの参加者数自体の低迷も気になるところ。
◇トライフープ岡山ボランティア(2019年10月より):http://tryhoop.com/club/volunteerstaff/
ファジと違って観客数が少ないため、リスクは低く感じていますが、今のところ、まだ1回しか参加できていません。フロントさんとも距離が近く、一番のびのび感のあるボランティア活動と思って参加していますが、前回参加した時に、いつも来ているメンバーの顔が見られなかったのが気になるところ。
◇岡山リベッツボランティア(2019年11月より):https://okayama-rivets.com/topic/detail/47
試合数自体が少なく、一番参加数が見込めないボランティア活動ですが、先日笠岡大会に参加した時はのびのび感があって楽しかった事を思い出しました。こちらもフロントさんと距離が近く、手弁当感が大きい運営が大昔のファジ運営を思い出し、面白くもありました。こちらはファンと選手の距離も近く、いい運営をされているなと思います。
②地域における支援活動 ◇ファジアーノ応援団・浅口(隔月偶数月開催):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/c/1556bd1214a32a21a87195dded76b82a
応援団・浅口は、引き続きコロナ禍で引き続き休止中です。来季はぜひ再開して欲しいと思っています。
③ウォーキングサッカー体験会(Wフィールド):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/c/4e5a4911d3d7103ab73fbcb4bc0ecc2c
ウォーキングサッカーも同様にコロナ禍で休止中です。コロナ太り解消に運動したいです。
④サッカーを語る会(2004年12月から毎月):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/c/25fe20142b1343a2a26230951ea41391
この会もコロナ禍でなかなか開催できていませんが、細々と時々やってます。会場のウルトラスさんで動きがありました。Mカツ店長が倉敷店から、新たに岡山店を復活オープンされ、倉敷店には元スタッフのT森氏がオーナーとして再登板。コロナで厳しい中頑張っておられます。


⑤その他
他、一番大きいニュースは倉敷アブレイズのV3リーグ参戦が決まった事。これは大きいですね。来年の秋から倉敷福田公園?で試合が行われるでしょうから観戦に行かなければいけませんが、そうでなくても3チームかぶっていたのに、うれしい悲鳴です。その他、運営面やファンづくりなど、当ブログもできる範囲で何かお役に立てればと思っています。2005年の頃のファジ関連の資料を引っ張り出しております。倉敷市民としてうれしいですね。
他、「カリスマの存在」の某黄色いチームですが、ネル監督の3季目。今季は降格候補と言われながら途中J1で2位まで上がり、7位フィニッシュでした。今季はユースから多くの優秀な選手(古賀選手はJ1新人王)が昇格して活躍しましたね。そうそう、元岡山の片山選手が入団してビックリです。また楽しみが増えました。黄色い瑛ちゃんって想像できないなぁ。
来年はどんな年なのか、いくつも大きな大会がありますね。W杯ではバスケ(8/25~)とラグビー(9/8~)、そして女子サッカー(7/20~)とてんこ盛りです。成績ではラグビーが一番有望株。バスケは日本(沖縄)でも開催されるので、行けるものなら行ってみたいですね。コロナもやや収まり、サッカーのW杯も終わり、結構いつもの年になっていくのではないでしょうか。という事で読者の皆さん、よいお年をお迎えください。
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers
リスペクトコラムです。
ちょっと手元の資料を整理していた中で、これらのものが出てきました。あくまで個人の主観の強い手元資料ですが、せっかくなので読者の方々と情報共有したいと思います。J2岡山の中の方の目に留まり、運よく来季以降にこれらのもので何か動きが生まれたらうれしいです。あくまで個人的考察です。他のクラブ(Bの方も)の方々も観に来られていると思いますが、岡山の「個性」ですので。
個人的な印象ですが、J2岡山は他のJクラブとくらべて、PB(プライベートブランド)化が目立つように思われます。三位一体の支援者(行政、企業、市民)から支援を広く受ける、地域の公共財であるJクラブとしては、実店舗(製造事業所)名を覆い隠すPBではなく、しっかりPRしてあげる地域ブランド化が望ましいのではないのではないでしょうか。


〔ファジフーズ〕
J2岡山は店舗の表示はテント番号のみで、実店舗名はほぼ表示されていません。店頭プライスカードの隅にかろうじて小さく表記されているが、ほとんど目に留まらず、公式HPでの表記はゼロです。
実店舗名の有無(公式HPでの表示)を中心に全Jクラブで調査しました。こちらのブログ記事によると、Jリーグ全58クラブの中で、実店舗名を全く表記させていないのはJ2岡山のみで、各出展事業者の実店舗名を表示させない事は、Jリーグが目指す方向性と少し乖離が出ているのではないかと思われます。Jクラブは地域の公共財であり、ホームタウン等の地元地域とともに、地域振興を協働することが本来の役割であると思われます。
PBはウィンウィンではなく、片方だけのウィンというカラーが強い印象があります。実店舗名を表記し、例えば「今度食べに寄ってください」と、本店等実店舗に関するPRチラシの店頭配布もOKにすれば、ウィンウィンの関係になるでしょう。
なぜ今まで実施される事が無かったのか、それは岡山総合グラウンドの出店基準の関係で、各実店舗名ではなく、「ファジフーズ」のみでの出店登録を選択した事情があるのかもしれません。もしそうであれば、クラブが最近指定管理者グループになったのでいくらか改善できるのではないでしょうか。
もし、出店者確保に苦労しているのであれば、自店の名前をPRできるという出店者メリットを加味すれば、出店を希望する店舗が増えるのではないでしょうか。


〔岡山再発見プロジェクト〕
最初にこのプロジェクトが発表された時に、やっとPB路線から脱却されると喜びました。公式HPには事業所名が少し表記されていますが、スタジアムイベントの出展ブースでは全くられません。ファジブランドの認定制度と思っていたら、実際はPB事業の一つなんだと認識してしまいました。
「岡山再発見プロジェクト」公式HPに「地方創生という課題解決」「商品の販売や発信のお手伝い」とありますが、実際はPB商品の委託製造販売に力を入れている事が中心で、地域課題の解決や県内事業所の販売・発信のお手伝いという目的から遠ざかっている印象が強いです。
最近Cスタのプロジェクトブースで、新たにフード商品の販売が見受けられます。よく見ると、実店舗(製造事業所)名の表記が無く、単にPB商品が増えただけという印象を持ちます。PB路線を広げていく事よりも、本当に大事な事は、目的どおり地方創生という課題解決や地域の事業所の商品の販売や発信のお手伝いに尽力する事ではないでしょうか。
県外で長く暮らしてきた者として、岡山にはよそはよそ、うちはうちという県民性を感じますが、これらの事業も何となく岡山らしい流れだなぁと個人的な印象を抱きます。


〔地域の物産展の開催〕
もう一つ他のJクラブではよく見かけるが、岡山ではイメージが薄かったのが、常設店舗以外の出店販売ブース(物産展)の設置です。かなり昔のスタジアムイベントで県民局単位の観光連盟で物産コーナーをやっていた覚えがあります。ひょっとしたら常設店舗の売上に影響するからやらなくなったのかもしれません。
来場するファン・サポーターのニーズは、常設店舗にこだわらずに、いい物、美味しい物を買いたいはず。J1にふさわしいクラブになりたいのなら、常設店舗だけに気を使うのではなく、もっとファン・サポーターのニーズに応えてもいいのではないでしょうか。ちょっと調べても全国のJクラブで、常設店舗を意識していない物産展を以下のとおり開催しています。
<他のJクラブの事例>
・J1神戸:カレーフェスタ(https://www.vissel-kobe.co.jp/news/article/2205.html)
・J1川崎:熊本県合志市物産展(https://kumanichi.com/articles/3323)
・J1鹿島:いばらぎ観光物産展(https://www.antlers.co.jp/news/game_info/54264)
・J1湘南:福島物産展(https://www.bellmare.co.jp/179258)
・J2千葉:ファジアーノ岡山戦 岡山物産展(https://jefunited.co.jp/news/detail/337?/news/2022/05/homegame/165147972015607.html)
・J2仙台:物産展(https://www.vegalta.co.jp/backnumber/2021/news-game/2021/11/post-816.html)
前にも書きましたが、PB化はどうせ自分のところの名前が出ないからというマイナスイメージを抱いてしまいます。詳しくは書きませんが、簡単に言うと本当のベストを尽くしていないかもしれないという事。岡山では無かったと思いますが、昔串カツを買ったら肉が入っていなかったと聞いた事例を思い出す。
あくまで個人的な主観で、ずれている部分もあるかもしれません。今までもスタグルは「ご当地グルメののれん街が理想」と言ってきました。例えばのイメージは百貨店の地下グルメコーナー。例えばてんちかフードガーデンで、天満屋ブランドばかりで、登録番号1番の店、2番の店として並んでいたらどうでしょうか? そんな事を個人的に思います。
スタグル関連⑥:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20221009
〃 ⑤:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20131228
〃 ④:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20130310
〃 ③:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20121130
〃 ②:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20120921
〃 ①:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20120812
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers
リスペクトコラムです。
Bリーグの島田チェアマンの「島田のマイク」を聴いているとたまに出てくるキーワードが「B.Hope」。リーグでの社会貢献活動で、Jリーグで言えばシャレンのような存在。前から知っており、そのうちリスペクトしなきゃと思っていて、なかなかリスペクトできていなかったのですが、また耳にしたので一気にやりました。Jリーグシャレンのような規模ではありませんが、立派な継続事業です。
【未来へのパスをつなごう B.LEAGUE HOPE】
〔活動理念〕
B.LEAGUE HOPE それは、B.LEAGUE がつなぐ未来へのパス。
「スポーツの力」に対する社会・地域からの期待に応え続けるためにも、「スポーツエンターテイメントの革新」のみならず、「Social Innovationの実現」を目指し、ステークホルダーとともにさまざまな社会的責任活動を「B.LEAGUE Hope(B.Hope)」と称し、推進していきます。
〔リーグの活動 B.HOPE ACTION〕
B.LEAGUE Hopeでは、クラブ、選手、地域、パートナー企業、選手会の方々と共に活動を実施しています。
〔関連団体 RELATIONS〕
これまでご一緒した活動事業等
くるみの森、スペシャルオリンピックス日本、ソフトバンク(スマートコーチ)、難病の子どもとその家族へ夢を、日本財団、日本バスケットボール選手会、Being ALIVE Japan、NPO法人フローレンス
まずはB.Hopeの公式HP。シンプルですが、わかりやすい。連携相手は、シャレンは行政とNPO法人ですが、B.Hopeは各種団体の存在が大きい印象があります。スポーツ団体でも地域課題を解決する社会貢献(連携)活動をここまでしっかりできているのはJとBの2つだけでしょう。
クラブの活動を見ると、B1とBリーグだけでB3は無かったです。学校訪問、子ども食堂、清掃活動、フードドライブなどが中心ですかね。ぜひB3も掲載して欲しいですね。トライフープもしっかり実施しているはず。他に何か情報が無いかなと探していたら、いいコラムがありました。
【Bリーグの社会的責任活動「B.HOPE」スポーツにとどまらないその取り組みとは?】
「Bリーグが設立当初から取り組んでいるのが、社会的責任活動の一環である『B.LEAGUE Hope』だ。この活動の中心にいる公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグの櫻井うららさんに話を聞いた。」
〔まったくの手探り状態からスタート〕
「『B.LEAGUE Hope』(以下B.Hope)の活動が始まったきっかけは、『我々はバスケットボールをやる団体ではない。バスケットボールという手法は使うが、社会的な意義を持たないと、存在する意義はない。だから、社会的な活動をしなければいけない』という思いからだった。」
「櫻井さんが中心となり、初めてB.Hopeの活動が行われたのは、Bリーグ初の開幕を目前に控えた2016年の夏。この時点ではまだB.Hopeは立ち上がっていなかったが、B.Hopeの活動領域である『Planet』『Peace』『People』の三つのうち、『Planet』にフォーカスし、集まった各チームの社長に、Bリーグが目指す社会的責任活動について話をした。
「地球が抱えている温暖化や気候変動といった環境問題を自分たちの問題だととらえ、その上でスポーツの力で何ができるか。そんなことを伝えたのですが、いきなり地球規模の話をされてもピンとこなかったのでしょう。ほとんどがポカンという感じでしたね」
〔理念や活動意義が選手に浸透してきた〕
「2017年1月にB.Hopeという傘ができると、その月に行われたオールスターゲームでは『People』に焦点を当て、小児難病の子どもたちをゲームに招待した。選手とハイタッチをするなど、日頃はバギーに乗って生活をしている子どもたちにとっては、特別な時間になった。だが一方で、専門的な団体からは「当事者だけでなく、家族に対してもそういう時間を作ることでこういう活動は成立する、という助言をいただきました』(櫻井さん)2018年のB2のファイナルでは、難病の子どもを亡くした母親が作っている和太鼓奏団に演奏の場を提供したのにとどまらず、その家族も招待した。」
「選手たちに浸透したきっかけは、2016年熊本地震の後に行った被災地の訪問だった。『事前に被災した地元の熊本ヴォルターズの選手たちから、実際にどうだったか話を聞いたことで、訪問する意味や意義がよく理解できたようです』
B.Hopeでは、活動とともにその前後、つまり、どういう気持ちで活動をして、どういう気持ちで活動を終えたのか、を大事にしている。例年Bリーグがオフになる6月に、東日本大震災の復興支援活動を行っているが、その際も移動のバスの時間を使い、スタッフが「この取り組みの肝は何か』丁寧に説明しているという。甚大な被害を受けた宮城県名取市に震災後小学校ができ体育館のこけら落としとして子どもたちとプレーした際も、そこに行くだけではなく、足場ができたばかりの防波堤を見たり、地元の人から当時の状況を聞いたりした上で訪問している。
〔目指すべきはNBA選手の姿勢〕
「B.Hopeを推進していく上で、選手たちの生きた教材になっているのが、NBAが2005年に設立した『NBA Cares(NBAケアーズ)』という社会貢献プログラムだ。この活動を視察したのはBリーグ・競技運営・経営企画グループの堀内武蔵さん。
『2017年にニューオーリンズでオールスターゲームが行われたときに行ったのですが、2005年のハリケーンの爪痕が残る地で、学校の近くに遊具を作ろうと、雨の中でNBAのスーパースターたちが、当たり前のように作業をしていたのです』
堀内さんは帰国するとその様子を選手たちに伝えた。堀内さんによると、選手たちは目指すNBA選手の競技面とは別の姿勢に感銘を受けたようで、『NBAケアーズの活動を知ることで、選手たちの中にB.Hopeの真の意義が芽生えました』。
B.Hopeの活動では現地に行くと、先方が求めているものと想定しているものが違うことが少なくない。たとえば、熊本地震では『仮設住宅が必要』という目に見える問題に行きがちだが、被災地に赴き話を聞いてみると、『子どもたちが声を出して遊ぶことができない』という悩みに行き着く。それならば『子どもたちが思い切り遊べる場所、時間を作ろう」と、B.Hopeとして活動をはじめた。櫻井さんは『事務局で作ってきた企画をやるだけでなく、現地の空気を感じ、現地に合った活動を臨機応変にすることで、より意味のあるものになる』と言う。
今後は、B.Hopeの認知度を高めたいと考えている。『コンテンツホルダーとしてBリーグの強みを活用しながら、国連などともつながっていきたいですね』
また、三つの『P』(『Planet』『Peace』『People』)に専門的にアクセスしながら、SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までによりよい世界を目指すための、持続可能な開発目標)にも目を向け、三つの『P』の活動をリンクさせていく。」
この櫻井さんという担当の方は、Jリーグで言うと長崎さん出身の髙田理事かな。事業がスタートしたのはBリーグが開幕したタイミングだったのですね。つまり、新リーグ開幕と同時に実施された訳で、Jリーグとは違う。最もJリーグは30年前なので無理も無い。
NBAケアーズという立派なお手本があるのも大きいですね。やはりアメリカはそういう文化がある。サッカーはヨーロッパなので、そこまでの文化は見当たらない。あるのかもしれませんが、リーグとしてはされていないのでは。NBAケアーズではリーグ×チーム×選手が三位一体となって10年間でチャリティ総額2億6千万ドル(約300億円)を集め、延べ330万時間の奉仕活動が行われ、世界26ヶ国970カ所に学び・遊び・そして住まいの場を建設してきたと報じられています。BリーグはJリーグシャレンを意識するのもいいですが、NBAケアーズ色を更に出していった方がいいのではないでしょうか。島田チェアマンの腕の見せ所ですね。
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers
リスペクトコラムです。
また失われた3年8ケ月の始まりです。先ほど日本協会の記者会見があり、森保監督の続投が発表されました。発表が今日までずれ込んだので、淡い期待を持っていましたが消し飛びました。2年契約ではないかという報道もありましたが、これもデマですべて一番悪い結果に映りました。ただ、個人的にはアジアカップの結果で交代して欲しいので、失われた2年になって欲しいと。
個人的な今後の予測は、欧州組選手を遠くの国から日本に呼び、スポンサーが喜ぶ強くない相手(もちろん欧州の強豪国は呼べないため、良くてせいぜい北中米くらいか)との勝ち試合を続け、大勝して勘違いする。アジアカップで苦戦し、一度監督交代論が出るが、田嶋ジャパンで押し切り、責任は問われずくらいの結果かな。2年のタイミングで替わってくれたらいいのですが、3年目に入ると今のままだと北中米W杯が、カタールW杯の結果再現になる事を容易に想像できてしまう。
戦術の引き出しが空っぽと思われる森保監督は、選手との対話と称して選手と戦術の合議制を継続し、ワンチャンサッカーを続ける。仮に結果を出しても、ギャンブル性の高い戦術のために、日本サッカー界には何も残らない(今大会では何か残りましたか?)のではないかと。ポジティブなコラムを紹介したいところですが、当ブログの論調と相反するので、続投反対論的なコラムを紹介して、森保ジャパン第二次政権を受け止めたいと思います。


【サッカー日本代表「第2次森保政権」は短命の可能性あり…戦友・横内コーチ契約満了の波紋】
「続投は既定路線とはいえ、その森保監督が時折、浮かない表情をしているという。ヘッドコーチ格の横内昭展コーチ(55)がJ2磐田監督に就任。長きにわたるパートナーがいなくなって「ショックが癒えない」(前出の関係者)というのである。
「森保監督は1987年に長崎日大高を卒業して日本リーグ・マツダ(現J1広島)に入団。その前年に横内コーチは福岡・東海大五高(現・東海大福岡)からマツダ入り。九州人同士の2人はすぐに意気投合。マツダと広島の選手同士として、広島と日本代表の監督とコーチとして、固い信頼関係で結ばれている」と放送関係者が前置きして続ける。
■精神的支柱のような存在
「現役時代に左サイドアタッカーだった横内コーチが攻撃面を取り仕切り、守備的MFだった森保監督が守備面を担当。うまくすみ分けができ、森保監督にとって横内コーチは精神的支柱のような存在でもあった。横内コーチの後任選びが難航しているという噂もあるが、誰が後任に就いても森保監督と横内コーチのような関係性は期待できそうもない。もし、ソリが合わなければ、第2次森保政権は短命に終わるかもしれない」
引用:ゲキサカ
【森保一監督に続投オファー 反町康治技術委員長の慎重な判断で年末までずれ込んだ】
「森保氏続投の方針はそう簡単には決まらなかった。カタールW杯では日本の歴史上、勝ったことのないドイツ、スペインから勝ち点3を奪い、首位で1次リーグを突破。決勝トーナメント1回戦でもクロアチアと延長、PK戦まで渡り合った。8強に最も近づいたベスト16だったと評価できる。岡田武史・元代表監督に次ぐ、世界で戦える日本人指導者も、長らく望まれていたことだ。ただ、オファー提示は年末までずれ込んだ。複数の関係者によると、理由は反町委員長が慎重に判断したためという。」
「森保監督の選手との合議制で戦い方を決める手法は、日本人の良さ「協調性」を発揮することにつながった。1次リーグのスペイン戦で採用した3―4―3は選手からの提案だった。一方、外国人監督がもたらす戦術が、この合議制を上回る可能性を秘めている。実際に反町委員長は前ドイツ代表監督のレーヴ氏、元チリ代表監督のビエルサ氏に接触したという情報があった。
それでも協会は森保氏にオファーを提示した。今回の「良い戦い」が、将来の8強入りに向けて最善の戦いとは限らないだけに、十分に検証され、議論され、他候補者より、森保氏の期待値が高いと見込まれての決断であることを強く願う。」
引用:スポーツ報知
これを読むと、戦術の引き出しが空っぽというのが頷けます。戦術で守備面はわかるが、攻撃面はやはりわかっていなかったのではないかと。だから欧州組の選手に戦術を教えてもらっていたらしいのかと。横内コーチはなぜ続投しなかったのかというのも気になる。ここでも選手との合議制というキーワードが出てきますね。このコラムでは今回の戦いが8強入りへの最善策とは限らないと言い切られています。
この2つのコラムを観た後に今日行われた森保監督の記者会見を聴いて下さい。正直、万歳万歳の盲目的な雰囲気になったのかと思って視聴してみると、深読みになりますが、決してそうでもないなと思いました。その会見の中で耳に留まった気になる発言をピックアップしてみます。
反町委員長(反):まだまだ足りない点もあるという事は話をさせていただきました。今回のW杯を通して見えてきたものとしては、当然個の成長、個を発掘させる事は大事。若手の発掘をやっていかなければならない。特に攻撃の能力の高いセンターフォワードの発掘が一番力を入れなければならない。個でも攻撃に違いを作れるような選手が果たして今回いたかなというと、まだまだ多くないと思う。今後を見据えてやってもらいたい。ドイツ戦やスペイン戦では受動的なサッカーをせざるを得なかった部分もあるかもしれないが、今後はもっと能動的なサッカーを目指す。もっとそういう所に力を注いでもらいたいと考えている。」
記者(記):次のW杯はグループリーグを勝ち抜いてもベスト32。もう2つ勝たないとベスト8に行けないという厳しい条件になるため、今まで以上に大きな上積みが必要だと思われるが、どこの部分が上積みすべきか?
森保監督(森):マイボールでゲームをコントロールする事。そこが速攻であれ遅攻であれ、我々がボールを奪って、ボールを握りながらコントロールしてゲームを決めに行く事ができなければならないと思っている。
記:森保監督は欧州に勉強しに行きたいと言われていたが、上積みという意味でも、今後欧州でのコーチ・スタッフ(の研修)として派遣する可能性はあるのか。
反:海外組の選手が多い状況、選手の視察も含めて、世界目線でそういう活動をして欲しいと考えている。
記:今までやってきた4年間で積み上げて来たもの、次に積み上げたいものは何か。
森:皆さんにもお聞きしたいです。機会があれば教えてください。違う視点があるかもしれないので。いい守備からいい攻撃というチームコンセプトでチーム作りをしてきた中で、コンセプトどおりの戦いはできていたのかなと。攻撃ではボール保持率を上げられず、特にドイツ、スペイン戦では特に低かったが、クロアチア戦ではある程度お見せできたと思う。足りない所は多いが、ボールを放棄するという事はこの4年間でほぼ無くなった思う。コスタリカ戦ではボールをつなごうとして失点になってしまったが、その意識で選手が勇気を持ってチャレンジしてくれた。
上の3つ目の質問で言葉に詰まり、逆に聞きたいと返し、いい守備からいい攻撃云々と答えたのを観て、「やはりこの人の引き出しには何も入っていない。欧州で研修しても何も吸収できないのでは」と思ってしまいました。
やはり、反町委員長はすんなり続投OKではなかったのですね。だから宿題という苦言を呈したのでしょう。横であの方も苦虫をつぶしたような顔をされていました。今の日本協会の中で反町委員長が一番わかっているのかもしれません。自分が次期監督になりたかったのかもしれませんが。個の成長、能動的サッカーは森保さんでは正直、3年8ケ月では無理でしょう。個も能動的サッカーもアジアでは発揮できても本番では全くダメでしょう。
いくつか当ブログで口にしていたキーワードが出てきました。「能動的サッカー」は、ボールの保持率が高いサッカー、「攻撃の能力の高いセンターフォワード」はCF、「欧州への研修」は世界を知る日本人監督(研修では意味ないですが)だったかな。今回の記者会見は田嶋ジャパンによる万歳万歳の盲目的礼賛で終始するかと思いましたが、反町委員長がしっかり締めてくれました。アジアカップで優勝できなかったら、4強止まりだったら「期待したが成長できなかった」と遠慮なく切って欲しいです。
すいません、今大会の当ブログの認識は、ドイツは不調(政治メッセージで分裂気味)、スペインは2位狙いだったために、たまたまタイミングよく勝ててしまった。もちろん選手の進化もあるが、肝心の指揮官は受動的なワンチャンサッカーで結果を出したが、決して世界で勝てる監督では無かった。森保監督もご自分でもそれがわかっているから、欧州に勉強をしに行きたいと言うのでしょう。そんな世界を知らない日本人監督と失われた3年8ケ月を過ごすのかと思うと、頭痛がしますがまぁしょうがないです。決まった事なので。元々は死のグループで誰も期待していなかったが、不調のまま政治的メッセージでチームが分裂したドイツに、ワンチャンサッカーでたまたま勝ってしまった時点で、今の流れは決まった。続投させたくてうずうずしていた田嶋ジャパンが待ってましたと内定させてしまい、トップダウンを貫いてしまう。今回の続投の要因はやはり田嶋ジャパンかな。こんなコラムもありました。
【森保監督続投に田嶋会長は早くから支持、反町委員長は外国人監督模索…条件面で難航も】
「W杯カタール大会の分析、検証、議論の末、森保監督以外の名が候補として俎上(そじょう)に載せられることはなかったという。田嶋会長はいち早く森保監督の続投を支持した一方、複数の関係者によると、反町技術委員長だけは早期の続投決定に慎重だった。」
「「欧州のクラブで指揮を執るトップ50の監督は連れてこられない」と日本協会関係者。マンチェスター・シティのグアルディオラ監督の年俸は2000万ポンド(約32億2500万円)。日本協会の予算はその10分の1とされ、最先端の欧州から一線級の指揮官を極東に引っ張ってくるのは、条件的にそもそも難しかった背景もあった。」
引用:中日スポーツ
こういう予算面の課題もありますが、極東は僻地視されている事もあり、なかなか一流の監督が来る可能性は低かったです。ビエルサ氏の名前が何度も出たし、一時期レーヴジャパンに期待を膨らましましたが、本当に目はあったのか疑問ではあります。こういう時期にビエルサさんの名前が出るのはたぶん3度目。もう4度目は無いでしょう。田嶋体制が早く終わり、価値観がガラッと変わり、世界を知った人材への現実路線になる事を楽しみにして待ちたいと思います。まだまだこのネタはありますが、キリがないので今回はこの辺りで。日本代表に対しては今後は更に距離感が広がりそうです。読者の皆さん、また長いぼやきになりますが、またお付き合いください。
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers
リスペクトコラムです。
今季の振り返りの大トリはJ2の2位になり、J1に自動昇格された横浜FCさんです。最後の最後まで地元岡山と競り合っていましたね。岡山が一番猛追していた時期、この勢いで行けば2位に浮上、来季はJ1に行くぞと正直思った事もありました。でも、最後に息切れ。横浜さんに行かれてしまいました。何が横浜さんと比べて劣っていたのか、そこが来季J1昇格へ向けての課題ではないでしょうか。当ブログでは何となく思うところはありますが。
横浜さんはやはり2度のJ1経験は大きかったのか、昇格の仕方を十分にご存じだったのかもしれません。何かプレースタイルも含めて、J2岡山と森保ジャパンが似て来たなとちょっと思ってみたり。


【横浜FC 試合前にJ1昇格決まった!四方田監督“有言実行”1年での復帰果たす】
「明治安田生命J2第41節が16日に行われ、3位・岡山がホームで12位・秋田に1―2と敗戦。この結果、2位・横浜FCは自動昇格条件である2位以上が確定し、J1昇格が決定。チームは18時キックオフ予定のホーム金沢戦開始前に1年でのJ1復帰を果たした。
昨季J1で最下位の20位に終わり、J2へ降格した横浜FCは今季から札幌でヘッドコーチを務めていた四方田氏が新監督に就任。指揮官は開幕前に「まずは自動昇格できる2位以内を目指そうと思ってます」と1年でのJ1復帰を目標に設定。「攻守にアグレッシブに、攻守一体となるサッカーを目指して戦っていきたい」と意気込み、開幕戦に臨んだ。
開幕戦で大宮に勝利すると、開幕から10戦負けなしの快進撃で首位を快走。第14、15節と連敗し首位から陥落するも、その後も上位をキープ。一度も4位以下に落ちることのない安定感ある戦いぶりで見事に“有言実行”となる1年でのJ1復帰を勝ち取った。」
引用:スポニチ
うーむ、やはり監督部分ですか。四方田監督が就任1年目で結果を出しました。四方田監督をリスペクトしてみると、意外な事に選手経験がありません。岡田ジャパンの時にスカウティングスタッフ、その後は岡田監督とともに札幌入り。2015年から札幌さんの監督に就任され、2年目にJ2優勝されてJ1に昇格。2018年から3年間ヘッドコーチを務めて、今季横浜さんの監督に就任されています。2度J1に昇格させている訳ですね。まさに昇格請負人だ。確かに今季は開幕から首位を独走状態で、さすが元J1という強さをしっかり発揮されていました。
あと、横浜さんといえば俊輔選手。今季限りでの現役引退を発表されています。また1人レジェンドがユニフォームを脱ぎますね。寂しいですが、また若い勢力が次に続いていると思います。
【成し遂げられた「1年でのJ1復帰」。横浜FCが期す“定着”へのチャレンジ】
〔十分に理解していた“J1復帰”の難しさ〕
「2022シーズンの『降格組』は4チーム。ベガルタ仙台、横浜FC、徳島ヴォルティスに大分トリニータ。その中で1年での復帰を達成できたのは横浜FCのみ。最終的にJ1参入プレーオフ圏内に入ったのも大分だけであったことを考えると、『昇格』がどれだけ難しく、厳しいことなのかがよくわかる。
今季、横浜FCは『1年でのJ1復帰』という目標を掲げた。降格した以上、『すぐに復帰』という空気感は自然と醸成される。2007年の1回目のJ1昇格は翌年に降格。次のJ1への扉を開くまでには、気付けば13年もの年月が経っていた。」
〔前回の昇格を知る武田英二郎が携え続けた覚悟〕
「クラブ2度目のJ1昇格を果たした2019シーズンから、J1を戦った2020、2021の2年を経て、チームを構成するメンバーはガラッと変わった。当時を知る選手は、松浦拓弥、齋藤功佑、武田英二郎、中村俊輔の4人のみ。今回の昇格の意味と意義とともに、今季の戦いを選手に振り返ってもらうと、こんな言葉が出てきた。
武田英二郎はこの1年を『ずっと苦しいというか、1年間ずっと勝たないといけないという気持ちとプレッシャーと戦いながらやってきたシーズンだったと思います』と振り返った。開幕からの連勝を含めたスタートダッシュが、周囲を『横浜FC、昇格するよね』という空気感にさせ、ずっとそれに追われながら戦ってきた感じがしたのだという。」
そうか、昨季は4チームがJ2に降格だったのですね。今季のJ2で台風の目になるはずなのに、他の3チームはもう一つの成績。というか、今季はそれ以外の元J1組もほとんど不調だった不思議なシーズンでした。だから岡山の目があったのかもしれませんが。横浜さんは過去2度のJ1はどちらも1年でJ2に舞い戻っています。来季はぜひJ1残留を果たしてください。
クラブ設立25周年記念事業をされるそうですね。ここでまた「岡山スタイル」を1つ思い出す。よそはどこも「クラブ設立」の周年事業なのですが、岡山はなぜか「株式会社設立」の10周年でした。「since 2004」と旧エンブレムにあるのに何でなんですかねぇ、誰か教えてください。当ブログは株式会社設立の前の歴史もしっかり知っています。まさか現経営陣は、なぜその前の時代について目をつぶろうとするのか。まさに岡山スタイル。
あと、クラブ公式HPを観ていたら、「ホームタウン」ページに目が留まりました。ページタイトルは「ホームタウン・社会連携(シャレン)」です。やっぱ価値観が違いますね。ページの内容もしっかりアーカイブ記事になっていました。ずっと更新されずに何年も使いまわしのところとは随分違います。こうして見ると、横浜さんがJ1にふさわしいクラブと思えてきました。旧横浜フリューゲルスのサポーターが作った市民クラブ、月並みですが、来季しっかりJ1に残留していただき、出来れば札幌さんのようにエレベータクラブを卒業して欲しいですね。
J2横浜FC関連:㉑ / ⑳ / ⑲ / ⑱ / ⑰ / ⑯ / ⑮ / ⑭ / ⑬ / ⑫ / ⑪ / ⑩ / ⑨ / ⑧ / ⑦ / ⑥ / ⑤ / ④ / ③ / ② / ①
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers
生観戦レポです。
昨日、Cスタで開催された、ラグビーリーグワン3部の、中国銀行レッドレグリオンズ対NTTドコモレッドハリケーンズの試合観戦に行ってきました。この週末は岡山のチームの試合が無く、何かあればいいのにと思っていたら、ラグビーの試合があると聞き、行ってみるかと奮起しました。リーグワンの岡山初開催だそうです。広島のチームが岡山で試合。サブホームタウン化を狙っているのか、それとも岡山でもリーグワン参入を検討している動きが密かにあり、試合運営の予行演習的に開催されていたりしてと、いつもの過大妄想も抱きながらCスタに向かう。


スタジアム前広場はどんな感じかなぁ、テントがポツンと2つあるだけだったりしてと思いながら到着。なにやら音楽も聞こえてきました。まずはブラスバンドの演奏が行われていました。チームの「ふれあい広場」というイベントエリアだそうです。そばにパトカーが留まっており、岡山警察音楽隊の演奏会でした。
何かいろいろイベントブースが並んでいて、ちょっと意外でした。まずはキックターゲットのラグビー版。スタジアムグルメのキッチンカーの2台来ていました。チームの公式ツイッターのアカウントフォロープレゼント企画もやっていました。


ゲートから入場。どっちも頑張れという立場なので、前半はホーム側、後半はアウェー側で座ってみる事にしました。観れればいいとかなり端っこの席に着席。ちょうど両チームが練習していました。おっと、オーロラビジョンが改装工事という事で、足場に囲まれていました。とにかく寒い。寒風が吹きすさぶとまではいきませんが、気温が低く、ガタガタ震えながら頑張って観戦しました。
おっと、この日のMCはダイナさん。ラグビーのルールわかっているのかなと思ってみたり。またどこかで会ったら聞いてみるとしよう。試合前に選手のリクエスト曲を試合前のBGMとして放送していました。ホストチームっていうんですね。
チームのマスコットが出てきました。選手入場。ホーム側はエスコートキッズを伴って、歩いての入場でしたが、アウェーチームはランニングで入場。


手拍子でカウントダウンからキックオフ。うーむ、べナルティキックとか結構外していましたね。得点もなかなか動かず。ダイナさんが、時折慣れない用語解説をしているが、どことなくぎこちな(笑)。サッカーとは違うなぁというダイナさんの声が聞こえてきそう。でも、試合中もうちょっと解説が欲しかったなぁと。
トライするが、コンバージョンをよく外していました。やはり、いつもTV等で見慣れた日本代表とはプレーの精度が違う。当たり前ですが。両チーム応援はなかったです。ラグビーの試合はこれがスタンダードなのかな。


選手はみんな半袖短パンで、寒くないのかなとつい思ってしまう。審判もそうだ。代表戦と比べて、ノックオンが多い気がする。これもしょうがないのですが。ホームの中国電力がが追いつくが、やはり、コンバージョン入らず。いかにコンバージョンが難しいのかわかった気がします。オフサイド判定も相変わらずよく分からず。フォーンが鳴る。音楽の一部のような鈍い音色。最後のトライで、自動的に7点入る。よく分からず。前半終了。


ハーフタイムにくらしきキッズチアリーディングクラブ「LUCKYS」のパフォーマンス。見事なダンスで、倉敷にも立派なチアスクールがあるんだと感心。
後半開始。一転一方的な試合展開になりました。1トライを取るが劣勢続き。時々、おお〜っという野太い声があちこちから挙がる。スタジアムのあちこちで、あのプレーはああなんだよとか解説者が解説している。ルールがわかりにくい競技であり、オーロラビジョンへの表示も無いから、余計わかりにくい。
一方的な試合のまま、ノーサイド。スコアは10-29と大阪の勝ちでした。面白い試合でした。またやって欲しいですが、岡山からリーグワンのチームが誕生しませんかねぇ。勝手な思い込みでしょうか。


帰り道でファジスクエアに寄り、ファジ不織布マスクを購入。抽選会に参加できて当たってしまい、某選手のサイン色紙をもらう。でも馴染みが無い選手だったので、その後に語る会で訪れたウルトラス倉敷店で、オーナーに個人的にもらってもらいました。やはり、喜んでもらえる人の手に行くのが一番と。語る会(密かに細々とやってます)の参加者4人が揃って、森保監督の続投反対論者だった事にはビックリしました。俺だけじゃないんだと。W杯談義で盛り上がり、ワンチャンサッカーはもうやめた方がいいという話になりました。
中国電力レッドレグリオンズ公式HP:https://rrrfc.red/
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪公式HP:https://docomo-rugby.jp/
リーグワン関連:③:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20220109
〃 ②:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20210817
〃 ①:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20210122
ラグビートップリーグ関連⑩:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20210122
〃 ⑨:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20210115
〃 ⑧:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20200327
〃 ⑦:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20190927
〃 ⑥:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20190829
〃 ⑤:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20190805
〃 ④:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20190731
〃 ③:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20190730
〃 ②:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20190716
〃 ①:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20180927
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers
リスペクトコラムです。
TBS(RSK)の日曜劇場の「オールドルーキー」。毎週観させていただいています。早いものでもう第8話まで放送されました。プロスポーツ選手のセカンドキャリアと、スポーツマネジメントがテーマであり、セカンドキャリアも時折取り上げている当ブログとしては、とても参考になります。
放送済みのストーリーについて、ポイントを押さえながらリスペクト記事にしようという事で、今回第4話から第6話まで一気に取りあげていきます。新町家のヒューマンドラマ部分は省略。


【ぶち壊せ!車いすテニスプレーヤー(第7話)】
車イステニスの吉木選手。世界を転戦するパリパラリンピックの日本代表候補でマネジメント依頼があり、受諾する。吉木選手は現在の課題は車イスの精度という認識で、長年サポートを受けていた車イスメーカーを変える決断をするが、替えた車椅子がフィットしない問題が出てくる。スポンサー探しに難航するが、パラ=可哀そうという概念を捨て、1人のアスリートとしての応援で営業したところ、スポンサーが決まる。結局、車椅子は元メーカーに戻す事になる。大会での頑張りが、1人の障がい者の少女に夢を与える。
ここで出たのがパラアスリートのセカンドキャリア。厳しいと思います。あと、法律で障がい者雇用の義務の事も出たので、パラアスリートの雇用は慈善事業では無いという気づきがありました。ドラマでは対戦相手として車椅子テニスの第一人者の国枝選手がゲスト出演していて、重みを増していました。「障がいはハンデではなく個性」という言葉が出てきましたね。ここで新町がエージェント資格を取る話が出てきましたね。


【飛び込め!プロの女子バレーボール選手(第8話)】
契約選手のVリーグ・古川選手(プロ契約)に、世界最高峰イタリアリーグ・強豪チームからオファーが来る。でも古川選手はなぜか断る。前の海外所属で調子を崩して帰国した時に出会った宮野コーチに誘われて、現在のVチームに入団した経緯があり、宮野コーチの存在が強調される。海外移籍に躊躇する理由は宮野コーチに対する恋愛感情だった事がわかる。
深沢と新町からアドバイスされた宮野コーチが、チームがリーグ優勝したら、自分もイタリアに行くと言うのを聞き、イタリアチームと移籍契約してめでたしめでたし。
今回は恋愛ネタでした。そういえば、女子チームを観ていた時に、そういうのもあるんじゃねとはおもっていました。この回もVリーグの蒼々たる顔が大勢も出ていました。オールスターのようですごかったなぁ。狩野、江畑、迫田、新鍋の4人の選手OGと植田元監督、そして元岡山選手の栗原さんの姿も。新町はサッカーエージェントの試験を受験し、合格しました。
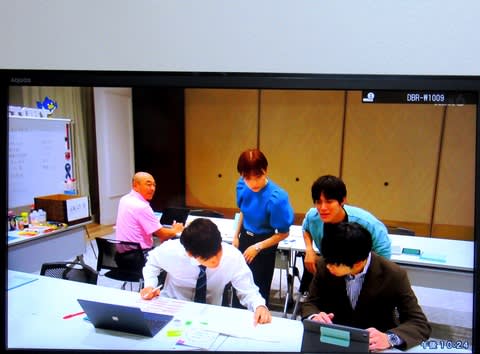

【救え!引退危機の水泳選手(第9話)】
ヴィクトリー社所属のトップスイマーの麻生選手のドーピング違反になり、4年間の資格停止処分が下りてしまう。麻生選手側はネット購入したサプリメントに禁止薬物混入の可能性を指摘し、意図的な摂取を否定し、不服申し立てをする。処分が軽くなった例があるとして、故意でなかった事を証明すると新町が麻生選手を励ます。
新町は麻生の外食記録を徹底して調査し、社長と対立。高柳社長は所属契約を解除。この事で新町の家族にも影響が出始めるが、逆に励まされる。ドーピング問題に詳しい弁護士の指導のもと、サプリメントをGADA(国際アンチドーピング機構)で検査を受ける事に。普段使用するあらゆる薬から禁止薬物の出どころを探す調査を行うが、社員が続々と協力していく。
GADAから世界スポーツ仲裁裁判所は、資格停止4ケ月への短縮を判断。しかし、高柳社長は処分が軽くなっても会社への損害は大きいと、麻生選手を所属選手には戻さないと。その後、麻生選手のこの件での記者会見を独断で開催し、高柳社長からクビを通告されてしまう。
社長の会社を守る姿勢もある程度理解できます。経営者だったらそう考えるのもしょうがない面もあるかなと。GADAの分析機関への依頼費用が200万円。世界スポーツ仲裁裁判所への申立金が300万円、その他に弁護士費用、通訳費がかかっているとありましたが、確かにそういう数字が出てくるとねぇ。通常こういう費用はクラファンとか支援者やスポンサーが捻出するのかもしれませんが、1人の社員の判断で事を進めるというのは、この辺はドラマだなぁと思います。
このドーピング問題は最近益々クローズアップされていますが、日本は長年ドーピングゼロを誇っていましたが、ここ最近五輪競技でちょこちょこと事件の報道が出てきました。特にライバル選手に混入させるという事例には頭を抱えました。


【さよなら!オールドルーキー(第10話:最終回)】
新町は退職。契約選手を引き抜かないようにと高柳社長から換言され、スポーツマネジメントを辞める事を表明。その後自転車は宅配業に就業したが、充実した表情を見せる。代わりの代理人で伊垣選手の海外移籍に苦戦し、ヴィクトリー社を辞める。その不満の勢いで深沢も城も退職。今回限りで伊垣選手の海外移籍をやらせて欲しいと高柳社長にお願いし、了解を得る。
3人で伊垣選手の海外移籍に尽力するが、上手く進まない。所属チームにも資料が送ったという事で、矢崎選手からGMが日本代表戦を観に来る事を聞かされる。矢崎選手の推薦もあり、試合で結果を出せばスカウトされる可能性が出てくる。初召集でもある代表戦が始まる。ここで高柳社長がGM(友人とか)の観戦席に同席。新町の一声も届いて2得点を決め、GMから獲得の意思を聞く。その後、高柳社長から会社復帰を提案され、戻る事になってめでたし、めでたし。
なぜか最終話のダイジェストが見当たらなかったです。ドラマの中の新町のセリフ「約束は約束」と、今回限りのマネジメントに固執する新町に好感を覚えました。トップアスリートらしい実直さ。架空の人物ですが、何かリアリティを感じる。スポーツはこの純粋さが必要。深沢は英語、城は独語ができるとあり、実際はこれくらいのスキルが無いとスポーツマネジメントはできないんだと。新町奥さんの「最高のセカンドキャリアだね!」というセリフ、番組最後の「ご協力いただいたすべてのスポーツ、アスリートの皆様にリスペクトを!」というテロップ感動を覚えながら、ドラマが終了しました。いいドラマでした。長くかかりましたが、このシリーズも完結できました。
W杯前のタイミングの放映で、先のラグビーW杯の前に放映された「ノーサイド・ゲーム」を思い出しました。どうもTBSさんはスポーツの大きな国際大会の前にこういうドラマを作られますね。まぁNHKも前年だったか大河ドラマを作っていたし。次はバスケのドラマを観たいですね。来年は日本も共催になるバスケW杯がある事だし。先日、映画の「スラム・ダンク」を観ましたが、W杯の前年のタイミングでロードショーになったのかもしれない。また、こういうのを観たいですね。しっかりリスペクトできました。
TBS公式HP「オールドルーキー」ページ:https://www.tbs.co.jp/OLDROOKIE_tbs/
Patavi「オールドルーキー」ページ:https://www.paravi.jp/title/95019
オールドルーキー関連④:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20220819
〃 ③:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20220731
〃 ②:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20220402
〃 ①:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20220621
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers
リスペクトコラムです。
昇降格シリーズのトリはJ2クラブです。同じシチュエーションに地元岡山もいた事もあって、こんなに遅いタイミングになってしまいました。改めて新潟さん、J1昇格おめでとうございます。やはり、新潟さんはJ1が似合うと思います。
新潟さんはご存じのとおり、当ブログでは「付加価値が高い公共財Jクラブ」のカテゴリ2(御三家)として、昔から評価が高く、総合スポーツクラブのスタンダードな存在です。これくらいの事ができている立派なクラブがJ2にいるのはおかしいと思ってました。観客動員数も多く、ビッグスワンでの「アイシテル ニイガタ」の大合唱の動画映像は未だにインパクトが強く残っています。

【紆余曲折あった!魅力的な新潟スタイルができるまで 特集:新アルビスタイルの真髄に迫る#1】
〔魅力的なサッカーで結果〕
「アルビレックス新潟は5年目の挑戦でJ1昇格を叶え、さらにJ2優勝も果たした。得点数はリーグ最多の73で、失点数も徳島ヴォルティスと並ぶリーグ最少タイの35。連敗は一度もなく、勝ち点は指揮官が目安として掲げた80を上回る84を積み上げた。さらに言うなら、警告数もリーグ最少。今季新設されたJ2アウォーズでフェアプレー賞を受賞した。
『本当に格好いいんですよ、うちの選手たち』 そう言って彼らを誇る松橋力蔵監督は、J2優勝監督賞に選ばれた。またJ2ベストイレブンには、小島亨介、舞行龍ジェームズ、堀米悠斗、伊藤涼太郎、高宇洋、高木善朗とリーグ最多の6名が選出された。
長年、粘り強く守ってからのカウンターを伝統としてきた新潟は、この3年間でボールを持って主導権を握り、魅力的なパスワークでゴールを陥れるチームへと変貌した。ボール支配率も、2年連続でリーグ首位となった。明確なスタイルを築き上げ、内容も結果も伴って、目標を達成した。」
5年ぶりだったのですね、結構長かったですね。最多得点、最少失点とリーグ№1だったら納得できます。地元岡山は毎季堅守で失点の少なさを口にしていますが、得点力が向上したら新潟さんみたいになれるかもです。
J2優勝監督賞に選ばれた松田監督ですが、主にマリノスさんで指導者の道を歩み、今季から新潟さんの監督に就任して1年で結果を出されました。Jクラブの監督経験が無い人が結果を出すのは難しいと思っていましたが、松田監督は異例ですね。なかなかこういう人材はいないと思います。名将ポステコグルー監督のそばで学ばれたのかな。そういう所が片野坂監督とちょっと似ているかな。やはり、ここでも「監督」かなと個人的に思いました。また、この3年でポゼッションサッカーに変えていったのも大きいのかな。やはりカウンターサッカーでは先が見えるのかもしれません。
【「新生」アルビレックス新潟が6年ぶりにJ1に帰ってくる。失速した昨季とは何が違ったのか】
「昨季、アルベルト監督(現FC東京監督。現在の登録名はアルベル)に率いられた新潟は、開幕から第13節まで10勝3分けのロケットスタートに成功しながら、シーズン後半に失速。最終的には6位に終わり、J1昇格を逃す結果に終わった。
しかし、アルベルト監督に代わり、新たに松橋力蔵監督が就任した今季は、開幕直後の4試合こそ1敗3分けと苦しんだものの、その後はじわじわと加速。徐々に勝ち星を増やして順位を上げると、第17節以降はJ1自動昇格圏(2位以上)からこぼれることがなかった。はたして、2017年シーズン以来となるJ1復帰の大願成就である。シーズンの進行とともに失速した昨季と、加速した今季。その違いを語る堀米の言葉は明解だった。
「練習量が増えて、試合終盤でもしっかり走れる選手が増えたことと、(選手起用の)ローテーションがすごくうまくいって、試合に出た選手がしっかりと与えられた時間、ポジションで結果を出せたこと。そのサイクルがすごくうまくいったなと思う」」
「かつてJ2では、低い位置で守備を固めて失点を減らし、ワンチャンスにかけるような現実的なサッカーが幅を利かせた時代があった。理想ばかりを追い求めても、J1へ昇格はできませんよ、とばかりに。
だが、近年は自らがボールを保持し、主体的にゲームを進めるスタイルで成果を手にするチームが増えてきた。今季の新潟もまた、その最たる例と言えるだろう。しかも、新潟はスタイルチェンジにとり組んでから、実質3年でJ1昇格までたどりついたという点でも特筆に値する。新潟らしいサッカーとは――。そんな問いに対し、伊藤が誇らしげに答える。
『しっかりと自分たちでボールを保持しながら、前に進んでいくということと、サイド攻撃や中央からの崩しといった、いろんなバリエーションの攻撃を自分たちがボールを保持しながら見せられるというところが、今の新潟のサッカーだなと思う』
2004年の初昇格から14シーズン、果敢な守備をベースに粘り強くJ1で戦っていた印象のある新潟だが、二度目の昇格となる今回は、おそらく前回とはまったく異なるインパクトを強烈に与えてくれるはずである。」


練習量の増加が大きいんですかね。確かにチームをステップアップさせた名将と言われる指揮官は、ハードな練習を課してチーム全体のスタミナアップを実現させていますね。なでしこジャパンの佐々木監督、ラグビーのエディー監督など、そういうイメージがありますね。選手に気を使って練習量を抜いている指揮官は結果を目前に逃しているのかもしれません。木山監督はどうなのか。
カウンターサッカーからポゼッションサッカーへのスタイルチェンジか。確かにポゼッションサッカーの理想を追いながら、負けが込んできて、カウンターサッカーに戻したチームを多く観てきました。そのまま貫き通せるのか、現実路線に妥協するのか。
地元岡山はまさに「低い位置で守備を固めて失点を減らし、ワンチャンスにかけるような現実的なサッカー」をずっと続けているのかもしれません。それで伝統の「失速」が続いているのかもしれないと思ってみたり。そういえば今季もポゼッションサッカーには見事に手こずり、歯が立たなかったですね。それでも面白いのが、その新潟さんには岡山は相性抜群だったという事。
【Jリーグ マネジメントカップ 2021:新潟、地元密着の強さを見せつけ大差で2連覇】
「日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループの1つであるデロイト トーマツ グループのスポーツビジネスグループがお届けするJリーグマネジメントカップも、今年で8回目を迎えました。ビジネスマネジメントの側面からの評価でJリーグ所属チームが優勝をかけて競いました。J2優勝の栄冠を手にしたのは新潟です。
〔Jリーグマネジメントカップ2021のJ2はアルビレックス新潟が2連覇で優勝〕
「新潟は経営効率分野、経営戦略分野で1位、マーケティング分野で3位、財務状況分野で10位となり、2位に15ポイントの大差をつけて堂々の2連覇を果たしました。」
「広い新潟においてはまだスタジアムに足を運ぶことが叶わないファン・サポーターも多く、スタジアムに来られなくとも楽しめるコンテンツの発信により力を入れ、制約が多い中でもクラブや選手を身近に感じてもらえる取り組みを継続してきました。それが功を奏し、BM面にも好影響を与え、クラブを強力に後押ししたものと推察されます。」

J2の結果の詳細、優勝した新潟さんの分析記事は、このマネジメントカップ2021のレポートにあるそうです。このマネジメントカップでの岡山の今季の順位は11位(2020年は16位)と、ずっと中位です。さて、3位と順位が飛躍した今季の順位が来年何位になるのか楽しみですね。こういうところでも評価があがらないと、J1にふさわしいクラブにはなれないと思います。
とにかく新潟さん、来季はJ1で暴れまくって下さい。市民クラブの象徴の存在、総合スポーツクラブの一つのお手本チームはやはりJ1にいなければなりません。クラブ経営の低迷で、クラブ社長に再登板された中野社長(当クラブでもリスペクト)もお喜びの事でしょう。今度は次につなげる承継者がテーマになってくるかもしれませんね。新潟さん、もうJ2には来ないで下さい。
J2新潟関連:㉚ / ㉙ / ㉘ / ㉗ / ㉖ / ㉕ / ㉔ / ㉓ / ㉒ / ㉑ / ⑳ / ⑲ / ⑱ / ⑰ / ⑯ / ⑮ / ⑭ / ⑬ / ⑫ / ⑪ / ⑩ / ⑨ / ⑧ / ⑦ / ⑥ / ⑤ / ④ / ③ / ② / ①
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers
リスペクトコラムです。
すっかり遅くなってしまいました。藤枝さん、J2昇格おめでとうございます。今だから白状しますが、J3最終節などで山雅さんがうっちゃるんだろなと思って観ていて、個人的には結果は意外でした。でも昇格は昇格。強いから2位でフィニッシュできたのだと思います。正直、藤枝さんは今までほとんど馴染みが無いクラブ。当ブログではかなり昔に、MYFCというネットオーナーシステムを紹介しており、当時は変わったクラブが出て来たなぁと思ったものでした。今回J2昇格を決めた際も、あのクラブがJ2に来るんだ、時代は変わったなという思いをまず思ってしまいました。でも実際のクラブの様子は違っていました。
【藤枝MYFCが初のJ2昇格、来季は清水&磐田と 静岡ダービーだ!】
「藤枝MYFCが初のJ2昇格を決めた。最終節の長野戦はスコアレスドローに終わったものの、勝ち点1を積み上げ、ともに勝利した鹿児島と松本を1差でかわして2位となった。選手たちは藤色の記念Tシャツを着用し、スタンドに駆けつけた約300人のサポーターと喜びを分かち合った。」
「須藤大輔監督(45)が決戦前に約束した「今シーズンで一番いい試合」を見せることはできなかった。序盤こそチャンスをつくったが決め切れず、次第に攻め込まれる展開に。後半はボランチを3枚に変えて相手の狙いを阻み、攻勢を強めて両サイドから攻め込んだものの、最後まで得点を奪えず0―0で90分が終わった。」
「もっと力を蓄えて、磨き上げた「超攻撃的サッカー」をJ2でも貫く。指揮官は「カウンターを許さない、ブロックを組まれてもこじ開けるような力をつけたい」と来季を見据えた。サッカーのまち・藤枝のプライドを持って強敵にぶつかっていく」


この須藤監督は、元Jリーガー(J1含む)で現役を藤枝さんで終えられています。その後鳥取さんの監督に就任し、J3降格後最高位の3位にまで順位を上げられたとか。家庭の事情で退任され、昨季途中で藤枝さんの監督に就任されたそうです。こうして見ると、今回の藤枝さんの躍進は須藤監督の力量もあるのかな、やはり監督の部分かと思ってしまう。
藤枝さんというクラブを少しリスペクトしてみましょう。2009年に創設。2010年に静岡FCと合併。2013年にJリーグ準加盟、2014年にJリーグに入会。かつてはイギリスのマイフットボールクラブ(英語版)に次ぐ世界で2チーム目の「ネットオーナーシステム」を採用し、ネットオーナーによる議論・投票により、戦術・運営・強化方針・人事などを決定していたが、2015年にネットオーナーサイトは閉鎖しており、アイデンティティを失った状態で今日に至るとの事。
そのネットオーナー制度の会員数は無料時代は300~400人、有料時代は60人程度であり、活動は困難な状況にあり、2015年に閉鎖されたそうです。そうですか、そんな歴史を歩んでこられて、今は普通のクラブになっているのですね。その辺りの話は日経クロステックの記事に出ていました。
【超攻撃的スタイルの「エンターテインメントサッカー」でJ2昇格 その強さに迫る】
「躍進の原動力となったのはクラブの『一体感』だろう。その雰囲気をつくったのは須藤監督の熱意だった。監督就任直後のミーティングでは『誰もやったことがないサッカーをする』と宣言。3点取られても4点取るスタイルを掲げた。練習では突拍子もないメニューもあった。例えば、守備が圧倒的に数的不利となる『4対9』のパス回しやフルコートでの『3対3』。戦う上でのベースとなる走力を鍛え、真夏でも同様のメニューを課した。
主将のMF杉田真彦(27)は『信じてついていけば面白いサッカーができると思った』。戦術面では選手のポジショニングなど細かい部分も要求。厳しい練習を積み上げてきた成果は徐々に結果として表れた。7月にはクラブ記録の6連勝。9月以降は約2カ月間負けなしでJ2自動昇格圏の2位を死守した。
MF久保藤次郎(23)も『こんなにやる気を出させてくれる監督は初めてだった』。須藤監督は士気を上げるための言葉選びやタイミングにも気を配った。趣味は読書と映画観賞。愛読書はプロ野球中日監督時代の落合博満氏を描いた『嫌われた監督』で、『自分にしか見えていない景色があるならば、そこを強みにすればいい。そう思えた時から吹っ切れた』。『オレ流』で何度も日本一に導いた名将の生きざまを参考にしてチームを束ねてきた。
昨オフにはベテラン主体だったチームから若手主体に刷新。監督の要望にフロントが応えた形だ。サポーターの存在も大きかった。今季ホーム平均入場者数はクラブ最多を更新。昇格を決めたアウェー長野戦には400人以上が駆けつけ、藤枝では初のパブリックビューイングも開催された。藤枝市をはじめとした行政も全面協力し、スタジアム改修を早期に進めた。昇格決定後、藤枝市の北村正平市長(76)は『今後も全力で応援していく』とサポートを約束している。」
須藤監督が「超攻撃的サッカー」という新しいチームづくりをした結果のようですね。今季はいわきさんが飛び抜けていましたが、その次の2位争いを藤枝さんがずっと演じていました。結果的には鹿児島さんも山雅さんも寄せ付けなかった。まさにファン・サポーターも行政も一体になって結果に結びつけた訳ですか。
ただ、J3の2位フィニッシュのチームはJ2で苦戦されています。2020年の群馬さんを除いて、今季の岩手さん、2021年の相模原さん、2019年の鹿児島さん、いずれもすぐにJ3に戻っています。藤枝さんも頑張って欲しいと思います。あと話題になっているのが、来季はJ2に静岡県のチームが3つある事。今日、J2開幕戦が発表になりましたが、地元岡山は磐田さん、清水さんと続けて対戦しますね。来季は3回ある静岡ダービーも楽しみです。何となくこれらのダービーを制したチームがJ1に行けるイメージを持ってしまいます。藤枝さんについて、いろいろ観ていると「ホームタウン」ページが立派で、行政による「ホームタウン会議」というのも面白かったです。しっかり地域に根付いた立派な地方クラブでしたね。
J3藤枝公式HP:https://myfc.co.jp/
J3藤枝関連③:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20210602
〃 ②:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20100130
〃 ①:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090124
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers
リスペクトコラムです。
つい先日、ギリギリでなでしこリーグ2部に残留を決めた湯郷ベルですが、本当に良かったと思います。経営体制も変わり、さぁこれからという時に最後の関門を潜り抜けた感じです。あれからいろいろ動きがありました。監督も替わり、入退団も続きました。来季に向けて強固なクラブづくりをしなければなりません。そんな中で先日、大物入団が発表されました。これがWEリーグ所属だったら、普通の補強でしたが、なでしこ2部ではサプライズ補強になりました。
【横山久美選手 2023シーズン加入】
「このたび、National Women's Soccer League(アメリカ)のNJ/NY Gotham FCに所属している横山久美選手が2023シーズンより岡山湯郷Belleに完全移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。
横山久美選手 プロフィール
■生年月日:1993年8月13日 ■出身地:東京 ■ポジション:FW
■経歴
・十文字中学高等学校 ・岡山湯郷Belle ・AC長野パルセイロレディース ・1.FFCフランクフルト(ドイツ)
・AC長野パルセイロレディース ・Washington Spirit(アメリカ) ・NJ/NY Gotham FC(アメリカ)
■代表歴 【国際Aマッチ 43試合出場/17ゴール】
・FIFA U-17女子ワールドカップ トリニダード・トバゴ 2010 ・FIFA U-20女子ワールドカップ ジャパン 2012
・EAFF女子東アジアカップ2015 ・女子サッカー アジア最終予選(リオデジャネイロオリンピック2016)
・AFC女子アジアカップ ヨルダン 2018 ・FIFA女子ワールドカップフランス 2019
■コメント
来シーズンから入団することになりました。再びここ湯郷でプレーすること色んな意味があり色んな思いで挑んでいきます。また湯郷が活気ある町に発展するよう少しでも力になれるよう頑張ります! また皆さんに会える日を楽しみにしています。」
横山選手お帰りなさい。覚えていますよ。本田監督時代に入団し、あれよあれよという間にヤングなでしこから、なでしこジャパンまで駆け上がりました。確か本田監督の退団を追うように長野さんに移籍したんじゃないかな。その後、欧州移籍し、去年だったかこういうニュースも耳にしました。
アメリカのチームの退団を知ったクラブ側(塚本会長)からコンタクトを取り、入団に至ったそうです。当時は津山信用金庫さんに勤務していたそうで、その時の人脈も役立ったのかな。WEリーグへの移籍の話もあったようですね。記者会見の中で、在籍時代は納得いくプレーはできていなかったので、終活するにはいい場所と言っているし、入替戦で降格になっても入団していたと思うと言っているので、本当に最後の場所への恩返しとして来たようですね。
一つだけ気になるのは「正直厳しくやらないと強くなれないかなと思っている」というコメント。若い選手を上手く厳しくやって欲しいですね。若い選手が縮み上がって、ガチガチのチームにしてしまうとますます負けて行きますから。鈴鹿さんのカズ選手のような存在になって欲しいかな。ベルでの記者会見を観るのもかなり久しぶりに思えました。
もう一つ、先日トライフープで津山に行った時に山陽新聞を買いましたが、県北の紙面に「作州ワイド版」というページがあって、目に留まりました。いい機会なのでちょっと紹介。

【Belle News】
〔日常生活編⑧ オフの日 動物と触れ合う/カフェでゆったり〕
後藤優香選手(今季で退団)は家から出ないか、遠出(大体県外)をするかの極端な過ごし方。遠出の時はその地域にある爬虫類カフェかエキゾチックアニマルカフェに行くが、岡山にはそういう施設が無いので困っています。オフはよくカフェ巡りをしていて、ふらふらといろんなところで足を運ぶ。少し前に津山市の「TREE TRUNK」というカフェに行き、隠れ家のようなたたずまいにとても癒されたとか。カフェではゆったりとした時間を過ごしてリフレッシュ。
〔お知らせ〕
18日の「ファン感謝祭」の告知。
担当者記者名を見ると、「山陽新聞津山支社勤務 岡山湯郷ベルMF・田崎美玖」との表記がありました。こういうのは他のチームでは見られませんね。県北で選手を地元企業に勤務させているベルだからこそで、いい取り組みだと思います。これからもこの「Belle News」は続けて欲しいです。そういえば、お隣の広島2チームからもっと移籍選手が来るのかと思っていましたが、まだ余り動きは見られませんね。横山選手がけん引して、来季はぜひなでしこリーグ2部優勝、1部昇格を果たして欲しいところ。
#がんばろう日本 #ThankYouHealthcareWorkers #ThankYouCaregivers

























