釧路は朝から雨かと思ったら昼過ぎから雪に変わりました。
気候が春めいてくると西高東低の冬型気圧配置が狂ってきて、これからが釧路は雪の季節。まだまだ油断はできません。
さて昨日は今年度最後の平日。市役所では永年勤続表彰や退職辞令の発令など、年度末ならではの光景が繰り広げられました。
日常の仕事でお世話になった先輩職員の多くが庁舎を去って行かれました。長年にわたる奉職本当にご苦労様でした。
これまでのご厚情に改めて感謝申し上げます。
※ ※ ※ ※ ※
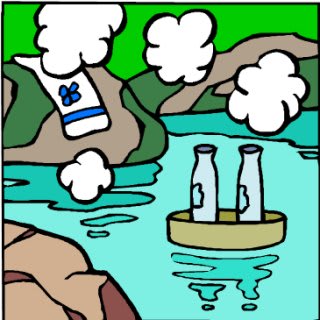
さて、報徳の教えで飢饉の村々を救った二宮尊徳は、「富み栄え平和な村をつくるには、よく分を守って(分度)、持っているものを進んで差し出せ(推譲せよ)」と教えます。
儒教ではそうした正しい自らの生き方を「仁」と言いますが、尊徳先生は、学者が難しい説明をしても良くわからない、と言ってこれを『湯船の教え』として分かりやすく説明してくれています。
『湯船の教え』とは、「湯船の湯を見れば世の中の道理が分かる」というもの。
つまり、「湯船の湯を手で自分の方へかき寄せれば、湯はこっちの方へ来るようだけれど、みんな向こうの方へ流れ帰ってしまう。これを向こうの方へ押してみれば、湯は向こうの方へ行くようだけれども、やはりこっちの方へ流れて帰る」
「少し押せば少し帰り、強く押せば強く帰る。これが天理なのだ」
「仁と言ったり、義と言ったりするのは、向こうへ押すときの名前であって、手前にかき寄せれば不仁になり不義になるのだから気をつけなさい」というのです。
また、「人の体の組み立てを見るがよい。人間の手は自分の方へ向いて、自分のために便利にもできているが、また向こうの方へも向いて、向こうへ押せるようにもできている。これが人道の元なのだ」
「鳥獣の手はこれと違って、ただ自分の方へ向いて、自分に便利なようにしかできていない。だからして、人とむ荒れたからには、他人のために押す道がある」
「それを、我が身の方に手を向けて、自分のために取ることばかり一生懸命で、先の方に手を向けて他人のために押すことを忘れていたのでは、人であって人ではない。つまり鳥獣と同じことだ。なんと恥ずかしいことではないか。恥ずかしいばかりではなく、天理にたがうものだからついには滅亡する」
「だから私は常々、奪うに益なく譲るに益あり、これが天理なのだと教えているのだ」
(二宮翁夜話 第172話)
※ ※ ※ ※ ※
退職される多くの方はまだまだ体も元気で時間もできることでしょう。
市役所を離れたこれからも、健康に留意されつつ、市政を熟知した市民として豊かな地域社会づくりに貢献をしていただきたいと思います。
まずはゆっくり温泉などでこれまでの疲れを落として、「湯船の教え」を思い出していただきたいものです。
本当にお疲れ様でした。
気候が春めいてくると西高東低の冬型気圧配置が狂ってきて、これからが釧路は雪の季節。まだまだ油断はできません。
さて昨日は今年度最後の平日。市役所では永年勤続表彰や退職辞令の発令など、年度末ならではの光景が繰り広げられました。
日常の仕事でお世話になった先輩職員の多くが庁舎を去って行かれました。長年にわたる奉職本当にご苦労様でした。
これまでのご厚情に改めて感謝申し上げます。
※ ※ ※ ※ ※
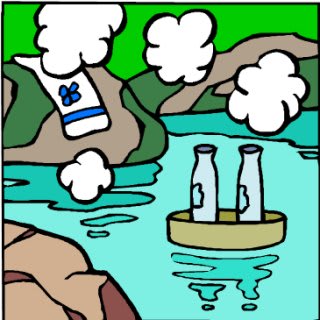
さて、報徳の教えで飢饉の村々を救った二宮尊徳は、「富み栄え平和な村をつくるには、よく分を守って(分度)、持っているものを進んで差し出せ(推譲せよ)」と教えます。
儒教ではそうした正しい自らの生き方を「仁」と言いますが、尊徳先生は、学者が難しい説明をしても良くわからない、と言ってこれを『湯船の教え』として分かりやすく説明してくれています。
『湯船の教え』とは、「湯船の湯を見れば世の中の道理が分かる」というもの。
つまり、「湯船の湯を手で自分の方へかき寄せれば、湯はこっちの方へ来るようだけれど、みんな向こうの方へ流れ帰ってしまう。これを向こうの方へ押してみれば、湯は向こうの方へ行くようだけれども、やはりこっちの方へ流れて帰る」
「少し押せば少し帰り、強く押せば強く帰る。これが天理なのだ」
「仁と言ったり、義と言ったりするのは、向こうへ押すときの名前であって、手前にかき寄せれば不仁になり不義になるのだから気をつけなさい」というのです。
また、「人の体の組み立てを見るがよい。人間の手は自分の方へ向いて、自分のために便利にもできているが、また向こうの方へも向いて、向こうへ押せるようにもできている。これが人道の元なのだ」
「鳥獣の手はこれと違って、ただ自分の方へ向いて、自分に便利なようにしかできていない。だからして、人とむ荒れたからには、他人のために押す道がある」
「それを、我が身の方に手を向けて、自分のために取ることばかり一生懸命で、先の方に手を向けて他人のために押すことを忘れていたのでは、人であって人ではない。つまり鳥獣と同じことだ。なんと恥ずかしいことではないか。恥ずかしいばかりではなく、天理にたがうものだからついには滅亡する」
「だから私は常々、奪うに益なく譲るに益あり、これが天理なのだと教えているのだ」
(二宮翁夜話 第172話)
※ ※ ※ ※ ※
退職される多くの方はまだまだ体も元気で時間もできることでしょう。
市役所を離れたこれからも、健康に留意されつつ、市政を熟知した市民として豊かな地域社会づくりに貢献をしていただきたいと思います。
まずはゆっくり温泉などでこれまでの疲れを落として、「湯船の教え」を思い出していただきたいものです。
本当にお疲れ様でした。















