
【公式HPはこちら↑】
ここ数日、突然バケツをひっくり返したような雨が降ることがしばしば、です。

災害も心配ですが、その一方でコチラ的には、、、、、、
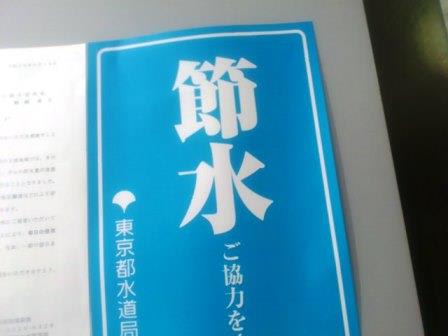
水ガメに少しは水がたまったかな、と期待したりもしますね。
そんなネタとして、日本酒がどのくらい「水」に頼っているかというお話。
例えば一升瓶=1,800ml。
アルコール度数やエキス分から考えると、80%は水、というのが第一の答え。
なので、1,440mlが水、ということになりますね。
実際には仕込み水だけでなく、お米を洗ったり蒸したり、ビンや機材を洗うなどにも水は使われますが、これらを含めると、「使うお米の重量の50倍ともいわれる水が必要」という記載もどこかで見つけました。
それでは、お米とお酒の重さの関係は?
酒類総研のHPによれば、
「1升(1.8L)のお酒を作るのに必要な白米は0.77kgとなります」
「玄米から考える場合には、精米歩合が関係しますので、純米酒の精米歩合を77%とすると、玄米1kgで1升のお酒ができます。」
と書いてあります。
この辺りから色々と仮定が入ってきますが、1升(瓶)を造るのに1kgの玄米が必要で、その50倍の重量(50kg=50リットル)の水が必要となることになります。
なるほど、本当に水は欠かせないものなんですね。
と、ここで終わらないのが、升本総本店。
それでは、その1kgの玄米を収穫するまでにどの位の水が必要なのか?
「公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構」という舌を噛みそうな長い名前の団体のホームページに「茶わん1杯のごはんを作るのに必要な水の量はどのくらい?」という質問がありましたよ。
気になる答えは、
お茶わん1杯分のお米を日本の水田で作るときに必要な水の量って、どのくらいなんだろう。
水田でお米を作るのに使う水の量は、10アール当たり2,000~3,300トンといわれている。お米の平年収量(玄米)は、10アール当たり530キログラム。ここから、玄米1グラムを作るのに、3.8~6.2キログラムの水を使うことがわかる。
お茶わん1杯分のお米は、精米で65グラムぐらい。玄米換算だと72グラムぐらいになる。そうすると、72×3.8~6.2=274~446キログラム。
最大で450キログラムぐらいは使うわけだ。これは1升ビンだと250本分にもなる。
世界では水不足が原因で、穀物生産が縮小している地域もある。大切な水を、むだに使わないよう心がけることが必要だね。
絵もあった

ここでの数字、「玄米1グラムを作るのに、3.8~6.2キログラムの水を使うことがわかる。」の大きい方の数字を使うと、玄米1kgでは6,200kg(6.2トン=6200リットル)の水を使うことになります。
つまり、整理すると、
一升瓶1本の日本酒の水分量:1.44リットル
〃 を製造するために使う水の量:50リットル
〃 の原料となる米を収穫するまでに必要な水の量:6,200リットル
となります。
※これには色々な注釈がつくのですが、知りたい方はご連絡ください。
うーん、ここまでくると、節水というより、雨乞いですね。
★★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★★
応援何卒よろしくお願い致します

応援のクリックを↑↑↑↑↑

【アルバイト・契約社員募集中!】
(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)
(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)
(3)酒類営業部門(通販管理)
日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。

















