ジュリアン・バーンズの短編集『Pulse』(2011年)を読む。この小説家の作品を読むのは『10 1/2章で書かれた世界の歴史』(白水社、原著1989年)以来だ。それも短編集(10 1/2章)であって、奇天烈なホラ話に妙に感動した記憶がある。しかし、本書は随分雰囲気が異なり、いかにも英国の、小声の笑いや皮肉を効かせた小話が集められている。
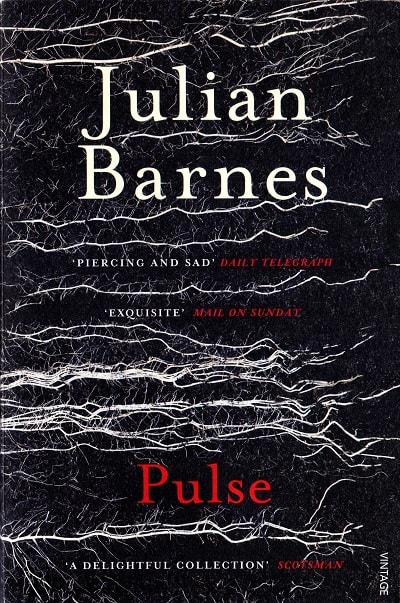
心にすり傷を残すような小説はいくつもあった。
「East Wind」は、離婚してロンドンに来た男がウェイトレスと恋仲になる話。相手の素性がまったくわからず、男は彼女の部屋を無断で物色する。そこには水泳大会で表彰を受ける彼女の写真があった。鎌を掛けるつもりで「スイマーだからね」と言ったところ、彼女は姿を消す。ググってみたところ、ドイツ語の記事があった。東ドイツ時代、ドーピングでの強化をしていた咎で罰せられた過去があったのだ。
「Gardener's World」は、ミニマルな園芸生活が趣味の若い夫婦の話。何だか落とし穴に落ちて鬱々としてしまうようだ。
「Marriage Lines」は、小さな飛行機しか飛ばない英国沖の小島に通う夫婦の話。彼らは微妙に排他的で、微妙に独善的で、しかしその世界しか受け入れることができない(「Gardener's ・・・」と同じだね)。やがて大きなジェットが飛ぶようになる。もうこの島に来ることはないだろう。そんな喪失の寂しさがある。(ところで、飛行機から見る雲の形を表現するのに「brainscape」という言葉を使っていて膝を打った。今度から飛行機に乗るたびに脳味噌を思い出すに違いない。)
「Harmony」は、原因不明の視力喪失の女の子を、磁力を使って治癒しようとする18世紀の話。おそらくは精神的な原因であり、奇跡的に見え始めるものの、それまで天才的であったピアノの演奏が鍵盤を見ることによってうまくいかなくなってしまう。父親は激怒、母親は娘がいかさま師にたぶらかされているという噂にヒステリックになり、娘の治療をやめさせる。娘は音楽家として大成、盲目のまま一生を過ごす。
「Pulse」は結婚の話。自分は相手と性格が合わず、離婚に至る。両親の仲は、大昔からそうであったように自然に睦まじい。ある時、父親が「妻の匂いがわからなくなった」と訴える。それだけでなく、強烈なもの以外の嗅覚がなくなってしまい、靴を磨いていても実感がない。夫に自身はじめての針治療を行う妻だが、その妻が脳疾患が原因で倒れ、死に向かってゆく。男は、自然に隣にいる父親と、離婚した自分とを見つめる。
「At Phil & Joanna's」という、ハチャメチャな会話シリーズもある。誰と寝たか忘れただとか、マーマレードとナショナリズムの関係だとか、アホな地球温暖化懐疑論だとか、話があちこちに飛びまくる。
と書くと面白かったようだが、実はさほど愉しめなかった。何だか陰鬱で、こそこそ笑っていて、秘かに抒情的であったりもして、気分は雨続きのロンドンなのだ。(別にロンドンが嫌いなわけではないのだけど。)
思い出した。去年、仕事相手の英国人とフランスを移動していて、どこかの店のカウンター越しに野獣のように怒鳴り合っているフランス人たちがいた。それを観察して彼が言った。
「フランスではよくああいう光景を見るんだけど、英国ではありえないんだよね。」
「じゃあ英国人は怒ったときどうするの。」
「静かに苛々している(爆笑)。」










