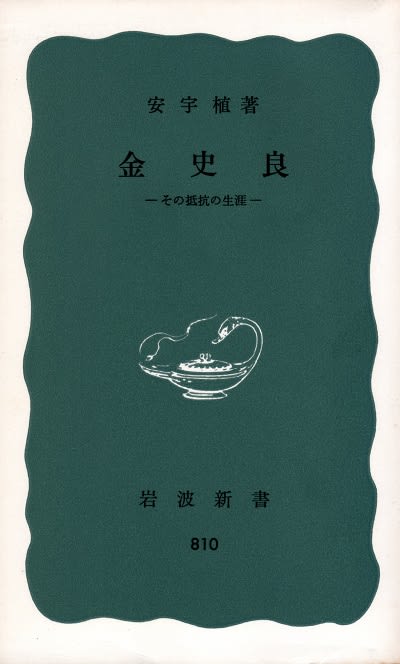ウランバートル郊外に巨大なチンギス・ハーン像があって、その中には当然のように土産物屋がある。
モンゴルで見る土産物といえば、ゲルのおもちゃ、馬頭琴のミニチュア、手袋、毛皮の帽子、Tシャツや絵葉書などの「いやげ物」、馬の置き物など。どうせ琴線に触れるようなものもないだろうと近づいてみると、びよ~んびよ~んという音が聞こえる。口琴を弾いている人がいる!
誰の手作りかわからないが、紛れもなくモンゴルの口琴である。早速ためしてみて、塩梅の良いものを買った。3万5千トゥグルグ、約2千円。
金属製の口琴は、指で弾く弦が飛び出ていて、危ないし保管が不便である。この口琴は、それがすっぽりと収まるよう溝が彫られた木の箱に、うまく紐で結えてある。よく考えられていて感心する。
音はというと、軽快で気持が良い。調子に乗って、ウランバートルの日本料理屋で仕事仲間に披露し、「顔が怖い」と評価された。
帰って手持ちの口琴と比較してみると、ハンガリーの匠ことゾルタン・シラギー氏作成の「ロココ」とは、また違った軽やかさだ。なお、アメリカ製の武骨な口琴は、文字通りぐぉ~~んと頭蓋骨が揺れておかしくなる。北海道で買ったアイヌのムックリは竹の音。
びよ~んびよ~ん。


手前左から、モンゴル製、ハンガリー製、アメリカ製。奥、アイヌのムックリ。
●参照
酔い醒ましには口琴
『沖縄・43年目のクラス会』、『OKINAWA 1948-49』、『南北の塔 沖縄のアイヌ兵士』(宮良瑛子の口琴の絵)
ハカス民族の音楽『チャトハンとハイ』(ハカスの口琴)
チャートリーチャルーム・ユコン『象つかい』(タイの口琴)
"カライママニ" カドリ・ゴパルナス『Gem Tones』(インドの口琴)
マーク・トウェイン『トム・ソーヤーの冒険』(アメリカの口琴)