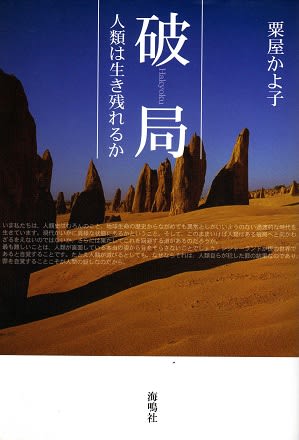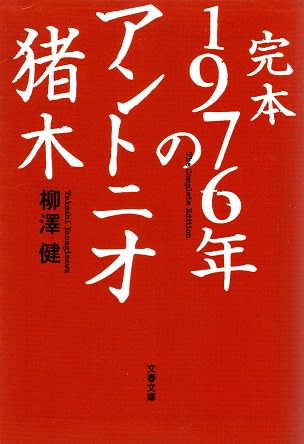ヘンリー・スレッギルがベースのフレッド・ホプキンス、ドラムスのスティーヴ・マッコールと組んだユニット、エアーでは、さまざまなレーベルで演奏を記録している。その中で、1978年にAristaに吹きこんだ2枚だけは、おそらくCD化されていない。
エアーの作品(録音順)
■ AIR SONG (Whynot, 1975録音)
■ WILDFLOWERS 1 (1976録音)(※オムニバスでありこのうち1曲のみ)
■ LIVE AIR (Black Saint, 1976・77録音)
■ AIR RAID (Whynot, 1976録音)
■ AIR TIME (Nessa, 1977録音)
■ OPEN AIR SUIT (Arista, 1978録音)
■ MONTREUX SUISSE AIR (Arista, 1978録音)
■ AIR LORE (RCA, 1979録音)
■ AIR MAIL (Black Saint, 1980録音)
■ 80°Below '82 (ANTILLES, 1982録音)(※邦題『シカゴ・ブレイクダウン』)
■ OPEN AIR SUIT(1978年2月21,22日)
「オープンエアー組曲」といった冗談なのか。この組曲には変わった趣向が施されている。A面は「First Hand」、B面は「Second Hand」と題され、「ロイヤル・フラッシュ78回転」、「宇宙的肛門」(ジャケットの猿か?)などといった手が繰り出される。

演奏の印象としては、カードゲームの複雑なルールのようにギクシャクしており、各人の音も次々に違う技を開陳するかのようだ。言ってみれば、音の絡みのショーケースである。そんな中で、B面では唐突にバリトンサックスが勢いよくベースと組み合う。スレッギルのバリトンはあまり例がなく、これだけでも面白い。
■ MONTREUX SUISSE AIR(1978年7月22日)
1978年のモントルー・ジャズ・フェスティヴァルに出演したときのライヴ録音である。いまだ続くこのフェスのデータベース(>> リンク)で調べてみると、同じ日のステージには、ムハール・リチャード・エイブラムスとオリヴァー・レイクのデュオや、ファラオ・サンダースらが登場したようであり、タイムスリップできればどんなにいいことかと夢想してしまう。
曲は盤の順の通りであり、最後に「ペイル通り」という短い曲(他の盤でも演奏している)のみ省略されている。

1曲目では、スレッギルはアルトサックスで参加する。まだステージで有機的に結びつく前の手探りの感がある。2曲目はテナーサックスである。このドラマチックな展開は特筆すべきだ。ジル・ドゥルーズのテキストを読みながら聴いていると、時間の進行に伴う展開とはまた異なる様相がイメージされてきた。音の雰囲気というエーテルがつまった三次元空間において、スレッギルのサックスは反復し、空間に揺らぎを与え、再結合を作り、相転移する。これは演奏者間のインタラクションとは雰囲気をかなり異にしている。知的でアナーキーな小編成の即興音楽は、のちにスレッギルが組み上げる高濃度・緊密な音楽とは異なるようでいて、実は底流が見えていたということかもしれない。
ライヴならではだが、ベースやドラムスのソロを十分に聴くことができるのも嬉しい点だ。マッコールのシンバルは聴きごたえがある。(ところで、ジャケットの妙なイラストはマッコールによるものだ。)
B面では、ベースとドラムス・パーカッションとのデュオが延々と続く。音が割れたパーカッションも含め、破綻しそうなスリリングさがある。10分以上も経った頃、スレッギルがバリトンサックスで乱入してくる。フラジオ奏法での高音を繰り出してくる様は、まるで破れかぶれであり、破綻のエッジでの舞踏のようであり、文句なしに素晴らしい。
改めて聴いてみて、エアーの最高傑作かもしれないという印象を強く抱いた。
●参照
○ヘンリー・スレッギル(1) 『Makin' A Move』
○ヘンリー・スレッギル(2) エアー
○ヘンリー・スレッギル(3) デビュー、エイブラムス
○ヘンリー・スレッギル(4) チコ・フリーマンと
○ヘンリー・スレッギル(5) サーカス音楽の躁と鬱
○ヘンリー・スレッギル(6) 純化の行き止まり?
○ヘンリー・スレッギル(7) ズォイドの新作と、X-75
○ヘンリー・スレッギル(8) ラップ/ヴォイス