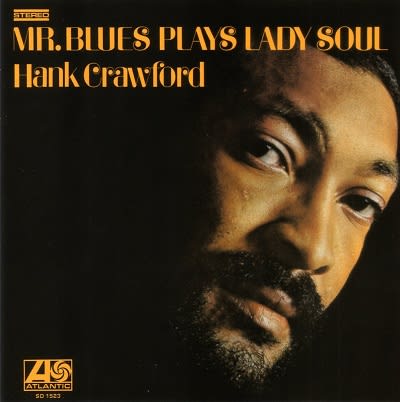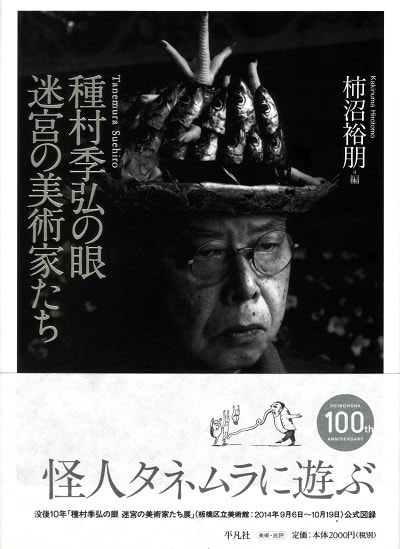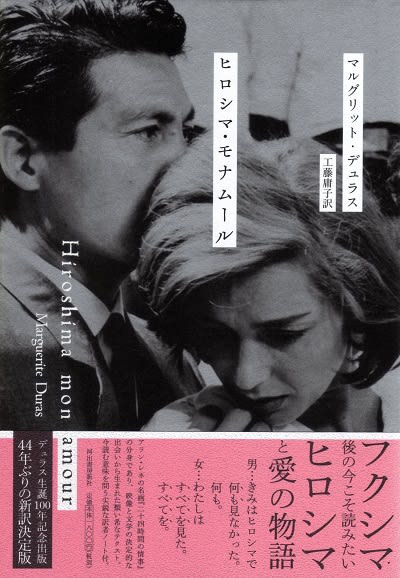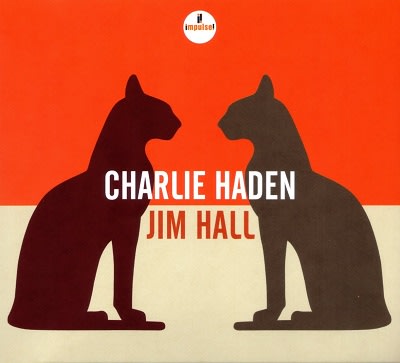1年半ぶり、5回目のハノイ。相変わらず食事が旨く、つい食べ過ぎて反省することを繰り返している。
■ Pho 24
ハノイには何店舗もあるフォーの店。また、ベトナムだけでなく他国にも展開している。ジャカルタでも見かけた。東京では、大森などに3店舗を構えていたのだが(味は同じで、当然値段が東京価格)、残念ながら、昨年撤退してしまった。
久しぶりに食べたらやはり旨い。これに比べると、ホテルの朝食や(Pho 24でない)東京のフォーの店の味が物足りなく感じてくる。

フォー・ボー

レアなカップ麺を発見。買わなかったが。
■ Wild Lotus
ティエンクアン湖の近くにあるベトナム料理店。店のつくりも料理も洒落ていて、外国人の客が多い。
海老グリルのオレンジソースが妙に気に入ってしまう。

牛肉のゴマ和え

海老グリルのオレンジソース

■ ASHIMA
数年前に登場した、きのこ鍋の店。ハノイとホーチミンに数店舗あって大評判らしい。今回ぜひ再訪したかった。
5種類くらいのきのことスッポン。特に翌朝の美肌効果はなかった。


調理前のスッポン
■ Duy Diem
ハノイ中心部から西に外れたあたりに、ブンチャ(細麺をつけ汁に浸して食べる料理)の店が並んでいるエリアがある。店頭で肉を焼いているところも多く煙もうもう。旧市街にも同様にブンチャが評判の店があるが、そちらは観光客で行列さえできているのに対し、こちらは地元住民ばかり。
この店をDuy Diemというご夫婦がはじめたところ、大当たりして、同じような店が周囲にもできたのだとか。
来るのは2回目。つけ汁のなかの肉が香ばしくて実に旨い。


■ CAY CAU
中心部にあるベトナム料理の店。中ではベトナムの弦楽器と笛による生演奏もあって居心地がいい。
柑橘のサラダが旨い。


柑橘のサラダ

海老のビール蒸し
※写真はすべて、Nikon v1 + 10mmF2.8