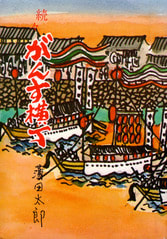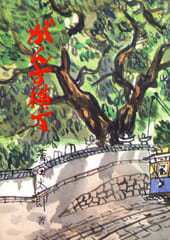妓楼から約40m先の古い民家。ここの二階の手すりにも透かし彫りが確認できた。復興期に建てられた家屋はこんな感じが多かったのかも知れない。民家のすぐ近くには旧平塚町の守護神・琴比良神社が鎮座する。
この町角を真直ぐ南へ行くと、平塚町の金比羅さんがあった。こどものころには、金時サンが持っていた大まさかりの印があるちょうちんを見た。社殿右側の石には、「昭和二十年八月六日原子爆弾に依り炎上」の文字が刻まれてあるのも、戦後の社殿と思われる。別の石柱には、昭和二十三年十二月再建、世話人安田寿夫、湊岩次郎など二十四名の名前が刻まれていた。また、明治四十四年十二月とある石鳥居が、そのまま二度のご用をはたし、それにシンガポール陥落とある九本の幟石も残っていた。
このあたりに製針工場があって、第一次世界大戦当時はなかなか活気のあった平塚町であった。
「がんす横丁(前述)」より引用
神社は昭和45年に現在地に遷座しているが、それ以前は老人ホームが建っている辺りにあった(これが被爆前の場所と同一かは自信がない)。辻を北上し鮮魚店の角を右折するとまたしても興味深い建造物が現れた。