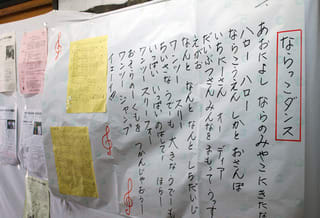| 日本めん食文化の一三〇〇年奥村 彪生農山漁村文化協会このアイテムの詳細を見る |
昨年9月の刊行時から読もうと思っていた大著を、先日やっと読み終えた。版元の紹介文には《そうめんやうどん、そばの始まり、めんのおいしさの俗説と真実、地方に花咲いた農山村のめん食文化の重要性…膨大な古文書にあたり、再現実験や科学分析を行ない、30余年に渡る全国調査を集大成した画期的労作》とあるとおり、まさに目からウロコの大スペクタクルである。
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_4540073052/
総ページ数が約600頁、重さ約1kgのハードカバーを通勤カバンに入れ、電車の中や退社後の喫茶店で、半月かけて読み終えたのだが、読後感は爽快である。よくこれだけ調べられたものだ。少し長くなるが、同書の概要を紹介させていただく。
版元の「著者紹介」には《奥村彪生(おくむら・あやお)伝承料理研究家。美作(みまさか)大学大学院客員教授、大阪市立大学大学院生活科学研究科非常勤講師。学術博士。著書多数。平成12年度和歌山県民文化賞受賞。 NHK「きょうの料理」、NHKラジオ『関西ラジオワイド 旬の味』、NHK『日めくり万葉集』などに出演》とある。お生まれが和歌山県(西牟婁郡すさみ町)お住まいが奈良県(香芝市)と、私と共通点があるので、以前から私淑していた。NHKの「日めくり万葉集」も奥村氏の出演分は、何度も録画を見直したものだ。
高校卒(和歌山工業高校卒業・近畿大学理工学部中退)ながら、昨年、美作大学大学院に、同書のモトになる「日本のめん類の歴史と文化」という博士論文を提出し、見事審査に合格して博士号を取得された。
同書で最もセンセーションを巻き起こしたのは、うどんは中国渡来の切麦(きりむぎ=ひやむぎ)を、日本人が独自に改良したものだ、という新説である。和歌山工業高校OB有志による祝賀会のブログ記事にその辺りが要領よくまとめられているので、紹介する。
http://tatemisak.exblog.jp/11850723/

釜粋(かまいき 奈良市東向商店街)のつけめん
《うどんのルーツ中国ではなく日本だった》《中国のワンタンがうどんの起源とする説に、料理人の立場から疑問を抱いていた。この説は、昭和初期の中国文学者青木正児京都大教授(故人)が発表、今ではうどんの起源として最も有力な説となっている》《青木説は、ワンタンの中国表記である「コントン」のコンは食へんに「昆」と書き、トンは饂飩(うどん)の飩だが、コンを食へんに「軍」と書くことがあり、ウントン、ウンドンとも読む。これが読みの同じ温飩になり、饂飩に変わった》とする。
奥村氏は《起源を探ろうと三十年かけて、中国各地で麺を食べ歩き日本国内の古文書を読みあさった。結果、中国には、湯で温めた麺をつけ汁につけるうどん本来の食べ方がなく、饂飩の「饂」の字もないことが分かった》。つまり「饂飩」は日本の造字で、日本語なのである(同書P252)。《うどんが切り麺ということに着目し、切り麺の歴史をさかのぼった。切り麺が中国から伝わったのは鎌倉時代。中国の切り麺の歴史をひもとくと、唐代に「ぷとう」と呼ばれる切り麺がある。これが発展したのが「切麺(ちぇめん)」で、宋代に盛んに作られるようになる。そして、この切麺が1200年代前半、留学僧によって伝えられ、日本で「切麦(きりむぎ)」と呼ばれた。切麦は中細麺で、今の冷麦のことだ。「この切麦こそがうどんの祖先」》。
《それでは、切麦がどのようにうどんに変化したのか。江戸時代の記録などによると、うどんは、ゆでた麺を水で洗った後熱湯につけ、つけ汁につけて食べていた。今でいう「湯だめ」だ。中細の麺を湯につけたのでは、どうしても麺が伸びてしまう。そこで、湯につけても伸びないよう発明された専用の太切り麺こそが、うどんというのだ》。
《うどんが初めて文書に登場するのは南北朝時代の1351年。法隆寺の古文書に出てくる「ウトム」がそれ。うどんの記述はその後、京都の禅寺や公家の記録に頻出する。留学僧によって切麦が伝えられたのが1200年代前半。当時、中国へ渡る留学僧は禅宗の僧が中心だった。こうした経緯から「うどんは、1200年代の終わりごろ、京都の禅寺で生まれた」》と推定される。
記録上、うどんを初めて食べたのは、法隆寺の快賢という僧兵であった。合戦で手柄を立てた祝いの席の酒肴に「ウトム」が出ている(同書P237)。《初めて記録に登場するのは奈良だが、その後の記録の多くが京都に集中していることから「発祥の地は京都とみるのが妥当」。麺をつけ汁につける食べ方について、「食べ方に美しさを求め、素材そのものの味を味わう禅宗の考え方につながる中国にはない食べ方だ」》とする。
 | 聞き書・ふるさとの家庭料理〈4〉そば・うどん奥村 彪生農山漁村文化協会このアイテムの詳細を見る |
うどんのルーツ以外にも、注目すべき新説が同書には続々と登場する。《「大阪のうどん、東京のそば」と言われる東西のめん文化の違いは、江戸時代の水事情が決定づけた――。奈良県に住む伝承料理研究家の奥村彪生(あやお)さん(72)=写真=が、大著『日本めん食文化の一三〇〇年』(農文協)の中で、丹念な調査をもとに新説を唱えている》(読売新聞 09.12.4付「東西めん文化 水事情反映 江戸時代の上水設備に差」)。
《「いらち(せっかち)な大阪人が、早くゆで上がるうどんを求めた」「粋な江戸っ子が、つるっとしたそばののどごしを愛した」 東西で好むめん類が違うのは有名だが、理由は漠然と説明されることが多い。NHKの番組「きょうの料理」の講師歴がある奥村さんは食べ歩きや文献調査を重ね、徳川時代後期の文献にある大阪のうどん屋のメニューに注目した。「うどん」「そば」「しっぽく」(具入り)など種類は豊富でも、すべて熱いめんだった。一方、江戸は早くからそばを水で冷やして洗い、盛りやざるで食べたという》。
《この原因を、奥村さんは当時の水事情にみる。物流用に運河が発達した「水都」大阪は当時、実は上水設備が不十分で井戸水も海水が混じり、水は「水屋」から買って飲んだ。「料理は安全が一番。水が悪ければ、沸騰させて使うしかない」。大阪では温かいめん類が広まった。それに対し、徳川幕府は住民の飲料水確保に力を入れ、神田上水や玉川上水を完成させる。ふんだんに水を使うことができ、冷たいそばの愛好者が増えた》。
《この条件に、大阪は、北海道や青森から北前船でコンブやカツオ節が手に入り、経済が栄えて換金作物の小麦が集まったこと、東日本は北関東や東北など良質なそば産地を控えることが、それぞれ重なった。素材の色や味を生かす京料理の影響も受けた大阪では、だしを利かせ汁の色の薄いうどん。素材より、つけ味を良しとした東京では汁の甘辛いそばが発達したという》。
《『麺(めん)の文化史』の著書がある国立民族学博物館の石毛直道名誉教授は「中国南部では中華めんを作る際、水がアルカリ性でないためかん水を混ぜる。各地のめん文化は水に影響され、大阪の水の悪さに着目したのは興味深い」と太鼓判を押す》。

京都のしっぽくうどん
奥村氏は、日本農業新聞の「論点」欄にも寄稿されているタイトルは「郷土のめん食文化/高齢社会に生かそう」(日本農業新聞 09.08.10付)である。まず、麺常識のウソを解明。
《(1)奈良時代の索餅(さくべい)は小麦粉と米粉で作る縄のごとく捻(ひね)っためん、あるいは揚げ菓子でなく、小麦粉単独で作る手延べめんであった。(2)索(素)麺(そうめん)は索餅が進化した手延べめん。古くなるほど美味(おい)しくなる説は誤り。せいぜい3年までで、のど越しは良いが味は失(う)せる》。
上述のとおり《(3)うどんは空海が伝えたのではなく、鎌倉末期から南北朝にかけて、京都の禅寺で誕生した太切りの熱湯漬け専用のめんであった。(4)そば切り(麺としてのそば)は信州で生まれたのではなく、京都の禅寺で室町時代に種が播(ま)かれて芽が出、寺方ネットワークで信州に伝えられて成長し、信州からこれまた寺方ネットワークで江戸に伝播(でんぱ)し、元禄のころに花が咲き、結実した》。
そばについては《高齢社会を迎え、ソバが体によいといって人気が高まり、消費量は伸びている。今、東京を中心に「さらしな」が人気だ。そこで私は、「さらしな」「並」「田舎」のそば切りをゆで、前後の栄養成分の比較試験を行った。その結果、たんぱく質や人間の体に有効な機能を持つルチンやギャバは「田舎」に最も多く、ゆでても溶出量は少ない。続いて「並」。「さらしな」は機能成分が全くなく、エネルギーが高いだけだった》。
《健康という視点でいえば「田舎」は最良で、「さらしな」は趣味食としての美食の極みだ。かつて農山村では、そば切りはハレの食べものであった。普段はそばがきやおやき、薄焼き、だんご汁、そば米雑炊などソバそのものの栄養を丸ごと体内に取り込み、身体と精神力、活力を養ってきた。これが生活食、かつ労働食、いわゆる健康食なのだ。いま一度、郷土食を見詰め、改良して高齢社会に生かそう》。
『日本めん食文化の1300年』の最終章には、こんなくだりがある。大阪ではコナモンというが、長野県ではこなもの(粉物)と呼ぶ。奥村氏は、南部(青森県東南部)や信州の粉物に注目する。それは麺類、そばがき、おやき、薄焼、団子などである。《実にバラエティに富んでいる。食糧が不自由なるがゆえの自由で豊かな発想から生まれた食べごとの文化である》(1.粉食[めん食]は庶民のゆたかな食文化)。
《こなものは食べてきた目的が違う。南部や信州では、コムギやソバ、他の雑穀を含めると、これらは生命の糧であった》。例えば《味噌煮込みうどんは農山村の夕餉の主食として用いられてきた。主食とおかずと汁が一体になっている。材料の無駄を一切しない栄養豊かな食べ方である。醤油を用いず味噌で味付けするのは、農山村では味噌は自家製であり、醤油は買うものであった。ために、醤油を買うと不経済であるからである》。
それらは《素朴なるがゆえにその美膳となした食べものには作る方の鼓動の響きと体臭を養った。貧しく(米を食べられないから)とも美しく生きる精神と美しい肉体、心遣いを養った。この作り手の魂がこもった鼓動の響が食べる者と共鳴してシンフォニーを奏でた。その響が明日への労働の英気となった》。
 | 「粉もん」庶民の食文化 [朝日新書065]熊谷 真菜朝日新聞社このアイテムの詳細を見る |
ここまで書いて、ふと思い出した。以前、タコヤキストの熊谷真菜さん(日本コナモン協会会長)が、ある知事と食文化について対談したあとで「粉もんより、もっとすばらしい食文化があるでしょう」と言われて憤慨した話を自著(「粉もん」庶民の食文化)に書いておられた。そのとき「粉食こそが、庶民の食文化の原点です」と逆襲されれば良かったのである。
このように同書は、日本の食文化に関する大いなる示唆を与えてくれるが、堅苦しい一方の本ではなく、麺類全般に関するウンチクが得られ、また美味しいお店への手引き書ともなる。1冊3990円の超大作は、おいそれと薦めるわけにはいかないが、「人類は麺類」を自認する麺類好きには、必読の快著である。