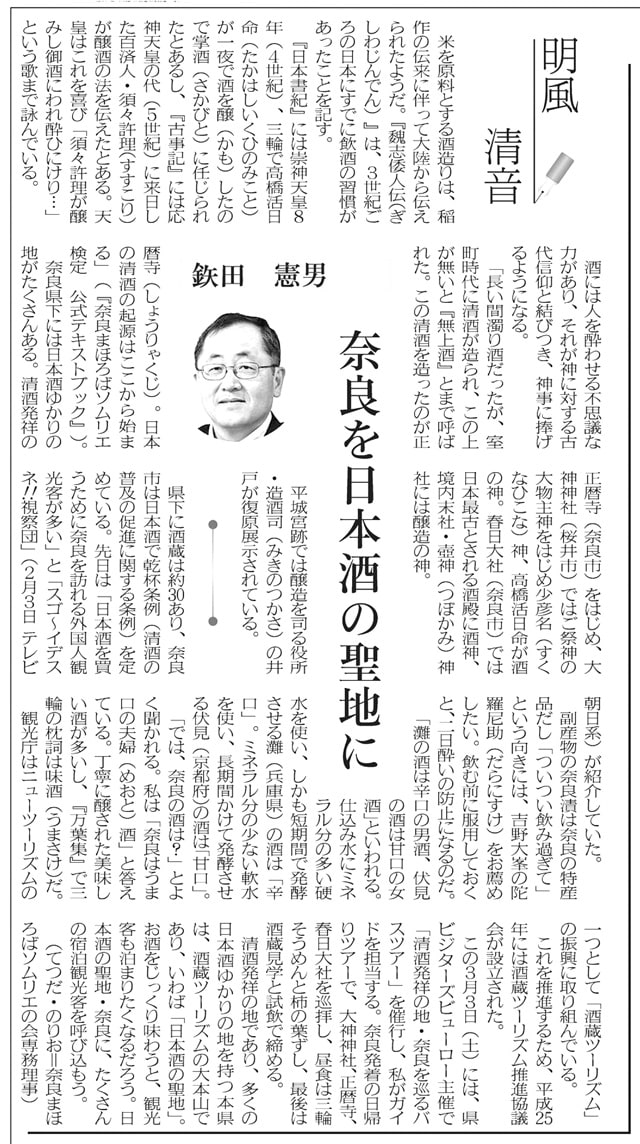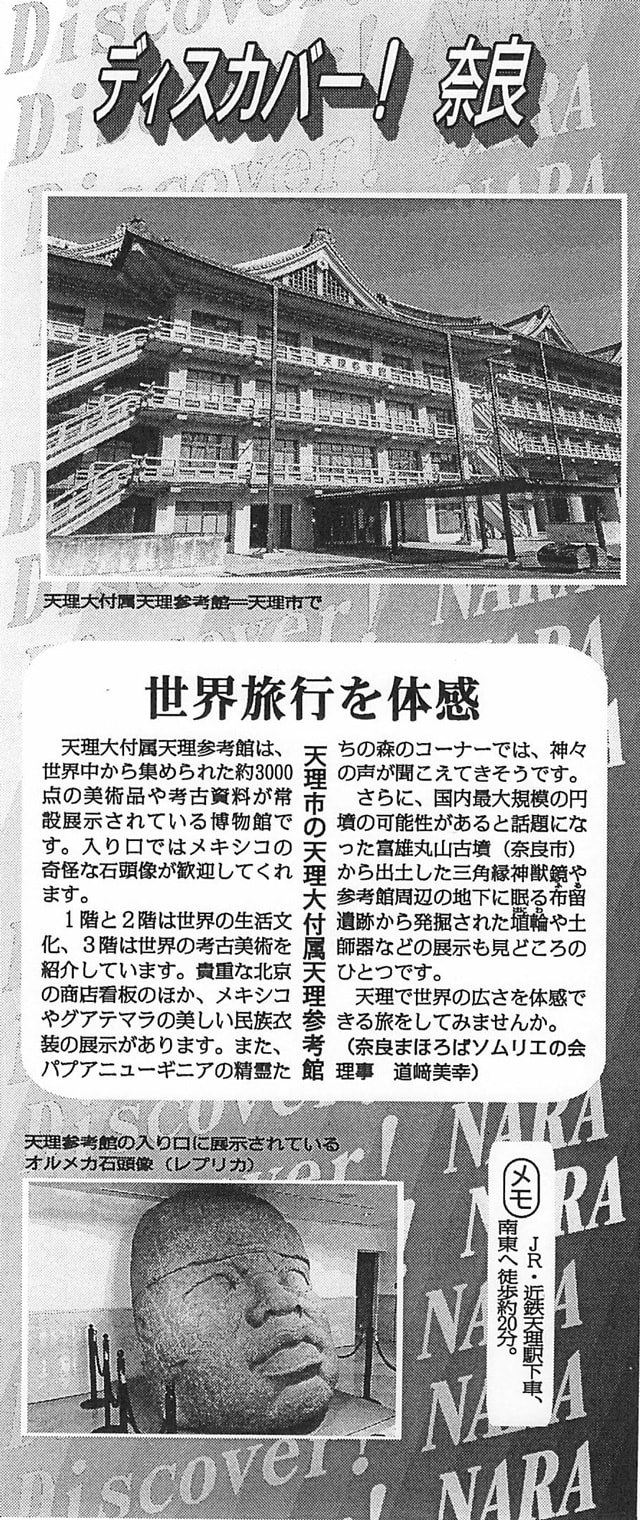奈良日日新聞に私が毎月第4金曜日に連載している「奈良ものろーぐ」、先週(2/23)掲載されたのは、「商都高田いまむかし 今年は大和高田市制70周年」だった。地元のお2人に昔のお話を聞き(2/1)、まとめたものである。しばらくはこの聞き書きシリーズで続けていくつもりだ。
※トップ写真は、片塩商店街で2月10日撮影
お2人のうち村島さんは同僚に紹介してもらい、上嶋さんは、村島さんからお声かけいただいた。大和高田市には親戚があったので、子供のころに何度か訪ねたことがある。60年近い前なので、大きな商店街に人がたくさんいたという記憶だけがある。その記憶に思いをはせながら、お話に耳を傾けた。では全文を紹介する。
大和高田市は今年、市制70周年を迎えた。64歳の私とは、あまり年が違わない。子どもの頃、母に手を引かれてアーケードの商店街を歩いたことを覚えている。お店も通行人も、キラキラと輝いていた。
ユニチカの前身・大和紡績が明治時代に工場を建て(昭和52年に撤退)、戦後のピーク時には市内に映画館は8館もあったという。今もJR和歌山線・桜井線、近鉄大阪線・南大阪線、国道24号・165号・166号が通じ、南都銀行も3店舗ある。
郷土史家の上嶋𠀋夫(うえじま・たけお)さん(94歳)と、村島硝子商事会長の村島靖一郎(せいいちろう)さん(84歳)に、この町の歴史についてお話を伺った。

今も風情のある町並みが残る(これら2枚は2/1の撮影)
上嶋さんの実家は食堂と馬冷池(ばれいいけ)の貸ボート店を営んでいた。今は池が埋め立てられ、大和高田さざんかホールと公園になっている。「女工さんが大勢いたので、休みになると隣町から若い男連中がやって来ました。戦前は2人乗りボートが30分で20銭。向こう岸で他のアベックと交代したり、乗り捨てやただ乗りされたこともありました」。
村島さんは「秋祭りは賑やかで、大きな神輿(みこし)や行列が練り歩きました。『大和のエソ祭り』といって、祭りの日にはエソという白身魚を食べました」「冬の祭礼のときは軽うてぬくい『まわた』を背中に着けました」。まわたは屑繭(くずまゆ)で作った綿入れのこと。そういえば高田周辺は、古くから綿作や繊維産業が盛んだった。

上嶋さん。「ユニチカには、女工さんを中心に約3千人が働いていました。東北や北陸の娘さんが多かったです。それが工場閉鎖で急にいなくなり、町は様変わりしました」。
村島さんの車で、市内をご案内いただいた。春日神社(同市大中東)には「弁慶の七つ石」がある。義経一行が頼朝に追われた際、静御前の母が住む地(礒野北町)を訪ねる途中、境内の石に腰掛けて一休みしたという。
常光寺(旭北町)には「八百屋お七」のモデルという「志ちの墓」。お七は井原西鶴の『好色五人女』に登場し、恋人に会いたい一心で放火事件を起こし、火あぶりの刑に処された少女だ。お寺の本堂脇に、墓石と立て札が建っていた。付近にはお七川と呼ばれる小川(溝)が流れ、この水をつけるとやけどが早く治るといわれる。
上嶋さんは「大和国中高田の町はお七が燃やす恋心/紅蓮(ぐれん)の恋やいと哀れ未練を流すお七川/今も昔も悲恋(こい)の町」という「高田悲恋歌(こいうた)」を作られた。
最後にJR高田駅から徒歩1分の「高田天神社」(三和町)へ。村島さんは同社の責任役員だ。社伝では第10代崇神天皇の頃に創始。高田一円の氏神さまで4月の御田植え祭、10月の御神輿渡御(とぎょ)などで知られる。

このお店では奈良漬を「うねび漬」の名前で販売されていた(片塩商店街で2/10撮影)
近郊への大型店の出店や地場産業の繊維・靴下の衰退で、環境は厳しいが、近鉄高田市駅前の片塩商店街は一昨年、経済産業省の「はばたく商店街30選」に選出され「お年寄りに優しく、元気になれる商店街」として、県外からの視察が相次ぐ。
「志を同じくする者が5人集まれば、地域を変えられる」という。この動きを広げ、賑わい再興に取り組んでいただきたいものだ。ガンバレ、商都高田!
片塩商店街はいろいろと趣向を凝らしていて、今はウエルカムボード(小型のサインボード)の巧拙を競う「第1回片塩ウエルカムボード大賞」コンテストも実施している(投票は3/3まで)。ウエルカムボードは、トップ写真にも右下に小さく写っている。
上嶋さん、村島さん、貴重なお話をありがとうございました。皆さん、ぜひ大和高田市をお訪ねください!
※奈良日日新聞ご購読のお申し込みは、こちらから

※トップ写真は、片塩商店街で2月10日撮影
お2人のうち村島さんは同僚に紹介してもらい、上嶋さんは、村島さんからお声かけいただいた。大和高田市には親戚があったので、子供のころに何度か訪ねたことがある。60年近い前なので、大きな商店街に人がたくさんいたという記憶だけがある。その記憶に思いをはせながら、お話に耳を傾けた。では全文を紹介する。
大和高田市は今年、市制70周年を迎えた。64歳の私とは、あまり年が違わない。子どもの頃、母に手を引かれてアーケードの商店街を歩いたことを覚えている。お店も通行人も、キラキラと輝いていた。
ユニチカの前身・大和紡績が明治時代に工場を建て(昭和52年に撤退)、戦後のピーク時には市内に映画館は8館もあったという。今もJR和歌山線・桜井線、近鉄大阪線・南大阪線、国道24号・165号・166号が通じ、南都銀行も3店舗ある。
郷土史家の上嶋𠀋夫(うえじま・たけお)さん(94歳)と、村島硝子商事会長の村島靖一郎(せいいちろう)さん(84歳)に、この町の歴史についてお話を伺った。

今も風情のある町並みが残る(これら2枚は2/1の撮影)
上嶋さんの実家は食堂と馬冷池(ばれいいけ)の貸ボート店を営んでいた。今は池が埋め立てられ、大和高田さざんかホールと公園になっている。「女工さんが大勢いたので、休みになると隣町から若い男連中がやって来ました。戦前は2人乗りボートが30分で20銭。向こう岸で他のアベックと交代したり、乗り捨てやただ乗りされたこともありました」。
村島さんは「秋祭りは賑やかで、大きな神輿(みこし)や行列が練り歩きました。『大和のエソ祭り』といって、祭りの日にはエソという白身魚を食べました」「冬の祭礼のときは軽うてぬくい『まわた』を背中に着けました」。まわたは屑繭(くずまゆ)で作った綿入れのこと。そういえば高田周辺は、古くから綿作や繊維産業が盛んだった。

上嶋さん。「ユニチカには、女工さんを中心に約3千人が働いていました。東北や北陸の娘さんが多かったです。それが工場閉鎖で急にいなくなり、町は様変わりしました」。
村島さんの車で、市内をご案内いただいた。春日神社(同市大中東)には「弁慶の七つ石」がある。義経一行が頼朝に追われた際、静御前の母が住む地(礒野北町)を訪ねる途中、境内の石に腰掛けて一休みしたという。
常光寺(旭北町)には「八百屋お七」のモデルという「志ちの墓」。お七は井原西鶴の『好色五人女』に登場し、恋人に会いたい一心で放火事件を起こし、火あぶりの刑に処された少女だ。お寺の本堂脇に、墓石と立て札が建っていた。付近にはお七川と呼ばれる小川(溝)が流れ、この水をつけるとやけどが早く治るといわれる。
上嶋さんは「大和国中高田の町はお七が燃やす恋心/紅蓮(ぐれん)の恋やいと哀れ未練を流すお七川/今も昔も悲恋(こい)の町」という「高田悲恋歌(こいうた)」を作られた。
最後にJR高田駅から徒歩1分の「高田天神社」(三和町)へ。村島さんは同社の責任役員だ。社伝では第10代崇神天皇の頃に創始。高田一円の氏神さまで4月の御田植え祭、10月の御神輿渡御(とぎょ)などで知られる。

このお店では奈良漬を「うねび漬」の名前で販売されていた(片塩商店街で2/10撮影)
近郊への大型店の出店や地場産業の繊維・靴下の衰退で、環境は厳しいが、近鉄高田市駅前の片塩商店街は一昨年、経済産業省の「はばたく商店街30選」に選出され「お年寄りに優しく、元気になれる商店街」として、県外からの視察が相次ぐ。
「志を同じくする者が5人集まれば、地域を変えられる」という。この動きを広げ、賑わい再興に取り組んでいただきたいものだ。ガンバレ、商都高田!
片塩商店街はいろいろと趣向を凝らしていて、今はウエルカムボード(小型のサインボード)の巧拙を競う「第1回片塩ウエルカムボード大賞」コンテストも実施している(投票は3/3まで)。ウエルカムボードは、トップ写真にも右下に小さく写っている。
上嶋さん、村島さん、貴重なお話をありがとうございました。皆さん、ぜひ大和高田市をお訪ねください!
※奈良日日新聞ご購読のお申し込みは、こちらから