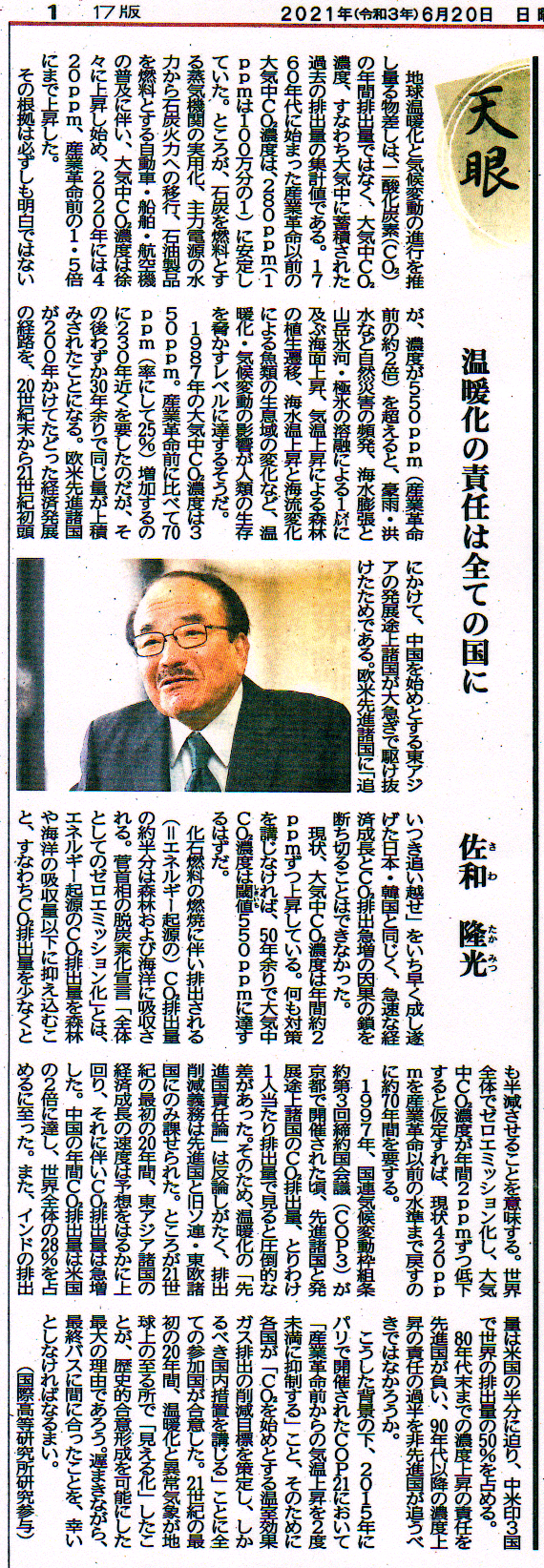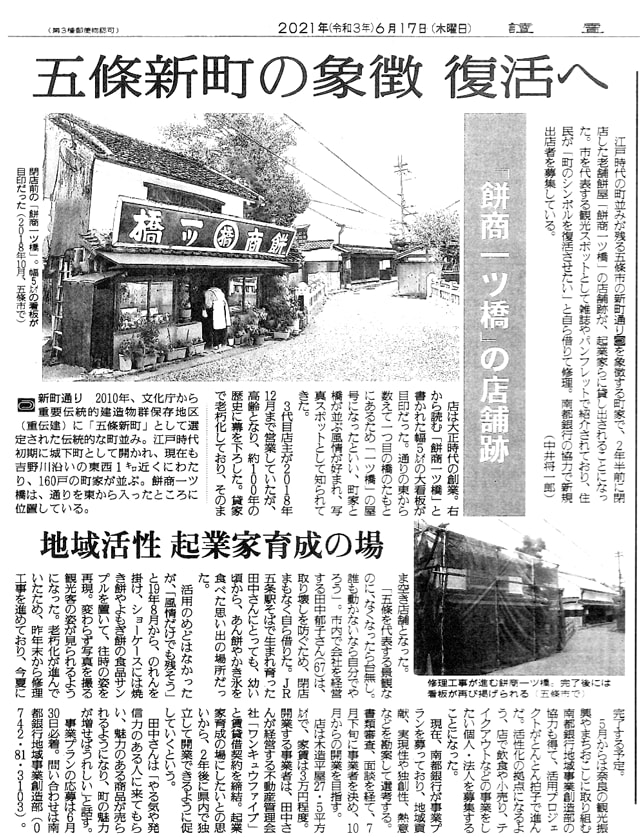大和当帰の根は漢方薬として用いられるが(=医薬品の対象)、葉は自由に使える。葉にはパクチー(コリアンダー)のようなセロリのような独特の香り(刺激臭)があり、食べると体が温まってくる。
県が推進する「奈良県漢方プロジェクト」(漢方のメッカ推進プロジェクト)では、大和当帰の魅力向上のため、YouTubeチャンネルを開設した(こちらのサイトから入る)。出演するのは小倉聡さん(中国菜館「桂花」オーナーシェフ)だ。金曜日(2021.6.25)の読売新聞奈良版〈「大和トウキ」発信強化〉によると、
「漢方の聖地」 県PR
県は、根が漢方薬に用いられる大和トウキの魅力発信を強化する。動画投稿サイト「ユーチューブ」にPRのためのチャンネルを開設したり、県内の製薬会社が開発した大和トウキ入りのドリンクの販路を拡大したりすることで、「漢方の聖地」としてのブランド力の向上を目指す。(土谷武嗣)
料理動画◇ドリンク販路拡大
日本書紀には、現在の宇陀市で推古天皇が611年に「薬狩り」をしたという記述が残る。日本の胃腸薬の元祖ともされる漢方薬「 陀羅尼助だらにすけ 」は全国的にも知られ、江戸時代には家庭で使った分だけ料金を後払いする配置薬の仕組みが生まれ、「大和の置き薬」として名をはせた。今でも県内には製薬会社が約50社ある。
ただ、農家の高齢化によって薬草の生産量が減少していたため、県は2012年に、大和トウキなどの栽培や漢方薬の製造、栽培技術の研究などを進めるプロジェクトチームを設立。県農業研究開発センター(桜井市)では薬草の栽培技術、県薬事研究センター(同)では効能、県産業振興総合センター(奈良市)では商品化などの研究を続けている。今年度は事業費として計2800万円を計上した。
これまではイベントなどを通じて県ゆかりの薬草や研究成果などを紹介していたが、新型コロナウイルスの感染拡大でイベントの開催が困難になったことから、県はユーチューブを活用した魅力の発信を企画。今年5月にチャンネル「奈良県漢方プロジェクト」を開設し、食材として利用できる大和トウキの葉を使った料理の動画を公開した。
動画には、大和トウキの天ぷらなどの料理を提供している「中国菜館 桂花」(生駒市)のオーナーシェフ小倉聡さん(62)が出演。「焼き豚入りトウキ葉チャーハン」と「トウキ葉エビマヨ」の調理を実演し、「色は淡い方が軟らかくておいしい」「香りはすがすがしいものがいい」など購入する際のポイントも紹介している。県は今後も、大和トウキの解説動画などの公開を検討しているという。小倉さんは「手軽に料理に使える薬草であることを多くの人に知ってもらうきっかけになるのでは」と期待している。
さらに、県では研究成果を県内の製薬会社に提供し、大和トウキ入りの栄養ドリンクを開発してもらう事業にも力を入れている。19年から、県内の製薬会社3社が4商品をすでに開発、販売している。
金陽製薬(五條市)は、血流改善や冷え性などに効果がある、大和トウキのエキス入りのドリンク2種類を同社のオンラインショップなどで販売。今後も大和トウキを活用した新商品の開発を目指していくといい、北山英樹社長(61)は「薬の多くは中国由来のものが多いが、国産の薬にこだわることで、ブランド力を向上させ、他社との差別化を図ることができる」と語る。
県は感染収束後に、首都圏や近畿圏で商談会や展示販売会などを開催し、販路の拡大を狙う。県の担当者は「漢方の産業化を進めるとともに、様々な方法で奈良の薬草の魅力を発信し、幅広い世代に県が薬草の聖地であることを広めていきたい」と力を込める。
大和トウキ セリ科の多年草で、奈良原産とされる。乾燥させた根は漢方薬に配合され、冷え性や血行障害などに効果があるとされる。2012年の薬事法改正で、葉が医薬品の対象から除外されたことで、食材としての活用が進む。葉はセロリのような香味があり、料理の香り付けなどで使われている。

県が推進する「奈良県漢方プロジェクト」(漢方のメッカ推進プロジェクト)では、大和当帰の魅力向上のため、YouTubeチャンネルを開設した(こちらのサイトから入る)。出演するのは小倉聡さん(中国菜館「桂花」オーナーシェフ)だ。金曜日(2021.6.25)の読売新聞奈良版〈「大和トウキ」発信強化〉によると、
「漢方の聖地」 県PR
県は、根が漢方薬に用いられる大和トウキの魅力発信を強化する。動画投稿サイト「ユーチューブ」にPRのためのチャンネルを開設したり、県内の製薬会社が開発した大和トウキ入りのドリンクの販路を拡大したりすることで、「漢方の聖地」としてのブランド力の向上を目指す。(土谷武嗣)
料理動画◇ドリンク販路拡大
日本書紀には、現在の宇陀市で推古天皇が611年に「薬狩り」をしたという記述が残る。日本の胃腸薬の元祖ともされる漢方薬「 陀羅尼助だらにすけ 」は全国的にも知られ、江戸時代には家庭で使った分だけ料金を後払いする配置薬の仕組みが生まれ、「大和の置き薬」として名をはせた。今でも県内には製薬会社が約50社ある。
ただ、農家の高齢化によって薬草の生産量が減少していたため、県は2012年に、大和トウキなどの栽培や漢方薬の製造、栽培技術の研究などを進めるプロジェクトチームを設立。県農業研究開発センター(桜井市)では薬草の栽培技術、県薬事研究センター(同)では効能、県産業振興総合センター(奈良市)では商品化などの研究を続けている。今年度は事業費として計2800万円を計上した。
これまではイベントなどを通じて県ゆかりの薬草や研究成果などを紹介していたが、新型コロナウイルスの感染拡大でイベントの開催が困難になったことから、県はユーチューブを活用した魅力の発信を企画。今年5月にチャンネル「奈良県漢方プロジェクト」を開設し、食材として利用できる大和トウキの葉を使った料理の動画を公開した。
動画には、大和トウキの天ぷらなどの料理を提供している「中国菜館 桂花」(生駒市)のオーナーシェフ小倉聡さん(62)が出演。「焼き豚入りトウキ葉チャーハン」と「トウキ葉エビマヨ」の調理を実演し、「色は淡い方が軟らかくておいしい」「香りはすがすがしいものがいい」など購入する際のポイントも紹介している。県は今後も、大和トウキの解説動画などの公開を検討しているという。小倉さんは「手軽に料理に使える薬草であることを多くの人に知ってもらうきっかけになるのでは」と期待している。
さらに、県では研究成果を県内の製薬会社に提供し、大和トウキ入りの栄養ドリンクを開発してもらう事業にも力を入れている。19年から、県内の製薬会社3社が4商品をすでに開発、販売している。
金陽製薬(五條市)は、血流改善や冷え性などに効果がある、大和トウキのエキス入りのドリンク2種類を同社のオンラインショップなどで販売。今後も大和トウキを活用した新商品の開発を目指していくといい、北山英樹社長(61)は「薬の多くは中国由来のものが多いが、国産の薬にこだわることで、ブランド力を向上させ、他社との差別化を図ることができる」と語る。
県は感染収束後に、首都圏や近畿圏で商談会や展示販売会などを開催し、販路の拡大を狙う。県の担当者は「漢方の産業化を進めるとともに、様々な方法で奈良の薬草の魅力を発信し、幅広い世代に県が薬草の聖地であることを広めていきたい」と力を込める。
大和トウキ セリ科の多年草で、奈良原産とされる。乾燥させた根は漢方薬に配合され、冷え性や血行障害などに効果があるとされる。2012年の薬事法改正で、葉が医薬品の対象から除外されたことで、食材としての活用が進む。葉はセロリのような香味があり、料理の香り付けなどで使われている。