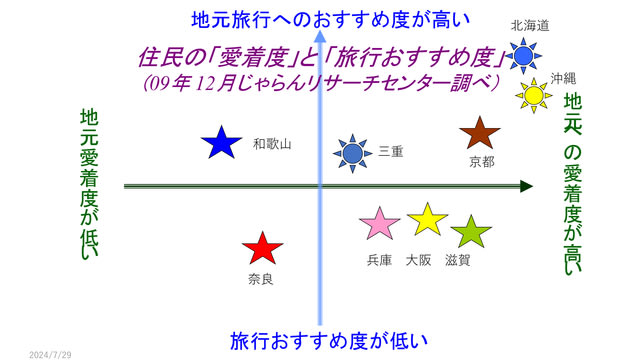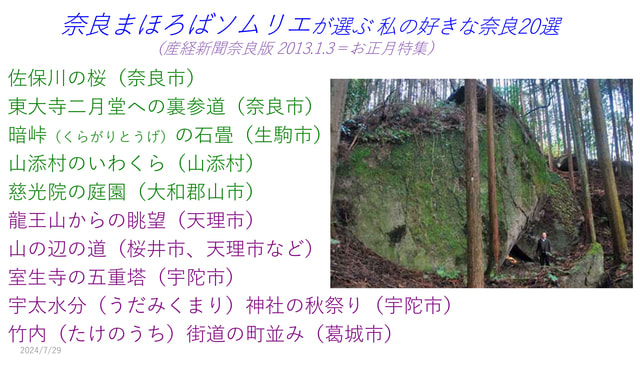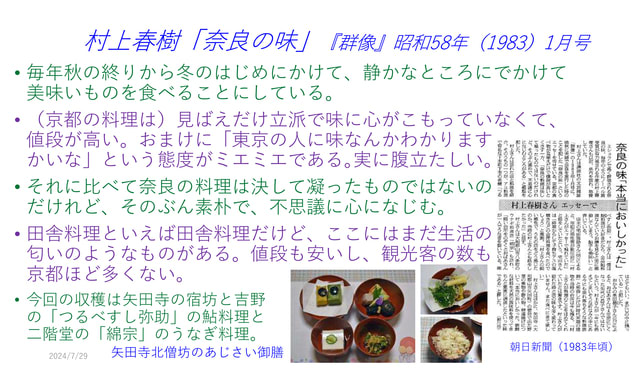ならまちで「奈良町情報館」を運営されている藤丸正明(ただあき)さん(株式会社地域活性局 代表取締役)が、ご自身のFacebookに、ならまちの商店主などにヒアリングされた「街角景気」を紹介されていた(2025.3.27付)。
※トップ写真は、奈良公園・片岡梅林(2025.3.27)。ここも、ほとんどが外国人観光客だった!
〈(景気は)昨年秋以降、特に良くない〉〈インバウンド客の増加は、日本人客の減少になる〉〈マクドナルドにできる行列は、すさまじい〉〈単価がそれまでよりも落ちて、さらには消費軸の違う客層が押し寄せると、地域が日々培ってきたものが根こそぎ壊されていく〉
〈奈良市の外郭団体がならまちの運営から外されるようになって、各施設の「顧客」が崩壊し、リピーターが減っていることが、地域に重くのしかかっている〉
〈宿泊と日帰りという消費軸の違う客層が存在し、そして年々、消費単価は伸び悩む傾向にある〉〈行政が現状を把握していなければ、そこに輪をかけて、地域は崩れていく〉〈いろんなお寺での体験事業は、とても良い〉
私も今月に入って、ならまち周辺を2組ほどのお客さんを案内したが(計2日間)、ならまちの外国人観光客の多さと、東向商店街の特定の店舗への外国人客の集中(マクドナルド、とんかつがんこ、どうとんぼり神座、京都勝牛など。いずれも地元資本ではない)を目にして、うんざりした。
相変わらず、ダイソーの「カチューシャ」を頭につけた若い女性(日本人・外国人とも)も多い(あれはトナカイの角の「クリスマスカチューシャ」だが、奈良では鹿の角として通年販売されているものだ)。
逆に感心したのは、「奈良からくりおもちゃ館」「砂糖傳増尾商店」「ならまち格子の家」の接客(おもてなし)だった。以下、藤丸さんのレポートと、それに対するコメントをかいつまんで紹介する。皆さんのご感想も、ぜひ教えていただきたい。
定期的にならまちの商店を回って景況感を聞いていますが、昨年秋以降、特に良くないという話をよく聞きます。インバウンド客の増加は日本人客の減少になるのですが、最近特にその印象が強いです。
逆に商店街を歩くとマクドナルドにできる行列はすさまじいですね。1300年祭の時と一緒で、行政やその関係者は人が増えたと息巻いても、1人当たりの単価がそれまでよりも落ちて、さらには消費軸の違う客層が押し寄せると地域が日々培ってきたものが根こそぎ壊されていきます。実際に店舗を止(や)める方が出てきています。
個人的に見ていて思うのは、奈良市の外郭団体がならまちの運営から外されるようになって、各施設の“顧客”が崩壊し、リピーターが減っていることが地域に重くのしかかっているように思います。また、宿泊と日帰りという消費軸の違う客層が存在し、そして年々、消費単価は伸び悩む傾向にあるように思います。
あと、昨年、痛感したのは、町がどれだけ頑張ってきてもらうための努力をしたとしても、真っ先に観光客が増加して収益が上がるのは、旅客分野であり、飛行機・鉄道の協力がなければ、観光事業は成り立たないわけで、さらに言えば行政が現状を把握していなければ、そこに輪をかけて、地域は崩れていくということですね。思ったことを徒然と書いてみました。
(上記に関するコメント)
地元住民のFさん(女性)。〈本当にその通りに痛感します。猿沢池周辺には 白タクがおり 生活者にもゆっくり出来ない街になっております〉。
Yさん(男性)。〈奈良は考えてみれば親戚、家族や色々な人と重層的に繋がっていて、また文化も学べるのがすごいです。藤丸さんのような方が近くにいてくださるおかげで大変勉強になります。寺社もすばらしいですがならまちのお店にも色々と繋がって、ふと気づくとリピーターになっています〉。
〈京阪神の学生の友人がいますが、奈良観光と食事会企画も楽しそうです。お茶よりも甘いものや肉食べたい友人が多いですが(笑)ちょっとシミュレーションしてみます〉。
藤丸さんの返信。〈奈良ってすごく深みのある街で、特にならまち界隈って日本人の人文的な歴史が詰まっている場所なので、いつも歩いていても飽きない、知らないことだらけで面白いと思います。また来る時声かけてください〉。
Mさん(女性)。〈神仏習合をテーマに、昨年秋から奈良市世界遺産5社寺で、禅ヨガイベントを開催させていただきました。この数年奈良にご縁を頂き、私なりの縁繋ぎ活動をしています!もっと何か方法はないか、と勝手に模索しています〉。
藤丸さんの返信。 〈奈良は体験が少ないですね。滞在時間の延長から、宿泊というライン(流れ)がもし可能だと推定できるのであれば、そこに当てはめるべきものは体験だと思います。いろんなお寺での体験事業はとても良いですね〉。
奈良市内で宿泊施設を経営されるKさん(男性)。〈これは肌感覚なんですが…。最近の傾向として、「ならまち」が観光コースから外れて、もはや、鹿と大仏と中谷堂が奈良になつてしまった感ですね。で、入っている店はと云えば、仰る様にマクドナルド。後、神座にとんかつがんこ、一番の南限が天平ホテル・スターバックスになる気がします〉。
〈つまり、一番メジャーなものしか行かない訳です。その原因は、「知らない」と云う事に尽きる気がします。是非はともかく、コロナ前のインバウント時は、中国人の団体が、ガイド役を先頭に、「ならまち」を闊歩していたのに、今はそうした団体が、ほとんど見なくなりました〉。
〈ただ、そうした団体が、「ならまち」のお客様になり得るかと云うのは、また別の話ですが、コロナ前とコロナ後で、極端に変わった感がします。この現象は、多分ですけど、ガイドがちゃんと連れて歩いたから、「ならまち」にも中国人が押し寄せた訳で、個人旅行が主体の現在は、自分で行く気にならないと訪れない訳です〉。
〈つまりこれも、役所の広報や、インターネットサイトの出し方に問題が有る気がします。インターネットサイトなどは、こちらで指示しないと、大阪も京都も奈良もいっしょくたになる傾向です。難しいですけど、地道にいろいろなネタ出しをやって、注目を集めて行くのが大切やと思います〉。
〈ただ、今の「ならまち」の状況って、これも昔の「ならまち」と変わって行った感もしますね。何やらよう判らない、ナニを売っているのか判らない店や、得体の知れないコーヒー屋なんかが増殖したのではないでしょうか。ここは、「ならまち」の底力で、元の「ならまち」のポテンシャルを復活させましょう〉。
※トップ写真は、奈良公園・片岡梅林(2025.3.27)。ここも、ほとんどが外国人観光客だった!
〈(景気は)昨年秋以降、特に良くない〉〈インバウンド客の増加は、日本人客の減少になる〉〈マクドナルドにできる行列は、すさまじい〉〈単価がそれまでよりも落ちて、さらには消費軸の違う客層が押し寄せると、地域が日々培ってきたものが根こそぎ壊されていく〉
〈奈良市の外郭団体がならまちの運営から外されるようになって、各施設の「顧客」が崩壊し、リピーターが減っていることが、地域に重くのしかかっている〉
〈宿泊と日帰りという消費軸の違う客層が存在し、そして年々、消費単価は伸び悩む傾向にある〉〈行政が現状を把握していなければ、そこに輪をかけて、地域は崩れていく〉〈いろんなお寺での体験事業は、とても良い〉
私も今月に入って、ならまち周辺を2組ほどのお客さんを案内したが(計2日間)、ならまちの外国人観光客の多さと、東向商店街の特定の店舗への外国人客の集中(マクドナルド、とんかつがんこ、どうとんぼり神座、京都勝牛など。いずれも地元資本ではない)を目にして、うんざりした。
相変わらず、ダイソーの「カチューシャ」を頭につけた若い女性(日本人・外国人とも)も多い(あれはトナカイの角の「クリスマスカチューシャ」だが、奈良では鹿の角として通年販売されているものだ)。
逆に感心したのは、「奈良からくりおもちゃ館」「砂糖傳増尾商店」「ならまち格子の家」の接客(おもてなし)だった。以下、藤丸さんのレポートと、それに対するコメントをかいつまんで紹介する。皆さんのご感想も、ぜひ教えていただきたい。
定期的にならまちの商店を回って景況感を聞いていますが、昨年秋以降、特に良くないという話をよく聞きます。インバウンド客の増加は日本人客の減少になるのですが、最近特にその印象が強いです。
逆に商店街を歩くとマクドナルドにできる行列はすさまじいですね。1300年祭の時と一緒で、行政やその関係者は人が増えたと息巻いても、1人当たりの単価がそれまでよりも落ちて、さらには消費軸の違う客層が押し寄せると地域が日々培ってきたものが根こそぎ壊されていきます。実際に店舗を止(や)める方が出てきています。
個人的に見ていて思うのは、奈良市の外郭団体がならまちの運営から外されるようになって、各施設の“顧客”が崩壊し、リピーターが減っていることが地域に重くのしかかっているように思います。また、宿泊と日帰りという消費軸の違う客層が存在し、そして年々、消費単価は伸び悩む傾向にあるように思います。
あと、昨年、痛感したのは、町がどれだけ頑張ってきてもらうための努力をしたとしても、真っ先に観光客が増加して収益が上がるのは、旅客分野であり、飛行機・鉄道の協力がなければ、観光事業は成り立たないわけで、さらに言えば行政が現状を把握していなければ、そこに輪をかけて、地域は崩れていくということですね。思ったことを徒然と書いてみました。
(上記に関するコメント)
地元住民のFさん(女性)。〈本当にその通りに痛感します。猿沢池周辺には 白タクがおり 生活者にもゆっくり出来ない街になっております〉。
Yさん(男性)。〈奈良は考えてみれば親戚、家族や色々な人と重層的に繋がっていて、また文化も学べるのがすごいです。藤丸さんのような方が近くにいてくださるおかげで大変勉強になります。寺社もすばらしいですがならまちのお店にも色々と繋がって、ふと気づくとリピーターになっています〉。
〈京阪神の学生の友人がいますが、奈良観光と食事会企画も楽しそうです。お茶よりも甘いものや肉食べたい友人が多いですが(笑)ちょっとシミュレーションしてみます〉。
藤丸さんの返信。〈奈良ってすごく深みのある街で、特にならまち界隈って日本人の人文的な歴史が詰まっている場所なので、いつも歩いていても飽きない、知らないことだらけで面白いと思います。また来る時声かけてください〉。
Mさん(女性)。〈神仏習合をテーマに、昨年秋から奈良市世界遺産5社寺で、禅ヨガイベントを開催させていただきました。この数年奈良にご縁を頂き、私なりの縁繋ぎ活動をしています!もっと何か方法はないか、と勝手に模索しています〉。
藤丸さんの返信。 〈奈良は体験が少ないですね。滞在時間の延長から、宿泊というライン(流れ)がもし可能だと推定できるのであれば、そこに当てはめるべきものは体験だと思います。いろんなお寺での体験事業はとても良いですね〉。
奈良市内で宿泊施設を経営されるKさん(男性)。〈これは肌感覚なんですが…。最近の傾向として、「ならまち」が観光コースから外れて、もはや、鹿と大仏と中谷堂が奈良になつてしまった感ですね。で、入っている店はと云えば、仰る様にマクドナルド。後、神座にとんかつがんこ、一番の南限が天平ホテル・スターバックスになる気がします〉。
〈つまり、一番メジャーなものしか行かない訳です。その原因は、「知らない」と云う事に尽きる気がします。是非はともかく、コロナ前のインバウント時は、中国人の団体が、ガイド役を先頭に、「ならまち」を闊歩していたのに、今はそうした団体が、ほとんど見なくなりました〉。
〈ただ、そうした団体が、「ならまち」のお客様になり得るかと云うのは、また別の話ですが、コロナ前とコロナ後で、極端に変わった感がします。この現象は、多分ですけど、ガイドがちゃんと連れて歩いたから、「ならまち」にも中国人が押し寄せた訳で、個人旅行が主体の現在は、自分で行く気にならないと訪れない訳です〉。
〈つまりこれも、役所の広報や、インターネットサイトの出し方に問題が有る気がします。インターネットサイトなどは、こちらで指示しないと、大阪も京都も奈良もいっしょくたになる傾向です。難しいですけど、地道にいろいろなネタ出しをやって、注目を集めて行くのが大切やと思います〉。
〈ただ、今の「ならまち」の状況って、これも昔の「ならまち」と変わって行った感もしますね。何やらよう判らない、ナニを売っているのか判らない店や、得体の知れないコーヒー屋なんかが増殖したのではないでしょうか。ここは、「ならまち」の底力で、元の「ならまち」のポテンシャルを復活させましょう〉。