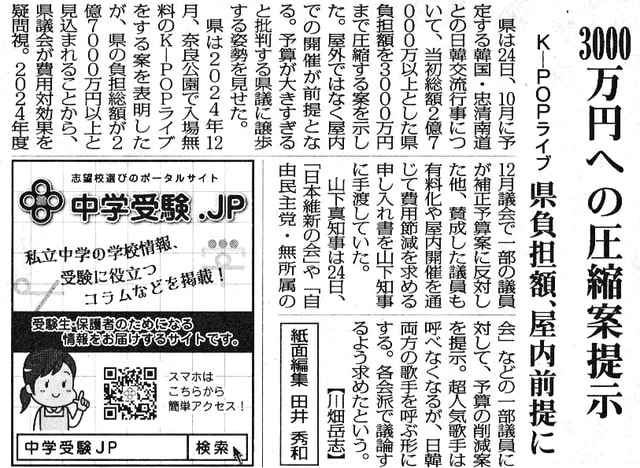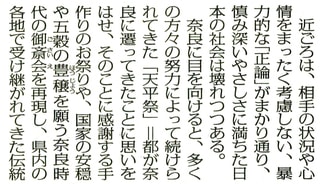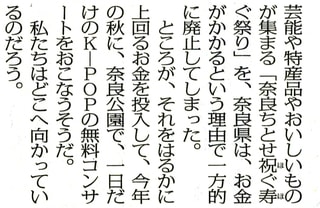養老孟司、茂木健一郎、東浩紀の3氏の鼎談を収めた『日本の歪み』(講談社現代新書、2023年9月刊行)に、興味深い話が紹介されていた(〈安倍元首相の国葬について思うこと〉の節)。2024年11月に刊行された養老孟司著『人生の壁』(新潮新書)でも、養老氏がこのくだりを引用されていたので、再びこの話を思い出した。
これを当ブログで紹介しようとネットで検索をかけていると、講談社のHPに、『日本の歪み』から抜粋した〈「安倍元首相の国葬」と「日本の宗教」について、養老孟司・茂木健一郎・東浩紀が語り合う!〉という記事が出ていた。
ポイントは東氏の〈GHQの草案で作られた憲法では、国家が宗教的活動をすること、公金を供することを禁じている。だから体育館で葬儀をやるしかない。でもそれには根本的に無理がある。だから人々は近くの神社に行く。宗教色をなくした追悼なんてできないんです〉というところにある。
2017年のこと。私は倉本聰の作・脚本による『やすらぎの郷(さと)』(テレビ朝日系)という帯ドラマを見ていた。昭和の時代、テレビで活躍した俳優、歌手、脚本家などが入居する老人ホームの話である。ある時、入居者の1人が亡くなり、ホーム内で葬儀が行われた。
「葬儀は無宗教で行われた」というナレーションが流れ、弔問客(入居者)は、遺影の前で手を合わせ、花を手向けていた。そこには読経もお香もろうそくもなく、僧侶も神職もいない。私は正直に言って「こんなのは葬式ではない。倉本聰は、こんな葬式を望んでいるのだろうか」と大いに疑問に感じた。「私が死んだら、ちゃんとお坊さんを呼んでほしいな」とも。
では、以下に『日本の歪み』の抜粋を貼っておく。皆さんは、どう思われるだろうか。
献花に訪れた人々の「無味乾燥」な長蛇の列
東浩紀 安倍晋三元首相の国葬の日、僕は九段下に一般向けの献花に訪れる人を見に行きました。献花台は靖国通りの武道館側の歩道に設けられていて、いちおう葬儀会場である日本武道館のほうに向いてはいたものの、かなり遠い。安倍さんの写真はあるものの、そもそも一日限りの金属の仮組みでしかない。
そこに花を手向けることでは心は満たされないのでしょう。人々がそのあとどうしたかと言えば、かなりの人が道路を渡って向かい側にある靖国神社に行っていたのが印象的でした。安倍さんの死を悼みに来た人が靖国神社に参拝する。それが意味するのは、実質的に安倍さんは靖国神社に祀られてしまったということです。
宗教色をなくした追悼なんてできない
ちょうどその前にイギリスのエリザベス女王が亡くなり、ウェストミンスター寺院で葬儀が行われました。国家元首の葬儀が宗教性を帯びるのは当然のことです。しかし日本ではそれができない。なぜできないかといえば、要は敗戦したからです。
戦後にGHQの草案で作られた憲法では、国家が宗教的活動をすること、公金を供することを禁じている。だから体育館で葬儀をやるしかない。でもそれには根本的に無理がある。だから人々は近くの神社に行く。宗教色をなくした追悼なんてできないんです。やっても機能しないんですよ。
炎天下に喪服を着てわざわざ九段下まで来て献花に並ぶ人たちは、それなりの強い気持ちをもって追悼に来ている。そういう一般弔問客をどう遇するかも、本来は国が考えなければいけないことです。しかし実際にはありふれた巨大イベントへ誘導するかのように、無味乾燥な長蛇の列に並ばせただけだった。
日本は死を悼む気持ちの受け皿すら作れないのだなと、その光景に日本の衰退を感じました。場当たり的な対応を繰り返し、なんとなくなんとかなっているように見えても、ベースのところで人心の荒廃が進んでいるように思います。
心の着地点が失われてしまった
茂木健一郎 僕は国葬の日、武道館で参列していましたが、儀式の形式を宗教的に中立的なものにすることで、何かが形骸化しているように感じました。そしてそれは、現代日本そのものの姿のように思いました。
私は科学者であり、現在得られている知見に照らして、知的な意味で全面的に肯定できる既存の宗教はないと感じています。一方で、生活人としての、あるいは関係性の中での自然な心の動きはその限りではない。宗教的なものを排除することで、心の着地点が失われてしまっている。
前に手塚治虫のトキワ荘マンガミュージアムに行ったときも、なんか落ち着かない感じがありました。「手塚治虫神社」があればよかったのかな(笑)。本来は心の落ち着かせ方の文化は土地ごとにそれぞれにあったはずですが、日本の場合にはそれが混乱しているのかもしれないですね。
東浩紀 夏に盆踊りが小学校の校庭で行われたりしますが、あれも本当は神社とか森でやるべきものですよね。どういう理屈で校庭になったのかわかりませんが、神社でやると宗教行事で、校庭でやると自治体の無宗教行事になるんでしょうか。
これを当ブログで紹介しようとネットで検索をかけていると、講談社のHPに、『日本の歪み』から抜粋した〈「安倍元首相の国葬」と「日本の宗教」について、養老孟司・茂木健一郎・東浩紀が語り合う!〉という記事が出ていた。
ポイントは東氏の〈GHQの草案で作られた憲法では、国家が宗教的活動をすること、公金を供することを禁じている。だから体育館で葬儀をやるしかない。でもそれには根本的に無理がある。だから人々は近くの神社に行く。宗教色をなくした追悼なんてできないんです〉というところにある。
2017年のこと。私は倉本聰の作・脚本による『やすらぎの郷(さと)』(テレビ朝日系)という帯ドラマを見ていた。昭和の時代、テレビで活躍した俳優、歌手、脚本家などが入居する老人ホームの話である。ある時、入居者の1人が亡くなり、ホーム内で葬儀が行われた。
「葬儀は無宗教で行われた」というナレーションが流れ、弔問客(入居者)は、遺影の前で手を合わせ、花を手向けていた。そこには読経もお香もろうそくもなく、僧侶も神職もいない。私は正直に言って「こんなのは葬式ではない。倉本聰は、こんな葬式を望んでいるのだろうか」と大いに疑問に感じた。「私が死んだら、ちゃんとお坊さんを呼んでほしいな」とも。
では、以下に『日本の歪み』の抜粋を貼っておく。皆さんは、どう思われるだろうか。
献花に訪れた人々の「無味乾燥」な長蛇の列
東浩紀 安倍晋三元首相の国葬の日、僕は九段下に一般向けの献花に訪れる人を見に行きました。献花台は靖国通りの武道館側の歩道に設けられていて、いちおう葬儀会場である日本武道館のほうに向いてはいたものの、かなり遠い。安倍さんの写真はあるものの、そもそも一日限りの金属の仮組みでしかない。
そこに花を手向けることでは心は満たされないのでしょう。人々がそのあとどうしたかと言えば、かなりの人が道路を渡って向かい側にある靖国神社に行っていたのが印象的でした。安倍さんの死を悼みに来た人が靖国神社に参拝する。それが意味するのは、実質的に安倍さんは靖国神社に祀られてしまったということです。
宗教色をなくした追悼なんてできない
ちょうどその前にイギリスのエリザベス女王が亡くなり、ウェストミンスター寺院で葬儀が行われました。国家元首の葬儀が宗教性を帯びるのは当然のことです。しかし日本ではそれができない。なぜできないかといえば、要は敗戦したからです。
戦後にGHQの草案で作られた憲法では、国家が宗教的活動をすること、公金を供することを禁じている。だから体育館で葬儀をやるしかない。でもそれには根本的に無理がある。だから人々は近くの神社に行く。宗教色をなくした追悼なんてできないんです。やっても機能しないんですよ。
炎天下に喪服を着てわざわざ九段下まで来て献花に並ぶ人たちは、それなりの強い気持ちをもって追悼に来ている。そういう一般弔問客をどう遇するかも、本来は国が考えなければいけないことです。しかし実際にはありふれた巨大イベントへ誘導するかのように、無味乾燥な長蛇の列に並ばせただけだった。
日本は死を悼む気持ちの受け皿すら作れないのだなと、その光景に日本の衰退を感じました。場当たり的な対応を繰り返し、なんとなくなんとかなっているように見えても、ベースのところで人心の荒廃が進んでいるように思います。
心の着地点が失われてしまった
茂木健一郎 僕は国葬の日、武道館で参列していましたが、儀式の形式を宗教的に中立的なものにすることで、何かが形骸化しているように感じました。そしてそれは、現代日本そのものの姿のように思いました。
私は科学者であり、現在得られている知見に照らして、知的な意味で全面的に肯定できる既存の宗教はないと感じています。一方で、生活人としての、あるいは関係性の中での自然な心の動きはその限りではない。宗教的なものを排除することで、心の着地点が失われてしまっている。
前に手塚治虫のトキワ荘マンガミュージアムに行ったときも、なんか落ち着かない感じがありました。「手塚治虫神社」があればよかったのかな(笑)。本来は心の落ち着かせ方の文化は土地ごとにそれぞれにあったはずですが、日本の場合にはそれが混乱しているのかもしれないですね。
東浩紀 夏に盆踊りが小学校の校庭で行われたりしますが、あれも本当は神社とか森でやるべきものですよね。どういう理屈で校庭になったのかわかりませんが、神社でやると宗教行事で、校庭でやると自治体の無宗教行事になるんでしょうか。