
昨年秋に束松峠に秋月悌次郎の「北越潜行の詩」の詩碑が建立された。その新聞報道以来、雪解けが待ち遠しかった。
初めて束松峠へ登った。49線を柳津のトンネルを過ぎて藤大橋を渡る。間もなく右、高郷方面へ向かって間もなく突き当たりを左へ。
天屋へはいると間もなく「福島県指定天然記念物 天屋の束松」の案内板があった。
「会津坂下町大字束松字天屋に、束松と呼ばれる特殊な樹形のアカマツが生育することが昔から知られ、束松という地名もこれに由来している。・・・・・
このような樹形はおそらく遺伝的なもので、成長するにしたがって独特の樹形を示すようになったものと思われる。」と。
ふもとに車を置き、約1時ほど旧越後街道の峠道を上った。
残っている「ひこ束松」をみたが、なるほど見事な松だった。
束松峠の頂上のは江戸時代に、また峠の途中に「養生のかいなく枯れたので平成10年6月空しく伐採」と看板があった。




所々に伐採した丸太がビニールにくるまれていた。
「松食い虫(マツノザイセンチュウ)とカシノナガキクイムシのくん蒸駆除作業中」と張り紙があった。大変な問題だ。


峠道は戊辰のころとそうは変わらないだろう。秋月悌次郎やあの山川健次郎も歩んだいにしえのこの峠道を踏みしめながら進んだ。
所々にコブシの花が風に揺れていた。峠の道にはショウジョウバカマが咲いていた。イワカガミはつぼみが膨らんでいた。
木々の芽吹きを撮りながら登った。
途中、オオルリに会った。梢に止まり盛んにさえずっていた。逆光で美しいルリ色は見にくかったが、真っ黒いくちばしが美しいさえずりを響かせてくれた。
峠近くには未だ残雪が道をふさいでいた。











 オオルリ
オオルリ
 アカネスミレ?
アカネスミレ?  オオイワカガミ
オオイワカガミ
峠の頂上に、歌碑が建っていた。傘下の片門、丘の向こうに坂下、若松の街が見える。


遙かに霞む磐梯山が聳え、木々の間から西会津の山並みも見えた。悌次郎の思いを偲んだ。
悌次郎は戊辰戦争の敗戦後、会津藩の善処と藩の若者の教育を懇願するため、旧友であった長州藩士奥平謙輔がいた越後にひそかに会いに行った。
その帰り道に雪の束松峠の頂上から故郷を眺め、藩の行く末を案じて「北越潜行の詩」を詠んだとされる。
 案内板
案内板  秋月も眺めた
秋月も眺めた
「行くに輿なく帰るに家なし」 ・・・・ 「愁い胸臆に満ちて涙巾を沾す」
案内板の漢詩を声を出して読んだ。
峠には登りはじめには山王神社の鳥居や峠の六地蔵、軽石へ抜ける束松洞門など昔の遺跡があり、それぞれ地元高寺地区の保存会を中心に道も整備され、
案内板で詳しく説明されていて感心した。
 六地蔵
六地蔵  洞門入口
洞門入口
帰りは片門から坂下へ抜けた。あちこちから飯豊の山並み、麗しの磐梯を眺めながら下道を帰宅した。
ようやく思いが叶った束松峠行きだった。 (2014.4.24)



(参)マイブログ 秋月悌次郎 http://blog.goo.ne.jp/tosimatu_1946/s/%BD%A9%B7%EE%C4%F0%BC%A1%CF%BA











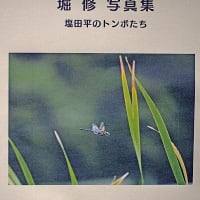








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます