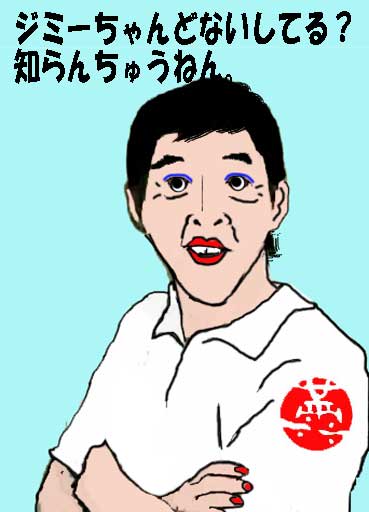都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
皆さん一度は聞いたことがあると思います。これは、詩人・小説家である佐藤春夫氏の「秋刀魚の歌」という詩の一説なのです。
さとう‐はるお〔‐はるを〕【佐藤春夫】
[1892~1964]詩人・小説家。和歌山の生まれ。生田長江・与謝野寛らに師事。初め「スバル」「三田文学」などに詩歌を発表、のち小説に転じた。文化勲章受章。詩集「殉情詩集」、小説「田園の憂鬱」「都会の憂鬱」「晶子曼陀羅」など。
大辞泉
秋刀魚の歌
あはれ
秋風よ
情(こころ)あらば伝えてよ
----男ありて
今日の夕餉(ゆうげ)に ひとり
さ○まを食らいて
思いにふける と。
さ○ま、さ○ま
そが上に青き蜜柑の酸(す)をしたたらせて
さ○まを食うはその男がふる里のならひなり。
そのならひをあやしみなつかしみて女は
いくたびか青き蜜柑をもぎて夕餉にむかいけむ。
あはれ、人に捨てられんとする人妻と
妻に背かれたる男と食卓にむかへば、
愛うすき父を持ちし女の児は
小さき箸をあやつりなやみつつ
父ならぬ男にさ○まの腸(はらわた)をくれむと言ふにあらずや。
さ○ま、さ○ま
さ○ま苦いか塩っぱいか。
そが上に熱き涙をしたたらせて
さ○まを食うはいずこの里のならひぞや。
あはれ
げにそは問はまほしくをかし。
しょっぱ・い【塩っぱい】
[形]1 塩味が濃い。塩辛い。「―・い漬物」2 勘定高い。けちである。「―・いおやじ」3 困惑や嫌悪で顔をしかめるさま。「―・い顔をする」[派生] しょっぱさ[名]
大辞泉
よくテレビでは「からい」という表現を使うので、「しょっぱい」は北海道弁だと思っていましたが、辞典に載っているということは、標準語だったのですね。皆さんの地方では使いますか?
秋刀魚の餌は主に脂質含量の多い動物性プランクトン(オキアミ類等)・稚魚を捕食し、消化器官は飲み込んだ餌を鰓(えら)で濾過して食べるそうです。胃袋がなく腸は真っ直ぐで短いので、内容物(餌)がいつまでも腸の中に止まっていないという特徴があるそうです。
そのため、七輪に焚かれた炭の上で、煙をもうもうと上げながら焼かれた秋刀魚の腸(はらわた)はなんとも美味なものといわれます。そかし、たいていの秋刀魚は鮮度が落ちているので、ただの苦いものになってしまうそうです。
やはり、水揚げされた直後の腸が美味しいそうです。ただし、秋刀魚の腸には激しい腹痛や吐き気を起こさせる寄生虫の「アニサキス」がいることがあるので、加熱は十分にしたほうがいいようです。
秋刀魚の腸(はらわた)は食べますか?うちでは誰も食べません・・・。
したっけ。