都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
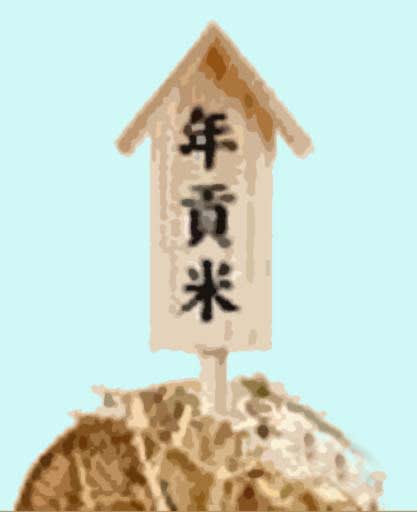 漢字で書くと「上前を撥ねる」となります。この「上前」は、もともとは「上米」と書き江戸時代、神社の領地を通過する際に寄進した年貢米の一部のことです。上米とは、容器に入った米の上の部分を取ることを「上米取り」と言ったことによります。
漢字で書くと「上前を撥ねる」となります。この「上前」は、もともとは「上米」と書き江戸時代、神社の領地を通過する際に寄進した年貢米の一部のことです。上米とは、容器に入った米の上の部分を取ることを「上米取り」と言ったことによります。
つまり通行税を指して「上米(うわまい)」といったのです。
大阪地方では「お前」を「おまい」と言うそうですが、「上米」の「まい」が「前」の「まい」と混同し、いつしか、「上前」となり仲介者がとる手数料の意となりました。そこに、「取る」という意の「はねる」を付し、上位者が取り次ぐべき代金の中から、一部を不正してかすめることを「上前をはねる」というようになったようです。「かすり(掠り)」ともいいます。
は・ねる【×撥ねる】
[動ナ下一][文]は・ぬ[ナ下二]《「跳ねる」と同語源》
1 とばし散らす。液体などをはじきとばす。「泥を―・ねる」「ワックスが水を―・ねる」
2 物や人をはじきとばす。「歩行者を車で―・ねる」
3 一定の基準に満たないものを選んで取り除く。検査などで不合格にする。「腐ったものを―・ねる」「面接試験で―・ねられる」
4 人の取り分の一部をかすめ取る。「もうけの上前を―・ねる」
5 拒絶する。断る。はねつける。「要求を―・ねる」
6 物の端を勢いよく上に向ける。文字の線などの先端を払い上げるようにする。「ぴんと―・ねた口ひげ」「筆順の最後に縦の棒を下ろして―・ねる」
大辞泉
 「上前をはねる」と似た言葉に「ぴんはね」というのがあります。ピンハネ(ぴんはね、ピン撥ね)は、他人の利益の上前を搾取することで、ある特殊な社会の言葉です。
「上前をはねる」と似た言葉に「ぴんはね」というのがあります。ピンハネ(ぴんはね、ピン撥ね)は、他人の利益の上前を搾取することで、ある特殊な社会の言葉です。
「ピン」はポルトガル語の「Pinta」を語源とする説。ちなみに「Pinta」は「10%(一割)の上前」の意味です。ピンをはねる、すなわち搾取するために「ピンハネ」と呼ばれる。賭博用語でも「1」を「ピン」と呼ぶそうです。
したっけ。



















