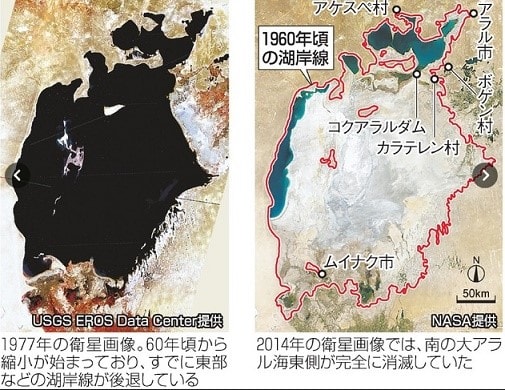(首都リヤドで、ジャマイカのラッパー、ショーン・ポールの公演を楽しむ若者たち【11月18日 WSJ】
2年前には想像もできなかった光景です)
【ムハンマド皇太子の「剛腕」で進む改革 同時に活動家の逮捕も】
昨日はイランのガソリン値上げの話を取り上げたので、今日は、そのイランと中東覇権を争うサウジアラビアの話。
サウジアラビアの実力者・ムハンマド皇太子が、女性の自動車運転や観光ビザ発給を認めるなど自由化を方向での経済・社会改革を進めていることは周知のところです。
下記のような変化もその一環です。
****サウジアラビア、未婚の外国人カップル同室宿泊可能に****
サウジアラビア政府は6日、未婚の外国人カップルがホテルの同じ部屋に泊まることを許可すると発表した。超保守的なイスラム教国のサウジアラビアは、先月末に初めて外国人への観光ビザの発給を開始したばかり。
これまでサウジアラビアでは、ホテルに宿泊するカップルは婚姻関係にあることを証明しなければならなかった。だが観光当局はツイッター上の発表で、この手続きは「もはや観光客には不要」だとしている。
同国は9月27日に一般旅行者の受け入れを発表。それまでは巡礼目的のイスラム教徒と外国人労働者、最近になってスポーツ大会の観戦者や文化イベントの来場者にのみビザが発給されていた。観光ビザの発給には、石油依存型の経済を多様化する狙いがある。
一方、当局は9月28日、観光客が露出度の高い服装や公共の場での愛情表現などの「良俗」に反した行為をした場合は罰金刑の対象になると警告している。 【10月7日 AFP】
******************
外国人への観光ビザの発給・・・・結構な話ですが、そもそもこれまで観光目的での入国を認めていなかったことが、サウジアラビアの(イランにも勝る)特殊性を物語っています。
「砂漠しかないようなサウジにどれだけ観光客が行くのだろうか?」とも思っていたのですが、“観光査証(ビザ)の発給を開始してから10日間で、2万4000人の観光客を受け入れていたことが分かった”【10月9日 AFP】と、順調な滑り出しのようです。
****サウジ、女性の軍入隊を解禁へ****
超保守的なイスラム教国サウジアラビアは9日、女性の軍入隊を認める方針を明らかにした。
サウジは大掛かりな経済・社会改革に着手し、女性の権利向上を狙った措置を次々と打ち出しているが、人権団体からは女性の権利活動家を弾圧していると非難されている。
外務省は、「権利向上への新たな一歩」とツイッターに投稿。女性が上等兵や伍長、軍曹にもなれるようになると明らかにした。
サウジは昨年、女性の治安部隊への入隊を認めていた。
サウジの事実上の統治者ムハンマド・ビン・サルマン皇太子は、女性の権利拡大を目的とする改革を少ないながらも承認し、運転や、男性の「後見人」の許可なしでの国外旅行を解禁してきた。
しかし同時に、ルージャイ・ハスルール氏ら著名な女性権利活動家の逮捕も監督してきた。 【10月10日 AFP】***************
記事にもあるように、ムハンマド皇太子の「改革」は、あくまでも王室を中心とする現体制の枠組みのなかにおける“上からの改革”であり、たとえ同じ女性の権利拡大であっても、既存政治にたてつくような人権活動家の活動を認めるようなものではありません。
また、経済で進める改革「ビジョン2030」(方向性としては、限りある石油に依存することのない、ドバイのような金融立国を目指すものか)ともセットになったもので、王族や既得権階層にも抵抗が大きい改革を進めるうえで、自由化の方向での社会改革に好意的な若者層など国民の支持を集める狙いもあってのものでしょう。(もちろん、皇太子の自由化に関する見識を一定に反映したものではあるでしょうが)
【保守派の反発・抵抗も 改革の今後は皇太子の政治的立場次第】
もちろん、女性の権利拡大といったことでは、保守派には強い抵抗感もあるようです。
****フェミニズムを「過激思想」と見なす動画が物議、サウジが事態収拾図る****
サウジアラビアの国家保安庁は先週末にフェミニズムと同性愛、無神論を過激思想と見なすアニメーション動画をツイッターに投稿したが、物議を醸したことを受けて動画を削除し、事態の収拾を図っている。
折しもサウジでは、同国の実質的な指導者であるムハンマド・ビン・サルマン皇太子が海外観光客に初めて門戸を開き、同国の超保守的なイメージを刷新しようとしている。
人権活動家らは動画を非難。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは「極めて危険」で「同国における表現の自由、生命、自由、安全に対する権利に深刻な影響を及ぼす」ものと批判した。
国家保安庁は12日夜、国営サウジ通信を通じて声明を出し、問題の動画には「多くの間違い」が含まれているとした上で、動画に関与した人物らに対して正式な捜査を実施すると発表。また、フェミニストらが収監され、むち打ち刑を科されるとした現地紙アルワタンの報道を否定した。
サウジの人権委員会は別の声明で、「フェミニズムは違法ではない」「女性の権利を最重要視」していると強調した。
いずれの声明も、同性愛と無神論には言及していない。イスラム教国であるサウジでは、同性愛と無神論は違法で、死刑に相当する罪とされている。 【11月14日 AFP】
********************
王族や既得権階層における皇太子の改革への抵抗ということで言えば、上記のような自由化の方向自体への反発に加え、カショギ氏殺害や汚職容疑がかけられた王族を含む富豪たちをホテルに大量拘束した件に見られるように、独善的で残忍、性急、強引な皇太子の性格・進め方への反発も大きいように思われます。
そうした状況で、解禁されたミュージカル公演の舞台で、出演者が刺されるという事件が。
****ミュージカル公演で出演者3人刺される、エンタメ解禁のサウジ****
サウジアラビアの首都リヤドで11日に行われたミュージカル公演で、出演者3人がステージ上に乱入したイエメン人の男に刺されて負傷した。男はその場で身柄を確保された。警察が発表した。
同国でのエンターテインメント解禁後、このような事件が起きたのは初めて。
事件があったのはリヤドのキングアブドラパークで、国営サウジ通信が伝えた警察発表によると、外国のミュージカル劇団のメンバーとみられる男性2人と女性1人が被害に遭った。
ステージに上がった男が出演者らを襲撃する映像を放映したサウジ国営テレビ「アルイフバリヤ」は、襲われた3人の容体は安定していると伝えた。
警察は、ナイフを持っていたサウジアラビア在住のイエメン人の男を拘束し、事件で使われたナイフを押収したと発表した。被害者の国籍や犯行の動機などは明らかにしていない。
中東の経済大国サウジアラビアでは現在、実質的な指導者であるムハンマド・ビン・サルマン皇太子がポスト石油時代を見据え、経済改革「ビジョン2030」を推進している。
これに伴い、超保守的な国家イメージを変革するために、これまで禁じられてきたコンサート、映画などのエンターテインメントや女性の運転などが解禁されている。一方でこうした近代化政策が、近年権力が縮小されている宗教警察など超保守派の反感を買っている。 【11月12日】AFPBB News
*******************
ムハンマド皇太子の進める近代化政策に対する超保守派の反発・・・・ということでしょうか。
そこらの事情をもう少し詳しく見ると、下記のようにも。
****サウジ社会変革、娯楽切り札に政治弾圧の闇も****
サウジアラビアの首都リヤド。ステージ前はぶつかり合いながら踊る群衆で埋め尽くされていた。ジャマイカのラッパー、ショーン・ポールが歌うのに合わせ、若い男女がiPhone(アイフォーン)をかざして体を揺らしながら口ずさんだ。「君の体に恋してる・・・シーツからその香りがする」
白いTシャツ姿で緑の国旗をスカーフのように首に巻いたサウジ人の若者が、隣で踊っていた観光客の女性とハイファイブをした。「ようこそ、新たなサウジアラビアへ!」。欧州から来たこの女性は、全身を覆う伝統服のアバヤを着ていなかった。
王位を継承するサウド家は政治的な締め付けを強めているが、社会の自由化は加速させている。イスラム教発祥の地であり禁欲的なサウジ王国で、日常生活の多くの面に開放感がもたらされている。
わずか2年前まで、ポップミュージックのコンサートはなかった。ましてや、女性が髪を隠すことなく、群衆の中で男性と踊れるイベントなどあり得なかった。
サウジ人女性は運転を禁じられ、レストランやホテルのフロントデスク、空港入管局で働くことも許されなかった。オンラインの査証(ビザ)発給が先月開始されるまで、欧米の観光客もいなかった。
サウジ諮問評議会のホダ・アブドゥルラフマン・アルヘライシ議員はこうした変化について、「これほど広く早く進むとは思ってもみなかった」と語る。
言うまでもなく、新生サウジは闇に包まれた一面も持つ。反体制派ジャーナリストのジャマル・カショギ氏は昨年、トルコの首都イスタンブールのサウジ領事館で殺害された。
米中央情報局(CIA)はムハンマド・ビン・サルマン皇太子の指示だったとの判断を示している。殺害事件を受け、反体制派を一掃しようとする皇太子の野望に世界の目が向けられ、皇太子の改革者としてのイメージは傷ついた。
ムハンマド皇太子は昨年、サウジ人女性の運転を許可する歴史的な決断を下した。その一方で政府は、まさにそうした女性の権利を訴えかけてきた活動家たちを投獄している。
米司法省は先ごろ、ムハンマド皇太子の批判者にスパイ行為を働くためツイッターのデータを違法に活用したとして、3人を起訴した。
かつて有力だったイスラム聖職者を含め、こうした批判者の多くは投獄され、一部は死刑囚となっている。国内の社会改革に対し、保守派の抵抗がほとんど見当たらない理由の一端はここにある。
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)のマダウィ・アルラシード客員教授は、「批判の声を上げる者は全て刑務所行きになった。刑務所に入っていない者たちも、恐怖にかられて沈黙している」と指摘。
「公の場で議論や批判が聞かれないからといって、批判がないわけではない」と述べた。リヤドのエンターテインメント会場では今月、初めて襲撃事件が発生。イエメン人の男がナイフを持ってステージに駆け上がり、上演中の3人に軽傷を負わせた。
サウジが進む未来は、長らく同国を先達とみなしてきた中東諸国やイスラム世界にとって極めて重要だ。サウジが成功を収めれば、イスラム過激派の訴求力が弱まるかもしれない。政治はともかく、社会にさらなる寛容さが広がる可能性がある。
失敗すれば、1970年代のイランで改革に取り組んだ王制の崩壊後に起きたような、激しい反動が起こるかもしれない。
サウジの命運は、ムハンマド皇太子の野心的な計画に大きく左右される。皇太子は石油依存型経済の改革や女性の労働市場参入、娯楽・観光産業の創出による成長促進を目指している。
「ムハンマド皇太子が若い世代の支持を得るため、娯楽を切り札にしたのは賢明だった。だが政治的なイスラム勢力はサウジで死んだわけではない、冬眠状態だ」とパリ政治学院のステファーヌ・ラクロワ氏は指摘する。「社会経済情勢が一段と厳しくなれば、論争が再燃する可能性は十分ある」
サウジの人々はつい最近まで、国内の倦怠(けんたい)感を逃れたければ外国を訪れるほかなかった。サウジ政府が新設した総合娯楽局のファイサル・バファラト局長は、「サウジ人歌手のコンサートに行きたければ、バーレーンやドバイ、エジプトなどに出掛けなければならなかった。奇妙な状況だった。今では潮流が逆転している。人々がここへやって来るようになった」と語った。
当局にとって目玉のプロジェクトは、2カ月にわたり開催中の祭典「リヤド・シーズン」だ。音楽祭から演劇祭、ファッションショー、期間限定レストラン、スポーツ大会、遊園地、さらにはサウジ初の屋外映画鑑賞会などが行われる。
バファラト局長によると、政府は祭典に500万人が集まると予想していた。だが10月11日の幕開けから3週間とたたないうちに、それを超える訪問者数を達成した。
同局長は「イベントはほとんど売り切れた」とし、「娯楽事業の投資収益率はお墨付きだということを、民間部門に知らしめる形になった」と言う。
国内リベラル派の多くによれば、遠い昔に変革の機は熟していた。現状が示すのは、サウジの人々が一般的な固定観念ほど超保守的ではないということだ。
「社会は40年前に用意が調っていた。地域社会は準備ができている、先へ進もう、とわれわれは何年も訴えていた。だが政府が聞き入れなかった」と語るのは、政府のテレビニュース番組を運営するためドバイからリヤドへ戻ったファリス・ビン・ヒザム氏だ。「今はどうか。もともと変革を拒んでいた人たちが、変化を楽しんでいる」【11月18日 WSJ】
******************
サウジアラビアはイラン以上に特殊な社会・・・という固定観念を捨てる必要があるのかも。
ただ、サウジの改革は良くも悪くもムハンマド皇太子の「剛腕」次第といった面も。
何かと評判の悪い皇太子が権力闘争に敗れて政治的に失脚すれば、改革の流れも止まります。
「もう少し様子を見てみよう」といったところです。