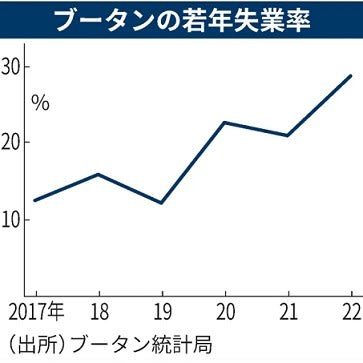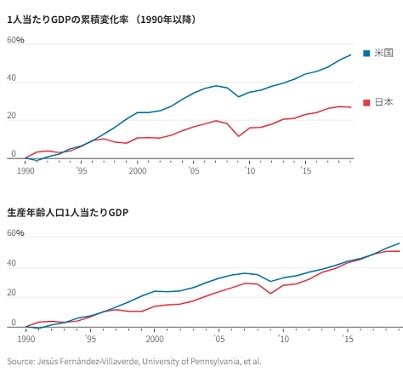(【1月7日 産経】)
【一時追い上げた国民党 近すぎる中国との距離感でやや失速も】
台湾と中国の距離感、ひいては日本を含む東アジアの今後の情勢に非常に大きな影響を与える台湾総統選挙が明後日13日に行われます。
これまでも何回か取り上げてきたように、現在の蔡英文政権の路線を引き継ぎ中国と距離を置く与党・民進党の頼清徳氏、中国に融和姿勢を見せる国民党の侯友宜氏、民衆党の柯文哲氏の3人の争いとなっており、選挙戦は中国との関係が大きな争点となっています。
選挙戦は、国民党の侯友宜氏、民衆党の柯文哲氏の「一本化」が失敗したこともあって、与党・民進党の頼清徳氏が一歩リードしていると報じられています。一時期、国民党の侯友宜氏が追い上げて支持率がほぼ並ぶという状況になったのですが、再び頼清徳氏のリードが広がっているとも。
****台湾総統選挙 蕭美琴副総統候補によって「若者層取り込み」に成功した頼清徳氏****
副総統候補の蕭美琴氏によって、若者層の支持が広がる
(中略)
須田慎一郎氏(ジャーナリスト))頼さんの最大のウィークポイントは若年層に支持されていないことでしたが、副総統候補に親米派の方を迎え入れて……。(中略)そこで若者層の支持が得られる状況になってきたのではないかと思います。
親中派の趙少康氏を副総統候補につけて失速した侯友宜氏
飯田)蕭美琴さんは、前駐米大使でリベラルな政治家でもある。そこが若い人たちにも支持されているのでしょうか?
須田)「若者層、無党派層の支持をどの程度集めることができるのか」というのが、台湾総統選挙のいちばんの注目ポイントだったはずです。
しかし、国民党に関しては親中派の色合いが濃くなってきてしまった。副総統候補の趙少康さんはもともとメディア経営者でしたが、親中派として名を売っていた人ですから。この人を副総統候補につけたのが、失速する要因になっていると思います。(後略)(「飯田浩司のOK! Cozy up!」で放送)【1月9日 ニッポン放送NEWS ONLINE】
********************
中国に近すぎることが若者層、無党派層を警戒させるという点では、国民党の馬英九前総統の「(中台)両岸問題では習近平国家主席を信用しなければならない」との発言も問題になっています。
****台湾の総統選、13日に投開票 馬氏「習氏を信用」発言が物議****
(中略)国民党の馬英九前総統は8日、ドイツメディアの取材に「(中台)両岸問題では習近平国家主席を信用しなければならない」と発言したほか、中国と台湾の統一について「受け入れられる」とも述べた。国民党の従来の立場から一歩踏み込んだ親中的な発言で、物議をかもしている。
頼氏は11日、記者団に対し「習氏を信用すれば、台湾は香港のようになってしまう」と馬氏の発言を批判した。柯氏も記者団に「習氏よりも自分(台湾)を信じた方が安全だ」とコメントした。
一方、侯氏は11日に記者会見を開き、馬氏の発言について「自分の考え方とは違う。私が総統になれば、任期中に統一問題に触れるつもりはない」と強調した。馬氏の発言を受けて有権者が国民党への警戒感を高める可能性があり、火消しに走った形だ。【1月11日 産経】
*******************
“火消”に追われる国民党・侯友宜氏は・・・
*****台湾総統選、国民党の侯友宜候補「台湾海峡の平和の促進者になる」…中国側に偏らない姿勢強調***
3日投開票の台湾総統選に立候補している最大野党・国民党の侯友宜ホウヨウイー新北市長と、副総統候補の趙少康ジャオシャオカン氏が11日、新北市で海外メディア向けの記者会見を開いた。侯氏は「中道を歩み、台湾海峡の平和の促進者としての役割を果たすべきだ」と語り、中国側に偏った向き合い方はしない姿勢を強調した。
侯氏は中国に融和的な政策を掲げるが、「(総統の)任期中は、統一問題に絶対に触れない」と明言した。防衛力を充実させる必要性も主張し「強力な軍備を整え、相手に安易に戦争を起こさせないようにすることが、対話と交流をする上での最優先事項だ」と話した。【1月11日 読売】
******************
馬英九前総統が中国と近いのは以前からの話で、野党候補一本化が失敗したのも中国に近い馬氏が表に出てきたためとも言われていますが、この時期にこれまで以上に踏み込んだ親中国発言をなぜ行ったのかはわかりません。
【高齢者を歌舞音曲でもてなす国民党集会 硬い演説好きの民進党集会】
二大政党の民進党と国民党の雰囲気・イメージについては、以下のようにも。難しい理屈抜きに、両政党の“カラー”がなんとなくわかります。そして、第3党・民衆党・柯文哲氏が一定に支持される理由も。
****“超”高齢化の国民党vsエリート民進党 ビギナーのための台湾総統選挙ルポ****
(中略)
集会に来た人を飽きさせない“工夫”
私が台北に到着した翌日の1月7日、 台北市内からバスで1時間の距離にある桃園市中壢区で、与党・民主進歩党(民進党)と最大野党の中国国民党(国民党)の集会がそれぞれ開かれていたため、行ってみることにした。
まず、はじめに目にしたのは機場捷運(空港地下鉄)の老街渓駅の駅前にある 広場で開かれていた国民党の集会だ。 地下鉄を降りると、出口に出る前から大音量の音楽や人々の歓声が響いてきた。台湾の国政選挙は4年に1度の「お祭り」という側面があり、集会では来た人を飽きさせない工夫がなされている(意地悪く言えば、面白くない集会には誰も来たくないのだ)。(中略)
広場の群衆の前には映画スクリーンばりに巨大な液晶モニターがいくつも備え付けられ、両脇に「民主要制衡」(民主主義のバランスを取ろう)、「政黨要輪替」(政権与党は交代交代で)とスローガンが出ている。
解説すれば、台湾の総統の任期は最長2期8年で、1990年代に国民党の李登輝政権下で民主化がおこなわれて以降の政権与党は、民進党(陳水扁)、国民党(馬英九)、民進党(蔡英文)……と8年ごとに交代している。過去の国民党独裁時代の影響もあり、台湾の選挙民には特定の政党に長期政権を担わせたくないという心理も存在する。なので、次は国民党の番だというわけだ。
では、政権奪還を目指す国民党は選挙集会でいかなる政見を述べたのか──?
「〇〇里」「〇〇村」と書かれたプラカードがちらほら
結論を言えば、私たちが会場の近くにいた約1時間弱の間には、演説はほぼなかった。会場はそこそこ熱気があったものの、ひたすら大音量で歌手たちが歌い踊って投票を呼びかけているだけである。
もちろん、この選挙集会には総統候補の侯友宜、副総統候補の趙少康のほか、党主席の朱立倫(2016年の総統候補で侯友宜の後ろ盾)、2020年総統候補で立法院選の比例第一位に名を連ねる韓国瑜など国民党のスターたちが勢ぞろいしていた。集会のなかでは彼らの演説もおこなわれていたとはいえ、タイムテーブルにおいてその割合は決して大きくないのだ。
広場にいる人々の顔ぶれは高齢者が多く、その間を小さな子どもたちが無邪気に走り回っている一方、現役世代の姿はあまり見られない。 おじいちゃんおばあちゃんが孫を連れてやってきているという印象だ。
高齢者の群れのあちこちには、「〇〇里」「〇〇村」と書かれたプラカードが出ている。これは日本でいう「大字」(おおあざ)くらいの規模の地域単位だ。古い政党である国民党の強みはこうした地方の村里長(日本の町内会長に近いが一応は公務員)に影響力があることで、地域における国民党の選挙集会の参加や票の取りまとめはしばしば彼らの呼びかけ(動員ともいう)によっておこなわれる。
地方の高齢者は政策そのものよりも従来の習慣や人間関係で投票行動をおこないがちな傾向もある。きつい言い方をするならば、そうした人たちには選挙集会で政策を語るよりも、歌舞音曲でもてなしてあげたほうが票につながるということかもしれない。
侯友宜陣営は「3D戦略」を提唱
会場では大音量の音楽に合わせて、人々が手にする青天白日満地紅旗(中華民国の国旗)の小旗が揺れ続けていた。なお、日本においては、国民党は「中国」寄りだと簡単に解説されることが多いが、彼らがこだわっている「中国」とは中華民国のことである。
多少の解説を加えると、近年の国民党が大陸の共産党と接近しているのは、もともとは民進党と対抗する目的で旧敵と手を握ったからであり、別に大陸側の政権に吸収されたいからではない。また、台湾経済は大陸と密接な関係を結んでおり、すでに高度成長期を終えて久しい台湾が経済を浮揚させるには、大陸とある程度は安定的な関係を保つことが現実的に必要でもある。
ただし、共産党側にはそれを利用して台湾を併合したいという狙いが常に存在する。前政権の馬英九時代の後半にはこの狙いが露骨にあらわれ、それにもかかわらず馬英九が対大陸傾斜に歯止めをかけなかったことで、市民に不安を抱かせた。
今回の選挙でも、侯友宜陣営は従来の民進党政権下における大陸側とのコミュニケーション不足が目下の緊張を高めていると主張しており、(1)抑止(Deterrence)、(2)対話(Dialogue)、(3)非エスカレーション(De-escalation)の「3D戦略」を提唱。台湾が香港のような中華人民共和国の主導下での一国二制度に置かれることには反対しつつ、中華民国憲法と合致する形での「九二共識」を前提として大陸側と向き合う立場を示している。
(なお「九二共識」とは、1992年に中台双方の窓口機関交流において口頭で合意が成立したとされる、大陸側と台湾側で「ひとつの中国」という認識は共有しつつも「中国」をどう解釈するかは双方に任されると国民党側が理解している合意──、のことである。大変ややこしい説明だが、こう書くより仕方ない)。
民進党の会場も平均年齢高し
国民党の集会を離れ、すこし離れた泰豊輪胎中壢廠の広場で開催されていた民進党の集会に向かう。 (中略)その数は国民党の集会よりもかなり多いように見えた。
いっぽう、人々の年齢層は、国民党の集会参加者よりはすこし若いとはいえ50〜60代がメインだった。実は民進党も、2016年に蔡英文が当選したときこそ若者の人気を集めていたが、経済の低調や物価・不動産価格の高騰といった問題が解決しなかったことや、民進党自体が結党から約40年を経て完全に既成政党化していることで、失望した若者の離反を招いているとされる(そうした若者は第三極の政党である台湾民衆党の支持に流れている)。
実際、会場を見ていると、2016年に私が現地で見た選挙集会と比べて、コアな支持者の高齢化は明らかだった。もっとも、それでも国民党の集会とは違い、若者や親子連れの姿もそれなりにみられる。人々の間に「〇〇里」の看板はすくなく、動員よりも自分で来る意志を持って来ている人たちが多そうな印象だ。
会場に足を踏み入れると、ボランティアスタッフから「選対的人、走対的路」(正しき人を選べば正しき道を歩む)というスローガンと、総統候補の頼清徳、副総統候補の蕭美琴の名前が印刷された緑色の小旗を渡された。
国民党が「中華民国」のアイデンティティにこだわるのに対して、民進党は「台湾」のアイデンティティによりこだわる政党だ。国民党の集会では目眩がするほど大量の中華民国国旗があふれていたのに対して、民進党の集会で国旗はほとんど見られない。
自分たちに投票するべき理由を理屈で説明
さらに国民党との集会の違いは、プログラム内での歌舞音曲のすくなさだった。この日は頼清徳と蕭美琴、さらに現総統の蔡英文、前行政院長の蘇貞昌といった顔ぶれが集まっていたのだが、彼らはとにかく演説を続けたがる。
(中略)外国人の目線から見ると、話が多すぎて多少退屈な印象を受けなくもない内容である。
民進党は1986年、まだ国民党の独裁体制下にあった台湾で、民主化を求める人たちを中心に草の根の泥臭い世界から始まった政党だ。しかし、今世紀に入ってからの2度の与党経験を経て、現在は都市型のエリート政党としての顔が強まっている。
LGBTや脱原発、ジェンダーなどの問題にも非常に高い関心を示す政党である(若者層の支持が離れている一因も「それらの理念もいいけれど自分たちの暮らしをなんとかしてくれ」という不満がくすぶっていることにある)。
リベラルエリートの党としては、有権者が自分たちに投票するべき理由は歌舞音曲のノリではなく理屈で説明しなくてはならないと考えているのかもしれない。もちろん、選挙活動としてはこちらの方が「真っ当」ではある。
経済・政治改革・雇用・少子高齢化…台湾が直面する課題
ところで、日本において台湾の選挙はしばしば「台湾独立か中国との統一か」といった文脈で語られがちだ。だが、実際のところ台湾の民意の大部分は、どの党を支持するかにかかわらず、広い意味での現状維持を希望する声が多数派を占める。ゆえに民進党であれ国民党であれ、そこから外れた選択肢は取れない。
中華民国体制を撤廃して台湾国を作るという「台湾独立」をおこなわずとも、中台分断から70年以上を経た中華民国は実質的には台湾とほぼイコールの存在になっている。
そのため、中華民国が(国際的承認は得ていないとはいえ)独立国家をもって任じている以上、台湾はすでに実質的に独立した状態にあると考えていい。
いっぽう、現在の中台間の力関係からすれば、「中国との統一」は中華人民共和国による台湾併合以外の形はありえない。現実的にそれを望む人は、たとえ国民党支持者でもほとんど存在しておらず、やはり現実的な選択肢ではない。
せいぜい、中国大陸と距離を置いてでも台湾のアイデンティティを強く保った状態で現状維持を志向するか(民進党)、中国大陸と友好的な姿勢を取りつつも中華民国アイデンティティを強く保った状態で現状維持を志向するか(国民党)。
習近平体制の中国の現状からすると、いずれもそれはそれで困難なことなのだが、台湾が取りうる対中姿勢は実質的にこの二択で、「現状維持」という点は変わらない。
ゆえに台湾の選挙民も、日本をはじめとした海外の人たちが想像するほどには、中台関係だけを理由として投票行為はおこなわない。選挙における他の争点は経済・クリーンな政治・雇用と労働環境・住宅難・少子高齢化……という、いずれの先進国も直面している課題である。
もっとも、そうであるからこそ、硬直した姿勢しか取れない既存の二大政党のありかたに対する不満も生まれ、既存の権威をポピュリズム的に批判する勢力も一定の支持を集める。それが今回の第三極である民衆党だ。 こちらについては、また別の原稿で書くことにしよう。【1月10日 安田峰俊氏 文春オンライン】
********************
【表裏・硬軟いろいろな働きかけで民進党敗北を画策する中国】
連日多くが報じられているように、中国は比較的宥和的な国民党を支援し、中国と対立的な与党・民進党の敗北を画策しています。
****中国「中台衝突の極度の危険性認識を」台湾総統選でけん制 台湾の有権者に対し「中台関係の分かれ道」と呼びかけ****
台湾の総統選が13日に迫るなか、中国政府は台湾の与党・民進党の頼清徳候補について「多くの台湾同胞が中台の衝突を引き起こす極度の危険性を見極めるよう望む」との談話を発表して、けん制しました。
国営の新華社通信によりますと、中国政府で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官は11日に談話を発表し、台湾の与党・民進党の頼清徳候補が政権をとった場合、「頼氏は“台湾独立”への活動をさらに推進し、台湾海峡は強風と高波で危険な状況になるだろう」と警告しました。
また、陳報道官は「“台湾独立”と台湾海峡の平和は水と火のように相いれない」「多くの台湾同胞が頼氏が中台の衝突を引き起こす極度の危険性を見極めるよう望む」と述べてけん制し、台湾の有権者に対し、「中台関係の分かれ道で正しい選択を行い、中台が繁栄し、発展する新しい局面をつくり出してもらいたい」と呼びかけました。【1月11日 TBS NEWS DIG】
国営の新華社通信によりますと、中国政府で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官は11日に談話を発表し、台湾の与党・民進党の頼清徳候補が政権をとった場合、「頼氏は“台湾独立”への活動をさらに推進し、台湾海峡は強風と高波で危険な状況になるだろう」と警告しました。
また、陳報道官は「“台湾独立”と台湾海峡の平和は水と火のように相いれない」「多くの台湾同胞が頼氏が中台の衝突を引き起こす極度の危険性を見極めるよう望む」と述べてけん制し、台湾の有権者に対し、「中台関係の分かれ道で正しい選択を行い、中台が繁栄し、発展する新しい局面をつくり出してもらいたい」と呼びかけました。【1月11日 TBS NEWS DIG】
*********************
こうした表向きの発言(威嚇?)だけでなく、水面下の画策も。
****台湾総統選まであと2日 狙われた“地域の代表” 中国招待され選挙応援依頼された疑い 「上海ガニ食べながら意見交換」****
台湾の総統選挙まであと2日ですが、選挙で重要な役割を果たす「地域の代表」らが中国に招待され、今回の選挙で特定候補の応援を依頼された疑いが浮上しています。捜査当局から取り調べを受けたという男性がJNNの取材に応じました。(中略)
中国は民進党を「独立勢力」と見なし対話を拒絶する一方、最大野党・国民党とは交流を重ね優遇策を講じるなど、台湾世論を“揺さぶる”かのような対応を続けています。 そしてこれも、世論工作の一環でしょうか。
記者 「いま、台北をはじめ各地で、地域の代表である『里長』に捜査の手が及んでいます」
「里長」は日本の町内会長に近い役割ですが、4年に一度、選挙で選ばれる「地域の代表」です。そんな台湾各地の里長が格安の料金で中国に招待され、見返りとして今回の選挙で特定の候補や政党の応援を依頼されたとして、当局が捜査に着手したのです。
JNNは、台北地検から先月、二度の事情聴取を受けたという当選歴6回のベテランの里長を訪ねました。(中略)これまで10回以上、去年は6月と10月に招待を受け、上海や南京を訪問したといいます。
聴取を受けた里長 「ひとこと言わせてもらいますが、本当にごく普通の日程で純粋に民間交流です」
去年参加したツアーは、ともに6日間程度。費用は日本円でおよそ6万円から9万円だったといいます。観光地や企業、団地などの見学のほか、上海ガニなどを食べながら意見交換したといいます。
中国側は地域の代表者だけでなく、台湾政策を担当する「台湾事務弁公室」の関係者が常に同席していたといいます。ただ、「一度も政治の話はしていない」と疑惑を強く否定しました。
「私たちは国家主権やどの政党がどうだとか、そんな話はしません。雑談で中国側に『民進党はどうなんだ?』と聞かれることもありましたが、私は笑ってましたよ」 7000人の地域住民を束ねる里長の男性はこう付け加えました。(中略)
中国は民進党を「独立勢力」と見なし対話を拒絶する一方、最大野党・国民党とは交流を重ね優遇策を講じるなど、台湾世論を“揺さぶる”かのような対応を続けています。 そしてこれも、世論工作の一環でしょうか。
記者 「いま、台北をはじめ各地で、地域の代表である『里長』に捜査の手が及んでいます」
「里長」は日本の町内会長に近い役割ですが、4年に一度、選挙で選ばれる「地域の代表」です。そんな台湾各地の里長が格安の料金で中国に招待され、見返りとして今回の選挙で特定の候補や政党の応援を依頼されたとして、当局が捜査に着手したのです。
JNNは、台北地検から先月、二度の事情聴取を受けたという当選歴6回のベテランの里長を訪ねました。(中略)これまで10回以上、去年は6月と10月に招待を受け、上海や南京を訪問したといいます。
聴取を受けた里長 「ひとこと言わせてもらいますが、本当にごく普通の日程で純粋に民間交流です」
去年参加したツアーは、ともに6日間程度。費用は日本円でおよそ6万円から9万円だったといいます。観光地や企業、団地などの見学のほか、上海ガニなどを食べながら意見交換したといいます。
中国側は地域の代表者だけでなく、台湾政策を担当する「台湾事務弁公室」の関係者が常に同席していたといいます。ただ、「一度も政治の話はしていない」と疑惑を強く否定しました。
「私たちは国家主権やどの政党がどうだとか、そんな話はしません。雑談で中国側に『民進党はどうなんだ?』と聞かれることもありましたが、私は笑ってましたよ」 7000人の地域住民を束ねる里長の男性はこう付け加えました。(中略)
台湾のシンクタンクの研究者は、里長は選挙への影響力があり、中国の明確なターゲットだと指摘します。
国防安全研究院 鍾志東氏 「里長は地域の民意そのものです。都会でも田舎でも、比較的簡単に引き込むことが出来る対象なのです」(後略)。【1月11日 TBS NEWS DIG】
国防安全研究院 鍾志東氏 「里長は地域の民意そのものです。都会でも田舎でも、比較的簡単に引き込むことが出来る対象なのです」(後略)。【1月11日 TBS NEWS DIG】
******************
前出【文春オンライン】に“古い政党である国民党の強みはこうした地方の村里長(日本の町内会長に近いが一応は公務員)に影響力があることで、地域における国民党の選挙集会の参加や票の取りまとめはしばしば彼らの呼びかけ(動員ともいう)によっておこなわれる。”とあるように、里長にカニをふるまうのは“有効”な選挙戦術なのでしょう。
もっと“直接的”な威嚇としては“中国ロケット、台湾上空を通過 総統選向け圧力か”【1月9日 産経】といったものもありますが、中国が前面に出れば出るほど台湾世論は中国を警戒し、民進党に票が流れるといった構図ではないでしょうか。
誰でも感じるそうしたことを無視して、なぜ中国が威圧的な手法を捨てないのか・・・これもよくわからないところです。